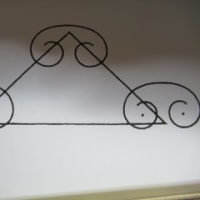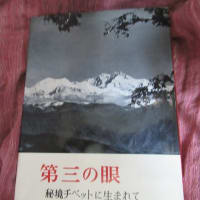だいぶ間があいてしまいましたが、現代の稲荷神の巫女さんであった三井シゲノさんの聞き書きを行ったアンヌ・ブッシィ著「神と人のはざまに生きる」という本のご紹介を続けます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
シゲノの話は筋が通って分かりやすかった。
しかし、失明の憂き目にあってから大阪の「玉姫大社」に辿り着くまで、9年の月日がたっている。
意思の強いシゲノは、その間どのような生活をしていたのだろうか?
また、「「夢のお告げ」の折りに「守護神」がのたまった」と彼女が言っていた言葉も思い出した。
「守護神」とは誰だったのか?
「玉姫」とは別の神だったのか?
私は再び彼女にたずねた。
そのとおりでございます。
故郷の「お滝」にて私は、左目が再び見えるようになったばかりでなく、また私の「守護神・白高(しらたか)さん」と出会ったのでした。
「白高(しらたか)さん」とは、「白狐さん」です。
私が24才のとき、あの事故があってから2年後、「お滝」に籠もり始めてから3か月も過ぎた頃、私はもっぱら「神さん」に、もろもろの神様に、身も心も捧げて拝んでおりました。
籠もり始めてからすでに10日ばかりも過ぎたころでしたか、滝に打たれながら「神さん」にお祈りを捧げておりますと、ちょうどその最中にふわっと「白狐さん」が目の前を横切ったのでした。

始めのうちは、「あれは何だったのかしら?」と一人不思議に思っておりました。
それに、とても複雑で奇妙な感覚がありました。
昼も夜も絶え間なく、ダバダバダバダバという音がするのです。
人里離れた、ひっそりかんとした所で、うるさいなんてことはあり得ないはずなのに、それなのにこの音ときたら。。
「もしやキツネかタヌキにつままれているのではないかしら?」とわが身を疑いました。
キツネやタヌキは、人里離れて暮らす人間を、いろいろな手でたぶらかすと世間では言われます。
「神さん」かなにか、別の尊い存在に化けて、かねてからの念願がついに成就したと信じ込ませて、まんまと手玉に取り、さんざんおかしなことをやらかした挙句の果てに、荒れ野の落ち葉と糞土のただ中に、呆れ顔で天を仰ぐ姿で捨てやるというのです。
それが一度切りのことでしたらまだしも、またかまたかとあのダバダバダバダバという音が耳について離れないのでした。
その後も幾度、白狐の姿を目にしたことでしょう。
こなたの谷からしゅっと飛び出して走り去るかと思うと、また別の所からしゅっと私たちの前を横切って、かなたに行くのでした。
それはまさに空を切る真っ白な犬といった風でした。
「お滝」に籠もり始めて間もない頃は、あれこそまさに本物の「白狐さん」だ、などとは、到底信じられませんでした。
「白高(しらたか)さん」の名と、それが自分の「守護神」であることを私が知りましたのは、この昭和2年のことでありました。
その日の朝、籠もり所で「お滝」に向かい、懸命に「神さん」に向かってお祈りを唱えておりますと、はじめて明るい光が、またさまざまな色が見えたのです。
周りの人は喜び、感嘆の声を上げました。
そして「「神さん」にお礼のお勤めをしなければ」と、護摩を焚くように勧めるのでした。
このようにして、私の祖母と大叔母と叔父、それに権現さんの先生、この4人が「お滝」に集まった時、ことが起こったのであります。
権現さんの先生が「神さん」へのお礼として、護摩を焚こうとしていたまさにその矢先に、「護摩焚き無用!」と私が言ったらしく、4人に先駆けて「神さん」を拝み始めて合掌した手を頭上にふりかざした私の身に、突如さっと「神さん」がお降りになったかと思うと、「白高(しらたか)!」と叫んだ、というのです。
そこで先生が「神さん」に「「白高(しらたか)」さん、この人の目がまた見えますようにしていただけるのでしょうか?」とお尋ねしますと、「不自由ないよ」という言葉が私の口から発せられたそうです。
皆にはこの一言が、たとえ目が見えないままでも、私はこれから生きてゆくのに不自由はしないだろう、どんな時もなんとかやってゆけるよう、「神さん」が見守っていてくださるのだから、という意味なのだとわかりました。
おばあさん(大叔母)のようになろうという気はちっともなかったのですが、そのような次第で、私はかつて彼女の辿った道に、再び足を踏み入れることになったのです。
それはまた、幼くしてすでに私が示していた素質に立ち返ることでもありました。
私はほんの8つの時、初めてこの身に「神さん」が降りてこられたと、昔から聞かされていたものですから。

一般に世間では、「稲荷さん」と「白狐さん」はまったく同じ「神さん」ということになっております。
大方そのとおりでありまして、どちらも農家の人々およびその家と田畑をお守りくださり、五穀豊穣を請け合ってくださる「神さん」で、キツネのお姿をしておられます。
当時はどこでもそうでしたが、私たちの村でも、家という家はすべてどこかに「稲荷さん」をお祀りしておりました。
私の生まれ育った家でも、やはり先祖代々、お家安泰を祈ってささやかな神棚に「稲荷さん」をお祀りしておりましたし、そこにはまた「龍神さん」という「地神さん」も祀られております。
この「神さん」は、そのお姿を金の宝珠の周りにとぐろを巻いた陶磁器製の白蛇にかたどられておりました。
実家ではこんな風でございましたが、夫の家では「稲荷さん」のことを「白髭さん」とか「白滝さん」と呼んでおりました。
あちこちに「稲荷さん」が祀られておりましたが、それというのも、そうしないとせっかくスイカやサツマイモを育てても、キツネやタヌキがやって来ては、畑を荒らしてしまうからでした。
ですからどの家も、軒下か、あるいは畑の一画にでも、ちょっとした簡素な板づくりの小祠を設けて、そこに木の打札を掲げておりました。
はじの方に「稲荷さん」の名を、真ん中に「伊勢大神宮」の名を、そして左には「氏神さん」の名を記したものです。
それにまた、家のご先祖様を祀る神棚にも、そうしたお札を一つ立てておりました。
私はおばあさん(大叔母)が「神さん」を降ろしているのを見ておりましたから、どのような具合に事が運ぶのか、知っておりました。
まず神殿の前に円座を敷いて、そこに正座し、とんとことんとことんと「神さん」をお呼びするのです。
そして御幣を両手にしっかりと握って、まっすぐ立てて、しゅしゅしゅっと振ったら、おばあさんの体が揺れ動き出し、周りの人たちはその様子を見て、「ああ、「神さん」が来た。「神さん」が来られた」とささやいておりました。
私もそばにいて、皆と一緒に見ておりました。
おばあさんはまた火護摩を焚き、人の頼みに応じて「神さん」にお伺いをたてておりました。
たとえば「木を刈りたいけれども、「神さん」の怒りに触れやしないか?」と気をもんでいるような人がやって来ましたが、私が御幣を持って来ますと、おばあさんはお祓いを始め、そのうち身を震わせて、こう告げるのでした。
「今、木を刈ると面倒なことになる。来たる大安の日まで待ちなさい」。
毎月28日の祭日に、私はおばあさんの手伝いに行っておりました。
その日はおばあさんが大祭を執り行う特別な日で、家の前で火を焚いて餅を焼くのでした。
村中の人たちがその分け前にあずかり、「神さん」のお恵みをいただくのでした。
いつもこんな調子でした。
ほんとうに、取り立てて学ぶことはありませんでした。
さまざまな人がやってきて、話をし、お茶を飲んで、というただそれだけのことで、私にはおばあさん(大叔母)に習おうなどという気持ちはちっともなかったのでした。
とは申しましても、私が「おばあさん」と呼び、他の人々からは「お稲荷さん」と慕われていたこの人は、大変威厳のある、信望の厚い先生で、お弟子さんも8、9人ついていたのでした。
(引用ここまで)
写真は、わたしが撮影した東京新宿の花園神社の稲荷社で、本書とは関係ありません。
*****
この本の著者であり、日本の民間宗教の研究者であるアンヌ・ブッシィさんは、研究をするにあたり、「現代の稲荷巫女について考えたいのならば、三井シゲノさんのことを調べれば、他のことを調べる必要はないですよ」と言われたということです。
まことに、こういう人もまれであるし、こういう研究書もまれであると思いました。
人と人の巡り合わせの妙味ともいえるかもしれません。
アンナ・ブッシーさんという人の聞き書きの記録がなければ、三井シゲノさんという、ごく近い年代に生きた巫女さんの人生は誰にも知られることなく、歴史の中に搔き消えていったことでしょう。
せっかくこのような資料があるのですから、わたしは、自分の心にも、滝行を課して、情報が多すぎる現代社会のただなかでも、心を揺らさないでいられるようになりたいと、改めて思いました。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「「神と人のはざまに生きる」(1)・・稲荷巫女、奈良から大阪へ」
「モンゴルのシャーマンの生活(1)・・祖先霊とつながる」(2)あり
「修験道とシャーマニズムとカラス天狗・・憑霊の心理学(5)」
「役行者と道教と、修験道と弁財天・・鬼のすがた」
「神々と交信する人々・・青ヶ島のハヤムシ(2)」
「岡本天明の予言と、ミロクの世」
「スカイピープルと古代人・・ホピ族のペテログラフ(岩絵)(2)」
 「日本の不思議」カテゴリー全般
「日本の不思議」カテゴリー全般