
澤村経夫氏が「熊野の謎と伝説」において描いている「熊野」を、もう少し見てみます。
*****
(引用ここから)
「日本書紀」上巻に「熊野諸手船(もろたぶね)」が登場する。
この「熊野諸手船」は、紀州の熊野ではなく、出雲の国美保に出現する。
現在でも美保神社の祭礼に、「熊野諸手船」が使用される。
熊野速玉神社の大祭にも、同じような諸手船が、祭船として使用されるが、
「熊野」と名がつく諸手船が、「出雲国」に忽然と現れるのはどんな意味があるのだろうか。
島根県八束郡八雲村には、「熊野」という地名がある。
そこに「熊野神社」があり、昔は出雲大社と肩を並べるほどの尊崇があつく、出雲の両大社と称せられた。
また九州の国東半島にある「熊野摩崖仏」などを取り上げていくと、「熊野」とはなにを意味するのか分からなくなる。
(引用ここまで)
*****
「諸手船」とは何かと見てみると、丸木をくりぬいた舟であることがわかりました。
「諸手船」の祭礼は、出雲の地で行われるのですが、「熊野諸手船」と呼ばれてきたというのです。
なぜ、出雲にありながら、熊野という名がついているのか、わからない、と著者は述べています。
“熊野”というのは、地名ではなく、全く異なる何かを指しているのではないかという思いから、著者は言葉を続けています。
Wikipediaによれば、丸木舟は次のようなものです。
***
諸手船(もろたぶね)は、島根県松江市美保関町の美保神社の神事に用いられる刳舟である。
1955年(昭和30年)2月3日に重要有形民俗文化財に指定された。
年に一度、12月3日の神事以外は境内に安置され海に浮かぶことのないこの諸手船は、およそ40年に一度造りかえることを旨として受け継がれてきた。
古くは、一本のクスノキの巨木を刳りぬいた単材刳舟だったとされ、現船はモミの大木を使い刳りぬき部材を左右に継ぎ複材化した刳舟である。
しかしいずれにしろ丸木舟とされるものであり、且つ現船は、保管されている古船や絵図に残されている明治時代の二世代前のものよりも太い木を使い、古式の技法に則り、いわゆる技術のゆりもどしも見受けられる。
昔の装束をまとった氏子9人が、二艘の諸手船に乗りこみ対岸の客人社の麓と宮前の間を櫂で水をかけあいながら競漕し、舳先に挿した「マッカ」と呼ばれる飾りを神社に奉げるのを競いあう。
また、和歌山県新宮市新宮の熊野速玉大社の御船祭で使用する諸手船は和歌山県の有形民俗文化財に指定されている。
***
では、この丸木舟による祭りは、どのような祭りであるのでしょうか。
同書には、和歌山の方の祭礼が、次のように描写されています。
*****
(引用ここから)
和歌山県新宮市の熊野速玉神社の「御船祭り」は秋祭りで、毎年10月16日に行われる。
神輿が熊野川に達すると、神幸船に神輿を移す。
この船には金爛の帆をあげ、二本の吹き流しを立て、舳先に五彩の稚児像と、「一つ物」が乗船する。
すると熊野側の対岸の“鵜殿”から、「烏止野(うどの)」の旗を立てた「諸手船」が着く。
神幸船は「諸手船」にひかれて、熊野川をさかのぼり、御舟島をまわる神事である。
神幸船の元型は南北朝末期に作られた。
神幸船は、神輿(みこし)などと機を一にする比較的新しい祭りの形態である。
神幸船に乗る「一つ物」は、別名“ショウマンサマ”と呼ばれる。
馬の背に乗せられた青年姿の人形は、本来の神が乗り移った「よりまし」と称するご神体である。
神輿(みこし)という新しいハイカラな祭りの形式が一種の流行で、いつの間にか本来の主人公の御神体が神輿の従者となってしまった。
新宮市の近くの蛭子(えびす)神社でも、御神体の大幡(おおはた)が神輿のお供になってしまった。
「神輿が海を渡れなくとも、大幡が海を渡ることができると、祭りが終わることが出来る」との言い伝えがそのことを明瞭に物語っている。
この様に考えると、「神幸船」は後世に作られたもので、「諸手船」が本来の神の座船であったはずである。
「諸手船」は新宮の対岸の“鵜殿”から出るが、同時に20人の“諸人(もろと)と称す船人が乗船する。
その舳先に、一人の女装した男子が立つ。
赤い頭巾を長くたらし、赤い衣に黒タスキと黒帯をしめた女装の男が、手に櫂をもって、意味不明の“ハリハリセー”と言いながら、舳先で踊るのである。
この奇怪な、しかも祭りで重要な役目を果たす赤衣の人が、なんの固称もつけられず、何の役目かも分からぬまま、遠い昔より受け継がれている。
ある人は「諸手船」を出す“鵜殿”の村のある滑稽で器用な婦人が即興の舞踏としておこなったのがはじまり、と説をなすが、そのように簡単に片づけてよいのだろうか。
神主がお顔張(おこわばり)で口鼻をかくして、神霊をお移しするような、古い行事がそのまま受け継がれている格式高い熊野速玉神社の大祭に、後世の即興の踊りなど、付け入るすきがあるとは思えない。
この赤い頭巾と黒い帯とタスキに、何かの深い意味が込められているのではないだろうか。
口にするのもおそろしい不吉の神、たたりの神、それゆえにないがしろにできず、祀らねばならぬ理由があるはずである。
柳田国男は、赤不浄は女性の血の忌み、黒不浄は死の忌みだと述べている。
熊野では人が死ぬと「死」の言葉をおそれて、「ようなかった」というように、口にするのも恐ろしい神であるために、その伝承が忘れ去られたのではなかろうか。
(引用ここまで・続く)
*****
wikipedia「舟渡御(ふなとぎょ)」より
船渡御(ふなとぎょ)とは、祭礼などでの神事の一つ。
渡御の一種で、神体や神霊を船に乗せて川や海を渡す。
広義には、その船を送迎する神事も含む。
一般的には、神霊の移った神輿を船に乗せて行われる。
Wikipedia「神幸祭」より
神幸祭(しんこうさい)は、神霊の行幸が行われる神社の祭礼。
多くの場合、神霊が宿った神体や依り代などを神輿に移し、氏子地域内への行幸、御旅所や元宮への渡御などが行われる。
神輿や鳳輦の登場する祭礼のほとんどは、神幸祭の一種であるといえる。
神幸祭は「神の行幸」の意味で、広義には行幸の全体を、狭義には神社から御旅所などの目的地までの往路の過程を指す。
後者の場合は目的地からの神社への復路の過程に還幸祭(かんこうさい)という言葉が用いられる。
神幸祭・還幸祭と同じ意味の言葉に渡御祭(とぎょさい)・還御祭(かんぎょさい)という言葉があり、渡御祭も広義には行幸(渡御)の全体を指す。
本来は、神霊を集落内の祭壇に迎える形であったものが、祭壇が祭祀の施設として神社に発展すると、迎える行為が逆の過程の里帰りとして残り、神幸祭が行われるようになったと考えられている。
このため、磐座などの降臨の地が御旅所となり、現在では元宮や元の鎮座地である場合が多い。
御旅所に向う神幸祭のおおまかな流れは
1. 神輿などに神霊を移す神事
2. 神社から御旅所への渡御
3. 御旅所での神事や奉納(御旅所祭)
4. 御旅所から神社への還御
5. 神霊を還す神事
であり、この過程が数日間に及ぶ場合もある。
2や4の過程において、氏子地域内を巡幸する場合が多い。
御旅所などに向わない場合には、神霊が氏子地域を見回る、或いは、ある特定の場所で神事などを行うために行幸される。
 関連記事
関連記事
画面右上の検索コーナーを、「ブログ内検索」にして、
「カラス」
「ワタリガラス」
「太陽」
「熊野」などで、関連記事があります。(重複あり)












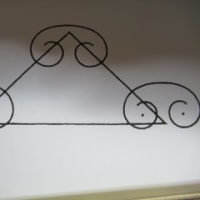


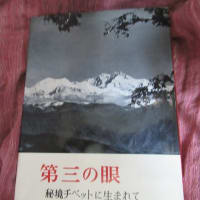







紋章や祭事の共通性もおもしろいですね
熊野本宮大社
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shrine_Kumano_hongu_torii01.jpg
三脚巴
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%84%9A%E5%B7%B4
コメント、ありがとうございます。
3という数のもつ力の神秘が、あらわれているのでしょうね。
紋章を見ているだけで、意識が変化するのが感じられますね。
すごく強力な力をもつシンボルだと思いますよね。
///様
わたしも今沖縄のことを考えていました。
沖縄は気になりますよね。