
「離島という最前線に学ぶ・・「離島経済新聞」統括編集長 鯨本あつこさん」
朝日新聞2015・12・09
・・・・・
全国の離島についての情報を、機関紙とウェブで発信しています。
5年前に始めてから、足を運んだ島は100近く。
人が住んでいる島が420ほどなので、4分の1ですね。
世界にさきがけて少子高齢化が進む日本の中でも、離島は早くからこの問題に直面しています。
いわば世界の最前線。
そこでの様々な取り組みは今後、高齢化を迎える世界の国々にとってヒントとなるかもしれません。
とは言え、始めた時からそう意識していたわけではないんです。
もともとデザイナーや編集者などの仲間と「日本のいいものを紹介するメディアを作ろう」と話していました。
そのころ瀬戸内海の大崎上島を訪ねると、自然が豊かで人が優しく、時間も穏やかに流れていた。
そう、離島もまた「日本のいいもの」なんじゃないかって。
島を見てきて、つくづく思うのは、やはり「人」の重要性です。
たとえば、クリエーターやアーティストが多い石垣島では、50組以上が「石垣島クリエイティブ・フラッグ」というグループに所属して、石垣島のポスター制作やイベント開催を請け負っています。
居住者がスキルを活かして仕事を産み出し、それまで県外に流れていた金が、島内に回るようになったんです。

3・11以降、都会からの「Iターン」が増えました。
どの島でも、スキルや意欲のある人たちが、探せばいるはず。
瀬戸内海国際芸術祭も開かれる小豆島には、若い独身女性たちも大勢います。
最新号で「移住定住」をテーマにアンケートをしたところ、7割が「不便」と答えました。
そうですよね。
でも、便利じゃないから、足りないものを補うために、手を動かしたり人と助けあったりする。
都会ならお金があれば、人としゃべらなくても生きていけますが、島ではそうはいかない。
周りの人といい関係を築けなければ、食べ物さえ手に入らないこともある。
煩わしさも含めて、「人と関わる」のが生きていくということ。
急いで進む中で見失った当たり前のことを教えられています。
「人口減少」と騒がれていますが、ふりかえれば江戸時代は3000万人ほどでした。
その後、急激に増えたのが異常だったのです。
これから徐々に減り、そのうち適正な規模になるだけ。
悲観することはないと思います。
つばき油の生産量日本1で知られる東京都の利島(としま)は、人口300人前後を維持しています。
資源を取りつくさず、そこそこの暮らしを保つ。
「縮む」時代を楽しく過ごすには、様々なものが「無い」中で生き残ってきた離島から学べることがありそうです。
・・・・・
確かな視点、頼もしいですね。
良い情報発信を、続けてください。
続いて、別記事のご紹介もします。
長いので、半分ずつにします。
・・・・・

「島国の島々ーニッポンの「これから」を訪ねて」
朝日新聞・別刷り「globe」2016・01・03
・・・・・
日本には6800あまりの島があり、うち420ほどに人が住む。
人口減少は、高齢化は、足早に進む。
一方で、歴史的に外国との接点にもなってきた。
海を渡り、人々や自然の息吹を写真でとらえてみたら、その風景に島国・日本の「これから」を見た思いがした。

〈長崎県・対馬〉
「韓国と対馬の「間合い」」
長崎県の対馬の北端、比田勝を訪ねた。
この日は少し曇っていたけれど、海の向こうの韓国・釜山に林立するマンション群がはっきり見えた。
2つの国を隔てる距離は、50キロほどしかない。
対馬は今、韓国からの観光ブームに沸く。
島内を案内する標識にも、店のメニューにも、ハングルがあり、スーパーは日本の日用品を求める観光客でにぎわう。
激増のきっかけは、円安・ウォン高と、対馬と釜山を結ぶ船の運航会社が、2011年に3社に増えたこと。
2015年は、年20万人を超えそうだ。
たった1時間ほどで、神社や和食など外国の「異文化」を味わえることが魅力だ、と観光客やガイドから聞いた。
ただ、人口32000人あまりの島に、文化や習慣の違う外国人がたくさん訪れるのだから、きれいごとばかりではない。
日本の報道やネットの書き込みでは「対馬が韓国に占領される」といったものもある。
それでも韓国の人たちは、対馬を訪れる。
対馬は、韓国の人たちを迎える。
どうしてだろう?
韓国の人たちは満足を得て、対馬は観光で潤う。
現実的な関係が、ここにはあるように思った。
釜山に住んでいたキム・ソンチョルは、2年半前、対馬の民宿の調理員に採用された。
客の多くは、釣りや登山などを楽しむ韓国の人たち。
観光ブームがなければ、ソンチョルが海を渡ることはなかっただろう。
1年半あまりがすぎた頃、対馬育ちのKさんが民宿で働き始めた。
二人は付き合い始め、今では二人で居酒屋を切り盛りする。
メニューは周りの店と重ならないよう、韓国料理に絞り、地元に溶け込もうと努める。
ソンチョルは、名前の漢字文字の一つが、吉を二つ並べているので、周りから「二吉(にきち)」と呼ばれ始めた。
彼は言う。「日本人が好きな韓国料理をたくさんの人に食べてもらいたい」
日本全体で見ると、昨年は2000万人近い外国人観光客が、訪れた。
中国の人たちの「爆買い」は、経済にプラスだが、マナーに閉口する向きも少なくない。
それでも外国人は日本に来る。
日本はこれからも、彼らをうまく受け入れていくことができるだろうか?
対馬という島で折り重なる「満足」と「摩擦」が絡み合った外国との付き合いは、なんだか日本の「写し絵」のような気がしてきたのだ。
(写真は、同朝日新聞より。対馬市で行われる恒例行事「朝鮮通信使行列」。仏像の盗難問題が絡んで一時中断したが復活したという。)
・・・・・
「国境の島へー対馬観光物産協会」HP
・・・・・
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「ゲートウェイとしての国境、という発想・・ボーダーツーリズムの試み」
「朝鮮と古代日本(1)済州島をめぐる考察」(6)まであり
「東アジアの軽みこそ強さである・・「江湖」の精神(東島誠氏)日本は大人になりそこねた(白井聡氏)」
「タイの人々と学び合う・・紀子さま父の実践18年目に」
「4500年前からの住人と岩絵・・河合隼雄のナバホへの旅(2)」(6)まであり
「梅も僕も 黒豚もいる 大地かな・・屋久島で豚を飼った山尾三省」
「山尾三省の遺言・・清らかな水と 安らかな大地」
 「アジア」カテゴリー全般
「アジア」カテゴリー全般 「野生の思考・社会・脱原発」カテゴリー全般
「野生の思考・社会・脱原発」カテゴリー全般















 wikipedia「幼形成熟」より
wikipedia「幼形成熟」より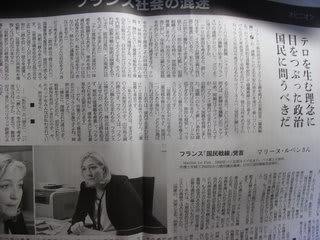


 wikipedia「イソノミア」より
wikipedia「イソノミア」より 「野生の思考・社会・脱原発」カテゴリー全般
「野生の思考・社会・脱原発」カテゴリー全般

 問
問 小熊
小熊









