
アメリカ大陸に人間がやってきた時の記憶を伝えるアメリカ・インディアン、イロコイ族の口承史を読んでみました。
解説には
「アメリカ大陸に住むインディアンとも呼ばれるネイティブ・アメリカンの人々は、その昔ベーリング海峡が陸続きだったころ、すなわちベーリング陸橋をわたり、アジア大陸からアメリカ大陸へやってきたモンゴロイドの子孫だという説が定着しつつある。
「一万年の旅路」はネイティブ・アメリカンのイロコイ族に伝わる口承史であり、物語ははるか一万年以上も前、一族が長らく定住していたアジアの地を旅立つところからはじまる。
彼らがベーリング陸橋を超え、北米大陸に渡り、五大湖のほとりに永住の地をみつけるまでの出来事が緻密に描写されており、定説を裏付ける証言となっている。
イロコイの系譜をひく著者ポーラ・アンダーウッドさんは、この遺産を継承し、それを次世代に引き継ぐ責任を自ら負い、ネイティブ・アメリカンの知恵を人類共有の財産とするべく英訳出版に踏みきった。」
とあります。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
石の雨が降った日
さて一族は、まわりの土地の様子を調べるために、物見の集団をいくつも送り出した。
彼らによれば、一族はほとんど周りを陸に囲まれた小さな海から“北の西の北“にいたが、そこから“南の東の南”には半円形に連なった島々があって、それらを渡れば、その小さな海を歩いて一めぐりできそうだった。
世界をめぐって「中つ火」へ戻ってきた者たちは、たくさんの知恵と学びの贈り物を持ち帰った。
それでもなお、我らは自分たちの生き方を誇りとし、それが続くことを願ってやまなかった。
そうするうちに世界は本当に変わり始めたのである。
しばらくの間、一族はせわしなく居場所を移した。
もし、その理由を聞けば、「今いる場所は力が強すぎて、どこかよそへ行きたいからだ」と答えただろう。
一部の者たちは山を越え、そのむこうに広がる大いなる渇きの地のはずれで暮らし始めた。
そこは、我らが好む場所ではなかったが、その者たちは戻ってこなかった。
それでも「長びと」たちは海辺で暮らし続けた。
当時は「長びと」と言っても様々な年齢の大勢の男女からなっており、それだけで一族と言えるほどだった。
「知恵」がたくさんの源からやってくるところ、そのことがよく理解されるところ、それが山手に学びの場を控えたわれらの知恵の「中つ地」であり、それは我らにとって、計り知れない価値を持っていた。
しかし世界は変わり、一部のものが強すぎると感じた力を、すべての者が感じるようになった。
空を飛ぶ者たちは、天高く舞い上がり、降りてこようとしなくなった。
鋭い牙は背中を砕かれる危険を忘れたかのように、我らの間を駆け回った。
そして万物が動き、治まりがつかなくなった。
そこで長びと達は海へ出ると、そのありさまに目を凝らした。
その時すべてが一変した。
遠い雷鳴のような音が聞こえてきた。
小さな石がその場で踊りだし、なかには丘を転がり落ちてくるものもあった。
大地が太い網にかかった鋭い牙のごとくのたうち始め、バラバラに裂けた。
一族はあまりの異変に泣き叫んだが、足元がふらついて、逃げることもかなわず、ころがり落ちる大石で押しつぶされる者もおり、誰一人として立っていることができなかった。
そうして大地が静まった時、多くの者が傷つき、魂は大地の上へと抜け出していった。
立っていた者たちも、どうしていいか分からず、石の降っている海辺に向かって走ったり、傷ついた者たちを助けて安全な場所へ運ぼうとしたりした。
異変が再び起こることは誰にも分かったからだ。
それは的中した。
大地はあえぐようにのたうち、空から石が雨のように降り注いだ。
石に当たって倒れない者はほとんどいなかった。
多くの者たちが悲鳴を上げながら山肌に倒れ伏した。
大地は揺らぎ、石が転がり、人々がうち叫んだ。
空気は雷のような音が鳴り響いて、息をすることさえできず、大石につぶされなかった者たちも、大きな轟で息がつまりそうに感じられた。
その時、一族の叫び声のかなたに、遠い音を聞きつける者たちがいた。
同時に砂地がみるみる広がって、海がすっかり退き、我らの入り江から水が消えたのである。
ある者は、大地が裂けて、海がそこへ流れ落ちたのだと呼ばわった。
しかし大地は一つであって、その中心に海が流れ込める場所などないことを知る者もいた。
そこである者は、きっと海が再び消えて氷になったのだと考えた。
ところが、広がった砂地を求めて山を降りてくる者たちから、口々に大きな叫び声が上がった。
「危ないぞ。海から離れろ。海が大きな壁になって押し寄せてくる」と。
そして人々の目の前に、身を守ってくれるはずの海が見えた。
食べ物や泳ぐ喜びを与えてくれる恵みの海が見えた。
彼らの世界の中心であるはずのその海が、怒れる山のごとく、憤れる熊のごとく、荒れ狂う嵐のごとく立ち上がったのだ。
それはすべてを踏みしだく死のように押し寄せ、「長びと」たちを、病人たちを、学び手たちを、石つぶてから身を隠そうとする者たちを呑み込んだ。
彼らをことごとく呑み込んで、また沖へ引いて行った。
そしてこの水の山から大地の山の高みへ逃げおおせた人々は、それより下にいるすべての者たちが波にさらわれていくのを、おののきながら見守った。
一瞬のうちに、我らの知恵のすべてが洗い流され、一族はこの異変に裸でまみえたのである。
(引用ここまで)
*****
人間の記憶という不思議な力に、圧倒される思いがします。
これが何の記憶なのか、わかりませんが、遠い魂の群れの姿が目の前に迫り、感動を覚えます。
 関連記事
関連記事
「ブログ内検索」で
イロコイ族 5件
ベーリング海峡 9件
などあります。(重複しています)













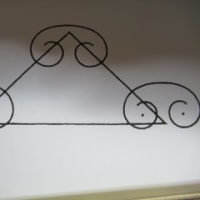


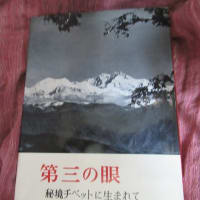








高地で奇跡的に生き残った人々の末裔は
低地に降りてきて文明の再興をはじめた
世界四大文明の突然勃興期=文明復興期
日本では縄文・弥生時代とよばれる
///様
コメントありがとうございました。
こういった記憶が語りつがれてきたとすると、驚異的なことですね。
インディアンの方々は、論争をするとき、相手の話をまるまる述べてから、反論を始める、という話もききました。
本棚や書類ケースが存在しない、文字によらない文化ですね。
>世界四大文明の突然勃興期=文明復興期
この世界四大文明と、無文字の文明がどうかかわっているのか、ということが、当ブログのテーマと言えるかもしれません。。