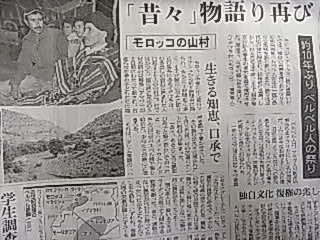
だいぶ古い記事ですが、ベルベル人という言葉を見た時、なぜか心がときめきました。
ウィキペディアによれば、1万年以上の先住民。やっぱり。
そして、まるで世界史の教科書を読んでいるかのように、西洋・中東史の始まりから存在しつづけた人々。。
「キリスト教徒にとっては、ノアの方舟が辿り着いた聖地アララト山に住んでいた人々」という意味をもつという。
彼ら西洋地域の人々にとっては、日本で感じるよりもはるかに複雑微妙な、陰影を含んだ存在なのだろうと思います。
いわゆる「消滅言語」の問題でもあると思いました。
2010年7月21日の朝日新聞の記事です。
*****
(引用ここから)
「昔々・・ 物語ふたたび・・10年ぶりベルベル人の祭り」
モロッコ・アトラス山脈の奥深い村々では、独自の言語をもつ北アフリカの先住民族ベルベル人が年に1度の祭りで民話を語り次いできた。
祭りは近代化の波に押され、10年前に途絶。
しかし村人たちは、今春文化人類学専攻の学生の協力を得て、伝統の祭りを復活させた。
現地で古老の話に耳を傾けた。
モロッコ中心都市マラケシュから約6時間車に揺られ、さらに1時間近く歩く。
4000メートル級の山並みに切り込む渓谷にあるイグブラは、むき出しの岩肌に囲まれた人口約250人の山村だ。
村ではかつて、毎年秋に周辺の5村共同の収穫祭「アマワ」が5日間にわたって催され、古老らが若者や子ども達に物語を語って聞かせていた。
その祭が久々に開かれた5月2日夜、村の広場のテントに約40人が集まった。
「昔々あるところに、漁師が息子と娘とくらしておったと。。」
モハメドさんがベルベル語で語り始めた。
少年達が熱心に聞き入る。
それはグリム童話のヘンゼルとグレーテルにちょっと似たストーリーだった。
漁師の後妻の命令で、子供たちは森に捨てられる。
機転がきく妹のおかげで2人は生き延び、人食い鬼の家で暮らす。
成長し美しくなった娘の前に、漁師がやってくる。
別の老人は、賢いネズミがライオンと戦って、人間を守る物語をかたった。
また獲物のない漁師が代わりに持って帰った蛇が子どもを噛んでしまう話も。
いずれも登場人物の失敗がかもしだすユーモアと子どもたちが学ぶべき教訓を含んでいた。
祭りには周辺の村々からも大勢訪れ、地元の歌や踊りや寸劇を楽しんだ。
今回は3日間だけの開催だった。
北アフリカに残るベルベル語は、後にこの地方の支配言語となったアラビア語とは全く異なる文法を持ち、童話や民話の形式の対話など、独自の口承文学を花開かせた。
特に民話が豊かで、村では少なくとも50本ほどの物語が伝えられている。
しかし村では出稼ぎが増えて若年層が減り、「アマワ」は途絶えた。
5年前には村々に電気が入り、テレビの衛星放送が受信できるようになったことから、民話を語る機会もめっきり減ったという。
「テレビで使われるアラビア語の会話が増え、村人はベルベル語を忘れるほどでした」と話す。
カナダ・モントリオール大で文化人類学を専攻するサラさんは2年前、多くの民話が残る地域があるとの噂を聞いて村を訪問、5か月滞在して収集に取り組んだ。
イブグラ村は無医村で、電気が通った後も水道と電話はない。
当初村人らは民話に関心を示さず、不便さばかりを訴えたという。
でもサラさんの相手をしていて初めて、村人らは「自分たちの伝える民話の価値に気づいた」と村人は言う。
「復活を主導したのは村人。彼らの熱意が伝統文化を継承させた」とサラさん。
本来は秋の収穫祭のはずが、ずれ込んで春祭りになった。
しかしイスラム教指導者として村人をまとめたモハメドさんは「時代に応じて祭りも変化して当然。
今後は「伝統文化保存」と「生活の向上」の二兎を追いたい」と話す。
・・・
独自文化、復権の兆し
ベルベル人はアラブ人の到来以前から北アフリカにいた先住民族だ。
人口は今なお約2000万人に達し、宗主国フランスなどへの移住者も少なくない。
ベルベル系の著名人としては14世紀の大旅行家イブン・バトゥータや、両親がアルジェリア出身のサッカーの元フランス代表ジダン選手らが知られる。
一部の住民の間には反アラブ意識が強く、アラブ人主導の政府と対立することもしばしばだった。
逆に政府としてはベルベル人組織を「分離主義的」として危険視したという。
モロッコではベルベル人が人口の半数近くに達すると言われる。
険しいアトラス山脈山中に住む人が多く、発展から取り残されがち。
それが逆に口承文学や音楽、踊りなど独自の文化を育むことにつながった。
オランダ・アライダデン大学のダニエラ・メローラ准教授によると、「アトラス山中のベルベル人は性におおらかで、民話や芸能でも男女関係をユーモラスに歌うものが少なくなかった。
しかし近年はアラブ化と厳格なイスラム教の浸透で、男女を分ける傾向が強くなった」という。
ベルベル語はモロッコの公共の場から排除され、話し手が減少したが、同国の民主化の進展によって近年はやや改善されているという。
メローラ准教授は村の祭り復活について「ベルベル人としての自覚を持ち、文化を後世に伝えようとする動きが強まっている」と評価している。
・・・
(引用ここまで)
*****

Wikipedia「ベルベル人」より
ベルベル人は、北アフリカ(マグレブ)の広い地域に古くから住み、アフロ・アジア語族のベルベル諸語を母語とする人々の総称。
北アフリカ諸国でアラブ人が多数を占めるようになった現在も一定の人口をもち、文化的な独自性を維持する先住民族である。
形質的にはコーカソイドで、宗教はイスラム教を信じる。
ヨーロッパの諸言語で Berber と表記され、日本語ではベルベルと呼ぶのは、ギリシャ語で「わけのわからない言葉を話す者」を意味するバルバロイに由来するが、自称はアマジグ、アマーズィーグ)といい、その名は「高貴な出自の人」「自由人」を意味する。
ベルベル人の先祖はタドラルト・アカクス(1万2000年前)やタッシリ・ナジェールに代表されるカプサ文化(1万年前 - 4000年前)と呼ばれる石器文化を築いた人々と考えられており、チュニジア周辺から北アフリカ全域に広がったとみられている。
ベルベル人の歴史は侵略者との戦いと敗北の連続に彩られている。
紀元前10世紀頃、フェニキア人が北アフリカの沿岸に至ってカルタゴなどの交易都市を建設すると、ヌミディアのヌミディア人やマウレタニアのマウリ人などのベルベル系先住民族は彼らとの隊商交易に従事し、傭兵としても用いられた。
古代カルタゴ(前650年–前146年)の末期、前219年の第二次ポエニ戦争でカルタゴが衰えた後、その西のヌミディア(前202年–前46年)でも紀元前112年から共和政ローマの侵攻を受けユグルタ戦争となった。
長い抵抗の末にローマ帝国に屈服し、その属州となった。
ラテン語が公用語として高い権威を持つようになり、ベルベル人の知識人や指導者もラテン語を解するようになった。
ローマ帝国がキリスト教化された後には、ベルベル人のキリスト教化が進んだ。
ローマ帝国の衰退の後、フン族の侵入に押される形でゲルマン民族であるヴァンダル人が北ヨーロッパからガリア、ヒスパニアを越えて侵入し、ベルベル人を征服してヴァンダル王国を樹立した。
王朝の公用語はゲルマン語とラテン語であり、ベルベル語はやはり下位言語であった。
ローマ帝国時代からヴァンダル王国の時代にかけて、一部のベルベル人は言語的にロマンス化し、民衆ラテン語の方言(マグレブ・ロマンス語)を話すようになった。
ヴァンダル王国は6世紀に入ると、ベルベル人の反乱や東ゴート王国との戦争により衰退し、最終的に東ローマ帝国によって征服された。
当時の東ローマ帝国はすでにギリシャ化が進んでいたため、ラテン語に代わりギリシャ語が公用語として通用した。
ベルベル語はやはり下位言語とされ、書かれることも少なかった。
7世紀に入ると、東ローマ帝国の国力の衰退を好機として、アラビア半島からアラブ人のイスラム教徒が北アフリカに侵攻した。
エジプトを征服した彼らは、その勢いを駆ってベルベル人の住む領域まで攻め込んだ。
ベルベル人はこの新たな侵略者と数十年間戦ったが、7世紀末に行われた抵抗(カルタゴの戦い (698年))を最後に大規模な戦いは終結し、8世紀初頭にウマイヤ朝のワリード1世の治世に、総督ムーサー・ビン=ヌサイルや将軍ウクバ・イブン・ナフィによっ
てベルベル人攻略の拠点カイラワーンが設置され、アラブの支配下に服した。
イスラーム帝国の支配の下、北アフリカにはアラブ人の遊牧民が多く流入し、ベルベル人との混交、ベルベルのイスラム化が急速に進んだ。
また言語的にも公用語となったアラビア語への移行が進んだ。
ベルベル語は書かれることも少なく、威信のない民衆言語にとどまった。
イスラーム帝国の支配下でも、ベルベル人は優秀な戦士として重用された。
711年にアンダルス(イベリア半島)に派遣されて西ゴート王国を滅ぼしたイスラム軍の多くはイスラムに改宗したベルベル人からなっており、その司令官であるターリク・イブン=ズィヤードは解放奴隷出身でムーサーに仕えるマワーリー(被保護者)であった。
ベルベル人は征服されたアンダルスにおいて、軍人や下級官吏としてアラブ人とロマンス語話者のイベリア人との間に立った。
彼らは数的にはアラブ人より多く、イベリア人より少なかった。
時とともに三者は遺伝的・文化的に入り混じっていき、現在のスペイン語にはアラビア語とともにベルベル語の影響が見られる。
またベルベル人の遺伝子もスペイン人やポルトガル人の遺伝子プールに影響を与えた。
イスラム化して以降のベルベル人はむしろ熱心なムスリム(イスラム教徒)となり、11世紀、12世紀にはモロッコでイスラムの改革思想を奉じる宗教的情熱に支えられたベルベル人の運動から発展した国家、ムラービト朝、ムワッヒド朝が相次いで興った。
彼らもイベリア半島に侵入し、征服王朝を樹立した。
これらはベルベル人が他民族を支配した数少ない王朝であったが、王朝の公用語はムスリムである以上アラビア語であり、ベルベル語ではなかった。
アンダルスに入ったベルベル人は当初、支配者はより一層アラブ化してアラビア語を話すようになり、下位の者は民衆に同化してロマンス語を話すようになった。
しかし年月がたち、改宗によってムスリム支配下の南部イベリアにおけるムスリムの全人口に占める割合が増加するにつれ、アラビア語の圧力はさらに高まり、ベルベル語話者やロマンス語話者の多くが民衆アラビア語に同化していった。
グラナダ王国の時代、支配下の人民の多くがロマンス語やベルベル語の影響を受けたアル・アンダルス=アラビア語を用いていたとされる。
ムワッヒド朝はアンダルスでのキリスト教徒との戦いに敗れて衰退、滅亡し、代わってモロッコ地域にはマリーン朝、チェニジア地域にはハフス朝というベルベル人王朝が興隆した。
マリーン朝はキリスト教徒の侵入に抵抗するグラナダ王国などのイスラーム勢力を支援し、イベリアのキリスト教勢力と激しい戦いを行ったが、アルジェリア地域のベルベル人王朝であるザイヤーン朝との戦いにより国力を一時失い、それに乗じたカスティーリャ王国により1340年にはチュニスが占領された。
しかしスルタンであるアブー・アルハサン・アリーにより王朝は一時的に持ち直し、1347年にはチュニスを奪回した。
しかしマリーン朝の復興は長く続かず、アブー・アルハサンの次のスルタンであるアブー・イナーン・ファーリスの死後は再び有力者同士の内紛で衰亡し、ポルトガル王国により地中海や大西洋沿岸の諸都市を占領された。
マリーン朝は最終的に15世紀の半ばに崩壊し、以後モロッコ地域は神秘主義教団の長や地方の部族が割拠する状態になった。
1492年にグラナダ王国が陥落すると、イベリアに居住していたベルベル系のムスリムは、アラブ系やイベリア系のムスリムとともにモリスコとされた。
モリスコは当初一定程度の人権を保障されていたが、やがてキリスト教への強制改宗によりイベリア人のキリスト教社会に同化させられ、それを拒む者はマグレブへと追放された(モリスコ追放)。
現在でもマグレブではこの時代にスペインから追放された人々の子孫が存在している。
16世紀には、東からオスマン帝国が進出した。
1533年にはアルジェの海賊、バルバロッサがオスマン帝国の宗主権を受け入れた。
1550年にオスマン帝国はザイヤーン朝を滅ぼした。
オスマン帝国の治下ではトルコ人による支配体制が築かれ、前近代を通じて、バーバリ諸国(英語版)におけるベルベル人のアラブ化は徐々に進んでいった。
今日アラブ人として知られる部族の多くは、実際はこの時代にアラブ語を受け入れたベルベル人部族の子孫である。
19世紀以降、マグレブ地域はフランスによる侵略と植民地支配を受けた。
フランス語がアラビア語に代わる公用語となり、アラブ人の一部にはアラビア語を捨ててフランス語に乗り換えるものもいたが、ベルベル人の一部も同様であった。
彼らはフランスの植民地支配に協力的な知識人層を形成し、フランス支配の中間層として働いた。
しかし一方で植民地支配に対する抵抗も継続し、このときベルベル人はアラブ人とともに植民地支配者のフランス人に対抗して、ムスリムとしての一体性を高めた。
しかし、独立後のマグリブ諸国では、近代国民国家を建設しようとする動きの中で、ベルベル文化への圧迫とアラブ化政策がかつてない規模で進められ、人口比の関係からもアラビア語を話す者が増えたため、20世紀後半にはベルベル語と固有文化を守っていこうとする運動が起こった。

wikipedia「コーカソイド」より
コーカソイドは、自然人類学における人種分類の概念の一つ。
欧州人を指すために使われてきたため白色人種、白人とも訳されるが、日照量の多い中東やインド亜大陸に居住したコーカソイドは肌が浅黒い者も多い。
コーカソイド とは、カスピ海と黒海に挟まれた所に実在するカフカース地方にある「コーカサス」(コーカサス山脈)に「…のような」を意味する接尾語のoidをつけた造語で、「コーカサス系の人種」という意味であり、インドから北西アジア(中近東)へ拡散し東ヨーロッパまで広範囲に拡散した。
元々はドイツの哲学者クリストフ・マイナースが提唱した用語であった。
彼に影響を受けた人類学者ブルーメンバッハが生物学上の理論として五大人種説を唱えた際、ヨーロッパに住まう人々を「コーカシアン」なる人種と定義した事で世界的に知られるようになった。
人類学が成立したヨーロッパは20世紀の半ばまで、ユダヤ教やそこから派生したキリスト教に由来する価値観が今以上に重んじられていた。
そのため、『創世記』のノアの方舟がたどり着いたとされたアララト山があるコーカサス地方はヨーロッパ人の起源地と考えられ、神聖視されていた(アルメニア教会に至っては聖地とされている)。
また聖典である『旧約聖書』の創世記1〜6章では、白い色は光・昼・人・善を表し、黒い色は闇・夜・獣・悪を表していた。
これらから初期の人類学を主導したヨーロッパ人学者は、自分たちヨーロッパ人を「ノアの箱舟でコーカサス地方にたどり着いた人々の子孫で、白い肌を持つ善なる人」と定義し、それを表した呼称として「コーカソイド」を用いたのである。
もっともアラブ人やペルシャ人も、宗教はアブラハムの宗教の1つであるイスラム教であり、コーカソイドという宗教用語を当てはめることもできるが、ヒンドゥー教を信仰するアーリア人は語源に合わないことになる。

関連記事

ノア 10件
消滅危機言語 3件
アブラハム 8件
などあります。(重複しています)

 関連記事
関連記事










 wikipedia「テングリ」より
wikipedia「テングリ」より
 「野生の思考」カテゴリー
「野生の思考」カテゴリー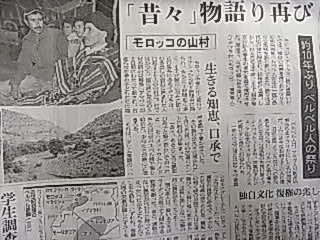

 「その他先住民族」カテゴリー
「その他先住民族」カテゴリー


 WIKI「キンブリ・テウトニ戦争」より
WIKI「キンブリ・テウトニ戦争」より 






 wikiストーンヘンジより
wikiストーンヘンジより




