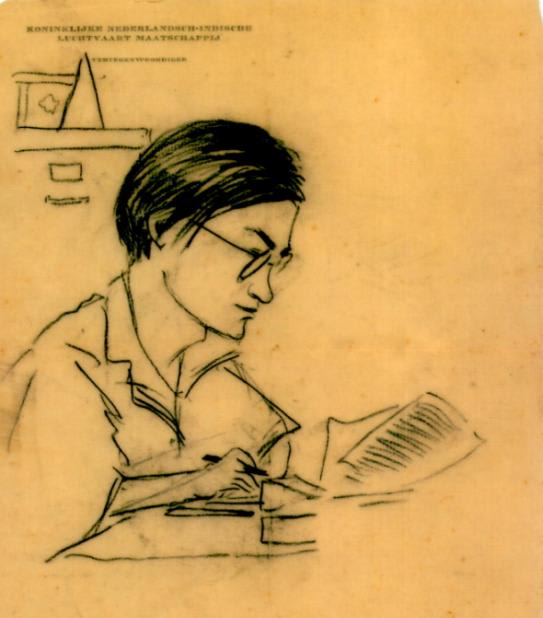このタイトルは、「天才映画詩人」と云われているタルコフスキーの遺作映画「サクリファイス」からとられています。この映画のなかで、ギリシャ正教の修道僧パンヴェの伝説が語られます。パンヴェは山に枯れた木を植えて、弟子に毎日水をやるように命じます。弟子は三年欠かさずそれを忠実に続けて、枯れ木は再生するというお話です。これを父親が幼い息子に語るのです。これは不毛なものを「希望」に変え続ける人間の意志への賛歌とも言えるのかもしれません。
柳田邦男の25歳の次男洋二郎は「犠牲」と「再生」を求めて「死」の世界を選んだのでした。この本はその息子洋二郎への心をこめた哀悼の書です。
心を病んだ次男洋二郎の自死から、医学的再生によって与えられた11日間の「脳死」の時間のなかに流れた、父親と母親(洋二郎への心労から、彼女もとうに病んでいる。この現実を受け止める力はない。)、長男賢一郎との濃密で真剣な「いのち」との会話でした。それはまた医療者と親族との「いのち」への向き合い方への真剣な問い直しだとも言えるでしょう。
柳田はこの本のなかで「二人称の死」という言葉を差し出してくる。「脳死=死」という「死が始まったところで終点とする。」という一人称から、「死が完結するまで待つ。」という「二人称の死」、つまり普通の人間の感性によって、家族、恋人、友人などが「死」を納得できる時間をおくということ。これは別の言い方をすれば「グリーフ・ワーク=悲嘆の仕事」という最も大切な、生き残された人間の時間となるはずだ。また「三人称の死」とは戦争、災害、テロなどによる見知らぬ人々の大量のいたましい死のことです。
この表題の「犠牲」には、もう一つの意味がある。どうしてもこの世では生き難い洋二郎は、自らの「死」と引き換えに「骨髄バンク」へのドナー登録をしていたことにもある。この望みは果たせなかったが、考えぬいた末に父と兄は、腎臓移植を待つ患者二名に洋二郎のいのちを託したのだった。
「脳死」「尊厳死」など、人間の「死」にはいまだうつくしい結論などはない。しかし、愛する者を「死」によって失うことの深い悲しみを救えるものはなにか?この世に生き難い洋二郎が愛読したさまざまな本のなかから、大江健三郎の言葉をお借りしてみよう。わたくしにはこれ以上は語ることができない。
「文学はやはり、根本的に人間への励ましをあたえるものだ。」
「まだいるからね。」・・・・・・・・・
(1995年・文藝春秋刊)