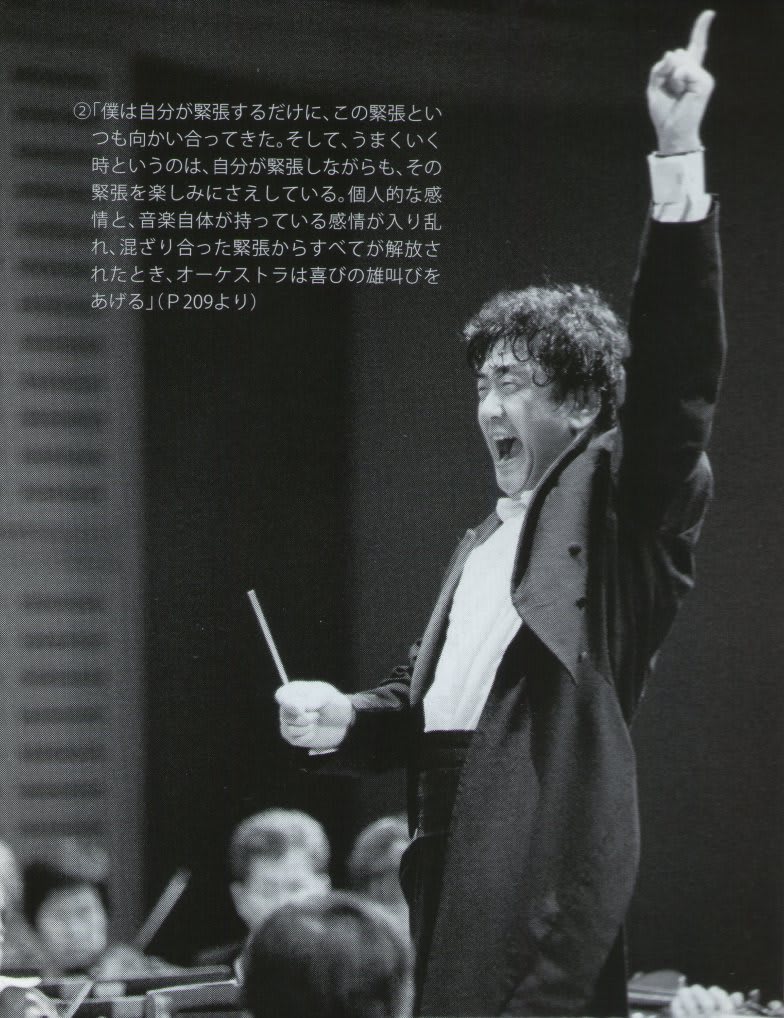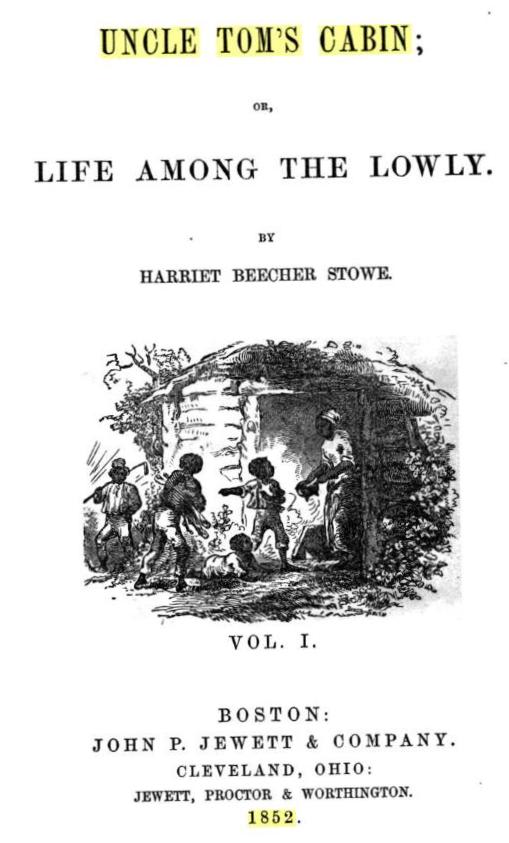
翻訳:丸谷才一
この本の再読の機会を下さった「K・Sさま」に感謝をこめて。
ハリエット・エリザベス・ビーチャー・ストウ(1811年~1896年)は、アメリカ合衆国の奴隷制廃止論者であり、
10冊以上の本を執筆した作家でもある。代表作『アンクル・トムの小屋』は奴隷の生活について描かれた物語であり、
最初は1851年から1852年にかけて、奴隷制廃止論者の団体において雑誌連載形式で発表された。
以後一貫して「奴隷制」に反対する著書を書いています。
「南北戦争 ・1861年~1865年」は、アメリカ合衆国に起こった内戦であるが、
奴隷制存続を主張するアメリカ南部諸州のうち11州が合衆国を脱退、アメリカ連合国を結成し、合衆国にとどまった北部23州との間で戦争となった。
南北戦争中の1862年にストウがエイブラハム・リンカーンと会ったとき、リンカーンがこう言ったとされる。
「あなたのような小さな方が、この大きな戦争を引き起こしたのですね。」
これと関連して思い出されるのが、アフリカ系アメリカ人の作家「アレクサンダー・パーマー・ヘイリー・1921年~1992年)です。
アメリカ沿岸警備隊のチーフ・ジャーナリストを務め、沿岸警備隊を退役後「リーダーズ・ダイジェスト」の編集主幹となった。
彼は1965年に「マルコムⅩの自叙伝」を 口述筆記で著した方でもあるが、著書「ルーツ」によって著名である。
「ルーツ」は突然拉致され、奴隷となった黒人少年「クンタ・キンテ」から3代に渡る物語である。このなかでは途中で「奴隷解放」が始まります。
しかし、働き者で信心深く心やさしい「アンクル・トム」は、売られた先での酷い仕打ちで亡くなります。この時代ではまだ「奴隷解放」はない。
「神様」と「賛美歌」がどれだけ彼の心を救い、「死」ですら恐れぬものとしたのだが、本当に神に抱かれたのだろうか?
この時代には「奴隷商人」が存在し、奴隷を買える身分の者(白人)は、その人間性によって、幾分幸せな奴隷もいたことはいましたが、
その経済力が崩壊すれば、奴隷を売るわけです。それに心の痛みを覚える者、そうではない者にわかれる。
屈強な働き者はよき商品となり、あるいは有能な技術を持った奴隷は重宝がられ、やがて工場主の「やっかい者」にされ、より悲惨な働き場所へ移される。
美しい女性奴隷は言葉にもしたくないような扱いを受け、可愛い子供の奴隷はまた別の売り方がある。
奴隷にはやさしいケンタッキー州の「シェルビー家」は経済危機に陥って、「トム」と子供を売ろうとする。
トムは黙って従うが、子供の母親は子供を連れて逃走する。そして子供の父親は自由を求めて逃走する。
(このケンタッキー州が、奴隷解放が最も遅れたところだったのでは?)
そこで、それぞれの奴隷の新しい運命が待っている。
そして、最後に「シェルビー家」の息子「ジョージ」の時代となり、おそらく「奴隷解放」が始まったのか?
あるいは「ジョージ」の考え方なのか?
奴隷は売られることもない。働いた分だけの賃金が支払われる。自由に生きることを知らない奴隷たちに、その生き方を教える。
喜びの時はきたれり
許されたる罪人たちよ、家路につけ
「アンクル・トム」の死、残された妻や子の悲しみ……その上に訪れた「喜びの時」なのだ。
(1993年・河出書房新社・世界文学の玉手箱-11)