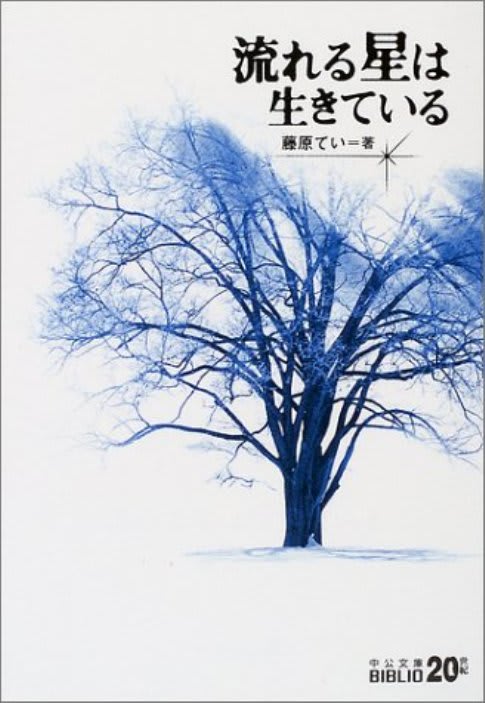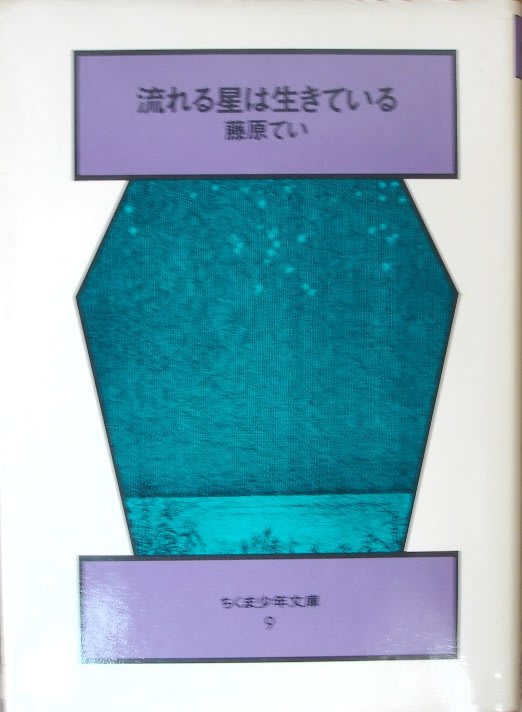36項目、各分野からの書き手によって、それぞれのテーマで構成された1冊です。そのなかから2項目について書きます。
(満州事変 日本の侵略なのか? 福田和也)より。
『当時の日本経済のあり様からして、日本は満洲を手にしても、何も出来ずに放りだすのではないか、と欧米各国は見ていた。ところが石原のブレーンである経済学者の宮崎正義や新官僚の代表格である岸信介は、満州をごく短期間のうちに、アジア屈指の工業国に変えてしまった。』
山室信一氏の『キメラ 満洲国の肖像』を読んだ後で、ここを読みますと、ちょっと驚きました。日本が侵略した満洲国ではありますが、そこに日本が残してきたものを評価するという側面があります。そう言えば、父も「満鉄は日本人がすべて帰国してしまったら、動かせなかった。」と言っていたことを思い出しました。また父は敗戦後、家族を連れて満州の哈爾浜から新京へ移動し、引揚げまでの期間、中国人の電気公司で働いていましたが、引揚げが決まって、日本人がすべていなくなったら、公司が立ち行かなくなるので、一番若い独身の日本人技術者が残ったという話を聞いた記憶がありました。「侵略」には違いないのですが、日本人の優れた技術はそこに残されたのかもしれませんね。(でも、侵略したことを美化する材料にはなりませんでしょう。)
(引揚げ 満州からの帰途になにが? 藤原正彦)より。
簡略して書きますと、正彦氏の母上である藤原ていの小説「流れる星は生きている」に書かれているように、父上(新田次郎)と別れて、1945年8月9日、母子4人だけで満洲の新京から無蓋貨車に乗り、北朝鮮の宣川まで。さらに馬糞の堆く積もった貨車で南朝鮮の開城へ。そこで母上は気を失った。米軍の日本人難民テントへ。さらに釜山へ。そこからやっと引揚船に乗り、博多へ。9月12日だった。新京脱出から1年1ヵ月経っていました。
さて、我が父は1945年8月13日に所属していた部隊ごと、哈爾浜から釜山へ引込線の列車に乗せられ、運ばれたが、哈爾浜に残した家族を置いて帰国できないと、釜山から逆戻りの命がけの2ヵ月の旅をしました。そして哈爾浜で家族が全員揃ったところで、冬は酷寒となる哈爾浜を離れて、新京へ南下しました。新京での引揚までの日々は前記の通りですが、命の危険は当然ありましたでしょう。(私は乳飲み子でしたので、記憶がありませんが。)
以下は父のメモから引用。(父は引揚の時には団長を務めました。)
『待ちに待った引揚げの許可が下りた。出発は1946年8月25日正午、ということだった。出発に先立って貨車を下見しておこうと、その数日前数人で出かけた。指定された貨車は無蓋車で1両50人の割り当てだった。真夏なので直射日光を遮蔽するため、みんなで日除けを作ったり、トイレを作ったりして出発の日を待った。
(ここに、藤原正彦氏の書かれた現実との大きな違いがありますね。)
8月25日昼過ぎ、列車は静かに動きだした。さらば新京!終戦の日から1年と10日、私たちが新京に来てからちょうど10ヶ月――長くつらい生活の終わりだった。
8月28日、葫蘆(コロ)島着。ここで3日待たされ、8月31日アメリカの貨物船で葫蘆島を出帆した。3日後の9月3日の夕方、船は博多港に入った。検疫のためあと6日間は上陸できない。9月9日の朝、上陸が許され全員無事日本の土を踏んだ。そして引揚げ者宿泊所に一泊し、下着、衣類の支給を受け、一同さっぱりした気持で「解団式」に臨んだ。私は妻子4人を連れて東海道線で東京へ、上野から東北線で小山へ、小山から妻の里へ着いた。時に1946年9月12日、忘れもしないこの日は私の36歳の誕生日だった。』
ここまで私事を長々と書きましたのは、ほぼ同じ時期に同じようなところで藤原正彦氏のご家族と、私達は、クロスしていたのですね。私達には父がいてくれたことが一家を支えたのだと強く思いました。1946年9月12日という共通点も忘れないでしょう。
……というわけで、2項目についてしか書けませんでした。
半藤一利氏の書かれた「ノモンハン事件」「昭和天皇」、柳田邦男氏の「零戦」、水木しげる氏の「戦場の兵士」など、納得できるものでした。
水木しげる氏は、文末をこのように結んでいました。
『私の子供のころは、男の子はみな兵隊になるのが憧れだった。日清、日露と戦争に連勝して、日本の全国民が戦争は儲かるものだという奇妙な錯覚を持ち、軍人が威張りたいだけ威張るようになってしまったのである。それが間違いのもとだと考えている。』
(2009年 第一刷 文春新書711 文藝春秋社刊)