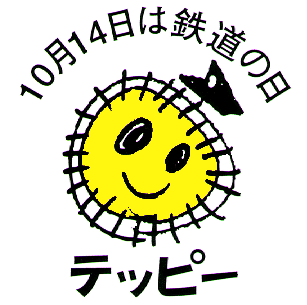平成の成人式 昭和の成人式
旗日、成人の日。
今年は成人式会場における、あの聞きたくもないアホの集団がバカ騒ぎするニュースが、聞こえてこなかったのをホッとしている。
と、57年前に成人式を迎えた大先輩が云っている。
昭和38年。戦後のどん底を抜け出し、自らの将来に少しの希望と光を感じ始めた頃に成人式を迎えた。
初めて自分で買ったスーツの上下。靴はおふくろが、当時のお隣さんだった靴屋さんで誂えてくれた足にぴったりのピッカピカ革靴。
気持ちは、何が何だかわからないまま「兎に角、男の大人として、行動に責任を持つ。働き、稼ぐ。」という単純な決意に燃えていた。のかな?
青年団の中心的年令にさしかかり、戦没者慰霊盆踊りだの、素人演芸会だのと、必死に駆けずり回る新成人だった、のかな?
酒の力を借りて人に迷惑をかけるなど、全く考えられもしない。ある意味、余り面白くない二十歳の出発だったような。
どっちにしても、「働かざる者食うべからず」。どうかすると「貧乏人は麦を食え」に、負けてたまるかであったような。
成人式に臨んで、大人にもなりきれてない輩が、単に酒を呑んで、人の迷惑顧みず大声張り上げたり、式そのものをぶっ壊すなどというお粗末は、その当時はなかった。
そんなことが許されるほど世間は甘くなかった。そんな輩が当時いたら、爪弾きにされ、厄介者扱いの汚名を着せられたものだ。
要するに、警察や官庁が大目に見てくれても、世間は許してくれなかった。だからどうだ!それがよかったのか?ウーンどうじゃったんじゃろう。
少なくとも、数年前の、荒れる成人式が当たり前のような『世間への甘え』はなかった。生きることへの必死さと、ひもじかった子供時代を覚えていたから。
その一方で、18歳から成人扱いとされる世の中。大丈夫なの?逆に22歳から成人と認める、という方が、今時の子供には会っているような気がするけどな~。
いずれにしても、少子高齢化は進むばかり。少数精鋭の時代を生き残れる成人になってくれることを願いたい。
他人のためじゃないよ。自分のためだよ。