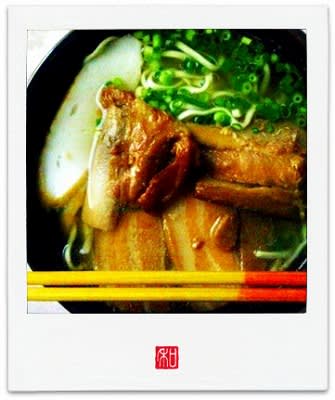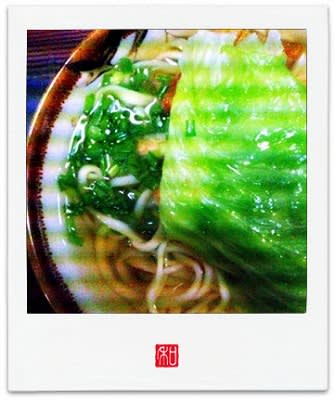先日行った本島最北巡り。
最大の目的はココ!
琉球七嶽の1つ、「安須森御嶽(あすむいうたき)」に登ること!
安須森御嶽は辺戸(へど)にある辺戸岳のことで、
鋭く切りたった岩山全体が聖地なのです。

安須森は琉球開闢(かいびゃく)の第一のポイントで、
天から降りたアマミキヨ(アマミク・阿摩美久)が最初に作った聖地。
(ちなみに以降、今帰仁の金比屋武→知念グスク・斎場御嶽(★ ★)→藪薩の浦原→玉城グスク(★ ★)→クボウ御嶽→首里森御嶽・真玉森御嶽と続く)
クボウ御嶽も訪れたことはありますが、高校生の時なんで写真はなし。
そのワイルドさと壮大さに惹かれ、
いつか行ってみたいと思いつつ約2年、やっと訪れることができました!

2年も待ったのは、
さすがにひとりでは行かないほうがいい場所だからです。
特に標高が高いとか樹海があるというわけではありませんが、
ご覧の通り、安須森は急斜面の崖があちらこちらにある岩山。
登山のためのロープや鎖はあるものの、
足場は決して良いとは言えず、
雨天時はもちろん、雨上がりなど湿気の多い日でも足元が滑り、非常に危険です。
気軽に観光・ハイキング気分で行くような場所ではありませんので、
経験者と一緒に行くことをおススメします。

↑写真で撮った登山道。
でもコレ、まだ写真撮る余裕があったトコです。
本気でギャー!ってなったトコはとにかく必死で
写真撮る余裕なんてないですからね。
高所恐怖症なワタシ……がんばりました!


ロープの状態や足元を確認しつつ、
(ゆるんだり切れてたり、岩がぐらぐらしてる場所もあり)
ゆっくり登って約20分。
頂上に近づいて来たころにぽっかりと開いた洞窟が。
黄金洞(くがにがま)です。

歪曲した岩の層が太古浪漫を駆り立てます。
さあ、頂上まであとわずか。
(ってか、ここからが1番怖かった…ので写真なし )
)
そしてそして・・・

やっとたどり着いた頂上360度パノラマ!
ひゃ~!
しかも、下界(笑)ではどんより曇り空だったのが
みるみる青空に!
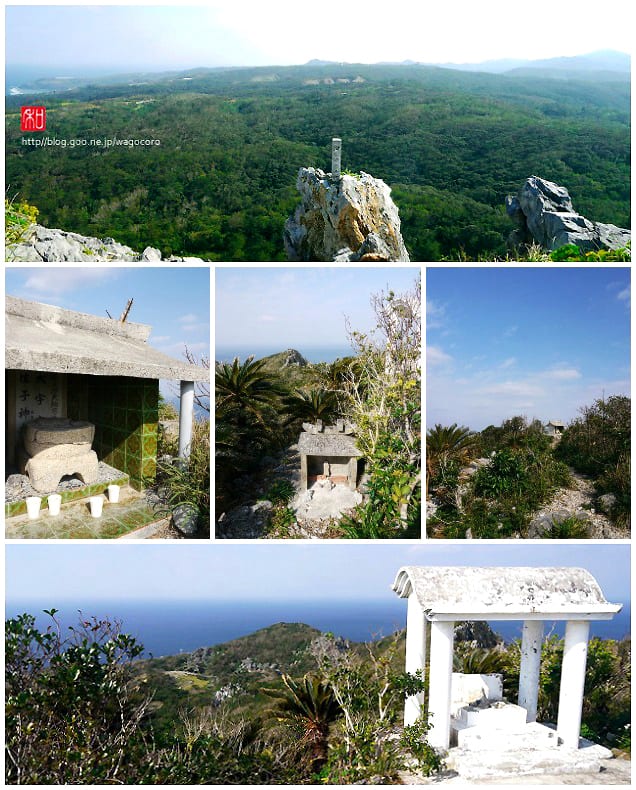
頂上にあった祠たち。
…一体どうやってこれらの石材やコンクリを運んだんだろう…。
恐るべし信仰心。

これでもなだらかな方の崖です。
(反対方向の崖は90度。今思い返しても脚がすくむ… )
)
柵はありません。
座り込んで高さと足場に気持ちを慣らすことしばし…(笑)
さあ、アマミキヨが見た雄大な景色を味わおう

↑クリックすると拡大します
北西…くらいかな?

↑クリックすると拡大します
北東あたり。

本島最北端、辺戸岬が見えます。
(なお、トップ写真は辺戸岬からみた安須森御嶽)

辺戸岬アップ。
安須森御嶽は今回登った場所だけじゃなくて
連なっている所も含めて安須森。
今回登った場所は宜野久瀬(シヌクシ)嶽。

右から「シヌクシ嶽」「アフリ嶽」「シチャラ嶽」、「イヘヤ」
(…たぶんあってるはず)
ただしこの「イヘヤ」だけは安須森には入らないらしく、
今は観光地になってます(→大石林山)。
ちなみに、アフリとは「涼傘(りゃんさん)」のことで、
アフリ嶽にキンマモン(キミテズリ)が降臨(!)した時、
涼傘が山を覆った(笠雲)という記録もあるそうです(「琉球神道記」)。
神秘的ですね~

琉球第一の聖地、安須森御嶽。
いい経験させていただきました
(めっちゃ充実感と達成感 )
)
実際に登った時はもう十分 って思ったけど、
って思ったけど、
今度はもっと緑がいっぱいの時にとか、
アフリまで行きたいかもとか、
さらに思ってしまうワタシなのでした
ええ、筋肉痛抜けるのに2日かかろうとも!(笑)
*参*
『琉球古道』(上里隆史著)
『琉球王国ぶらぶらぁ散歩』(おおきゆうこう・田名真之著)
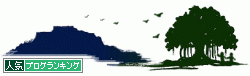
今日もご訪問ありがとうございます。
ぽちっとクリック応援してくれたら嬉しいです★
















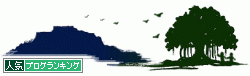

























 で周ればあっと言う間なんだけどネ。
で周ればあっと言う間なんだけどネ。






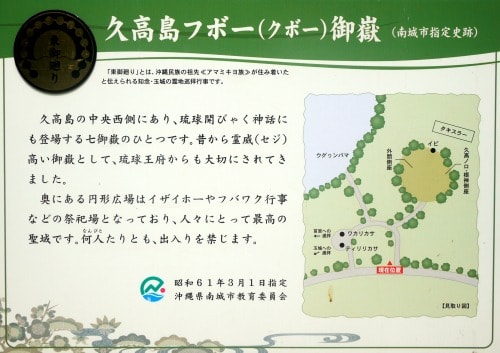


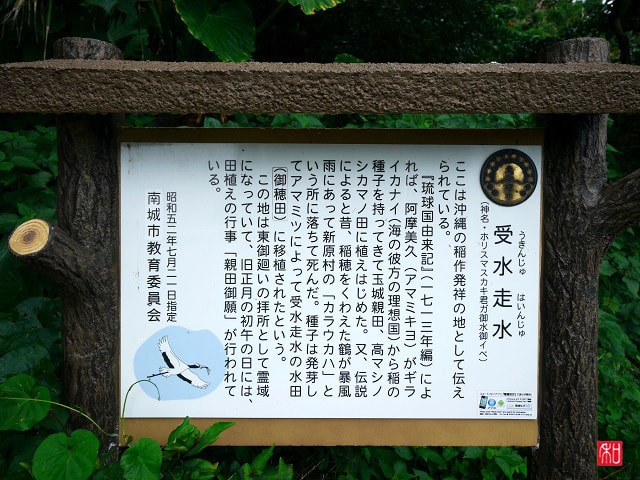














































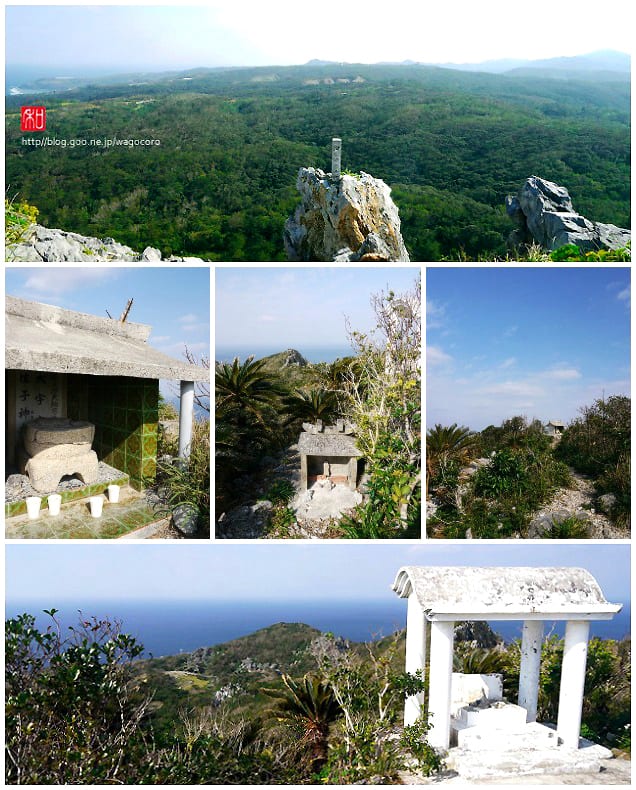

 )
)