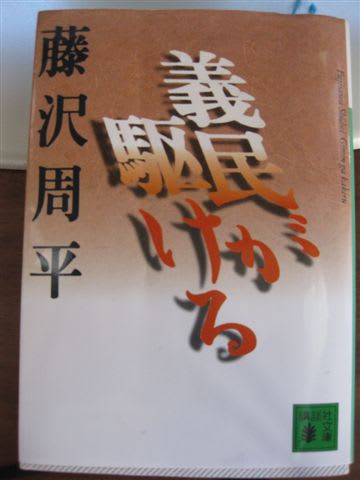岩木山の標高は1,625m。八甲田山の最高峰は八甲田大岳1,584mである。昨日「東北の日本百名山」の番組を見ていて、安達太良山は1,700mだった。
わたしはずっと八甲田山の白きたおやかな峰々を見ながら、岩木山よりも八甲田山の方が標高が高いと思い続けていた。しかし岩木山が県内最高峰だと知ったのは、先日の八甲田山へ出かけた時だった。自分の思い込みの間違いは、こうしてみれば結構あるものだとふと思う。
2000m以下の山々は、高さだけが魅力ではない。低山には澄み切った渓流や滝の美しさがある。岩魚や山女魚などが生息している。渓谷や巨木の森に踏み入れば森林浴も楽しめるし、バードウォッチングで心も和む。湿原では高山植物やルリイトトンボなどの昆虫もたくさん生息している。春や秋には山菜も楽しめるし、何より四季それぞれの楽しみ方があるのだ。
お金をそんなにかけなくても健康のそばにある、低山トレッキングは初老期の私向きかなと思うこの頃である。
錦色に身をまとった岩木山が、これから徐々に白い衣装を着替え始める。私達の生活も、それに合わせて冬ならではの暮らしに身を慣らしていくのだ。
わたしはずっと八甲田山の白きたおやかな峰々を見ながら、岩木山よりも八甲田山の方が標高が高いと思い続けていた。しかし岩木山が県内最高峰だと知ったのは、先日の八甲田山へ出かけた時だった。自分の思い込みの間違いは、こうしてみれば結構あるものだとふと思う。
2000m以下の山々は、高さだけが魅力ではない。低山には澄み切った渓流や滝の美しさがある。岩魚や山女魚などが生息している。渓谷や巨木の森に踏み入れば森林浴も楽しめるし、バードウォッチングで心も和む。湿原では高山植物やルリイトトンボなどの昆虫もたくさん生息している。春や秋には山菜も楽しめるし、何より四季それぞれの楽しみ方があるのだ。
お金をそんなにかけなくても健康のそばにある、低山トレッキングは初老期の私向きかなと思うこの頃である。
錦色に身をまとった岩木山が、これから徐々に白い衣装を着替え始める。私達の生活も、それに合わせて冬ならではの暮らしに身を慣らしていくのだ。