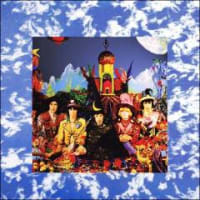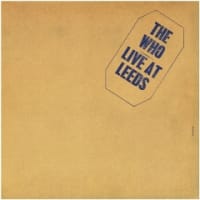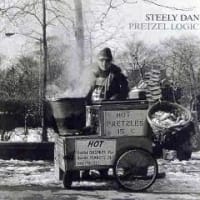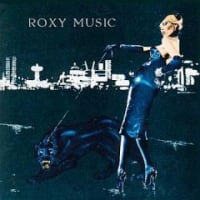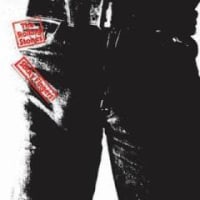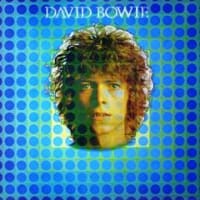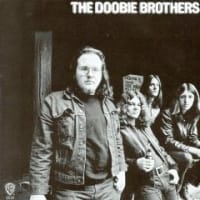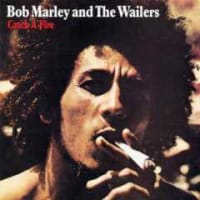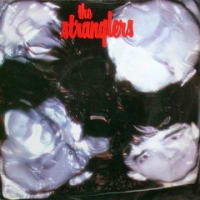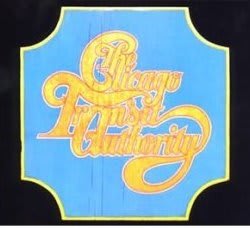
実はこの作品に関しては随分以前に一度レビューを書いているのだが、昨年、輸入盤であるがシカゴのボックスCDを手に入れた。無論、シカゴの作品は殆どがアナログレコードであり、アナログを再生出来るシステムは実家のオーディオ・ルームにしかないから初期の作品はかなり長いこと聴いていなかった。このボックスは10枚組で、シカゴⅠ~Ⅲはアナログでは2枚組だったがCDでは1枚に収まっている。そしてシカゴⅤ~Ⅷ、Ⅹ、Ⅺ、「ホット・ストリート」の10枚組である。Ⅳは「アットカーネギーホール」というアナログでは4枚組のライヴアルバム、Ⅸはベストアルバムなので、その2セットは除いてある。こんな豪華なCDボックスがなんと3000円で販売されていたら、普通は買うだろう、という訳であの、シカゴの往年の名作のデジタル版の取得に成功した(笑)。
しかし、いつ聴いてもこのシカゴのファーストアルバムは素晴らしい。いや、勿論、シカゴの良さはファーストだけではないが、この「ブラス・ロック」という特有の世界を切り開いたのは、BS&Tと共に大きな功績であるし、筆者は不思議とシカゴだけに填ってしまったのも事実。多分、それだけシカゴは自分に取ってリアルタイムな時代が並行していたのだからかもしれない。またこの作品の特徴として、ブラスセクションが前面に出ているというオトの重厚さもさることながら、このバンドには当時ロックという音楽の定義のひとつでもあった「社会性」というものを極めて前面に押し出していたことも事実である。ロックが所謂黒人音楽に対してその独自性を貫くひとつの要因として、アナーキーニズムはある種必要な素因であったが、一方でポップス、つまり大衆に向けた流行音楽のパーセンテージが多くなってくると同時に、ロック音楽もその使命感が徐々に薄れていった部分は事実であり、例えばその象徴はウッドストックなどに見られる「愛と平和」という半ば抽象的で、かつ非現実的な方向性への示唆になってしまったのは60年代末の傾向であった。そんな中にあってこのシカゴの作品は実に衝撃的であったが、今、改めて聴きなおすと、それはとても計算されていた事に気がつく。まず、この楽団編成によって可能な「音作り」である。当時は気がつかなかったがシカゴの編成は、はじめに編成ありきではなく、この音楽を如何にセンセーショナルに大衆に伝えるかを考え抜いて作られた編成であったこと。当時、ビートルズやストーンズによってロック音楽は既に確立していたし、それは10年前の1950年末と比べて、異常な進化と、大衆を惹きつけるに十分なほど魅力的な音楽に変わっていたこと。つまり、同じ土壌では、大衆にアピールができなかったことである。また、この2枚組というのも大変意味があって、アナログでいうC・D面が、彼らの「論調」である。しかし、いきなりそんな社会性を主張したら、当時の耳の肥えた音楽ファンには敬遠される。だから、A・B面において、そのブラス・ロックの迫力と、ビートルズにも並ぶメロディアスな内容でリスナーを注目させることに成功したのである。この試みは成功し、シカゴはいきなりメインストリームに踊り出ることになる。そして4枚目の作品までは、まさに怒涛の勢いで音楽ファンを注目させるのである。
ところで、アルバムは”Chicago Transit Authority”、所謂「シカゴ運輸局」というユニット名で発売されたのであるが、これに関しては同名のバス会社から法的訴訟を受けた為、結果、彼らは次の作品から「シカゴ」と名乗るようになった。バンド名は短い方が覚え易く、結果的には良かったのだと思う。
こちらから試聴できます