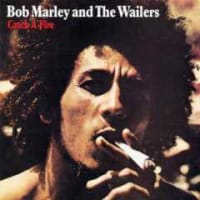ポリスというバンドはとても不思議で、また興味があるのは、作品を出すたびにその音楽傾向が変わっていることである。いい見方をすればアルバムという作品を大事に考え、それぞれの中で完結をさせていること、で、逆に悪い見方をすれば、その度に方向性がかわるバンドとして、要は一定性がない、ポリシーがないという言い方もできる。勿論、私は彼らの大ファンで、多大なる影響を受けたミュージシャンのひとつであるから、当然後者だとは思っていない。で、前者なのであるが、果たしてバンドという括りで考えたときその共通観念が崩壊したときには、間違いなく解散という道を辿るであろうということは、当然の事、物の道理である。そして(結果論になって恐縮だが)この作品を聴いた際に、私はこのバンドに次の作品発表があるのかどうかは実は大変疑問であった。この作品は次に「シンクロニシティー」という途轍もない大作・名盤が控えているので、今になってはその通過点という評価になっているが、この発表段階においてはポリスの最高傑作であったことは間違いなく、しかしながら但しそれは、ロックという音楽の範疇での可なり高度な音を出しているという意味においてであって、バンドの面白さという点、音楽の好き嫌いという観点からいえば、やはり、ファーストアルバムの「アウトランドス・ダムール」は超えられない。
前述したが、だからこの作品は意外に一般的には評価が高くない。ポリスファンには「シンクロニシティー」の序章にしか過ぎないというどちらかというと肯定派と、いや、この音楽性の大きな変更は全く解せないという過去の作品と比較すると一番中途半端な位置づけに首を傾げる否定派の両極端に分かれると思われる。つまり敢えて断言はしないがこの作品はポリスファンなら「一番好きなアルバム」だとは言わない。もしポリスの作品の中でこの作品が一番好きだという人がいたら(勿論、そういう人が居たって良い)その人はポリスファンではないし、ポリスファンだと言われるのなら、他の作品をもう一度全部聴き直して欲しいと思う、そういう位置付けの作品なのである。勿論、最初の3曲は個人的には大好きだ。特に、"Spirits in the Material World”と"Invisible Sun"は、前作までは整理されていなかった音をきちんと纏めた感が強い。ポリスの魅力のひとつに退廃的な音と、一方でそれを蘇生させる期待感を感じさせる組み合わせがあるが、それが、前作の、例えば"Don't Stand So Close to Me"などでは蘇生が中途半端に終わっていたのを、この曲はきちんと終着させている。この辺りがニューウェイヴのミュージシャンの中にあって、彼らが決してインテリジェンスが高いだけでなく、音に対しての拘りと責任を持って自分たちの音に自負を持っているところである。しかし"Every Little Thing She Does Is Magic"はその極みな曲である一方で、シングルチャートで全米3位まで上がったことは驚きでもあるが、大ファンとしては戸惑いの方が多い。そして圧巻は"Demolition Man"であろう。この6分近い大作(ポリスの楽曲は長い曲が殆どなく、実はこの曲が一番長い)は、そもそもスティングがジャマイカ出身の女性レゲエ・ミュージシャンでもありモデルでもあるグレイス・ジョーンズに提供した曲であるが、全くアレンジをかえてこの作品でセルフカバーしたもの。単調なロックのメロディという感じでもあるが、実に当時のポリスというバンドの位置づけを表している気がしている。実はこの辺りの作品を聴いて、私が前述した「ポリスって次の作品があるのかな」って思ったのである。当時の音楽界において、彼らは一体、何処に軸足をおいて、なにを訴求しようとしているのか、私がもっとも気になった曲であり、同時に、この後の曲にもそれを感じながら、なんとこの作品は終わってしまうのであった。
敢えていえば、もしかしたらポリスはわざとこのアルバムの曲の並びをそうしたのではないかと思うのは、明らかに前3作とはその辺りの拘りが違うからである。ジャケットも3人を記号化したもので、無論この背景にあるのは機械文明である。しかし敢えてそのテーマを掲げている訳ではない。単にファーストアルバム以来ずっと3人の顔を載せてきた、その流れだけである。そんなある意味で「尻切れ蜻蛉」なアルバム発表に当時の私は次作への期待を持てなかった焦燥感を、実はこの作品を聴く度に蘇らせてしまうのである。
こちらから試聴できます