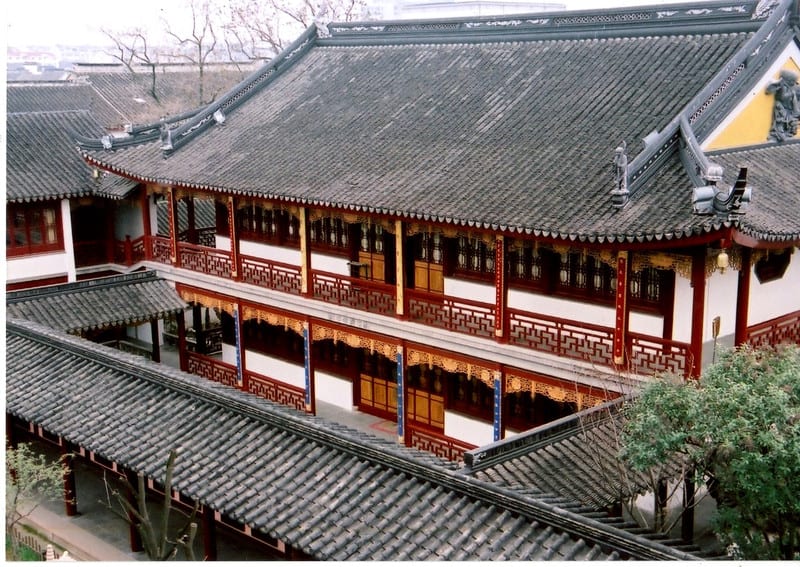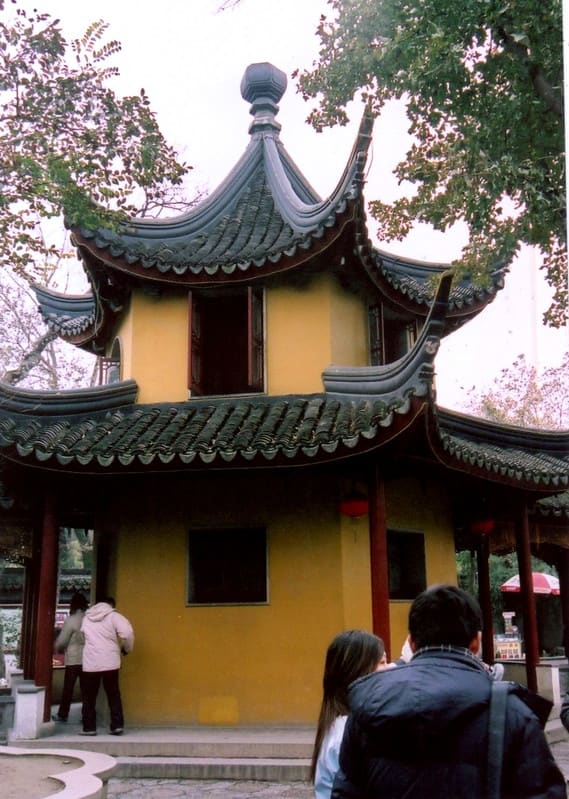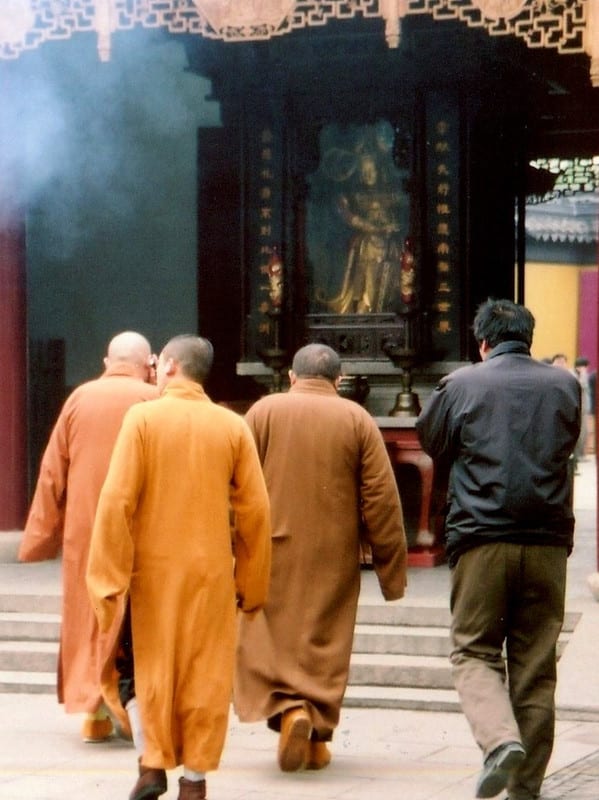図書館から借りていた、葉室麟著 「銀漢の賦(ぎんかんのふ)」(文藝春秋)を読み終えた。本書は、江戸時代、老中松平定信が治世していた頃の、著者創作の北九州あたりの小藩月ヶ瀬藩を舞台にした長編時代小説である。藩主と家老の確執、藩内の権力争い、政争に巻き込まれた人々、日下部源五、松浦将監、十蔵、三人の男の友情のあり方と顛末、小藩の新田開発の意味、松浦家の美人姉妹志乃、みつを巡る人間関係とそれぞれの思いの交錯等々、様々な切り口が絡み合いながら巧妙に展開する、読み応え有る作品だと思う。
(注)2007年に、第14回松本清張賞を受賞している作品。

▢主な登場人物
日下部(くさかべ)源五・さき、たつ、
松浦将監(しょうげん、岡本小弥太、松浦月堂)・みつ、享(すすむ)、三五郎、伊藤重輔、
十蔵・たみ、蕗(ふき)、
松浦兵右衛門、志乃、みつ、
岡本弥太郎・千鶴、小弥太、
藤森吉四郎
津田伊織・たつ、
藩主浅川惟忠(これただ)・惟孝、山崎多聞、
磯貝駒右衛門、辻勘五郎、
松本五郎右衛門、
鷲巣角兵衛、鷲津清右衛門、稲葉又兵衛、
九鬼夕斎(九鬼大膳)
老中松平定信、柴野栗山
谷文晁(谷文五郎)
▢あらすじ・感想等
物語は、家老である松浦将監(小弥太)が、郡方の日下部源五の案内で、月ヶ瀬藩と隣藩森岡藩の国境、風越峠を訪れ、すでに絶縁状態になって久しい源五に、「源五よ、わしは間も無く名家老どころか、逆臣と呼ばれることになるぞ」と、つぶやくところから始まっている。
源五が、苦い感慨とともに、少年時代から回想していくという構成になっている。
日下部源五と岡本小弥太が始めて出会ったのは、貫心流の磯貝駒右衛門の道場だった。源五と小弥太が道場で知り合ったその日に、笹原村の百姓十蔵とも知り合いになり、三人は、友としての絆を深めていくが、やがて、小弥太は、松浦家の養子婿に入り、家老職にまで上りつめていき、ある時を境に、それぞれ絶縁する事態に至るのだった。
源五、小弥太、十蔵の三人が、まだ13~14歳だった頃、一緒に、祇園神社と呼ばれる高原神社の夏祭りに出掛け、満天の星空を見上げ、その時、小弥太がなにげなく、「知っておるか、天の川のことを銀漢というのを」と言う。
宋の詩人・蘇軾の「中秋月」
暮雲收盡溢清寒
銀漢無聲轉玉盤
此生此夜不長好
明月明年何處看
の一節、「銀漢声無く玉盤を転ず」から用いたものだが、本書の最後の段階で、著者は、源五に、「銀漢とは、天の川のことなのだろうが、頭に霜を置き、年齢を重ねた漢(おとこ)も銀漢かもしれんな」と語らせている。
少年時代に、身分差を超えて友となった三人の男達だったが、成人後は、あることを契機に友であることを断絶して、それぞれの生き方をとる。幾星霜の果てにも心の友としての絆が絶えてはいなかった。著者は、この物語の底流を表象するのに、「銀漢」という言葉を選んでいるのだった。
源五は、普請組五十石の家の子で、鉄砲衆を経て、新田開発指導の群方という役目の下級武士だったが、小弥太も少年時代は、普請組七十石の家の子だった。小弥太の父親弥太郎は、江戸で側用人だったが、何者かに斬殺され、岡本家は半知となり、母親千鶴とともに国に戻ってきていたのだった。
家老となった将監と藩主浅川惟忠との確執、儒学者で側用人の山崎多聞の画策、幕閣の一員に入りたい一心の藩主惟忠、国替えを推し進める幕府の裏の理由とは?
源五に、上意討ち?、暗殺?、命令、・・・、家老松浦将監に、隠居命令?
先の家老九鬼大膳を失脚切腹に追い込んだ将監だったが、追い込まれている?
月ヶ瀬藩に何が起ころうとしているのか?、
将監は、命を賭ける・・・、
源吾の腹は決まる・・・。
山中の死闘・・・、
すべてが収まって、命が繋がった源五は、すっかり荒れ果てた九鬼大膳(夕斎)の隠居所だった鷹島屋敷の屋敷番となった。夕斎が死んだのは、20年前、松浦将監もこの夏死んだ。
「将監も、もうこの世にいないのか」、
襲う寂しさ、孤独感。ふっと、茶室に、女中、蕗(ふき)が入ってきた。
「わしは、なにも聞いておらんぞ」・・・・・、
「小弥太よ、そちらへ行くのは、十年ほど遅れるぞ、勘弁せい」
月は耿々と輝いている。