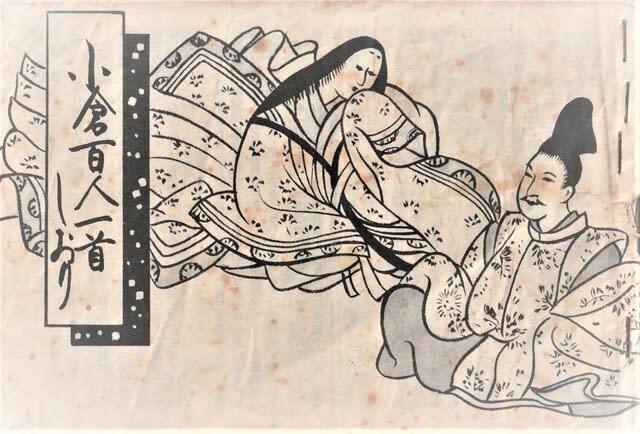gooブログの「アクセス解析」の「アクセスされたページ」欄を、時々覗くことがある。「アクセス数」を気にしてでのことではなく、すっかり忘れてしまっているような、随分前に書き込んだ古い記事にアクセスが有ったりするのを、楽しみにチェックしている風なのだ。
そんな記事に目に止まった瞬間、「エッ、こんな記事にアクセス?」と驚くと同時に、「そう言えば・・・・」、記憶が蘇り、つい、自分もクリックし、改めて読み返してみたりしているのだ。
「gooブログ」=「記憶力がまるで無くなっている爺さんの自分のための記憶補助ツール」と決め込んでいる爺さんには、「アクセス解析」もまた、便利で有難いツール、大いに活用しているという次第。
5年前、2019年1月に、ブログ・カテゴリー「懐かしいあの曲」に書き留めていた記事、「明日に架ける橋」にアクセスが有ったことに気が付いた。
「おお!、懐かしい!」・・、早速、コピペ、リメイクすることにした。
そんな古い記事を、クリックひとつで引っ張り出して読んだり、加筆、訂正、修正、コピペ、リメイク等が出来るのも、ブログのメリット。従来の紙ベースの日記、日誌、備忘録、懐古録、雑記録の類では、絶対考えられないことであり、ブログを始める前までは、想像も出来なかったことである。今、出来ることは、やってみる・・、長生きした分、その時代を少しでも享受したいものだ等と、つぶやきながら・・・。
「明日に架ける橋(Bridge over Troubled Water)」(再)
雪の能登半島からは、懸命に安否不明者の捜索救助活動が続けられている様子や、被災された方々の避難生活の窮状等々が、刻々と伝わってきており、心痛むばかりだが、そんな時に、ふっと思い浮かんだ曲が有る。
「明日に架ける橋」だ。
困難に直面した時の慰めとなる曲として聴いている方も少なくないのではと思う。
今更になってネットで調べてみると
「明日に架ける橋(Bridge over Troubled Water)」は、1970年(昭和45年)に、ポール・サイモン作詞・作曲、アート・ガーファンクル リード・ボーカルで発表された、サイモンとガーファンクル(Simon & Garfunkel)の楽曲。
当時、よくラジオ等から流れていて、耳に馴染んだ曲のひとつだ。
数多のアーチストにカバーされ、スタンダード・ナンバーになっており、日本でも、尾崎紀世彦や森山良子等が歌っていた。
「明日に架ける橋」・サイモンとガーファンクル (YouTubeから共有)