
8年ぶりの四日市・・
四日市市立楠中学校区学びの一体化全体研修会でした。
こども園、小学校、中学校の先生方が約40名の参加です。
お世話をしてくださった山上先生は、わたしの現職の頃からのお付きあいで、前任校の大池中学校区の研修会も呼んでくださってました。
四日市は8年で転勤が決まっているとのこと、8年間で学校で実績をつくって、校区に広げていくというきっちりとした仕事をしておられます。
今日の研修のお題は「不登校の子どもたちへの支援」ということでした。
ここ3年ほど全国的には2万人ずつ増えている不登校ですが、一向に減る気配を見せていません。
現場のほうも大変なことだと感じるのですが、今日は「主体的」と「対話的」というワードを軸にしてワークショップをしました。
先生方のふりかえり、すごいです。
これだけのものが返ってくるには、実践の基盤があるからでしょうね。
ロールプレイングのお相手をしてくださった吉田さん、お疲れ様でした。
リモートの練習からの本番でしたが、よく演じていただいたと思います。
気づきを参加のみなさんでシェアしていただいて、もう一歩成長してみませんか。
***
| いじめ・不登校を防止する人間関係プログラム | |
| 深美隆司 価格:¥ 2,000(+税) | |
| 学事出版 |
| 子どもと先生がともに育つ人間力向上の授業 | |
| 深美隆司 価格:¥ 1,800(+税) | |
| 図書文化社 |
あいあいネットワーク of HRS
ホームページURL:http://aiainet-hrs.jp


















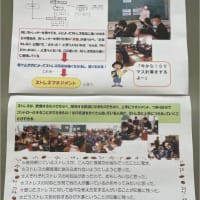






質問していただいた言葉のなかに答えがあるように感じます。「言葉」で伝えたり、表現したりできないわけですから、そのひとつひとつの「言葉」を大切にしてあげてみてはどうでしょうか。「訊いて聴く」ということは非常に大事です。今日のロールプレイングは実はそうなんですね。なぜ?と訊いて、そのフィードバックを聴く、ということですね。さえぎったり、否定したり、話題を奪ったりするのは依存的なコミュニケーションであり、マウントを取ろうという姿なのですね。「訊いて聴く」をくりかえしてあげれば、自然とコミュニケーションの力がついてきます。手間がかかってめんどくさいかもしれないですが、一度試してみてください。
大人の中で出勤できなくなる大人が増えてきていると感じています。本日の学びを活かしていけると良いなと思っています。
主体的の反対にある依存的なことと比べることにより、主体的のイメージがはっきりしました。そして、人間関係プログラムの構成もよく分かりました。
そして、否定のモデルと肯定のモデル、私メッセージとあなたメッセージの違いなど、私の中で「なるほど」と思えました。
いじめ・不登校のメカニズムを分かりやすく、楽しく理解できました。これらのことを、これから生かしていきたいと思います。
ありがとうございました。
昨日、アクティビティのファシリテーションについて話したところだったので、自分にとってもタイムリーなお話だった。子どもたちが自己との対話をさせる時間を学校でもっと作っていかなくてはならないと感じた。
キャベツの歌…お父さんから始めなくても…あと、中指立てるのもめちゃめちゃ抵抗ありました…アイスブレイクとはわかっていても、これから始まることに一抹の不安がよぎりました。でも、いい意味で不安を裏切ってもらいました。ありがとうございました。
また、不登校の子どもたちの内面を理解できたように思いました。
小学校の低学年のうちから、対話の仕方を丁寧に支援しながら、保護者や家庭環境を知ることも大切だとかんじました。
貴重なお話をありがとうございました。
不登校やいじめの被害者になりやすい人と加害者になりやすい人は表裏一体なのだということがわかった。そのため、言葉のかけ方一つで人の気持ちも変わるし、自分の心に余裕をもつこともできる。悪い面が目立つと、そこばかり気になってしまうことがあるが、自己の内面と現れが乖離しないような接し方を自分自身も心がけると同時に、児童にも身につけていく力であると学んだ。
中学校区で、頭を悩ませてせいる問題である不登校ですが、小学校から中学校へのつなぎの部分が気になっています。学校種の違いから、子どもたちへの接し方の違い、指導法の違いがあるのだろうかと想像はするのですが、教員の日々の多忙さを目の当たりにすると。なかなか情報共有をできていないのが現状です。
課題は、子どもたちが連続して、安心して学び続けられることではないかと考えています。
主体的と依存的の対比、受身的と攻撃的の共存にはなるほどと思いました。
ありがとうございました。
人間関係では攻撃的・受身的の両面があり、誰かを攻撃して自分を保つという仕組みができているという部分は自分自身や目の前の子どもたちにも思い当たるところがありました。また最後には、自分自身と向き合うことを通して、他者と向き合うということを改めて感じ、これまでの自分を考えるきっかけとなりました。
研修の中では、一つ一つの言葉が持つ意味を考えたり、言い換えの言葉や同じイメージの言葉を探したり、なんとなく理解した気になっていることがたくさんあると感じ、印象深かったです。今日はありがとうございました。
そのためには、自分の気持ちを安定させて、生きていくことが必要。
自分に対話、共感してもらえる人に対話が大切
不適応を起こしている人に「どうしたん?」と聴ける自分でありたい。
人との関わりや対話を楽しめる人生でありたい。
社会が完全に成熟しているとは、思えない。これから、社会に出る子どもたちには、指示にも従える柔軟さも身につけさせたい。
時代の変化にも合わせ、子ども達の事を大切に考えていきたいと思います。
ペアやグループでの話し合い、劇なども加えていただき、とてもわかりやすかったです。
加点法でやっていきたいと思います。
とても良い刺激を受けました。
自分の頭の中でモヤモヤしていた、「どこまでレールを引いて、どこから自分で走らせるか」というのが、依存と主体という言葉で論理的に説明されて整理されてスッキリした研修でした。
生徒保護者だけでなく、私の周りにいるいろんな人とアサーティブなコミュニケーションをとれるようになりたいと思ったと同時に、まずは自分自身が主体的にならなければならないと気づくことができました。
そして、鏡を使った場面で、自己との対話の重要性になるほどなぁとなりました。
色々な気づきをありがとうございました。
生徒の姿を思い起こしてみると、依存的な生徒が多くいます。それに対して、こちらも否定的な言葉をかけがちですが、そうするとより依存的で攻撃的な生徒を生み出しかねません。そのような生徒にこそ、自らが主体的なモデルでありたいと思いました。今日はありがとうございました。
相手の言葉を繰り返すことは普段からなんとなく実行していました。が、そんな効果があったのかと改めて知ることができ嬉しく思いました。
1学期、苦手に感じていた生徒についても、相手を受け入れるところからもう一度頑張ってみようとおもいました。
ありがとうございました。
また、自分は減点法で子どもを見ていたように思います。今後、加点法で子どもの姿を捉えられるようにしたいと思いました。
貴重なご講演ありがとうございました。とても楽しく、学ぶことができました。
訊くつなぐもどすの授業の在り方を追究したいと思います。
最後のロールプレイが印象的でした。
①くりかえす
②共感する
③主張する
④選択する
のアサーションが大変勉強になりました。
コミュニケーション術ですね。
トレーニングします。
今日は本当にありがとうございました。
質問ですが、まだまだ言葉でうまく伝えたり、表現したりできない子たちには、どんなことを大事にしていけばいいでしょうか。
ありがとうございました!
不登校の背景を時代の流れと共に説明してもらい、やっぱり今残っている指導スタイルは時代や子ども達に合っていないと思いました。
アサーションはまた授業で子ども達とやっていこうと思います。学力の前にコミュニケーションや自分がしんどくならないための方法を身につけておくことは、すごく大事で普段の生活から学べていない子が多いので、授業でやることの重要性を改めて感じました。
自分もアイメッセージ使っていきたいです!
家では妻に対しての共感をあまりしていないので反省。
好きなことは、美味しいものを求めて旅に出ることです。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏休みは給食がないので毎年体調を崩します。
趣味…漫画を読む、お風呂に行く
この夏にやりたいこと…筋トレをしてお腹をかっこよくする
先日、インターハイのバスケットを観ました。思わず身体が動いてしまいました。