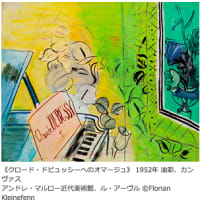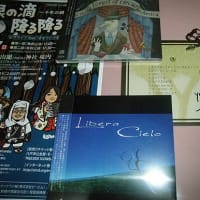※ネタばれあります。これからごらんになる方はご注意ください。
マイティ・ハート/愛と絆
(1部略)実在のジャーナリスト、ダニエル・パールの妻が著した手記を映画化した社会派ドラマ。事件の真相、夫への愛をつづった原作に感銘を受けたブラッド・ピットが製作を務め、妊娠しながらも懸命に夫を捜す妻をアンジェリーナ・ジョリーが熱演する。監督は、『グアンタナモ、僕達が見た真実』のマイケル・ウィンターボトム。その衝撃と感動のドラマは第60回カンヌ国際映画祭で絶賛され、大きな話題を呼んだ。
あらすじ: 2002年のパキスタンで、ウォールストリート・ジャーナルの記者ダニエル(ダン・ファターマン)は、妻マリアンヌ(アンジェリーナ・ジョリー)とディナーの約束をした後、ある取材に出かける。しかし、それを最後に彼との連絡は途絶えてしまう。妊娠中のマリアンヌと友人たち、地元警察などによる懸命の捜索が開始されるが……。
実は、私は、この映画の予備知識ゼロで試写会参加しました。
なので、結末を知っていて観た人たちとは、全然違う視点で映画を観たことになります。
家に帰って反芻している時&この記事を書くのに、検索してる時に
確かにこの事件の報道を聞いた記憶があることを思い出した、そんなレベルです。
(関係ないですが、ネットのおかげで、こうした観賞系の楽しみ方に幅がでたなぁ、と今思ったので、書き留めておこー)
観たあとに、ダラ子様としゃべっていて、
「こういう報道は、耳にしても、結局非日常だから残らないんだね」とか
「戦争ジャーナリストはどこかで死を覚悟をしているだろうから・・・」
という話などをしたのですが、深層心理をのぞきこむと、ヒトゴトでよかった、と思ってる自分に出会います。映画として観れる観客サイドでよかった、と。
海外の方々はテロリストの卑劣さへの憤りを感じられ、この映画で、テロ撲滅への思いを強くされるのかもしれません。
が、私が思ったのは「日本が今の戦争やテロ行為から少し距離をおいた立場のままいて欲しい。」という非常に短絡的にしてエゴな感想でした。
映画そのものは、あふれかえるような情報の嵐で、人物の名前も関係性も流れのままガンガン登場して、優先順位等関係なく描かれていきます。だから、観てるとなにがなんだか「どうなってるの?これって誰?どういう関係」な部分も多い。また、顔がみんな似てるので味方・敵の判断すらつきにくいシーンも・・・。(記憶力のないあっしだから余計か?・汗;)、が、それはそれで緊迫感・生々しいリアル感を生んでいると思います。ドキュメントともまた違う、空間・時間の再構成で、手法としては実験的だけど、この混沌さ、私はけっこう好きかも。
誘拐事件って多かれすくなかれ、誘拐された家族側からみたらこんな感じなのかな、と思えました(家族には知らされない情報、マスコミの騒ぎ方やねつ造等々)。
いや、見終わった時、「これはもう観ないだろうな」と思ったのですが
2日たって、「結末を知った上で、もう1度観てみたい」に感想が変わったのは、映画の混沌さのおかげかも。1つの実験映画として観る価値があると思います。
個人的にはちょっと違和感あるシーンもありますが、
(テロとか戦争の映画でいつも感じる、最近はアニメですら感じる、どうしようもない欧米人ならではの生活スタイルというか意識のようなもの・・・彼らには戦争被災者とは違って、帰れる場所があるのだな、という。)
妊婦役のアンジェリーナの描き方に、プラピの「愛」を感じた映画でした。
テロ・・・。個人のしあわせ・正義と、国民のしあわせ・正義と、世界のしあわせ・正義は全部「層」が違う。でも個人レベルでしか実感できない。日本の立ち位置が、今はまだテロ対策の援助的ポジションであること。でもけっこう高確立で標的にされる立場でもあること。そしてもし家族や知人がそうしたテロ行為で命を落としたら・・・。そして事実、決して対岸の火事ではなく、いろんなレベルで影響は確実にある。意識はしておかなければ。
そんなことを考えたり・・・。
テロ特措法が期限切れ インド洋給油部隊に撤収命令(朝日新聞) - goo ニュース
インド洋で海上自衛隊が補給活動を行う根拠となってきたテロ対策特別措置法が2日午前0時(現地時間1日午後7時)で期限切れとなった。石破防衛相は1日午後、海自の補給艦「ときわ」と護衛艦「きりさめ」に撤収命令を出し、両艦船は日本に向け出発した。01年12月から6年近く続いた給油活動は、活動再開のめどが立たないまま中断に入った。
マイティ・ハート/愛と絆
(1部略)実在のジャーナリスト、ダニエル・パールの妻が著した手記を映画化した社会派ドラマ。事件の真相、夫への愛をつづった原作に感銘を受けたブラッド・ピットが製作を務め、妊娠しながらも懸命に夫を捜す妻をアンジェリーナ・ジョリーが熱演する。監督は、『グアンタナモ、僕達が見た真実』のマイケル・ウィンターボトム。その衝撃と感動のドラマは第60回カンヌ国際映画祭で絶賛され、大きな話題を呼んだ。
あらすじ: 2002年のパキスタンで、ウォールストリート・ジャーナルの記者ダニエル(ダン・ファターマン)は、妻マリアンヌ(アンジェリーナ・ジョリー)とディナーの約束をした後、ある取材に出かける。しかし、それを最後に彼との連絡は途絶えてしまう。妊娠中のマリアンヌと友人たち、地元警察などによる懸命の捜索が開始されるが……。
実は、私は、この映画の予備知識ゼロで試写会参加しました。
なので、結末を知っていて観た人たちとは、全然違う視点で映画を観たことになります。
家に帰って反芻している時&この記事を書くのに、検索してる時に
確かにこの事件の報道を聞いた記憶があることを思い出した、そんなレベルです。
(関係ないですが、ネットのおかげで、こうした観賞系の楽しみ方に幅がでたなぁ、と今思ったので、書き留めておこー)
観たあとに、ダラ子様としゃべっていて、
「こういう報道は、耳にしても、結局非日常だから残らないんだね」とか
「戦争ジャーナリストはどこかで死を覚悟をしているだろうから・・・」
という話などをしたのですが、深層心理をのぞきこむと、ヒトゴトでよかった、と思ってる自分に出会います。映画として観れる観客サイドでよかった、と。
海外の方々はテロリストの卑劣さへの憤りを感じられ、この映画で、テロ撲滅への思いを強くされるのかもしれません。
が、私が思ったのは「日本が今の戦争やテロ行為から少し距離をおいた立場のままいて欲しい。」という非常に短絡的にしてエゴな感想でした。
映画そのものは、あふれかえるような情報の嵐で、人物の名前も関係性も流れのままガンガン登場して、優先順位等関係なく描かれていきます。だから、観てるとなにがなんだか「どうなってるの?これって誰?どういう関係」な部分も多い。また、顔がみんな似てるので味方・敵の判断すらつきにくいシーンも・・・。(記憶力のないあっしだから余計か?・汗;)、が、それはそれで緊迫感・生々しいリアル感を生んでいると思います。ドキュメントともまた違う、空間・時間の再構成で、手法としては実験的だけど、この混沌さ、私はけっこう好きかも。
誘拐事件って多かれすくなかれ、誘拐された家族側からみたらこんな感じなのかな、と思えました(家族には知らされない情報、マスコミの騒ぎ方やねつ造等々)。
いや、見終わった時、「これはもう観ないだろうな」と思ったのですが
2日たって、「結末を知った上で、もう1度観てみたい」に感想が変わったのは、映画の混沌さのおかげかも。1つの実験映画として観る価値があると思います。
個人的にはちょっと違和感あるシーンもありますが、
(テロとか戦争の映画でいつも感じる、最近はアニメですら感じる、どうしようもない欧米人ならではの生活スタイルというか意識のようなもの・・・彼らには戦争被災者とは違って、帰れる場所があるのだな、という。)
妊婦役のアンジェリーナの描き方に、プラピの「愛」を感じた映画でした。
テロ・・・。個人のしあわせ・正義と、国民のしあわせ・正義と、世界のしあわせ・正義は全部「層」が違う。でも個人レベルでしか実感できない。日本の立ち位置が、今はまだテロ対策の援助的ポジションであること。でもけっこう高確立で標的にされる立場でもあること。そしてもし家族や知人がそうしたテロ行為で命を落としたら・・・。そして事実、決して対岸の火事ではなく、いろんなレベルで影響は確実にある。意識はしておかなければ。
そんなことを考えたり・・・。
テロ特措法が期限切れ インド洋給油部隊に撤収命令(朝日新聞) - goo ニュース
インド洋で海上自衛隊が補給活動を行う根拠となってきたテロ対策特別措置法が2日午前0時(現地時間1日午後7時)で期限切れとなった。石破防衛相は1日午後、海自の補給艦「ときわ」と護衛艦「きりさめ」に撤収命令を出し、両艦船は日本に向け出発した。01年12月から6年近く続いた給油活動は、活動再開のめどが立たないまま中断に入った。