まだ、猛暑が残っていた今年の9月23日土曜日、宮崎レコード音楽愛好会好会代表の田中さんに誘われて、小林市のお医者さんを訪問することになった。その家庭にある蓄音機で音楽を聴くということであった。こちらに蓄音機を借りてきて、みんなで聞いたほうがいいのではないかと、提案したのだが、それは出来ないという。たかが、蓄音機でレコードを聴くために、一日を費やして小林市に出かけることもないと、断っていたのだが、再度、いっしょに行こうよ、ぜひ聴いてほしいと言われて承諾したのだった。戦前、我が家にも一台蓄音機はあったし、20年代の始めころは、高校の演劇部や文学部のクラブ活動で、蓄音機で音楽を聴いた記憶は残っている。だが、その蓄音機でのベートーベン「運命」は、ぼくらにどんな風に聴こえたのか、そんな記憶はもう喪失してしまった。戦前、宮崎市でも蓄音機によるクラシック鑑賞会は、文学同人やいわゆる文化人たちのの間では行われていたが、いったいかれらが聴いたという蓄音機のクラシック音楽は、現在聴いてみて、聴くに堪える音質を奏でることが出来たのかどうか、この疑問は、ぼくのなかで燻っていたので、こんどは承諾して田中さんに連れて行ってもらうことにしたのであった。
案内された部屋は、医院とは独立した別棟の居住宅で、その家屋に特別に接続され音楽室であった。そこは20畳くらいのホールであった。そこで分かったのは、このお医者さんは、蓄音機の持ち主でもあったが、なによりも、田中さんたちと同じ同好の士、真空管アンプの製作者であった。そのアンプでレコードを聴く鑑賞者であった。壁には数千枚のレコードジャケットが長さ5メートルほど天井まで収納されていた。その向かいの壁には、さまざまの真空管や、基盤、変圧機、導線や部品、棚の中にはいろんな工具もそろえられていた。正面に、ドイツの大ホールで使用されていたという人の背丈ほどあるタンノイとかなんとかいう名の大スピーカが2台左右に間をおいて据えられている。その真ん中に蓄音機が据えられ、米国製という蓄音機は、こちらの胸くらいまであり、レコードを回す筺体からは、巨大なにラッパが聳えていた。これらを目にしただけて、お医者さんは、そこらにはないマニアックなアンプ愛好者であること、理解できたのである。そばにあっった新聞の取材切抜きを読むと、小学生のころから、家にあった蓄音機やアンプのレコード音楽に魅了され、今日、つまり80歳ちかくまで、レコード音楽に惹かれてきたという記事も目に付いた。レコード音楽と再生アンプは、生涯の伴侶であったわけである。そこまでのめりこんだ、いやのめりこめる音楽の再生とは、なんなのか、その音楽を今日、聴こうとしはじめているのだという緊張感にぼくは包まれだした。すでに蓄音機の印象も変わっていた。かくも大きい蓄音機があったのだという事実を知らされたのだ。だが、まずは、真空管アンプで、レコードを聴くことになった。
アンプにスイッチが入ると、20センチほどもある剥き出しの真空管の内部に赤い光が灯った。お医者さんの製作で、1球16万円!!かかったという。これが左右の大スピーカのまえに一個づつある。2球だけで32万円、そのほかもろもり全体の値段は、桁が違うのだ。これだけの金をかけて、どんな再生が可能なのか。興味は深まってきて、耳をそば立てた。レコード音楽は室内楽弦楽四重奏であった。曲名も知らなかった。音、つまり音楽演奏が両脇の巨大スピーカーから流れ出しだした。はっとというか、思わず注意が向いたというか、すぐに気づいたのは、それぞれの楽器の位置が分かったことだ。そのうちに楽器でなく演奏者の位置が分かり、その気配も感じられる。そして、このホールの正面は、パリかベルリンか、そんな異国の演奏室内が、まざまざと感じられてきだしたのだ。それにもまして、演奏者が弾いている息のようなものまであるようなきがしてくるのであった。これはまさに驚くべき体験であった。始めに期待した高音がいいとか、低音が効いているとかの域ではなかった。演奏している奏者の気配があらわれたのであった。さらに、後で思い出して興味があるのは、このとき、ぼくをつつんでいた感性は、室内楽の存在、その曲の芸術性、つまり音楽鑑賞であるよりも、このレコードの再現している音楽演奏という「気配」の出現であった。その後、歌劇や交響曲、バイオリンやピアノを聴いたのだが、この室内楽の再生音の臨場感は感じられず、鮮明な音楽としてのみ聴くことができた。それはまさに快適な音楽再生である。言ってみれば、ぼやけてない写真をみる快感である。アマのデジカメ写真にくらべてプロの写真であるということを感じさせられたのである。
こういう体験をしたあと、蓄音機は、なにを訴えるのか、にわかに興味は倍加しだした。さて、ここで注意してほしい。蓄音機には、音量スイッチはないということだ。音を大きくしてたり小さくして聴いたり、まして低音を効かしたり、高音を効かしたりなどはできないことである。ラッパ型の集音器からあふれる音量で聴くしかない。音がぼやければ針を代え、手巻きのハンドルでばねを巻いてスピードを調節するしかない。電流は流れていないことである。これでレコードからどんな音を、ここではクラシック音楽を楽しむことができるのかだということになる。そこで、聴いたのは、バイオリンの独奏、オペラの一部、オーケストラ、なかんずくシューベルトの歌曲であった。それが結構聴けたのである。ああ、これなら、昭和の初期のころ、旧制高校生らが、クラシック音楽を、蓄音機で堪能できたことも想像できるのであった。お医者さんの蓄音機は大阪の中古市場で仕入れることができたといい、蓄音機時代のビンテージのシゲッティのバイオリンレコードなどで、音がいいということもあろうが、家庭用の蓄音機でもかなりの音楽を楽しめたと思えるのであった。そこで、最後で聴かしてもらったのが、昭和20年代末期に録音されたという美空ひばりのレコード一枚、6万円だったという貴重品だった。その歌声は、まさに10代の彼女であったし終戦当時の楽器の質の悪さまで伝わってきて、焼け跡の匂いまで漂ってくるノスタルジーがかんじられたのである。蓄音機から流れ出した音楽は、最高級の自家製真空管アンプから流れ出した音楽とは、また別の世界であった。蓄音機によるレコードの再生音は、針と集音機という物理的作用以外になにもないということで、こういう音をだすとしかいいようがない。音の波長を録音し、その波長を、逆方向にそのまま音にもどしたということで、録音の物理的振動の再生にもっとも忠実なのかもしれない。これだけで、有効だったのだということは、感動を生むのでもあった。
さて、ここまでで、ぼくはひとつの興味ある事実に気づかされた。生涯を通してのレコード音楽の再生アンプの追求とは、どういう意味を持つのかということである。どこまで行ったら満足の位置に達せられるのかという、疑問である。これから先はぼくの頭の中の仮想実験になる。以下のべていこう。
案内された部屋は、医院とは独立した別棟の居住宅で、その家屋に特別に接続され音楽室であった。そこは20畳くらいのホールであった。そこで分かったのは、このお医者さんは、蓄音機の持ち主でもあったが、なによりも、田中さんたちと同じ同好の士、真空管アンプの製作者であった。そのアンプでレコードを聴く鑑賞者であった。壁には数千枚のレコードジャケットが長さ5メートルほど天井まで収納されていた。その向かいの壁には、さまざまの真空管や、基盤、変圧機、導線や部品、棚の中にはいろんな工具もそろえられていた。正面に、ドイツの大ホールで使用されていたという人の背丈ほどあるタンノイとかなんとかいう名の大スピーカが2台左右に間をおいて据えられている。その真ん中に蓄音機が据えられ、米国製という蓄音機は、こちらの胸くらいまであり、レコードを回す筺体からは、巨大なにラッパが聳えていた。これらを目にしただけて、お医者さんは、そこらにはないマニアックなアンプ愛好者であること、理解できたのである。そばにあっった新聞の取材切抜きを読むと、小学生のころから、家にあった蓄音機やアンプのレコード音楽に魅了され、今日、つまり80歳ちかくまで、レコード音楽に惹かれてきたという記事も目に付いた。レコード音楽と再生アンプは、生涯の伴侶であったわけである。そこまでのめりこんだ、いやのめりこめる音楽の再生とは、なんなのか、その音楽を今日、聴こうとしはじめているのだという緊張感にぼくは包まれだした。すでに蓄音機の印象も変わっていた。かくも大きい蓄音機があったのだという事実を知らされたのだ。だが、まずは、真空管アンプで、レコードを聴くことになった。
アンプにスイッチが入ると、20センチほどもある剥き出しの真空管の内部に赤い光が灯った。お医者さんの製作で、1球16万円!!かかったという。これが左右の大スピーカのまえに一個づつある。2球だけで32万円、そのほかもろもり全体の値段は、桁が違うのだ。これだけの金をかけて、どんな再生が可能なのか。興味は深まってきて、耳をそば立てた。レコード音楽は室内楽弦楽四重奏であった。曲名も知らなかった。音、つまり音楽演奏が両脇の巨大スピーカーから流れ出しだした。はっとというか、思わず注意が向いたというか、すぐに気づいたのは、それぞれの楽器の位置が分かったことだ。そのうちに楽器でなく演奏者の位置が分かり、その気配も感じられる。そして、このホールの正面は、パリかベルリンか、そんな異国の演奏室内が、まざまざと感じられてきだしたのだ。それにもまして、演奏者が弾いている息のようなものまであるようなきがしてくるのであった。これはまさに驚くべき体験であった。始めに期待した高音がいいとか、低音が効いているとかの域ではなかった。演奏している奏者の気配があらわれたのであった。さらに、後で思い出して興味があるのは、このとき、ぼくをつつんでいた感性は、室内楽の存在、その曲の芸術性、つまり音楽鑑賞であるよりも、このレコードの再現している音楽演奏という「気配」の出現であった。その後、歌劇や交響曲、バイオリンやピアノを聴いたのだが、この室内楽の再生音の臨場感は感じられず、鮮明な音楽としてのみ聴くことができた。それはまさに快適な音楽再生である。言ってみれば、ぼやけてない写真をみる快感である。アマのデジカメ写真にくらべてプロの写真であるということを感じさせられたのである。
こういう体験をしたあと、蓄音機は、なにを訴えるのか、にわかに興味は倍加しだした。さて、ここで注意してほしい。蓄音機には、音量スイッチはないということだ。音を大きくしてたり小さくして聴いたり、まして低音を効かしたり、高音を効かしたりなどはできないことである。ラッパ型の集音器からあふれる音量で聴くしかない。音がぼやければ針を代え、手巻きのハンドルでばねを巻いてスピードを調節するしかない。電流は流れていないことである。これでレコードからどんな音を、ここではクラシック音楽を楽しむことができるのかだということになる。そこで、聴いたのは、バイオリンの独奏、オペラの一部、オーケストラ、なかんずくシューベルトの歌曲であった。それが結構聴けたのである。ああ、これなら、昭和の初期のころ、旧制高校生らが、クラシック音楽を、蓄音機で堪能できたことも想像できるのであった。お医者さんの蓄音機は大阪の中古市場で仕入れることができたといい、蓄音機時代のビンテージのシゲッティのバイオリンレコードなどで、音がいいということもあろうが、家庭用の蓄音機でもかなりの音楽を楽しめたと思えるのであった。そこで、最後で聴かしてもらったのが、昭和20年代末期に録音されたという美空ひばりのレコード一枚、6万円だったという貴重品だった。その歌声は、まさに10代の彼女であったし終戦当時の楽器の質の悪さまで伝わってきて、焼け跡の匂いまで漂ってくるノスタルジーがかんじられたのである。蓄音機から流れ出した音楽は、最高級の自家製真空管アンプから流れ出した音楽とは、また別の世界であった。蓄音機によるレコードの再生音は、針と集音機という物理的作用以外になにもないということで、こういう音をだすとしかいいようがない。音の波長を録音し、その波長を、逆方向にそのまま音にもどしたということで、録音の物理的振動の再生にもっとも忠実なのかもしれない。これだけで、有効だったのだということは、感動を生むのでもあった。
さて、ここまでで、ぼくはひとつの興味ある事実に気づかされた。生涯を通してのレコード音楽の再生アンプの追求とは、どういう意味を持つのかということである。どこまで行ったら満足の位置に達せられるのかという、疑問である。これから先はぼくの頭の中の仮想実験になる。以下のべていこう。











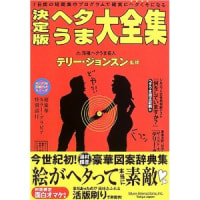












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます