新年の1月があっと終わった。今年の元旦は、宮崎駅前の東西に700メートルの大通りがメインストリート橘通りと交わる十字路交差点、そのまわりに並ぶ山形屋、ボンベルタ、カリーノのデパートを核にした周辺の市街地を歩き回る気分を失っていた。出て行ってもおもしろくないからである。正月の雰囲気は、ここ5年くらいの間で根こそぎ消えていってしまったからだ。5年前に山形屋に隣接したところに黒木製茶のお茶の喫茶店があった。元旦3日は、ウエイトレスも和装で、文字通りお茶を運んでくれた。琴の音の流れる室内には、まさに元旦があった。急須のお茶もお湯も、後は自分でお茶を点てて味わえる。このお茶喫茶は、無料であった。正月だけでなく、いつでも無料!!なのだ。お茶は販売されていたが、購入を勧められることもない。
ぼくは、一年ほどよく通ったのだが、有料にすべきだと、いやして欲しいと、頼んだが有料にはならなかった。2年ほどして、ウエイトレスのサービスは無くなって、自分でお茶を点ててということになり、ここでかなりお茶のいれかたを習うことができたのだが、2回目の元旦を迎えたころ、閉店になってしまった。無料であろうと、有料であろうと、閉店はたぶんさけられなかったろう。なにしろ来客は信じられないほどすくなかったからだ。黒木製茶は、こことは別にもう一店、同じ喫茶店を船塚町方面に開店していた。e-Chafeという店名でChafe カフェを茶フェにしたのであろう。吹き抜けの2階で、ビュッフェの版画や具体美術の武谷武判の鉛筆の抽象ドローイングが掲げられていた。室内は、水を打ったように静寂で、装飾も無駄なくきまっていた。外からみるとなんでもない建物だが、室内は外観の平凡さとは想像もできない非凡な凝りようであった。お茶といっしょに添えられたお菓子が、店から発注して作らせたものとかであり、こだわりが感じられた。300円であった。土曜の午後は、もはやぼくの定石となった座席で、本読みに通った。ここも5年ほど前に閉店してしまった。お茶にこだわる意識が、大衆に及ばなかったのだ。このようなこだわりの店は、自分で探し出すほか、なかなか目に付かないのだろう。
喫茶店といえば、コーヒーだけを専門とする喫茶店で、薄暗い室内にクラシックが流れて止まないというような昔風の喫茶店は、絶滅危惧種であろうが、まだ生きつづけている店もひっそりと市街のあちこちと、生息している。ほどんど息を潜めたような凍りついた姿がいい。ふと、思い出して5年ぶりに大淀の宮交シティ・ダイエーデパートの北の路地横町にある喫茶店「if」を訪ねてみた。もう無いと思ってきてみたら、なんと現在もちゃんとまだ店があった。5年前とおなじように、手を伸ばせばとどくような低い軒と、本日開店中とそっけない標識、傾いたドア、そのほかはすべて蔦に覆われてしまった黒塗りの店が、闇から目を光らすようにして開店していた。
この喫茶店は、映画ifに感動したオーナーによって名づけられた。彼女は銀行員だった職を辞して始めたという。映画は60年代末に封切られた青春映画で、英国のパブリックスクールに反逆する生徒たちの話で、60年代の学校反乱などと軌を同じにしていた。銀行員から喫茶店へと転進した彼女にも時代の風がかんじられたのだろう。あれから半世紀ちかく、彼女はこだわりを貫いてきているわけだ。室内は、落書きでうめつされていて、聞くと、近くの南高校生などの溜まり場でもあったという。政治、反体制、ヒッピー、アングラの時代でもあったのだ。政治と革命の夢、こうした時代を抜けて、今もつづいているのだ。こういう店が残っているというのも街の深みであり、面白さではないかと思われる。まだ健在であったのかと、寒空がふと暖かくかんじられたのではあった。
さて、このifの路地をそのまま北へすすみ南宮崎駅前の椰子の植えられたとおりを向かうへ渡り、数年前にあった宮崎交通本社ビルの角の道路をさらに200メートルほど行くと、戦前から稼動していた竹工場の跡があった。岐部竹工場である。平屋の一区画におよぶ木造建築でガラス越に内部の製造機械が、大型の車輪やベルトや梁や、なにか舞台装置のように見えた。建物の昭和初期の建築の手触り感のある玄関、板壁、街灯、ガラス窓と見飽きぬのであった。しかし、去年の早い時期についに壊されて、あとは白い売り地になっていた。ここに隣接していた稲荷神社もむき出しとなり、裸で昼間に放り出されたようで、味気の無い小さなお堂に変わってしまった。たしかに商売ではなんの役にも立たなくなった工場であったが、この廃墟の工場の存在が、太田3丁目の町をどれほど豊かなにしていたかは、なくなってしまって初めて分るのだ。こうしてまた一つ街は、浅くなった。
街の均質化、平板化は、ここ20年以上も都市問題として問題化されてきている平凡きわまる常識の主題なのだが、わが宮崎市は、世界の諸都市でも例をみない自転車駐輪監視員を何十年と巡回させて、規制をしてきた。ようやく監視員は消えたのだが、消えたのは、監視員のまえに通行人であった。こうして、客も消え、店も消え、正月も消えていった。そのことは、都市問題の専門家としてますはやらねば課題であるのだが、行政依頼人としてなんの批判力も行動もうしなった都市専門家が、津村市政の「シンガポール幻想」に取り付かれてしまっていた。批判をやらないあんな連中が都市問題の主体とは、空恐ろしい話ではないか。そんな私は今年も、元旦の分厚い新聞を読む気も無く放り投げてしまったのであった。











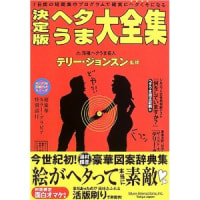












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます