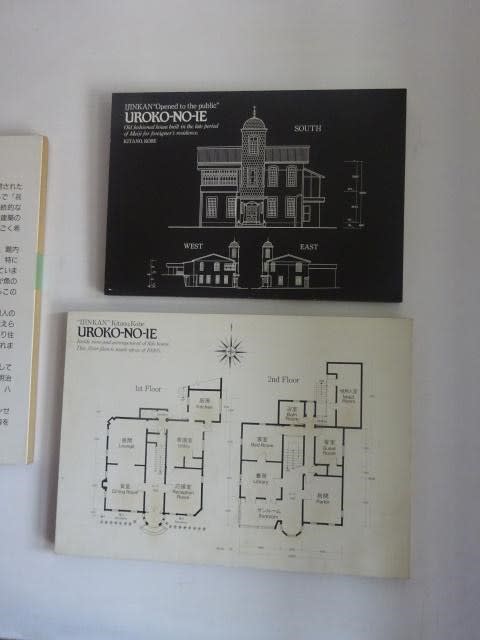会社親睦会の会長がどうしても「天空の城」竹田城跡へ行きたいと
いうことで、ここを目玉に神戸、姫路方面へ社員旅行に行って来た。
2日間素晴らしい天候に恵まれて、中味の濃い印象深い旅であった。

バスの車中から国道越しに撮った竹田城跡のある山。
たまたま交通標識が邪魔してしまったが、この標識の上に
ちょこっと写っているのが、全国屈指の山城遺構、国史跡の竹田城跡だ。

ここ山城の郷は天空の城と呼ばれる竹田城跡への登城口として親しまれて、
自然豊かな山並みを展望できるくつろぎの施設です。
(兵庫県朝来市和田山町殿13-1)
ここでは食事処、売店があり、和牛の最高但馬牛のメニューや
但馬の地酒などの特産品が売られている。


ここは朝来市はもちろん、但馬全域の観光情報を発信する拠点となる
観光案内所もある。ここでは「竹田城跡雲海トリックアート」や甲冑の
試着体験コーナーなどくつろげる空間となっている。


竹田城跡へ行くにはここ山城の郷から竹田城跡登山道入口まで1.4㎞、
バスやタクシーで行ける。徒歩では20~30分位かかる。我々は団体の貸切りバスで
登山口まで行った。一般客用の天空バスにはこの様なマッピング絵が
描かれていて思わずシャッターを押してしまった。

中腹駐車場からは城跡までずーと登り坂を歩く。この地点は600m地点、
あと大手門までは残り200mの地点だ。この辺りに来ると呼吸が乱れ
自分との戦いが始まる。かなりきつい坂道であった。

縄張り(平面構成)の規模は南北400m、東西100mに及び、
完存する石垣遺構としては全国屈指のもので、
平成18年には日本城郭協会により「日本100名城」に選定された。

今回大正解だったのは、こちらのガイドさんをお願いしたことだ。
城跡に行ってみたら、案内の表示が何もなく、ガイドさんの説明を聞かなかったら
その価値、その意味が何も分からずに唯見て回って終わってしまったはずだ。
ガイド費もたった2,000円とタダみたいだった。

ガイドさんと待ち合わせした所に石がゴロゴロ置いてあった。これはここにトイレを
造ろうと掘ったところ出てきた石で、城壁に使われている花崗岩と同じものだという。

実は竹田城跡が一躍全国的に有名になったのはこの一枚の写真からだ。
雲海に浮かぶ姿から、「天空の城」「日本のマチュピチュ」などとも形容され、
その風景は幻想的そのものだ。因みに竹田城の周辺は山あいの盆地で、
しかも円山川から立ち上る霧によって雲海がよく発生する。
秋口から初冬にかけてよく晴れた早朝には、城址の石垣を眼下に一面の雲海が広がる。

竹田城跡では、いくつかの映像作品でもロケ地として使用され
この城跡をさらに有名にさせている。その一つが高倉健主演の「あなたへ」(2012年)だ。
それ以外に黒沢明監督の「影武者」(1980年)
天と地と(1989年)春日山城として使用。
軍師官兵衛(2014年 石垣山城として)など。

ひたすら坂道を約20分かけてようやく城跡北千畳へ到着。
竹田城は播磨・丹波・但馬の交通上の要地に築城された。
築城当初の姿は不明な点が多いが、石垣遺構周辺に存在する
曲輪からすると現在の本丸・天守台の存在する
山頂部から三方に延びる屋根上に曲輪を連続的に配置し
堀切や竪堀で防御性を高めていたものと思われる。

石垣のたもとには照明用のライトが設置されて、夜はライトアップされ、
それは幻想的な姿になるらしい。一度は是非見てみたいものだ。


ガイドさんからこの石垣の所で城跡の石積の構造の話が詳しくあった。
竹田城の石垣は、安土城や姫路城と同じ「穴太(あのう)積み」で築かれている。
穴太積みとは、滋賀県大津市坂本町穴太に住む「穴太衆」という人々が
持つ石積み技法をいう。又、石垣をよく見ると幾ヶ所かに石割りの為の
くさびの跡が遺されているのがわかる。

石垣の積み方である算木積みとは石垣の出角部分において
長方体の石の長辺と短辺を交互に重ねて積んでく技法で、
これにより石垣の強度が増し崩れにくくなる。
表面が小さな石は奥まで石が入っており
隙間埋めには小さな石が置いてあるだけで敵が登ろうとすると
落ちる様にしてある。説明を聞いていると、戦の多い時代の城は
いかに敵にとって攻めずらくするかの知恵がこれでもかこれでもかと
活かしたつくりになっているのを痛感する。

城跡の所々には野生の藤が美しく花を咲かせていた。今回の旅では
色々な所でこの藤の花が咲いていたのが印象的であった。

城跡から見る景色は素晴らしい。眼下にはいくつかの集落が見えたが、
この街はガイドさんによると昔、西側にあったが、西方の敵が(毛利)攻めてくる
危険性があったので安全な東方のこの地に集団移転をしたらしい。


見学路は黒いフカフカしたラバーの様なものが敷かれていた。
おそらく城跡を傷めない為の工夫だと思う。疲れた足には負担が少なく歩き易い。

ここで城の歴史について触れてみよう。
嘉吉元年(1441年)嘉吉の乱勃発後、山名氏と赤松氏の間に
深刻な対立が生じていた。竹田城はこの時、赤松氏に対する
山名氏方の最前線墓地のひとつとして築城された。
以後、太田垣氏7代にわたり城主となるが、
天正5年(1577年)、羽柴(豊臣)秀吉の但馬攻めにより
羽柴秀長が城代となった。これ以降、竹田城は
織豊方の拠点城郭として機能した。

播但自動車道の和田山JCTと和田山PAの間にある橋
「虎臥大橋」。通称めがね橋は竹田のまた隠れた魅力のひとつ。
橋長は402mあり、アーチ的デザインが素晴らしい橋だ。
その先には但馬牛の畜産研究所がある。ガイドさんの話では
但馬牛は、神戸牛、松坂牛などのブランド牛の全ての元の牛だと自慢していた。

城跡から遥か下に小さくスタート時点の山城の郷が見えた。昔の武士は
下から城へ登城する生活はさぞ大変だったことだろう。


この日は団体客は我々だけで観光客は本当に少なかった。
だから1人1人がゆったりと城跡を楽しむことができ、
悠久の時に浸ることができた。竹田城跡は先程紹介した
一枚の写真が公表される前は年間1万人程度の
観光客であったが、この写真でその存在が広く
知られてからはピークで年間50万人の観光客が殺到したとか。
現在はピークが過ぎ年間25万人程とガイドさんが言っていた。

ピーク時は通行路から人が溢れ、石垣の縁の草も踏まれ枯れ、
雨が浸透して崩れる危険が出てきた為、ロープを張って通行路を限定したと
ガイドさんが説明していた。関西人は初ものが好きで、何でも珍しいものを
見に来る傾向があってブームになったが、今は大分落ち着いたとか。

真ん中の大きな石はパワーストーンだとか。この説明を聞いた女子大生が
左上の方にハートの形の石を発見し、ラブストーンをみつけた
エピソードもガイドさんが語っていた。


南千畳から見た南二の丸、本丸方面の一枚。この角度から撮るのが
ベストポイントだとか。それにしてもこの急な山によくも石垣の石材や
城の建築資材を運搬したものだとその当時に思いを馳せてしまう。

ガイドさんが見せてくれた竹田城跡を使った映画の一夜城の一枚。
これはCGで作った為。数秒で出来た城だと言っていた。

さぁーいよいよ下山。来る時はこれだけに姫路から片道2時間程度時間をかけて
来るだけの価値があるのかと思っていたが、それだけの価値が充分あると納得。
爽やかな気持ちで浮世の世界へ戻った。

下山途中、朝来市の竹田城課のカラーコーンを発見。
今は観光交流課に変わったらしいが
その当時はガイドさんの言葉を借りれば数100年静かな眠りを解かれ、
黒船来襲の様に役所が対応したイメージが伝わって来た。

この山では野球のバットで利用されるアオダモが採れるとのこと。
アオダモの材には粘りがあるのでバットに向いているからとか。

最後に雲海の中で本丸から南千畳を望んだ竹田城跡の写真一枚を紹介したします。
ここは苦労して来るに充分値する素晴らしい所であった。