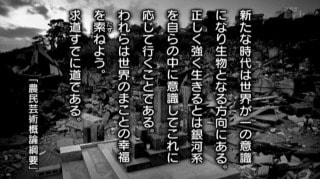今は引退してしまった山口百恵さんの歌に、宇崎竜童作曲・阿木燿子作詞の「しなやかに歌って」(1979)という曲があります。
「しなやかに歌って、淋しい時は しなやかに歌って、この歌を」という歌詞から始まり、この同じフレーズが6回歌詞の中に入っています。
二日前に、
「しなゆ」という「やまと言葉」(2)補正
というブログをアップした時に、万葉学者の中西進先生の1994年にNHK放送大学でで講義された「古代日本人の宇宙観」の使用したテキストから、
<引用>
末通女等(おとめら)が袖布留(そでふる)山の瑞垣の久しき時ゆ思ひきわれは
(万葉巻四)
というのは『万葉集』の柿本人麻呂の名歌ですが、少女たちが袖をふるというのは魂を招く美しくも厳かな神事で、その華やかで若々しい仕草と対応するのが神域のみずみずしい、生命にあふれた垣根でした。
瑞枝(みずえ)ということばもあります。これも神域の長寿の木が生命力の象徴のみずえようにさし伸べている枝です。
そこで当然、人間についても同じように考えることになります。みずみずしい姿こそが最高の理想像で、これを「しなう」(しなふ)といいました。弾力がある姿です。弾力はみずみずしくなければ出てきません。
反対にみずみずしくなくなると、しないません。『万葉集』では「しなふ」姿が男女ともに賛美されました。しなやかな姿ですね。
<以上>
という文章が含まれた部分を引用しました。
この文章を引用しながら、先の山口百恵(以下百恵さん)さんの「しなやかに歌って」が浮かびました。
「しなやかに歌って」とは、イメージ的には「こだわりなく」「何かに囚われることもない」・・・・
そんなイメージが湧きます。作詞された阿木燿子は、自分の前から去った男性について、未練を断ち切る言葉として「しなやかに歌って」と一人称の自戒を促している。恐ろしいまでに完成の鋭さと表現力を感じました。
ここに表現されている「しなやか」は、現代語です。
日本語大辞典(講談社)には、
しな-やか(形容動詞)
1 たわみしなうさま
2 やわらかくなよやかなさま
3 やさしいさま
大辞泉(小学館)
しな-やか(形容動詞)
1 弾力があってよくしなうさま。
2 動きやようすがなめらかで柔らかなさま。
3 姿態などがなよなよして上品なさま。たおやかなさま。
と解説されています。
さてこの百恵さんの歌の「しなやかに」は、この中のどの「さま」になるのか、非常に考えさせられます。
別れの寂しさ、別れの辛さに耐え切れずとんでもないことを考えてしまう。そんな女性に一人称でささやく「しなやかに歌って」は、
軟弱になりなさい。弱く、悲しみに沈みなさい。
と囁いているのではないように思います。
心に柔軟性を持ちなさい。悲しい時は悲しいが、そっと時が過ぎるのを待ちましょう。
執着は程々に、心に余裕を・・・・。
総じて自らの出会いと別れの偶然性・必然性をよく噛みしめて、ニーチェ的な「悦び」を持てと言っているように思うのです。
私の個人的な勝手な解釈です。こういう時のも聞く「アンテナ」をもっていることが重要なのかも知れません。
「アンテナ」の話は、曹洞宗大教師の青山俊董先生の受け売りですが、その際沢木興道先生の「耳鳴りがするまで聞け。初めて聞くつもりで聞け」旨の話がありました。沢木先生に直接言われた言葉ですから、沢木先生の著書にあるわけではないのですが、一連のこの話は「無情説法」ということにもつながる話だと思います。
この「無情説法」については、ブログを書いて反省とともに勉強したことがあります。
さて沢木興道先生はこの「無情説法」についてどう語られていたかですが、『沢木興道全集 道元禅師偈頌講話 第五巻』に掲載されています。その文頭部分を紹介します。
<引用>
無情説法
無情説法
無情説法不思議。
(無情の説法不思議)
三世如来信受之。
(三世の如来之を信受す)
更有阿誰還得会。
(更に阿誰有ってか還って会することを得ん)
一杖技杖等閑知。
(一枝の柱杖等閑に知る)
『無情の説法』これは通常から考えると、有情・無情、生あるものを有情といい、草や木や山や川を無情という。無常が説法する。これは古いところでは、『華厳経』の中にも「殺説衆生説(せつぜつしゅじょうせつ)といい、普賢菩薩(ふげんぼさつ)の大身、山雲海月みな説法する、山も雲も月もみな説法するとあり、あるいは『阿弥陀経』の中にも「水鳥樹林」水・鳥・林の声を聴いて、悉皆念仏念法念僧とこうある。
祖師の中では大証国師に無情の説法ということがある。それから洞山大師において、無情の説法ということがある。いま道元禅師は『永平広録』の巻の六に
「無情の説法」という題でお説きになる。
中国の宋の時代に、蘇東披が常総禅師に無情の説法という説法を聴いて、つぎの詩をつくった。
谿声は是れ広長音。
山色豈に清浄身ならざらんや。
夜来八万四千の偈。
他日如何(いか)んが人に挙似(こじ)せん。
蘇東坂において谿声山色----谿の声やあるいはまた山の色が、谿の声は仏の説法であり、山の色は仏の姿であると、こういうた。道元禅師にも、
峰の色 谿の響きもみなながら わが釈迦牟尼の 声と姿と
という歌がある。人間は毀誉褒貶(きよほうへん)に動かされる。音楽に画してすぐオロオロして流転する。説法を聴く。それを最極上等とセリ上げてゆくと、無情の説法というところまでゆく。だから、
音もなく香もなく常に天地は書かざる経を繰返(くりかえ)しつつ
という歌があるが、宇宙一ぱいが『一切経』であり、宇宙一ぱいが仏である、ということになる。
東洋はかりでなく、西洋でも、人間はどうもあてにならぬという。人間のいうことにはかけひきがあったり、また人間は感情に動かされたり、時の権門に動かされたりする。哲学者や宗教家や思想家の最後のねらいは、この無情の説法をきくというところにあるのではなかろうか。むしろ人間というものが、一番深い迷いをしているものではなかろうか。
・・・・<以下略>
大事なことは耳鳴りがするほど聞け!
しかも、毎回初めて聞く思いで聞け!
強烈に厳しさのある言葉です。青山先生が若い時に教えられら言葉です。
青山先生は、特に解説されませんでしたが
まっさらな気持ちで、自己のもつ既成概念も捨て・・・
という意味合いを感じました。しかし、凡夫のわが身、その境地にはほど遠く、自己の価値観で聞くことになってしまう。せめその境地に近づきたいものです。
「聞く思い」ということをよく考えると、「未だその境地には到らないが」の意味を含んでいます。
「毀誉褒貶」その意味は、「ほめることと、けなすこと」です、そんな気持ちで聞き批評する。そんな聞き方をするのが常です。
そんな時に「しなやかに」を思う。
「柔らかなさま」とは「柔軟なさま」
「しなやかに歌って」が「しなやかに聞いて」に聞こえる。
そのようなことを考えているとあるブログに「禅的柔軟」という言葉に出会う。
道元さんが書かれた『寶慶記(ほうぎょうき)』に書かれている「柔軟心」からです。
『寶慶記』の解説書として私は西嶋和夫老師の『寶慶記講話上・中・下』(金沢文庫)を使用していますので次の言葉を引用したいと思います。
36和尚或示曰・・・・
和尚示すには、仏仏祖祖の身心脱落を弁肯するは、乃ち柔軟心なり。這箇を喚んで仏祖の心印と作すなり。
<解説部引用>
「心ノ柔軟ニナル」ということが仏道修行の目的だと、こういうことになりますと、普通、仏道というものを誤解しておる場合には、意外な印象を受けるわけであります。仏道というのはばかに堅っ苦しいもので、普通の人がとてもやれないような難しいことをやって、特別の境地に到達するんだ、というふうな考え方をしておる人々にとっては、仏道 修行の目的が心を柔らかにすることだというのがなかなか納得いかないという面があるわけであります。
ただ、道元禅師が中国からお帰りになったときにも、「中国から何をおみやげにお持ち帰りになりましたか」というふうに人から聞かれた際に、「柔軟心」といわれた。柔らかな気持ち、弾力的な気持ちを持って自分は日本に帰ってきたと。
だから、仏道修行のねらいというものは、心を柔らかにするということにあるわけであります。
ここでも、「世世ニ諸ノ功徳ヲ修シテ、心ノ柔軟ナルヲ得レバ也」、釈専がなぜ人間の住んでおる婆婆世界に生きて仏道修行をされたかというならば、仏道修行の目的が心を柔らかにすることにあったからであると、こういうふうに天童如浄禅師が教えられた。
「道元拝シテ白サク、作麼生カ是レ心ノ柔軟ナルヲ得ン」、そこで道元禅師が礼拝をしてから申し上げていうには、「作麼生カ是レ心ノ柔軟ナルヲ得ン」、いったいどのようにしたら心の柔らかさというものが得られるでありましょうかと、こういう質問をした。
そうすると、「和尚示スラク」、天童如浄禅師が教えていわれるには、「仏仏祖祖ノ身心脱落ヲ弁肯スル、乃チ柔軟心也」、「仏仏祖祖」というのは、釈尊以来、代々の祖師方、仏道修行をして真実を得られた方々、祖師と呼ばれる方々という意味でありまして、それらの方々が目標とされた「身心脱落」を、どういうものかということを実際にわきまえること、これがすなわち柔軟心であると、こういうふうにいわれたわけであります。
この「身心脱落」という言葉の意味でありますが、天竜如浄禅師はこの『寶慶記』の中でも、「参禅は身心脱落だ」と、こういうふうにいわれておるわけであります。坐禅をしておることが、体の束縛、心の束縛から脱け出した状態だ、だから坐禅をすることによって、体の束縛から離れ、心の束縛から離れた状態でジーッと坐っておることがすなわち柔軟心だと、こういうふうに天童如浄禅師がいわれておるわけであります。
「身心脱落ヲ弁肯スル」というのは何を意味するかというならば、坐禅をするということを意味しておるわけであります。柔軟心とは何かという質問に対して、坐禅をしておる状態が柔軟心を得た状態だと、こういうふうにいわれたわけであります。
<以上同書下p22~23>
この言葉は。「36和尚或示曰・・・・」で始まる文章の最後の言葉です。
坐禅をしない人は、その柔軟心が持てないのか。とも読み取れるのですが、そもそもこの「36和尚或示曰・・・」は、「羅漢支仏之坐禅」について書かれたものです。
仏道の修業の方法には、「声聞乗」という修業の仕方があって、お釈迦様の説法を聞くことで、理論を通じて、言葉を通じて仏道を仏道を勉強していく仕方を「声聞乗」なのだそうです。その「声聞乗」の最終段階が、「羅漢」とか「阿羅漢」と呼ばれる境地で、「支仏」というのは「辟支仏」という言葉があって、普通「縁覚乗」というのだそうです。
この「辟支仏」「縁覚乗」ということは、仏道修行に関連して、環境の良し悪しを非常に重要視して、山里深くに分け入って、ひとのほとんどいないような自然の環境の中で仏道修行することが最も優れたやり方であるというふうな考え方の修行法を縁覚乗の仏道というのだそうです。
「大悲を聞く耳も持っていない」者、専門家でもない素人が道元さんや西嶋老師のことば等を勝手に使用しと批判されそうですが、あくまでも自己の思考の世界の遍歴ブログです。
私は日常的に自分や他人の「慈悲心」を聞く(見るも含める)機会が、他の方よりも多いかと思います。そんな縁から自ずから考えさせられることが多々あるわけで、その遍歴を書いています。
横道にそれてしまいましたが、「羅漢ト支仏ノ坐禅ハ」何かがお釈迦様と異なる、それは何かということがこの「36和尚或示曰・・・」の言わんとしていることで、「柔軟心」もそこにあります。
お釈迦様の坐禅は、自分自身が悟って苦しみから苦しみから逃れるということが目的ではなかった。では、何を目的にされたかというと、一切衆生を救うために坐禅をされた。
「一切衆生を救うため」とは「大悲」であり「大悲ヲ聞ク」そのことについて書かれています。
「羅漢ト支仏ノ坐禅ハ」何かがお釈迦様と「異なる」「欠けている」ものは「大悲ヲ聞ク」ということなのだそうです。
素人の私自身が、今聞こえるのは私自身の理解です。
夜が明けてくると、外では鳥の鳴き声がします。窓から外を見ると夜明けの光の中で風に小枝が揺れています。
しなやかな鳥の歌声であり、しなやかな小枝の揺れでもあります。古語の「しなゆ」げんだいごの「しなやか」、水分がなくなるとその柔軟性が失われます。
瓢(ヒサゴ)の水は天からそそがれます。昨日は晴れたり時には強い雨が降り、また全国的に風も強かったようです。
度を超す「しなやかさ」も、硬さ以上に問題があります。
ここまできてようやく沢木興道先生の
大事なことは耳鳴りがするほど聞け!
しかも、毎回初めて聞く思いで聞け!
の「聞け」、青山先生の「出会いは宝」が「聞こえる」ように思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なを「聞く」ということについて、なぜブログ
きく文化(3)・法華経・耳根最も利なり[2010年10月23日]
を書くになった意味が自分自身で解りました。
また私が学んでいるブログに、
いわゆる仏々祖々の身心脱落とは、柔軟心なのである。柔軟だから、壁に当たったときにはそれをなんとかやり過ごそうとする。或いは、そもそも壁に当たらない。そういう生き方を目指すべきなのである。苦悩への対処の「選択肢」の数を増やす、それが「身心脱落」である。そして、柔軟心を得るには、それこそ「堅固な修行」を必要とする。しかも、時間もかかる。もし、今満ち足りていて、そしてこの記事をご覧になったという人、遅くないから明日から、いや、今日から仏教を学んでみて欲しい。
と書かれていた意味もよく解りました。

にほんブログ村

にほんブログ村 このブログは、にほんブログ村に参加しています。

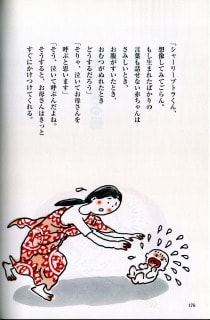


![]()