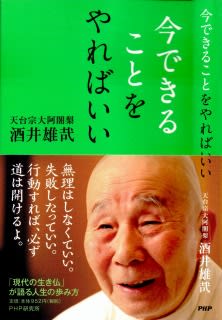二日ほど前の「世界は“空”である」の続きになります。Eテレの100分de名著『般若心経』第2回目は「般若心経」の中の「空」についてで、講師の佐々木閑先生曰く「空」は般若心経の核心の思想であるという言葉から始まりました。
前回書いたとおりにこの「空」の思想は仏教の縁起の理法にも関係する思想です。このブログはテレビの内容にも触れますが批評ではなく、個人的な深みのある理解に向けてのメモです。
さて時々言及する「空即是色」ですが、インドの「ゼロ」思想に根拠をおく思考転回においては、
「ある」
「ない」
「あると同時にない」
「あるでもない、ないでもない」
は存在しません。物々交換から貨幣交換をたどる交易において発展する経済取引におけるバランスシート(貸借対照表)においては、「ゼロ」概念が不可欠です。損益に対する重要ポイントだからです。メソポタミア文明、インダス文明が花開いた地方では早くからこの思想が発展しました。労働に対する対価もその範疇にあります。働かざる者には労働賃金である対価穀物、対価金銭は存在しません(ゼロ)。
奴隷的身分が徹底されるならば「ゼロ」は徹底した概念です。そういう自己存在において徹底された裸の実存であり「我」は持ち得ないわけです。
「あるでもない、ないでもない」と感覚がつかめないのは慈悲という献身的な自己犠牲(この表現は誤解を招きますがあえて使います)が発生しないことを意味します。
意味のないゼロの中に意味をもたすことができないからです。
あるスリランカの僧侶が「般若心経」の今回2回目の番組で取り上げられた「空即是色」について次のように語った有名な話があります。
<僧侶曰く>
『般若心経』では「色即是空」と言っています。それはお釈迦 様もおっしゃっていた真理であって、「物質的現象には実体が無い」というのは客観的事実です。でも「空即是色」は完全に間違いです。「実体がないものは物理的現象だ」とは言えません。
般若心経の中では、何かしら文学的に成り立つかもしれませんが、真理ではありません。
経典を書いた人が真理を分かっていなかったみたいです。
という話で玄奘三蔵法師さまは「真理が分っていない」と批判されたわけです。その論理的根拠は「即是」にあるようです。(※番組では鳩摩羅什訳ではなく三蔵法師訳としているのでここでは三蔵法師とします)
そもそも可能的事実のみが「語り得るもの」であって「意志、価値、倫理、死、魂、神、神秘、永遠、人生、精神など」は「~は云々である」と言及できないもので、本来はウィトゲンシュタインがいうように「語り得ぬもの」で、それをあえて語り漢字4文字のすばらしさがあります。
何もないのではない。あるけれども「言葉では表せない」「人に伝えることができない」ようなものだが「存在」はしているという微妙な感覚を、大衆のために(大乗思想)語るためそのような表現をするのであって、「即是」という「云々である」が使われているわけです。どうしても「ゼロ」思想に執着すると、この微妙なニュアンスが直覚としてつかめないようです。
人によっては鈴木大拙先生の「即非」がよいのではという学者先生もおられますが、「般若心経」の今日ある歴史的事実がそれを拒んでいるのは明白です。「ゼロ」思想に固執している者は自分の厳格な学問の方法を固く信じているので、知らず識らずのうちに、その方法の中に這入って、その方法の虜になってしまうということです。
すなわち現象の具体性というものに目をつぶってしまうということです。現象の具体性とは何か、それは『般若心経』の番組が放送される以前に数多くの超訳や私訳も含めた『般若心経』が出版され日本人の心をとらえているということです。
さて「空(くう)」は、般若心経の核心の思想であるという話にもどります。
前回「五蘊皆空」について書きましたが、引き続いて言及していきます。番組で丁寧に説明されていました。そして今回は「色即是空」で、色(しき)とは「この世を作っている物質すべて」のことを言い、それは「空」だと言います。
「空」とは実体を持っていないもので、私たちは実体のあるものを「物質」と名づけます。しかし「物質」という言葉は物の概念を表わすものですから「空」だということになります。
いったい「空」とは何か?
【番組ナレーション】
この世界は常に移ろい続けています。太陽は朝、東から昇り夕方には西に沈みます。すると月が東から出て、その月はまた日々、形を変えてゆきます。
満開の桜もわずか十日もすれば風に散ってしまいます。この「移ろい行く世界」には「何かの法則があるのではないか?」古代インドの仏教徒たちはそれを「空」と名づけたのです。
とてもきれいな説明だと思います。三蔵法師さまは現地語で書かれたものを「空」という漢字に訳しました。古代インドの仏教徒たちの理解をさらに三蔵法師さまが意訳したということです。超訳というのでもなく私訳でもなく、当時の中国人の知識で理解できるようにということです。
だからそこには三蔵法師さまの経験が語られているということです。数学的なということは科学的なともいえるのですが「ゼロ」という具体性のあるバランスシートにおけるプラス・マイナスの境の「ゼロ」ではなく、老子(道徳経)の知識でもどうにかこうにか意味理解ができる形に、ということです。
道徳経の第11章の「空のはたらき」については既にブログに書きましたのでここではこれ以上言及しませんが、他者との関係性における「nothing」ではなく「移ろい行く世界」であり「空(うつ)ろな連関性の世界」を示す経験の感覚表現です。「感覚」ですから本来は語り得ない現象にある働きのことを言うのです。
前回はあらゆる現象のそれぞれの奥にある一つの法則を眺め、その法則性に全てを集約していくのが科学であるとことを書きました。科学は経験というものを尊重します。経験科学の場合の経験というものは、科学者の経験であって自然現象のある部分を取出し、観察や実験の方法でとり上げ、これを計量というただ一つの点に集約させるという意味です。それは私たちが日常生活で行っている経験の領域を合理的に説明しようとするものです。
しかし上記で言及した可能的事実はどうでしょう。精神や心とはこうだと定められないことは誰もが知るところです。人間精神な働きの微妙さ計量計算には到底ゆだねられないものです。
科学は観察や実験などの結果を計量計算し宇宙の法則性などを明らかにしたった一つの法則を見つけようとします。
「空」はすべての現象を統括する一つの法則で我々は「感じる」ことができると説明されました。
これは人間の経験にもとづくもので、支配しているたった一つの法則で、仏教では「空」としたわけです。くり返しになりますが、「これは何だ?」と問われてもわからない、本来は「語り得ぬもの」で説明できないで直覚として「感じる」ことができるだけというわけです。
「色即是空」というのは一つの大きな宇宙観。
とい解説がありました。この場合の「色」には肉体や精神、自然現象から精神現象も含まれます。したがってここでは身心二元論の身心並行論の肉体と精神のパラレルな関係はありません。
タレントの伊集院光が司会を担当しているのですがいつもこの人の鋭い直覚には驚かされます。
両親が出会い自分が生まれた(それが自分であった)という不思議(もやもや)=現象
旨を話し、「それが空ですか」と質問していました。島津百理子アナも「身の回りの説明できないことも」と質問し、佐々木先生は、
「若い人が段々と歳をとってゆく」とか「美しさが損なわれてゆく」とか、そういう移り行く世界も源(もと)は「空」の中から現れてくるそれぞれの現象だと理解することができる。
と解説されて「空は悟りそのもの」ということでした。
次に解説されたのが「色即是空」の次の言葉の「空即是色」です。文頭で書いたスリランカの僧侶が誤りだとし、三蔵法師を真理をわかっていない人物とみなす発言をした言葉です。
番組では小劇場風な会話でこの「空即是色」が語られていました。
【男性A】(コーヒーカップの中のミルクとコーヒーの織り成す渦から)すべては移ろい行くからこそ美しい。コーヒーに溶けていくミルクは次々と形を変え、褐色の液体の中に白い繊細な模様を描いていきます。その変化するさまが美しいから、つい私はカップの中をじっと覗き込む癖があるのです。
【男性B】(カメラで喫茶店の窓から下界の景色を撮っている)俺も一度サラリーマン時代に般若心経を読んだことあるよ。おかげで会社辞めてカメラを始めた。
【男性A】 この世はすべて空だって言われたら吹っ切れるよね。
【男性B】 この窓から見える景色も常に変わっているから美しいんだよね。その中で心を奪われる瞬間に何度出会えるか。移ろい行く世界・・・その刹那に心を奪われてシャッターを切る・・・それが「写真」。だから面白くて写真始めた。これって「空即是色」だよな?
この話について佐々木先生は、
【佐々木閑】 写真の話は、連続して流れる時間の流れを何とかして我々は一瞬それを切りとって、捕まえてみたいという人の思いの表れ。一生懸命連続したものを切り取って表現したいというものの一つは「芸術」になり、絵画はその中の狭いもので全体の何かあるものを切り取って他人に示したい、自分で見てみたい芸術になります。
そういう世界を司っている法則を切り取って世に出してみたいだしたい、というのが物理学やになります。考えてみますと人が何かを作る、創造するという働きの裏には必ず何かわからない大きな、後ろにある「空」なるものを切り取って自分の手の中に収めたいという思いがいつもある。
そう思うと人間が作り上げてきた様々な文化というような活動の根底には「色即是空」「空即是色」という構図があると思います。
以上
ここで伊集院さんがありまた鋭いことを言います。
【伊集院光】
例えば引力というものを人間が知らない時も、引力を知らないで人間は立っているではないですか。リンゴは落ちるではないですか。・・・である日ニートンが「これ引力だ」と発見して空の一部を切り取るじゃぁないですか。まだ絶大なる空はあるのですが。
そうすると万有引力というものは、ちょっと前までは空であったわけで、万有引力があるから立っていられるということは「空即是色」ということですか?
以上の質問に佐々木先生は「そうです。」と答えさらに伊集院さんと佐々木先生の間で次のような会話が交わされます。
【伊集院光】
そうやって考えると何か一つ一つのことにワクワクするのが解ります。不思議に感じた「今自分は立っている」「物が落っこちる」これは何だろう? という・・・これは「空」があるぞというワクワク感・・・・。
【佐々木閑】
わたしたちが世界に関して何か新しいものを見つけたときのその驚き、喜びというのは結局は、「空」の世界にちょっと触れた時の喜び、衝撃だろうと思うのです。それが我々の発見の喜びあるいは物を作る喜びのエネルギー、原動力になっていると思います。
毎日を生きて行く自分の一瞬一瞬に意味を見出す。いつも意味を考えるという立場では「空」というものはポジチィブなエネルギーを我々に与えてくれます。
上記の中で語られる「空即是色」に納得できた人が多いと思います。現象・色(空)の一瞬を刻み取り、納得するものを感じ取る。その作用としてポジチィブなエネルギーが与えられる。空の思想にはそういう説明も成り立つわけです。
科学の目は今現在を合理的に数量計算によって観察し、時には実験で真理をつかもうとしますが精神活動はさらに超えたところにある、ということになるようです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回はベルクソンの『道徳と宗教の二源泉』から次の言葉を紹介したいと思います。
<『道徳と宗教の二源泉』(岩波文庫)の「静的宗教の一般的機能」から>
・・・・・人間とは、自分の行動に確信が持てないで、躊躇したり模索したりする唯一の動物、成功の希望と失敗の危惧を抱きながら行動を企てる唯一の動物である。
また自分が病気に罹りやすいことを感じており、また自分が死なねばならぬことをも知っている唯一の動物である。
人間以外の自然は、全く安心しきって花を咲かせている。植物だって動物だって、危難に見舞われることは同じことなのに、あたかも永遠を憩いの場所としているかのように、それらは過ぎゆく瞬間に安らっている。
田園を散歩するとき、われわれはこのかわらぬ信頼の幾分かを吸い、心和らいで家路につく。
だがこう言ったのではまだ充分でない。社会生活を営む生きとし生けるもののうちで、社会の歩みから逸脱し、共同の利益が危いというときにも利己的な関心事にかまけていられるのも、人間だけである。
人間を除けばどこを見ても、個体の利益は、同格でなり従属してなり、全体の利益と必ずよく調整されている。人間にあってのこの二重の不完全さ(不安と利己心)は、知性を購(あがな)う代価なのである。
人間は、その思考力を働かせば、どうなるかともしれぬ行く末を思いやらずにはいられず、それが恐怖や希望を呼び覚ます。また人間は、自然によって社会的存在として造られている以上、この自然から受ける要求に思いをいたさざるをえないが、同時にまた、他人のことなど構わずに、ひたすら自分のことだけを気にかけたほうが得になる場合が多いことを、胸中ひそかに思わずにはいられまい。
両者いずれの場合にも、正常な、自然な秩序が破られてしまう。けれども、知性を欲したのは自然である。動物進化の二つの主要線の一方の端に知性をおき、これを他方の到達点たる最も完全な本能の対にしたのは自然である。してみれは、知性によってこの秩序が乱されるが早いか、間髪を入れず、自動的に秩序が復原されるようにあらかじめ自然が手配しておかなかった、などということはありえまい。
事実、知性に属していながら、さりとて純粋知性とも言えぬ仮構機能の目的は、まさにそれである。その役割は、われわれがこれまで論じてきた宗教、つまりわれわれが静的と呼んだ宗教を仕上げることであり、自然宗教というこの言葉に別の意味がついていさえしなければ、これを自然宗教と呼ぶこともできよう。
そこで、この宗教を正確な言葉で定義するためには、これまで述べてきたことをまとめて言うだけでよい。それを知性を働かせる場合、個人に対してはその元気を殺ぎ、社会に対しては解体的に作用する懸念のある要素に対して、自然がとる防御反応なのである。・・・・・略
<上記書p240~250>
ベルクソンという人は科学を否定する人ではなく逆に失語症の研究でも知られるように科学的な思考をする哲学者です。ここで語られる「自然」は身心二元論を超えたものに思います。
自然宗教の中で大乗仏教はさらにいうなら「般若心経」は超えている、とも私には思えるのです。日本人には「般若心経」が好きな人が多い、その意味理解が苦手でも直覚でそう感じるのです。
※今回も思いのままに書き込み、読み直しをしていませんのでいつもの私の文章になっていますがあくまでも個人メモですのでご了承ください。