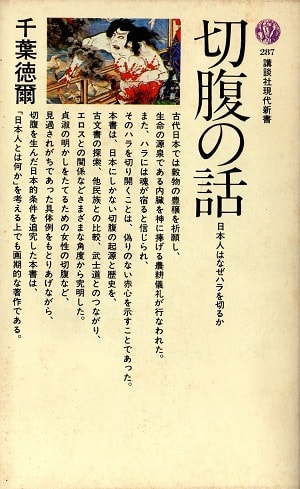小林正樹『切腹』と『怪談』を観る。
『切腹』(1962年)はかねてから観たかった作品で、昨年末にNHKで放送されたのを録り忘れて嘆いていたところ、編集者のSさんが送ってくださった。

江戸時代初期、泰平の世にあってどこにも雇ってもらえない素浪人が続出する。そのひとり、津雲半四郎(仲代達矢)も井伊家を訪ねる。もはや生きていてもいいことはない、ならば腹をかっさばいて自死したいので庭先を貸してくれ、と。実は、妻子が病気ながらオカネもなく、思いつめた娘婿も同じ手口で井伊家を訪れており、応対した家老(三國連太郎)や家来(丹波哲郎)はそれを見越したうえで切腹をさせる。津雲の訪問は、その復讐であった。
時間がゆるやかに進む中での、仲代や三國の重々しい台詞と顔。丹波と仲代との対決(黒澤明『用心棒』があった)。仲代と井伊の家来大勢との長い殺陣。いや激しく面白い。
一連の騒動が終息したあと、井伊の家老は、すべてをなかったかのように片付ける。素浪人の扱いはもとより、死んだ何人かの家来でさえ、病死という形にせよとためらうことなく命令するのである。体制にとってはひとりひとりのイノチや想いなど何の価値もなく、すべては権力とオカネ。現代性も感じさせられる。
はじめに切腹させられる娘婿の素浪人に対し、丹波は、昨今切腹を簡単にしておいて介錯にゆだねる場合が多いが、ここでは横・縦と十文字に切れ、と脅す。そして、オカネに困ったため竹光しか持っていないことを知りながら、腹になんとか体重をかけて竹光を刺した素浪人に、まだだ、まだだ、と鬼のように怒鳴るのである。たとえ切腹するような事態になったとしても、こんな目には遭いたくないものだ。
千葉徳爾『切腹の話 日本人はなぜハラを切るか』(講談社現代新書、1972年)によれば、切腹にもいろいろな方法があったようで、必ずしも十文字切りが正式な作法とは言えないようだ。実際、難しいようである。(痛すぎていつまで経っても全部読めない本である。「はらわたの妨害」って何だ、筒井康隆を読んでいるみたいだ。)
「・・・まず横一文字に深く切り、次に傷口を拡大すべく十文字にとりかかると、一般に困った問題がおこる。それはみぞおちあたりに突立てて下に切りおろすと、その圧力が腹圧に加わる上に、横一文字の切口は開きやすいので、たいてい一文字の切口まで切り下げると腸がはみ出し、それがなめらかでやわらかいから容易に切断されず、結局切口の下半分を縦に切るのは大変困難である。何しろ血は出るし、痛いし、息ははずむし手はすべるしという具合だから、考えただけでもきれいな十文字腹を切るのはなまなかな気力、体力ではできないことといえる。その上に、たとえはらわたの妨害をのりこえたとしても、横一文字の下の切口はピンとはりつめているわけではなく、押えれば外側か下側にまくれるのだから、これに切り込んで十文字を完成するのは大した努力が必要である。」
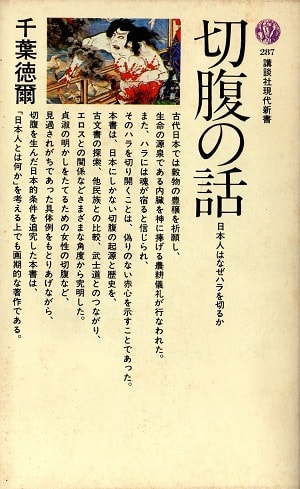
続いて制作された『怪談』(1965年)も、音楽・武満徹、撮影・宮島義勇、美術・戸田重昌、題字・勅使河原蒼風という同じ豪華スタッフで制作されている。『切腹』と違いカラー作品であり、戸田・宮島の色が冴えわたっている。戸田重昌は、多くの大島渚作品や篠田正浩『処刑の島』においてと同様に、毒毒しい色のインスタレーション的なセットを展開し、名カメラマン・宮島義勇は人工的な色にこだわって、この独特な世界を完成させている。
ここでラフカディオ・ハーンの小説から選ばれたのは、「黒髪」、「雪女」、「耳無し芳一」、「茶碗の中」の4話である。それぞれ見所があり、とくに「耳無し抱一」における壇ノ浦での平家没落場面の迫力は凄まじい(安徳天皇が尼とともに入水するとき「草薙の剣」は見えなかったが)。しかし芸術至上主義というのか、大作至上主義というのか、感心はしても怖くはないのだった。