高橋哲哉『記憶のエチカ 戦争・哲学・アウシュビッツ』(岩波書店、原著1995年)を読む。
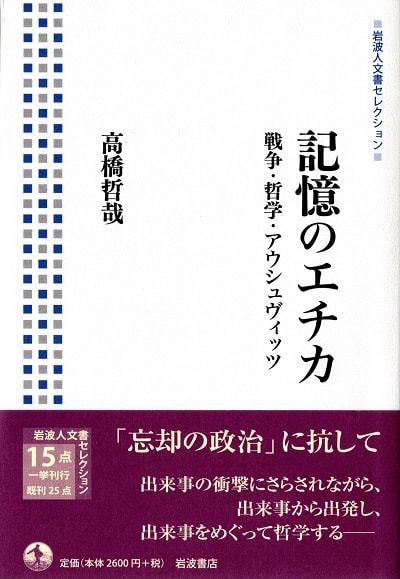
ドイツによるホロコーストは、ユダヤ人虐殺だけでなく、その痕跡をも残さぬことを方針とした。その結果、何万人もの者が、生きた跡を残さず、どこの誰ともわからぬまま地上から抹消された。クロード・ランズマン『ショアー』(1985年)は、まさに、その「どこの誰ともわからぬ者」たちの、微かに残された声を吸い集めたドキュメンタリー映画であった。本書も、『ショアー』の衝撃により書かれた論考を含んでいる。
したがって、膨大なる声なき声を歴史の中に位置づけていくことは、どこの誰というラベルがいかなる形でアーカイブに残されているかという観点とは異なったものとなる。『ショアー』に対する批判にも、後者の観点に基づくものがある。すなわち、ホロコーストはなかったという歴史修正主義であり、従軍慰安婦、沖縄の「集団自決」、南京大虐殺に対してもなされてきた、誤った行為である。膨大なる声なき声に向けられる、人の想像力の問題でもある。
著者は、このような本質的に<記憶されえぬもの><語りえぬもの>が穿つ<忘却の穴>について、まなざしを向け続けることの重要性を説く。絶えず、想像力を決定的に欠いた為政者たちが、<忘却の穴>を、ただの<穴>だとして、内壁を削り取ろうとするからだ。
この点について、ハンナ・アーレントが残した言説に関する分析は興味深い。アーレントは<忘却の穴>を明確に見出しながら、その視線は揺れ動いた。彼女にとって記憶されるべきステージの人間は、どこの誰というラベルが付された<ヨーロッパ人>だったからである。もしアーレントがこのインターネット時代に生きていたなら、自らの痕跡を不自然なまでに刻んでいこうとするSNSを、どのように観察しただろう。
著者は、<記憶されえぬもの>を穴に落としたままの歴史について、エマニュエル・レヴィナスを引用してもいる。
「歴史の裁きはつねに欠席裁判である。」
「歴史の裁き、すなわち可視的なものへの裁きから帰結する不可視の侮辱は、それが叫びや抗議としてのみ生起し、あくまで私のうちで感得される場合には、いまだ裁かれる以前の主観性あるいは裁きの忌避を証示するにすぎない。」
こうして見てくると、記憶されたどこの誰が物語を形成する、スティーヴン・スピルバーグ『シンドラーのリスト』が、<知的野蛮>だとする著者の指摘にも、頷けようというものだ。
クリスチャン・ボルタンスキーのインスタレーション「MONUMENTA 2010 / Personnes」が、その膨大なる声なき声を、無数の古着によって表現していたことを思い出す。そこには、名前のタグはない。もちろん、顔も、その古着を来た人がどこに消えたのかもわからない。しかし、記憶の厚みはいかなる手を使っても消し去りようがない。
●参照
○クロード・ランズマン『ショアー』
○クリスチャン・ボルタンスキー「MONUMENTA 2010 / Personnes」
○高橋哲哉『犠牲のシステム 福島・沖縄』、脱原発テント
○高橋哲哉『戦後責任論』
○エマニュエル・レヴィナス『倫理と無限』
○エマニュエル・レヴィナス『存在の彼方へ』
○ジャック・デリダ『アデュー エマニュエル・レヴィナスへ』
○合田正人『レヴィナスを読む』









