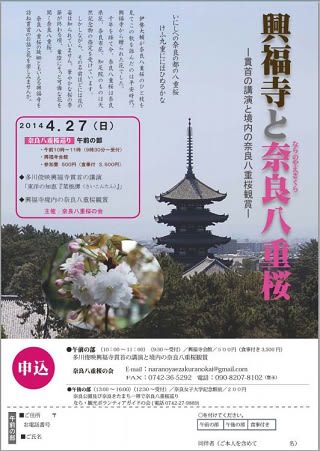気に入っていた、器が欠けてしまい、金継ぎで修理しました
教室に通い始め、半年掛かって出来上がった記念の品です


いぶし銀で仕上げました


随分前から、漆を使って割れたり欠けた器を修理する「金継ぎ」に興味がありました
最近はカルチャーセンターでも講座が開かれる程一般的になりましたが
20年ほど前は、漆職人さんが修理されてる・・・程度の情報しか無かったのです
数年ほど前から、先生を探し始めて・・・
驚いたのは、接着剤を使って、簡単に直す方法が主流になっていた事。
ほとんどのカルチャースクールは、接着剤や硬化剤を使って、仕上げに金粉・銀粉を蒔くのです
奈良や京都で有名な先生も、この方法でした。
それでは嫌なので・・・探しました!
漆だけを使った昔ながらの方法で修理されている先生にやっと出会いました。
漆を使うので・・・もちろんかぶれます。
私は弱い体質のようで、実際に漆に触らなくても、かぶれたり、痒くなるのです。
初心者という事もあって、半年掛かって、小さな「欠け」がようやく、完成。
かゆくてもかぶれても、楽しんで続けて行きたいです。
教室に通い始め、半年掛かって出来上がった記念の品です


いぶし銀で仕上げました


随分前から、漆を使って割れたり欠けた器を修理する「金継ぎ」に興味がありました
最近はカルチャーセンターでも講座が開かれる程一般的になりましたが
20年ほど前は、漆職人さんが修理されてる・・・程度の情報しか無かったのです
数年ほど前から、先生を探し始めて・・・
驚いたのは、接着剤を使って、簡単に直す方法が主流になっていた事。
ほとんどのカルチャースクールは、接着剤や硬化剤を使って、仕上げに金粉・銀粉を蒔くのです
奈良や京都で有名な先生も、この方法でした。
それでは嫌なので・・・探しました!
漆だけを使った昔ながらの方法で修理されている先生にやっと出会いました。
漆を使うので・・・もちろんかぶれます。
私は弱い体質のようで、実際に漆に触らなくても、かぶれたり、痒くなるのです。
初心者という事もあって、半年掛かって、小さな「欠け」がようやく、完成。
かゆくてもかぶれても、楽しんで続けて行きたいです。