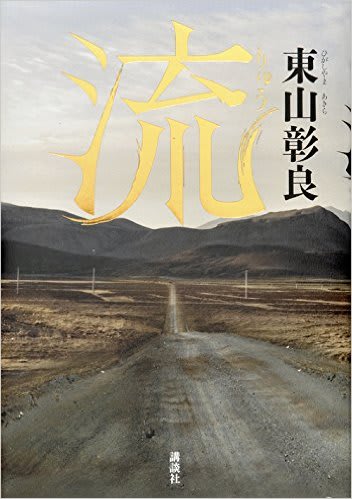
1975年台北。17歳の少年が主人公だ。祖父が殺された。その犯人を探す。そこから始める自らの、そして家族のルーツ探し。84年、彼が中国に行き、祖父が何者だったのかを知るまでの10年に及ぶドラマだ。戦後から30年。さらに秋生の17から27歳までの10年。彼とともに、台湾のたどった道を描く。
2年間の軍隊生活で、恋人を失うという中心に描かれるお話が、あれじゃぁ、まるで『恋恋風塵』じゃないか、と思った。もちろん、盗作ではない。そんなこと、日常茶飯事だったはずだ。
これは先日見た『湾生回家』とも連動する作品だ。日本、台湾、中国の関係を、この小説から改めて考えさせれる。これは故郷って何なのか、を描く小説でもある。自分が生まれた場所が故郷だ。国籍なんかじゃない。生まれ、暮らし、過ごした場所。人はそこに深く影響を受ける。そこから追われた時、どうなるのか。湾生たちのドラマをさらにこの小説は広げる。
祖父たちは山東省から台湾に流れてきた。だが、秋生は「湾生」だ。国民党や共産党なんか、関係ない。背景となる45年からの30年間。死んだ祖父が台湾で暮らすことで何を感じ、何を思ったか。冒頭で死体として登場する秋生の祖父のドラマこそが、この小説の根幹をなす。だから、最後は彼がどうして台湾に逃げたか、に辿り着く。
80年代の中国と台湾の関係や、今の台湾をこの小説と重ね合わせる。さらには台湾で『湾生回家』がヒットする背景とか、いろんなことが、気になるし、いろんなことを考えさせられる。
背景として日本も登場する。秋生が日本語を勉強し、日本で仕事をする。あの当時の日本と台湾の関係は、今とは微妙に異なる。僕が台湾に心魅かれたのは明らかにホウ・シャオシェンの影響だった。先にも書いた『恋恋風塵』と『童年往時』が始まりだ。80年代のことだ。だが、この2作品で描かれる台北は50年代から60年代で、その風景があの当時僕にはとても懐かしく思えた。80年代に作られたホウ・シャオシェンの映画はどれも素晴らしかった。だが、『悲情城市』(89)以降の作品は、僕にはあまり乗れないものばかりになった。
なんだか、まるでこの小説とは関係ない話ばかりだ。でも、そんなこんなのことを、思いだす。何がどうして、こんなにも心魅かれるのか。自分の故郷である1960年代の徳島の風景とも連動する。あの頃の記憶は自分の原風景だ。60年代、家族で大阪に出てきて、大正区で暮らした幼かった日々。すぐそばには工場ばかりがあり、商店街の中で過ごした幼年時代。
こんな話は、もうこの辺でやめよう。この小説は実に良く出来た作品だ。まず、これを読めばいい。そこにはいろんなことが書かれてある。エンタメ小説としても、楽しめる。だが、それだけでは、当然ない。これは傑作である。保証する。


























