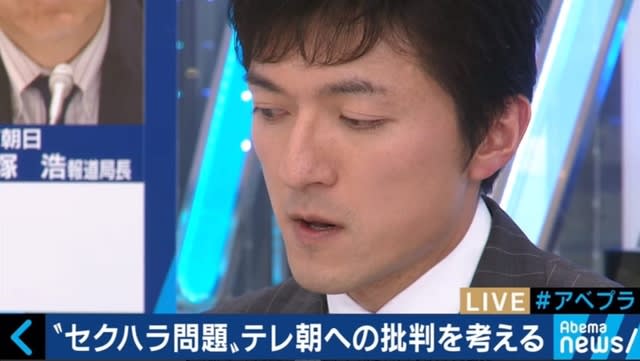2018-04-29 00:19:41 Inc
I've always loved magic. For me, it went beyond entertainment; it was an intellectual endeavor. I enjoyed trying to figure out how an illusion was done. The actual solution didn't matter because it was the process of thinking about the effect that I liked.
When I was younger, there was a TV show called, "Breaking the Magician's Code." Each week, the "masked magician" revealed how some popular tricks were done.
On the show, which is now on Netflix, he first performs the illusion as the audience would see it. Then he would do the trick again, showing how it was done. I would watch the show and pause after he performed it the first time, before the reveal. I would then write down all of the different ways I think he could have done the trick. Only after I had at least one solution, I would watch how it was done. The reveal typically involved showing the trick from different camera angles. In doing this, the solution becomes obvious.
My love affair with magic started when I was a young kid. Over the years I've found that magic and innovation are close cousins. Although there are many more parallels, here are three concepts I learned about innovation by studying magic:
1. The brain can't be trusted.
Magic is so impressive because the brain doesn't always process everything it sees accurately. It takes shortcuts, makes assumptions, and (often incorrectly) fills in gaps. When we see someone go in a box to conceal their body, only revealing their head and feet, we automatically assume that the feet are from the same person whose head we are looking at. But what if they aren't? With innovation, our brain is also often fooled. We take shortcuts and fill in gaps, leading to incomplete solutions. Be sure that any time you develop a new idea, you look at it from multiple perspectives. What are you missing? What assumptions are you making? Just like the reveal, you need different camera angles.
2. Start with the illogical.
Although this may seem obvious, magic tricks must appear impossible. Something must be done that appears to defy the accepted laws of the universe. Cut someone in half, without killing them. Make someone disappear. Read our minds. Magicians make the impossible possible. Compare this to the world of innovation where we're typically only looking to make the possible possible. How can we learn from this mindset? When looking for solutions to a pressing, ask yourself these starter questions: What would be an impossible solution? What is the worst solution? What solution might get us arrested? Then ask, what are the attributes you like about these "crazy" ideas and how can I leverage them to find an unusual yet workable solution?
3. Performance is as important as the method.
Anyone can perform tricks. But real magicians know there is much more to magic than knowing the secret. On Britain's Got Talent, one of the finalists performed a trick I bought years ago for about $20 at a local magic shop. It is simple to do. When I perform it, it is mildly entertaining. When he performed it, it was a minor miracle. With innovation, the performance is as important as the solution. New technology is great, but you need to back it up with excellent human support. The experience your customers have with your new innovation is as important as the innovation itself. Technology can easily be replicated by your competition. However, a good performance is much more difficult to copy.
I was recently at a convention with 500 magicians. Given I'm a magic geek, I loved it. But over time I've come to realize that the real magicians are the hard-working people in companies who are trying to make the world a better place through innovation. And when we view innovation through the lens of magic, it can even make it more enjoyable. Or as Walt Disney once said, "It's kind of fun to do the impossible." Now go make some magic!
PUBLISHED ON: APR 17, 2018
野心的な起業家がマジシャンから学ぶべき「3つのトリック」
Inc.
2018/04/28
優れたマジシャンが持つスキルは、野心的な起業家にも当てはまるものだ。みなさんは必要なスキルを持っているだろうか。
マジックとイノベーションの共通点
私は長らくマジックを愛してきた。私にとってマジックは、単なるエンターテインメントを超えた知的な試みだ。このイリュージョンの仕掛けはどうなっているのかと考えるのが楽しいのだ。といっても実際の答えは重要ではなく、そのイリュージョンについて考えるプロセスを楽しんでいたのだ。
私が若いころ、『Breaking the Magician's Code』(破られたマジシャンの掟!)というテレビ番組があった。「覆面のマジシャン」が毎週、有名なトリックの種明かしをするというものだ。
現在はネットフリックスで配信されているこの番組で、覆面のマジシャンはまず、観客が通常見るとおりにイリュージョンを実演する。次にその同じトリックを、今度は仕掛けがわかるようにやってみせる。
私はいつも、マジシャンが最初にトリックを披露して、種明かしをする前で一時停止して、思いつくトリックの答えをすべて書き出すことにしていた。少なくとも1つは答えを思いついてから、種明かしのパートを観るのだ。
種明かしはたいてい、トリックを異なるカメラアングルから映す形で披露された。違う角度から見ると、答えが一目瞭然でわかる。
私のマジックへの愛は幼いころに芽生えたが、年月を経てみると、マジックとイノベーションはよく似ていることに気づく。共通点はいろいろあるが、私がマジックの研究を通じて学んだイノベーションの秘訣を3つ、以下にご紹介しよう。
1. 脳はだまされる
マジックが人を驚かすのは、脳が見たものすべてを正確に処理するとは限らないからだ。脳はときに近道をとり、推測を立て、空白を埋める(しばしば間違ったやり方で)。
誰かが箱の中に入って体を隠し、頭と足だけを出したら、その足は箱から出ている頭と同じ人間のものだと、われわれは自動的に推測する。しかし、実際は違っているとしたら──。
イノベーションにおいても、われわれの脳はしばしばだまされる。近道して空白を埋めた結果、不完全なソリューションにたどり着くのだ。
新しいアイデアを練るときは、いろいろな角度から見てみることが肝心だ。見落としている点はないか。推測しているところはないか。マジックの種明かしと同じで、カメラアングルを変えてみることが必要なのだ。
2.「不可能」を出発点にする
言うまでもないことかもしれないが、マジックのトリックは不可能に見えるものでなくてはならない。この世の普遍的法則を無視しているかのような、何らかの仕掛けを施さなくてはならない。
人間を生きたまま真っ二つにしたり、その場から消し去ったり、相手の心を読んだりと、マジシャンは不可能を可能にする。
それに比べてイノベーションの世界では、たいていは、最初から可能なことを実現しようとしてばかりだ。そんな姿勢から、どうやって何かを学ぶことができるだろう。
問題のソリューションを見つけようとするときは、まず初めにこんな問いを自分に投げかけてみるといい。「不可能なソリューションにはどんなものがあるか」「最悪のソリューションとは」「下手をすると逮捕されかねないソリューションとは」
問いに答えたら、次にこれらの「クレイジーな」アイデアで自分が気に入った要素はどこか、またそうした要素を生かして普通ではないが実現可能なソリューションを見つけ出すにはどんな方法があるかと、考えを巡らせてみよう。
3. パフォーマンスはトリックと同じくらい重要
トリックを実演するだけなら誰だってできる。しかし本物のマジシャンは、マジックとはネタを知っていればいいというものではないことを理解している。
オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で、あるファイナリストが実演したトリックは、私が何年も前に地元のマジックショップで20ドルほどで購入したものだった。いたって簡単なトリックだ。
私がそれを実演しても、ちょっとした余興にしかならない。しかし、そのファイナリストが実演してみせたトリックは、ちょっとした奇跡だった。
イノベーションにおいても、パフォーマンスはソリューションと同じくらい重要だ。最新のテクノロジーがいくら素晴らしくても、われわれ人間の優れたサポートが欠かせない。新たなイノベーションが顧客にどんな体験をもたらすかは、イノベーションそのものと同じくらい重要だ。
テクノロジーは、たやすくライバルに取って代わられることもある。しかし、優れたパフォーマンスを真似るのは、それよりはるかに難しいことだ。
* * *
私は先日、500人のマジシャンが集まるコンベンションに参加した。マジックおたくの私はおおいに楽しんだが、しかし時間が経つにつれて、本物のマジシャンとは、企業においてイノベーションを通じて世界をより良くしようと熱心に働いている人々なのではないかと気づいた。
そして、マジックというレンズを通してイノベーションを見ると、それはいっそう楽しいものに思える。かつてウォルト・ディズニーが言ったように「不可能と思われることをやってのけるのは、けっこう楽しいこと」なのだ。われわれもマジックを実現してみせよう。
原文はこちら(英語)。
(執筆:Stephen Shapiro、翻訳:高橋朋子/ガリレオ、写真:mazartemka/iStock)
©2018 Mansueto Ventures LLC; Distributed by Tribune Content Agency, LLC
This article was translated and edited by NewsPicks in conjunction with IBM.
I've always loved magic. For me, it went beyond entertainment; it was an intellectual endeavor. I enjoyed trying to figure out how an illusion was done. The actual solution didn't matter because it was the process of thinking about the effect that I liked.
When I was younger, there was a TV show called, "Breaking the Magician's Code." Each week, the "masked magician" revealed how some popular tricks were done.
On the show, which is now on Netflix, he first performs the illusion as the audience would see it. Then he would do the trick again, showing how it was done. I would watch the show and pause after he performed it the first time, before the reveal. I would then write down all of the different ways I think he could have done the trick. Only after I had at least one solution, I would watch how it was done. The reveal typically involved showing the trick from different camera angles. In doing this, the solution becomes obvious.
My love affair with magic started when I was a young kid. Over the years I've found that magic and innovation are close cousins. Although there are many more parallels, here are three concepts I learned about innovation by studying magic:
1. The brain can't be trusted.
Magic is so impressive because the brain doesn't always process everything it sees accurately. It takes shortcuts, makes assumptions, and (often incorrectly) fills in gaps. When we see someone go in a box to conceal their body, only revealing their head and feet, we automatically assume that the feet are from the same person whose head we are looking at. But what if they aren't? With innovation, our brain is also often fooled. We take shortcuts and fill in gaps, leading to incomplete solutions. Be sure that any time you develop a new idea, you look at it from multiple perspectives. What are you missing? What assumptions are you making? Just like the reveal, you need different camera angles.
2. Start with the illogical.
Although this may seem obvious, magic tricks must appear impossible. Something must be done that appears to defy the accepted laws of the universe. Cut someone in half, without killing them. Make someone disappear. Read our minds. Magicians make the impossible possible. Compare this to the world of innovation where we're typically only looking to make the possible possible. How can we learn from this mindset? When looking for solutions to a pressing, ask yourself these starter questions: What would be an impossible solution? What is the worst solution? What solution might get us arrested? Then ask, what are the attributes you like about these "crazy" ideas and how can I leverage them to find an unusual yet workable solution?
3. Performance is as important as the method.
Anyone can perform tricks. But real magicians know there is much more to magic than knowing the secret. On Britain's Got Talent, one of the finalists performed a trick I bought years ago for about $20 at a local magic shop. It is simple to do. When I perform it, it is mildly entertaining. When he performed it, it was a minor miracle. With innovation, the performance is as important as the solution. New technology is great, but you need to back it up with excellent human support. The experience your customers have with your new innovation is as important as the innovation itself. Technology can easily be replicated by your competition. However, a good performance is much more difficult to copy.
I was recently at a convention with 500 magicians. Given I'm a magic geek, I loved it. But over time I've come to realize that the real magicians are the hard-working people in companies who are trying to make the world a better place through innovation. And when we view innovation through the lens of magic, it can even make it more enjoyable. Or as Walt Disney once said, "It's kind of fun to do the impossible." Now go make some magic!
PUBLISHED ON: APR 17, 2018
野心的な起業家がマジシャンから学ぶべき「3つのトリック」
Inc.
2018/04/28
優れたマジシャンが持つスキルは、野心的な起業家にも当てはまるものだ。みなさんは必要なスキルを持っているだろうか。
マジックとイノベーションの共通点
私は長らくマジックを愛してきた。私にとってマジックは、単なるエンターテインメントを超えた知的な試みだ。このイリュージョンの仕掛けはどうなっているのかと考えるのが楽しいのだ。といっても実際の答えは重要ではなく、そのイリュージョンについて考えるプロセスを楽しんでいたのだ。
私が若いころ、『Breaking the Magician's Code』(破られたマジシャンの掟!)というテレビ番組があった。「覆面のマジシャン」が毎週、有名なトリックの種明かしをするというものだ。
現在はネットフリックスで配信されているこの番組で、覆面のマジシャンはまず、観客が通常見るとおりにイリュージョンを実演する。次にその同じトリックを、今度は仕掛けがわかるようにやってみせる。
私はいつも、マジシャンが最初にトリックを披露して、種明かしをする前で一時停止して、思いつくトリックの答えをすべて書き出すことにしていた。少なくとも1つは答えを思いついてから、種明かしのパートを観るのだ。
種明かしはたいてい、トリックを異なるカメラアングルから映す形で披露された。違う角度から見ると、答えが一目瞭然でわかる。
私のマジックへの愛は幼いころに芽生えたが、年月を経てみると、マジックとイノベーションはよく似ていることに気づく。共通点はいろいろあるが、私がマジックの研究を通じて学んだイノベーションの秘訣を3つ、以下にご紹介しよう。
1. 脳はだまされる
マジックが人を驚かすのは、脳が見たものすべてを正確に処理するとは限らないからだ。脳はときに近道をとり、推測を立て、空白を埋める(しばしば間違ったやり方で)。
誰かが箱の中に入って体を隠し、頭と足だけを出したら、その足は箱から出ている頭と同じ人間のものだと、われわれは自動的に推測する。しかし、実際は違っているとしたら──。
イノベーションにおいても、われわれの脳はしばしばだまされる。近道して空白を埋めた結果、不完全なソリューションにたどり着くのだ。
新しいアイデアを練るときは、いろいろな角度から見てみることが肝心だ。見落としている点はないか。推測しているところはないか。マジックの種明かしと同じで、カメラアングルを変えてみることが必要なのだ。
2.「不可能」を出発点にする
言うまでもないことかもしれないが、マジックのトリックは不可能に見えるものでなくてはならない。この世の普遍的法則を無視しているかのような、何らかの仕掛けを施さなくてはならない。
人間を生きたまま真っ二つにしたり、その場から消し去ったり、相手の心を読んだりと、マジシャンは不可能を可能にする。
それに比べてイノベーションの世界では、たいていは、最初から可能なことを実現しようとしてばかりだ。そんな姿勢から、どうやって何かを学ぶことができるだろう。
問題のソリューションを見つけようとするときは、まず初めにこんな問いを自分に投げかけてみるといい。「不可能なソリューションにはどんなものがあるか」「最悪のソリューションとは」「下手をすると逮捕されかねないソリューションとは」
問いに答えたら、次にこれらの「クレイジーな」アイデアで自分が気に入った要素はどこか、またそうした要素を生かして普通ではないが実現可能なソリューションを見つけ出すにはどんな方法があるかと、考えを巡らせてみよう。
3. パフォーマンスはトリックと同じくらい重要
トリックを実演するだけなら誰だってできる。しかし本物のマジシャンは、マジックとはネタを知っていればいいというものではないことを理解している。
オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で、あるファイナリストが実演したトリックは、私が何年も前に地元のマジックショップで20ドルほどで購入したものだった。いたって簡単なトリックだ。
私がそれを実演しても、ちょっとした余興にしかならない。しかし、そのファイナリストが実演してみせたトリックは、ちょっとした奇跡だった。
イノベーションにおいても、パフォーマンスはソリューションと同じくらい重要だ。最新のテクノロジーがいくら素晴らしくても、われわれ人間の優れたサポートが欠かせない。新たなイノベーションが顧客にどんな体験をもたらすかは、イノベーションそのものと同じくらい重要だ。
テクノロジーは、たやすくライバルに取って代わられることもある。しかし、優れたパフォーマンスを真似るのは、それよりはるかに難しいことだ。
* * *
私は先日、500人のマジシャンが集まるコンベンションに参加した。マジックおたくの私はおおいに楽しんだが、しかし時間が経つにつれて、本物のマジシャンとは、企業においてイノベーションを通じて世界をより良くしようと熱心に働いている人々なのではないかと気づいた。
そして、マジックというレンズを通してイノベーションを見ると、それはいっそう楽しいものに思える。かつてウォルト・ディズニーが言ったように「不可能と思われることをやってのけるのは、けっこう楽しいこと」なのだ。われわれもマジックを実現してみせよう。
原文はこちら(英語)。
(執筆:Stephen Shapiro、翻訳:高橋朋子/ガリレオ、写真:mazartemka/iStock)
©2018 Mansueto Ventures LLC; Distributed by Tribune Content Agency, LLC
This article was translated and edited by NewsPicks in conjunction with IBM.