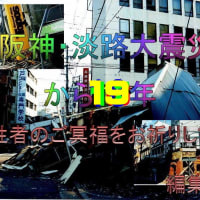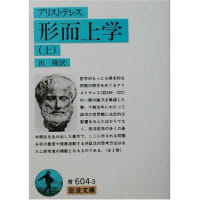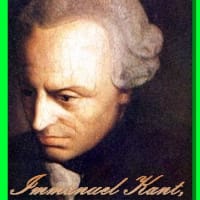日本側の韓国併合に向けての動きも急ピッチになった。首相の桂太郎と外相の小村寿太郎は、一九〇九年四月一〇日、一時帰国していた伊藤博文を説得すべく、大磯の自宅を訪問した。韓国併合に逡巡する伊藤に決断を迫ったのである。意外にも伊藤は、すぐさま、首相と外相の韓国併合論に賛成した。ただし、列強の反発を買わない工夫とタイミングが必要であると力説したという(信夫[一九四二]、三〇〇ページ)。
桂は、伊藤の同意を受けて、元帥陸軍大将・山縣有朋(やまがた・ありとも)にも報告している。山縣は、当時の日本における最高指導者であった。一九〇九年四月一七日付の山縣宛書簡において、桂は、韓国皇帝が何らかのミスを冒してくれれば併合がし易くなるのだがとの、陰謀工作を示唆することを書いている。徳富蘇峰の『桂伝』には陰謀を示す桂の言葉は意図的に除外されているが(徳富[一九一七]下巻、四五四ページ)、山辺健太郎の資料にはこの言葉が収録されている(山辺[一九六六]、二一六ページ)。
そして、一九〇九年七月七日、韓国併合の方針が閣議で了承された。閣議で、桂首相は、鍵を握っているのは、ロシアとの合意であり、ロシアの合意を得られ次第、併合に踏み切ると語った(徳富[一九一七]下巻、四六五ページ)。
当然ながら、韓国併合を決意し、ロシアを引き込もうと工作している日本に英米は反発した。同盟国の英国側を懐柔すべく、統監の伊藤博文は、ロシアとの交渉の中身をある程度は英国に伝えておくようにと小村寿太郎に要請しているが(一九〇九年一〇月一日付伊藤の桂宛書簡、徳富[一九一七]下巻、四六六ページ)、効果はなかった。
上述の米国のF・ウィルソンは、一九〇九年九月に満州・韓国問題で清・露と協議していた日本の動きを、米国が推進する門戸開放政策に敵対するものだと牽制した(Hunt[1973], p.205)。
第二次桂内閣の逓信大臣であった後藤新平(しんぺい)が、当時のロシアとの太いパイプを持っていたらしい。彼の斡旋で、伊藤・統監がロシアの大蔵大臣・ココフツォフ(Vladimir Nikolayevich Kokovtsov)に面会すべく、一九〇九年一〇月一四日、ハルピンに向けて旅立った(Lone[1991], p. 160)。そして、ほぼ二週間後の一〇月二六日、既述のように、ハルピン駅頭で安重根によって射殺されたのである。
伊藤暗殺を知らせる電報が入った時、桂は英国の駐日大使・クロード・マクドナルド(Claude MacDonald)と面会していた。桂は、伊藤暗殺後も日本の対外姿勢に変化はない、つまり、対英協調を継続しつつ韓国併合は行うと明言したとマクドナルドが、英国の外務大臣・グレイに報告している(F. O.[1909], 410/54, MacDonald to Grey, 28 October, 1909)。
桂の姿勢を見た英米は、日本の新たな満州権益を阻止する点で協同行動を採ることになった。一九〇九年一一月九日には、ノックスが英国の外務大臣(Foreign Secretary)のエドワード・グレイ(Edward Grey)に、当分の間、満州鉄道を国際的協調団による共同管理に委ね、然るべき時がくれば清に買収させるという米国案への賛成を求めた(Hunt[1973], p. 205)。
韓国併合に踏み切るとした閣議決定を受けて、小村は、一九一〇年三月一九日、セント・ペテルスブルグ(St. Petersburg)駐在の日本大使・本野(もとの)一郎にロシアとの第二回の対話再開を行うように指令した(第一回協約は一九〇七年)。しかし、ロシアの外務大臣、アレキサンダー・イズボルスキー(Alexander Iswolsky)は、一九一〇年四月段階では、韓国に関する現状の如何なる変更も許さないとの強硬姿勢であったが、本野一郎が、一九〇七年段階でロシアは日本の韓国領有は認めていたはずだと突っぱね、イズボルスキーも、当時の皇帝(Tzar)・ニコライ二世(Nicholai Aleksandrovich Romanov)を説得してみると折れた(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/j_russia_2005/2_4.html)。
一九一〇年五月には、駐日英国大使のマクドナルドは、韓国併合は認められない、その点では米国も同様であると何度も桂首相に警告し、本国に状況が急展開しそうだと打電している(F. O.[1910], 410/55, MacDonald to Grey, 19 and 22 May, 1910)。
しかし、最終的には、一九一〇年七月四日、「第二回日露協約」と「秘密協約」が調印され、日露間で満州・韓国問題の秘密合意が成立した(徳富[一九一七]、下巻、四四〇~四二ページ)。
第一次世界大戦中、有名な「石井・ランシング協定」が日米間で交わされた。これは、一九一七年一一月二日、ワシントンで、特命全権大使・石井菊次郎と米国務長官・ロバート・ランシング(Robert Lansing)との間で締結された協定である。建て前的には中国に領土保全を保証し、中国における各国の商工業活動の機会均等という従来からの米国の主張を日本が承諾したことになっていたが、実際には、満州と内蒙古東部における日本の「特殊の権利または特典」を米国が承認するという日本側に有利な内容であった。この日本に有利な協定は、ワシントンで締結された一九二三年四月一四日の「九か国条約」で廃棄された(池田[一九九四]、参照)のであるが、「石井・ランシング協定」を含め、ランシングの独断専行は当時の大統領のウッドロー・ウィルソン(Woodrow Wilson)を悩ませ、一九二〇年にはウィルソンはランシングに辞任を命じた(http://www.firstworldwar.com/bio/lansing.htm)。
日本に有利な「石井・ランシング」協定は、第一次世界大戦に全面的に参戦する米国が、太平洋での安全保障に不安を抱き、ハワイの防衛を日本に委任しようとしていたからであるとも言われている(Macmurray[1935]、参照)。
いずれにせよ、日本の韓国併合が、西太平洋・東アジアの緊張関係の中心にあったことが、当時の国際関係史を簡単に振り返るだけでも理解できるだろう。
桂は、伊藤の同意を受けて、元帥陸軍大将・山縣有朋(やまがた・ありとも)にも報告している。山縣は、当時の日本における最高指導者であった。一九〇九年四月一七日付の山縣宛書簡において、桂は、韓国皇帝が何らかのミスを冒してくれれば併合がし易くなるのだがとの、陰謀工作を示唆することを書いている。徳富蘇峰の『桂伝』には陰謀を示す桂の言葉は意図的に除外されているが(徳富[一九一七]下巻、四五四ページ)、山辺健太郎の資料にはこの言葉が収録されている(山辺[一九六六]、二一六ページ)。
そして、一九〇九年七月七日、韓国併合の方針が閣議で了承された。閣議で、桂首相は、鍵を握っているのは、ロシアとの合意であり、ロシアの合意を得られ次第、併合に踏み切ると語った(徳富[一九一七]下巻、四六五ページ)。
当然ながら、韓国併合を決意し、ロシアを引き込もうと工作している日本に英米は反発した。同盟国の英国側を懐柔すべく、統監の伊藤博文は、ロシアとの交渉の中身をある程度は英国に伝えておくようにと小村寿太郎に要請しているが(一九〇九年一〇月一日付伊藤の桂宛書簡、徳富[一九一七]下巻、四六六ページ)、効果はなかった。
上述の米国のF・ウィルソンは、一九〇九年九月に満州・韓国問題で清・露と協議していた日本の動きを、米国が推進する門戸開放政策に敵対するものだと牽制した(Hunt[1973], p.205)。
第二次桂内閣の逓信大臣であった後藤新平(しんぺい)が、当時のロシアとの太いパイプを持っていたらしい。彼の斡旋で、伊藤・統監がロシアの大蔵大臣・ココフツォフ(Vladimir Nikolayevich Kokovtsov)に面会すべく、一九〇九年一〇月一四日、ハルピンに向けて旅立った(Lone[1991], p. 160)。そして、ほぼ二週間後の一〇月二六日、既述のように、ハルピン駅頭で安重根によって射殺されたのである。
伊藤暗殺を知らせる電報が入った時、桂は英国の駐日大使・クロード・マクドナルド(Claude MacDonald)と面会していた。桂は、伊藤暗殺後も日本の対外姿勢に変化はない、つまり、対英協調を継続しつつ韓国併合は行うと明言したとマクドナルドが、英国の外務大臣・グレイに報告している(F. O.[1909], 410/54, MacDonald to Grey, 28 October, 1909)。
桂の姿勢を見た英米は、日本の新たな満州権益を阻止する点で協同行動を採ることになった。一九〇九年一一月九日には、ノックスが英国の外務大臣(Foreign Secretary)のエドワード・グレイ(Edward Grey)に、当分の間、満州鉄道を国際的協調団による共同管理に委ね、然るべき時がくれば清に買収させるという米国案への賛成を求めた(Hunt[1973], p. 205)。
韓国併合に踏み切るとした閣議決定を受けて、小村は、一九一〇年三月一九日、セント・ペテルスブルグ(St. Petersburg)駐在の日本大使・本野(もとの)一郎にロシアとの第二回の対話再開を行うように指令した(第一回協約は一九〇七年)。しかし、ロシアの外務大臣、アレキサンダー・イズボルスキー(Alexander Iswolsky)は、一九一〇年四月段階では、韓国に関する現状の如何なる変更も許さないとの強硬姿勢であったが、本野一郎が、一九〇七年段階でロシアは日本の韓国領有は認めていたはずだと突っぱね、イズボルスキーも、当時の皇帝(Tzar)・ニコライ二世(Nicholai Aleksandrovich Romanov)を説得してみると折れた(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/j_russia_2005/2_4.html)。
一九一〇年五月には、駐日英国大使のマクドナルドは、韓国併合は認められない、その点では米国も同様であると何度も桂首相に警告し、本国に状況が急展開しそうだと打電している(F. O.[1910], 410/55, MacDonald to Grey, 19 and 22 May, 1910)。
しかし、最終的には、一九一〇年七月四日、「第二回日露協約」と「秘密協約」が調印され、日露間で満州・韓国問題の秘密合意が成立した(徳富[一九一七]、下巻、四四〇~四二ページ)。
第一次世界大戦中、有名な「石井・ランシング協定」が日米間で交わされた。これは、一九一七年一一月二日、ワシントンで、特命全権大使・石井菊次郎と米国務長官・ロバート・ランシング(Robert Lansing)との間で締結された協定である。建て前的には中国に領土保全を保証し、中国における各国の商工業活動の機会均等という従来からの米国の主張を日本が承諾したことになっていたが、実際には、満州と内蒙古東部における日本の「特殊の権利または特典」を米国が承認するという日本側に有利な内容であった。この日本に有利な協定は、ワシントンで締結された一九二三年四月一四日の「九か国条約」で廃棄された(池田[一九九四]、参照)のであるが、「石井・ランシング協定」を含め、ランシングの独断専行は当時の大統領のウッドロー・ウィルソン(Woodrow Wilson)を悩ませ、一九二〇年にはウィルソンはランシングに辞任を命じた(http://www.firstworldwar.com/bio/lansing.htm)。
日本に有利な「石井・ランシング」協定は、第一次世界大戦に全面的に参戦する米国が、太平洋での安全保障に不安を抱き、ハワイの防衛を日本に委任しようとしていたからであるとも言われている(Macmurray[1935]、参照)。
いずれにせよ、日本の韓国併合が、西太平洋・東アジアの緊張関係の中心にあったことが、当時の国際関係史を簡単に振り返るだけでも理解できるだろう。