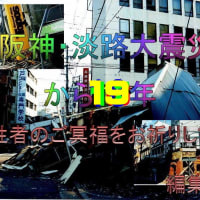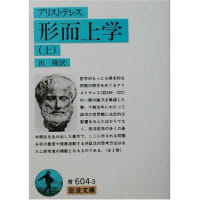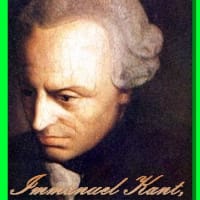日本の不平等条約改正の足取りを整理しておこう。明治政府にとっての重要な外交課題は、幕末に締結された安政の仮条約が不平等条約の改正、つまり、治外法権の撤廃、関税自主権の回復であった。
まず、一八七一年、岩倉遣外使節団を派遣し、条約改正予備交渉に着手したが失敗した。
欧米諸国を相手にしての正式の関税自主権の回復交渉は、一八七八年、寺島宗則外務卿の時に開始された。この時、米国が賛成したが、英国、ドイツの反対で交渉は不成功に終わった。
一八八六年、第一次伊藤内閣の外務大臣・井上馨が条約改正のための会議を諸外国の使節団と改正会議を行う。しかし、その提案には外国人判事の任用などの譲歩を欧米に示したため、小村寿太郎、鳥尾小弥太、法律顧問・ボアソナードがこれに反対意見を提出し、民権派による抗議・爆弾テロで負傷し、一八八七年に辞任、改正交渉は失敗。
一八八八年、外務大臣・大隈重信が、治外法権廃止を第一に交渉に臨み、米国、ドイツ、ロシアの賛意を得たが、交渉に際して、大審院に限定したとはいえ、外国人判事を任用するとしたために、憲法違反であるとの反対をうけ、彼も爆弾テロで負傷して、一八八九年辞職した。
一八九一年、外務大臣・青木周蔵が、六年後に治外法権撤廃・関税自主権回復させるという交渉に臨み、治外法権については、英国の同意は得たものの、大津事件のために同年辞職を余儀なくされ、交渉は中断することになった。
一八九四年、第二次伊藤内閣の外相・陸奥宗光が、治外法権撤廃に照準を定め、各国別に交渉し、日清戦争直前に治外法権を完全に撤廃した日英通商航海条約の調印に成功した。さらに関税率の一部引き上げにも成功し、居留地の廃止と外国人の内地雑居が実現した。
陸奥外相の条約改正後は、残された関税自主権の回復が改正の眼目となったが、一九一一年、第二次桂内閣の外相の小村寿太郎が、日露戦争後の国際的地位の向上を利用して、関税自主権回復に成功した(http://note.masm.jp/%C9%D4%CA%BF%C5%F9%BE%F2%CC%F3/、二〇一〇年八月一六日アクセス)。
一八九四年の通商条約では、欧米からの輸入品にかける日本の関税水準は、まだ日本に不利なものであった。しかし、一九〇九年二月、日本政府は英国製品の輸入関税を五〇〇%に引き上げるという法外な提案を英国に対して行った(Hotta-Lister[1999], p. 43)。これは、日本政府が関税自主権の回復に英国の政治力を使おうとしたからであろう。
当時は、内外で保護主義が高まり、自由貿易を国是とする英国は大きな岐路に立っていた。ドイツ、米国の保護主義によって、英国製品は世界市場から駆逐されるという恐怖を英国産業界は抱いていた。関税率交渉をめぐる大議論が英国内で沸騰しているまさにその局面で日本政府が英国に対して居丈高な要求をしたのである。そもそも関税の自主権がなく、それまでの交渉がことごとく失敗してきたのに、一九〇九年に五〇〇%課税という法外な要求をしたのは、日本側に勝算があったのだろう。
日本との関税改革交渉は、英国にとって非常に重要な課題であった。後に保守党で首相になったアンドリュー・ロー(Andrew Bonar Law)が、一九一〇年一一月、マンチェスター・自由貿易・ホール(Manchester's Free Trade Hall)で保護主義の導入を呼びかける講演をした。そして彼は、日本の工業力の台頭への恐れを表明した。日本のよく組織された安価な労働力が日本の綿産業を支えている。いまは目立たないがいずれは、インド市場などで日本の綿製品が溢れるようになり、英国製品は強力な厳しい競争にさらされることになるだろう。こうした事態の到来を避けるためにも、特恵を供与できる体制を作っておく必要があると訴えたのである(Law[1910])。
英国が実際に自由貿易原則を棄てるのは、第一次世界大戦中の一九一五年のマッケナ関税(McKenna duties)(5)まで待たねばならないが、少なくとも二〇世紀に入ってからの関税論議は英国経済の斜陽化を示すものであった(Hunter[2003], p. 16)。
幼稚産業を保護しなければならなかった日本が関税自主権を回復することが至上命令であったことは当然である。
ちなみに、一八七〇年から第一次世界大戦勃発前の一九一三年にかけての世界の輸出額は、年平均で三・四%ののびを示していた。ところが、英国の輸出の伸びは小さかった。同期間の英国の輸出額は年率二・八%の伸びにすぎなかった。日本は八・五%であった(Maddison[2001], p. 362)。
貿易だけではない。一八九〇年代から一九〇〇年代には、成熟国から新興国への国際的な資本移動も活発であった。日本について言えば、一八九七年に金本位制を採用した効果が大きかった。金の裏付けのある円は、投資家の信用を得る強い武器であった。
日英同盟下で、日本は、中央政府はもとより、地方自治体、公共団体が積極的にロンドンで起債した。ただし、規模から言えば、日本への英国資本の流入は他地域に比べてまだまだ小さかった。
日英同盟によって、国際金融市場であるロンドンから資金を呼び込もうとする意図が日本政府にあったのは当然であろう。しかし、日本の期待に反して、国際資金の日本への流入は芳しくなかった(Nish[1966], p. pp. 253-55)。日本政府も日本企業もロンドン金融市場からの借入には困難を覚えていたのである。
一九一四年の国際資本移動に占める英国資本のシェアは四三%もあった。しかし、そのほとんどは米国、ラテンアメリカ、英国自治領、英領植民地に向かい、非英連邦域には、二%前後でしかなかった(Kenwood & Lougheed[1994], pp. 27-29)。例え、日英同盟が結ばれていても、ロンドンの金融界は日本に魅力を感じていなかったのである。
それでも、日露戦争の軍事費調達にあたっては、よく知られているように、クーン・レーブ商会(Kuhn Loeb & Co.)のジェイコブ・シフ(Jacob Henry Schiff, 1847-1920)(6)の貢献が大きかった。当時の日本銀行副総裁・高橋是清による起債活動をユダヤ人のシフが応援し、第一回起債予定額一〇〇〇万ポンドのうち、五〇〇万ポンドをシフが引き受けたのである。
まず、一八七一年、岩倉遣外使節団を派遣し、条約改正予備交渉に着手したが失敗した。
欧米諸国を相手にしての正式の関税自主権の回復交渉は、一八七八年、寺島宗則外務卿の時に開始された。この時、米国が賛成したが、英国、ドイツの反対で交渉は不成功に終わった。
一八八六年、第一次伊藤内閣の外務大臣・井上馨が条約改正のための会議を諸外国の使節団と改正会議を行う。しかし、その提案には外国人判事の任用などの譲歩を欧米に示したため、小村寿太郎、鳥尾小弥太、法律顧問・ボアソナードがこれに反対意見を提出し、民権派による抗議・爆弾テロで負傷し、一八八七年に辞任、改正交渉は失敗。
一八八八年、外務大臣・大隈重信が、治外法権廃止を第一に交渉に臨み、米国、ドイツ、ロシアの賛意を得たが、交渉に際して、大審院に限定したとはいえ、外国人判事を任用するとしたために、憲法違反であるとの反対をうけ、彼も爆弾テロで負傷して、一八八九年辞職した。
一八九一年、外務大臣・青木周蔵が、六年後に治外法権撤廃・関税自主権回復させるという交渉に臨み、治外法権については、英国の同意は得たものの、大津事件のために同年辞職を余儀なくされ、交渉は中断することになった。
一八九四年、第二次伊藤内閣の外相・陸奥宗光が、治外法権撤廃に照準を定め、各国別に交渉し、日清戦争直前に治外法権を完全に撤廃した日英通商航海条約の調印に成功した。さらに関税率の一部引き上げにも成功し、居留地の廃止と外国人の内地雑居が実現した。
陸奥外相の条約改正後は、残された関税自主権の回復が改正の眼目となったが、一九一一年、第二次桂内閣の外相の小村寿太郎が、日露戦争後の国際的地位の向上を利用して、関税自主権回復に成功した(http://note.masm.jp/%C9%D4%CA%BF%C5%F9%BE%F2%CC%F3/、二〇一〇年八月一六日アクセス)。
一八九四年の通商条約では、欧米からの輸入品にかける日本の関税水準は、まだ日本に不利なものであった。しかし、一九〇九年二月、日本政府は英国製品の輸入関税を五〇〇%に引き上げるという法外な提案を英国に対して行った(Hotta-Lister[1999], p. 43)。これは、日本政府が関税自主権の回復に英国の政治力を使おうとしたからであろう。
当時は、内外で保護主義が高まり、自由貿易を国是とする英国は大きな岐路に立っていた。ドイツ、米国の保護主義によって、英国製品は世界市場から駆逐されるという恐怖を英国産業界は抱いていた。関税率交渉をめぐる大議論が英国内で沸騰しているまさにその局面で日本政府が英国に対して居丈高な要求をしたのである。そもそも関税の自主権がなく、それまでの交渉がことごとく失敗してきたのに、一九〇九年に五〇〇%課税という法外な要求をしたのは、日本側に勝算があったのだろう。
日本との関税改革交渉は、英国にとって非常に重要な課題であった。後に保守党で首相になったアンドリュー・ロー(Andrew Bonar Law)が、一九一〇年一一月、マンチェスター・自由貿易・ホール(Manchester's Free Trade Hall)で保護主義の導入を呼びかける講演をした。そして彼は、日本の工業力の台頭への恐れを表明した。日本のよく組織された安価な労働力が日本の綿産業を支えている。いまは目立たないがいずれは、インド市場などで日本の綿製品が溢れるようになり、英国製品は強力な厳しい競争にさらされることになるだろう。こうした事態の到来を避けるためにも、特恵を供与できる体制を作っておく必要があると訴えたのである(Law[1910])。
英国が実際に自由貿易原則を棄てるのは、第一次世界大戦中の一九一五年のマッケナ関税(McKenna duties)(5)まで待たねばならないが、少なくとも二〇世紀に入ってからの関税論議は英国経済の斜陽化を示すものであった(Hunter[2003], p. 16)。
幼稚産業を保護しなければならなかった日本が関税自主権を回復することが至上命令であったことは当然である。
ちなみに、一八七〇年から第一次世界大戦勃発前の一九一三年にかけての世界の輸出額は、年平均で三・四%ののびを示していた。ところが、英国の輸出の伸びは小さかった。同期間の英国の輸出額は年率二・八%の伸びにすぎなかった。日本は八・五%であった(Maddison[2001], p. 362)。
貿易だけではない。一八九〇年代から一九〇〇年代には、成熟国から新興国への国際的な資本移動も活発であった。日本について言えば、一八九七年に金本位制を採用した効果が大きかった。金の裏付けのある円は、投資家の信用を得る強い武器であった。
日英同盟下で、日本は、中央政府はもとより、地方自治体、公共団体が積極的にロンドンで起債した。ただし、規模から言えば、日本への英国資本の流入は他地域に比べてまだまだ小さかった。
日英同盟によって、国際金融市場であるロンドンから資金を呼び込もうとする意図が日本政府にあったのは当然であろう。しかし、日本の期待に反して、国際資金の日本への流入は芳しくなかった(Nish[1966], p. pp. 253-55)。日本政府も日本企業もロンドン金融市場からの借入には困難を覚えていたのである。
一九一四年の国際資本移動に占める英国資本のシェアは四三%もあった。しかし、そのほとんどは米国、ラテンアメリカ、英国自治領、英領植民地に向かい、非英連邦域には、二%前後でしかなかった(Kenwood & Lougheed[1994], pp. 27-29)。例え、日英同盟が結ばれていても、ロンドンの金融界は日本に魅力を感じていなかったのである。
それでも、日露戦争の軍事費調達にあたっては、よく知られているように、クーン・レーブ商会(Kuhn Loeb & Co.)のジェイコブ・シフ(Jacob Henry Schiff, 1847-1920)(6)の貢献が大きかった。当時の日本銀行副総裁・高橋是清による起債活動をユダヤ人のシフが応援し、第一回起債予定額一〇〇〇万ポンドのうち、五〇〇万ポンドをシフが引き受けたのである。