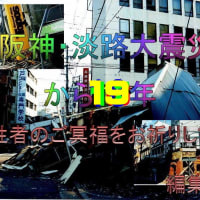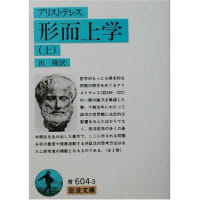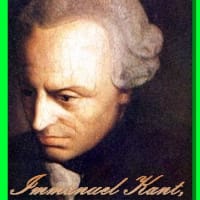「お金儲けは悪いことですか?」と尋ねられたらこう答えよう。「悪いことです。あなたの巨額の儲けの陰で、無数の人々が露頭に放り出された」と。少々罰金をくらっても、はるかに多くを貯め込めた人たちが、今後とも輩出するであろう。
金儲けが悪いことであることを戦前の日本の農村の悲惨な状況で説明しよう。
不在地主が農村を破壊した
戦前の日本を破産に導いたのは、農村の貧しさであった。不在地主一人の収入が、村のすべての小作人の収入を上回っていた。人は、絶対的には低くても、平均線上に自分の収入があるとき、それほどの怒りに駆られることはない。しかし、突出した少数の人たちに収入が独占され、圧倒的多数の人々が平均線上よりはるかに少ない収入しか得られないとき、人々は強烈な貧しさの感情に打ちのめされる。戦前の日本の農村の多くは、後者の状態にあった。
そもそも、農業は儲からない代表的な産業である。農民は借金を重ね、借金返しのために、農地を手放した。悪辣な金貸しが農地を取り上げた。金貸しは大地主になった。土地を手に入れた金貸しは、土地なき農民に農地を貸し出し、小作料のつり上げに血道を上げた。土地なき貧農が増えれば増えるほど、小作料はつり上がった。農民の貧困が不在地主の懐を潤した。そして、地主に転がり込んだ莫大な小作料収入は、農地の改良事業に投資されず、さらなる農地の買い占めに投資された。
小作人も、永年の小作権を保証されないために、短期で目一杯の収益を得るべく、土地を酷使した。契約が保証されている短い期間に最大の収穫を得るべく、土地の生産能力の長期的維持という観点を脱落させて、土地の能力のすべてを消費し尽くすという略奪的農業に、小作人たちは向かわざるを得なかった。こうしてわずかの温度変化にも耐えられない農地が増えてしまった。貧困の悪循環に戦前の日本の農村は陥っていた。
しかし、戦前の為政者たちは、農村の改善よりも、植民地の農地を零細な日本の農民に分配する政策を選択した。貧しい農民ほど好戦的にならざるを得なかった。
金融が社会を破壊する
金融業のみが繁栄し、圧倒的多数の給与生活者が将来を保証されなくなるとき、戦前の農民と同じく、従業員の現場が崩壊する。職場が生き甲斐ではなく、恐怖の場となり、対話の場でなく、他人を蹴飛ばす地獄の場となる。
市場は合理的であると、金儲け至上主義者から、お題目のように語られる。しかし、市場はけっして公平ではない。栄耀栄華の生活を送っている人々の職業を見れば、もっとも端的にそれが分かるであろう。
一攫千金のチャンスを生かした人々の中で、何万人の人員を雇用している「モノ作り」の経営者はいるのであろうか。豪邸を誇るのは、特定の産業のオーナーだけである。金融を生業とし、人の射幸心を煽る産業部門の経営者に金持ちが集中している。
産業は、二種類に区分される。素人相手の産業は、素人が正確なコストを知らないという事情もあって、供給者が、価格決定の主導権をもつ。それに対して、玄人相手の産業では、製品価格は、寡占度の高い購買者によって決定される。このような状況があるために、玄人相手の産業は儲からない。
もし、市場が、完全に自由になり、儲けが市場の唯一の価値判断になってしまえば、儲からない玄人相手の産業部門は衰退し、素人相手の産業部門だけが生き残るであろう。
市場経済が、全面開花すれば、社会は儲かる産業のみが残存することになる。儲かる産業とは、従業員を酷使し、設備投資も行わず、ビルのような不動産も、工場ももたず、ひたすらマスコミにおもねる身軽な産業に限りなく傾斜する。その典型が金融業である。
このぬかるみはいつまで続くのか。社会に英知があれば、早晩悪徳金融は廃絶されるだろうに。
戦後の日本は、儲かる産業と、儲からない産業とを区分した、それぞれの業態に応じた金融組織の棲み分けがあった。
このような合理的な金融組織が、護送船団方式の打破という、米国発のスローガンによって破壊され、金融のデパート化を目指した自由化によって、金融組織は、儲からない「モノ作り」から離れ、儲かるファンド投資に傾斜することになった。
日本の金融組織は、儲からない産業部門を見捨てて、儲かるファンドに急速に投資するようになった。
金融庁が、平成十九年三月十五日、国内金融機関のヘッジファンドへの投資実績の数値を発表した。金融機関によるヘッジファンド商品投資は、平成十七年度で、約三兆円と、前年よりも約四〇%増えた。平成十二年度では約〇・三兆円であったのだから、わずか五年で、六倍にも増えたのである。
ファンドの主役は、M&Aである。しかし、転売目当てのM&Aは、従業員の首切りを、大前提にする。
ゴールドマンサックスのCEO(最高経営責任者)の平成十八年のボーナス以外の報酬は七千万円、ボーナスは六十三億円もあった。つまり、報酬のほとんどは、業績連動型のものであった。経営陣が、マネーゲームで巨額の報酬を得ているという事態を、額に汗して働く庶民が、平静に受け止めることは不可能である。
これは、戦前の日本の寄生地主と水呑み百姓の構図そのものである。農地に匹敵する企業の職場が崩壊してしまうことは不可避である。
「業績連動報酬制度」が経営者のモラルをゆがめている
日興コーディアルの不正会計が世上を賑わしている。この不正行為は、主としてコールセンター大手の「ベルシステム二四」の増資、吸収を巡る過程から発生したものであることは明白である。
平成十九年一月七日、証券取引等監視委員会の勧告に基づき、金融庁が、日興コーディアルグループの提出書類に虚偽記載があったとして、証券取引法違反の疑いで、同社に五億円の課徴金支払い命令を出したのは、平成十七年三月期決算の内容が問題にされたからである。
日興コーディアルグループは、こうして利益を過大に見せかけた虚偽の決算報告を背景に、平成十七年十一月、総額五百億円の社債を発行した。利益が上がる会社という市場の信頼から、社債は、償還金利を安くしても売れた。虚偽の発表をして発行した有価証券の場合、発行額の百分の一が課徴金になるというのが証券取引法の規定である。日興の課徴金が五億円というのもそうした規定による。
ここで、問われるべきことは、虚偽報告を行う誘惑に駆られる原因である。そもそも、会社には、実態よりも利益があるとの見せかけをする誘因と、実態よりも利益が上がっていないと見せかける誘因とがある。どちらの虚偽の誘因に会社が駆られるのかは、時々の事情による。これまでは、利益の上がった会社が、法人税を支払いたくないために、利益を隠すというのが粉飾決算の一般的な姿であった。
しかし、近年の、粉飾決算の多くが、見せかけの過大利益を誇示している。ここに、問題の本質が横たわっている。
利益が上がれば株価が上がる。株価が上がれば、他社を株式交換で吸収し易くなる。そして、なによりも、経営陣は、ストック・オプション(価格が上がった株を売却して利益を得る権利)によって、自社株が上がれば自己の報酬を増やせる。
結論を言えば、諸悪の根源は、「業績連動報酬制度」にある。会社の業績が上がれば、ストック・オプションだけではなく、経営陣の役員報酬がそのまま増えるという仕組みが悪である。エンロンも、このような粉飾決算によって経営陣が莫大な報酬を得ていたことが糾弾されたのである。
米国の金融近代化法に従う日本
シティグループという金融コングロマリット(銀行、証券、保険、クレジットカードといったあらゆる金融業務を傘下にもつ金融組織)が日興コーディアルを傘下に納めようとすることは、日本の巨大証券会社が、外資の軍門に下るということ以上に巨大な意味をもつ。これで、銀行、証券、保険、クレジットカード間の垣根が事実上撤廃され、金融の縦横無尽の拡大領域が切り開かれたことになるからである。
米国の金融近代化法は、法案審議を主導した各委員長の名前を取って、「グラム・リーチ・ブライリー法」(一九九九年)として知られている。この法律によって、戦後体制は一挙に大恐慌以前の体制に戻された。銀行、保険、証券を分離するという、恐慌を経験した後の「グラス・スティーガル法」(一九三三年)による金融業務を分けていた垣根が撤廃され、これら金融機関の相互提携・相互参入が可能になったからである。金融に関するあらゆる業務が、金融持株会社を創設することで、一つの母体で運営されることが可能になったのである。六十六年間続いてきた米国の金融制度がこの法律によって大転換した。以降、米国のみならず、世界中で、金融コングロマリットが誕生することになった。
米国発の金融の自由化とは、グラス・スティーガル法を撤廃する動き以外のなにものでもなかった。大恐慌の教訓は、無惨にも踏みにじられてしまったのである。そして、日本は嬉々としてこの路線を踏襲している。
日興コーディアルという証券会社をシティグループという、銀行を含む巨大金融コングロマリットに売り渡すということは、活発な外資と提携して日本の金融市場を活性化させると、為政者は豪語するが、これは日本の憲法を改革することよりも巨大なインパクトをもつものである。つまり、シティグループによる日興の買収は、日本でも、銀行と証券、そして保険の垣根が木っ端微塵に破壊されることを意味している。日本人は、これを心底歓迎しているのであろうか。これで、金融機関はより安全になったと本気で考えているのであろうか。金融機関はますます脆弱なものになるべく奈落に落ちようとしているのではないだろうか。
株式が購買力となる。現金を使わずに株式の交換で企業を買収・転売できる。しかも、外資の親企業の株を使って(三角合併)。金融なって雇用が滅ぶ時代に入ってしまった。