3月最後の週末、ジャストタイミングで桜が満開の予想。
昨年は佐賀県に桜を見に行きましたので、今年は熊本県に行ってみることに。
行程は、九州道菊水ICで降りて、①山鹿エリア、②菊鹿エリア(相良寺など)、③菊池エリア、そして帰路に、④平山温泉に立ち寄り、九州道南関ICに乗る、という感じです。
 (熊本県の県北エリアをめぐります。)
(熊本県の県北エリアをめぐります。)
今回の小旅行では、満開の桜を見ることはもちろんですが、各エリアで訪れる寺社にお参りして御朱印をいただくことも楽しみ。
「山鹿灯籠」の繊細な和紙細工の超絶技巧を持つ「灯籠師」が手掛けた御朱印帳があります。
 (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。)
「記念に現地でこの御朱印帳を買って回ろう。」と計画していたところ、UCHさんが取り寄せてくれました。

御朱印帳のカバーは山鹿灯籠と同じ和紙で灯籠師が彫ったもの。
実物を手にすると、何とも言えない味わい・趣きがあります。
 (金色の紙は、御朱印の該当ページを示す❝しおり❞として使います。)
(金色の紙は、御朱印の該当ページを示す❝しおり❞として使います。)
実はこの御朱印帳、唯一販売している「山鹿灯籠民芸館」でも限定品、品薄で入手困難な一品。
UCHさん、ありがとうございました!
さて、九州道を快適にドライブし、最初の目的地をナビにセットするために玉名PAにイン。

福岡から1時間半かからず到着。
最初の目的地は、山鹿の市街地までの道中にある、「鍋田水遊び公園」と「鍋田横穴群」です。
 (写真左を上っていくと、「チブサン古墳」という古墳時代後期の前方後円墳があります。)
(写真左を上っていくと、「チブサン古墳」という古墳時代後期の前方後円墳があります。)
「鍋田横穴群」は、大正11年に国の史跡に指定されました。
 (柵のあたりの岩肌には絵(装飾)が彫られています。)
(柵のあたりの岩肌には絵(装飾)が彫られています。)
今から1400年以上も前の絵を間近に見ると、不思議な気持ちになります。
ほんの少し歩いてみるだけでも、横穴がたくさん。
 (こちらは絵は彫られていません。)
(こちらは絵は彫られていません。)
これらの横穴は、古墳時代後期に作られた「横穴墓」で、61基もあるそうです。
この横穴群を背にすると、そこには菊池川の支流の岩野川がゆったりと流れ、そして桜が満開です。
 (このあたりを「水遊び公園」と言うようです。)
(このあたりを「水遊び公園」と言うようです。)
川沿いの桜が川面に映ってとてもきれいでした。

こんなにいいスポットなのに散策しているのは私一人。
幸先よく桜の美しい景色を見ることができました。
これから、豊前街道沿いの山鹿の中心地に向かいます。
まずは、「山鹿灯籠民芸館」へ。

「山鹿灯籠」の紹介ビデオを観ながら、ボランティアの方と雑談。
その後、館内を回りながら、いろいろと説明していただけます。
有名な「山鹿灯籠」(全て和紙と糊のみで作られています)。

灯籠の頂点の擬宝珠(ぎぼし)、のりしろは無く、和紙の断面が斜めになるように切って、その断面同士を糊付けしているそうです。
そんな超絶技巧を持つ「灯籠師」は現在9人(上の写真の9人)とのこと。
この灯籠であれば設計図は頭の中に入っているので、約3日で完成させることができるそうです。
ホールの天井を見上げると、灯籠と、江戸時代に細川藩主が利用した「御前の湯」の天井に描かれていた狩野洞容(とうよう)作と伝えられる「双龍の絵」があります。

「山鹿灯籠まつり」のクライマックス「千人灯籠踊り」、観てみたいですねぇ。
 (昨年観覧しようと思いネットで予約を試みましたが、時すでに遅し、完売でした。)
(昨年観覧しようと思いネットで予約を試みましたが、時すでに遅し、完売でした。)
雨が降ると、灯籠にビニールをかぶせて踊るそうです。
「山鹿灯籠まつり」は頭上に乗せる灯籠だけでなく、「奉納灯籠」というのがあり、例えば、この静岡の「浅間神社」の細工なども「大宮神社」に奉納されるそうです。
 (この手の大作は制作に数ヶ月を要するそうです。灯籠師は多忙なり。御朱印帳が限定品になる所以かもしれません。)
(この手の大作は制作に数ヶ月を要するそうです。灯籠師は多忙なり。御朱印帳が限定品になる所以かもしれません。)
民芸館では別館で灯籠師の実演を見学できます。
今日は灯籠師のうち最若手の方が製作中。

カゴに置いてある細工は実際に手に取ることができますが、灯籠の擬宝珠、めちゃめちゃ軽い、そして継ぎ目を一切感じません、すごい!
山鹿灯籠は、その昔、菊池川一帯に立ちこめた深い霧に進路を阻まれた景行天皇のご巡幸を、山鹿の里人が松明を掲げて御迎えしたことに由来するそうです。
以来、里人達は毎年欠かさず「大宮神社」に松明を献上。和紙で作られた優美な金灯籠を奉納するようになったのは、室町時代に入ってから、とのことです
210円の入館料で、かなり勉強になった「山鹿灯籠民芸館」でした。
ほとんど観光客もいない豊前街道を少し散策してみます。
ポストはじめ、至る所で灯籠が乗っかっています。
 (この灯籠はもちろん金属製。)
(この灯籠はもちろん金属製。)
民芸館のすぐ近く、空海が開いた「金剛乗寺」。
 (独特の石門が密教っぽい。)
(独特の石門が密教っぽい。)
街中の山門というのも不思議な雰囲気です。

境内では桜がほぼ満開。

お参りをさせていただいたので、御朱印をいただこうと思いましたが、お宮参りでしょうか、みなさん忙しそうでしたので遠慮しました。
こちらは「八千代座」。

今日は座内を見学できる(貴重な)日らしいですが、十数年前に妻と来た時に、確か奈落の下まで見学した記憶があるので、外観だけにしました。
「八千代座」から引き返して、民芸館を通過して国道に出ると、足湯があります。
 (何とも広々とした贅沢な足湯広場です。)
(何とも広々とした贅沢な足湯広場です。)
国道向かいには、山鹿温泉の元湯「さくら湯」。

立ち寄り湯といきたいところですが、お天気が下り坂とのことで、先に進みます。
車に戻って、「大宮神社」へ。

ここでも駐車場(とても空いています)でお宮参りの準備をしているご家族がいました。
のぼりに書かれた「天皇陛下御在位三十年」という文字に、間もなく平成が終わるという雰囲気を感じます。

境内、独り占め状態。

山鹿灯籠の由来のある大宮神社ですので、奉納された灯籠が展示されているようです。
 (「燈籠殿」。)
(「燈籠殿」。)
お参りして御朱印をいただきました。

「平成」といただく御朱印は今回がおそらく最後かと思うと、感慨深いものがあります、、、。
次は、少し戻る感じになりますが、訪ねてみたかった「日輪寺」へ。
桜やツツジで有名とのことですので、「混み合っているかなぁ」と思ったら、ほぼ誰もいませんでした。(笑)
 (田原坂にも近いですからね。)
(田原坂にも近いですからね。)
日輪寺の山門(梵鐘)。
 (境内から見ていますので❝裏側❞です。)
(境内から見ていますので❝裏側❞です。)
山の中のお寺らしく、自然とすごく調和していて、落ち着く感じがします。
 (右の高台にあるのは、おそらくお食事処。)
(右の高台にあるのは、おそらくお食事処。)
日輪寺は、平安時代に天台宗の寺として開山、鎌倉時代に曹洞宗に改められ、歴代藩主(菊池武時、加藤清正、細川忠利など)から手厚く庇護された名刹。
忠臣蔵にも縁があり、細川藩にお預けとなった大石内蔵助ほか17人の遺髪を納めた「赤穂義士遺髪塔」があります。
お参りを。

お寺の方が見当たらないので、恐る恐る❝呼び鈴❞を押して、御朱印をお願いしました。

「なで佛はこちら」という朽ちかけた案内板があったので、登って行くと、びっくり。
巨大な像が。

高さ30mの大仏様で、「おびんずる(お賓頭盧)さま」。
「おびんずるさま」はお釈迦様のお弟子さん、16羅漢の1人で、神通力や超能力に優れていて、この像に触ると病気が治る、とのことです。
真正面からだと大きさのみに目が奪われますが、横から見ると、かなり反り返ってお立ちだそうで、人間なら転倒必至らしいです。(笑)
日輪寺は墓所でもあり、園内には桜が咲き誇っています。

中央に見える石橋は「湯町橋」で、1814年に鍋田(阿蘇凝灰岩の産地)の石工が造った、豊前街道の吉田川に架けられていたものを、河川改修のため昭和49年にこの地に移された、とのこと。
再び山鹿の中心地を抜けて、桜の名所「一本松公園」へ。
シンボル、「石のかざぐるま」。

中央の一番大きな風車で重さ16トン、羽根の直径は2.2メートル、でも、ススキの穂が揺れる程度の風で回るそうです。
実際、石であることを感じさせないくらい、音もなくグルグル回っていました。
この風車、このあたりに産出する石でできているのかと思いきや、スペイン産の赤御影石だそうです。(笑)
桜は、まぁ見事な咲きっぷりです。

さすがにお花見のお客さんが(今までのスポットよりは)大勢で、駐車するのに少し手間取りましたが、首都圏に比べれば楽勝。
みなさん、広々とした公園の芝生でゆったりとお花見されています。
 (これぐらいのゆったり感。)
(これぐらいのゆったり感。)
なだらかな山の斜面に公園があるので、ゆとりを感じます。

そして眺望もかなり良し。

そこかしこに古墳があります。

「石のかざぐるま」の近くにある「茶臼塚古墳」に昔「一本松」があったという案内板がありました。
一本松は枯れてしまったそうですが、公園の名の由来はきっとこの一本松でしょうね。
外観こそ斬新ですが、店内はかなりレトロな売店があります。

昭和の香りのする遊具に囲まれるように売られているうちわが目を引きます。

このあたりの地区、鹿本町来民(くたみ)は、「来民渋うちわ」(和紙に柿渋を塗って作る)で有名だそうで、京都、香川と並び、うちわの日本三大産地だそうです。
うちわを作る工程に必要だからでしょうか、「竹割り器」が売られています。
 (買う人がいるのでしょうか。)
(買う人がいるのでしょうか。)
私は、お腹が空いたので、「栗まんじゅう」を買いました。
 (「栗(山鹿産)」に惹かれました。)
(「栗(山鹿産)」に惹かれました。)
売店前の、桜を一望できるベンチでいただきましたが、美味しかったですねぇ。
公園内を歩きながら桜を見ていると、遠景に「不動岩」を発見。
 (デジカメのズームで。)
(デジカメのズームで。)
高さ80メートル、根回り100メートルの奇岩で、太古から5億年以上の時間を経て、この奇岩が形成されたそうです。
見たかった不動岩も見ることができてラッキーでした。
適度に人でにぎわっている一本松公園を後に、県道を北上し、菊鹿エリアに行きます。
目的地は「相良寺」ですが、道中、「アイラトビカズラ」を見に立ち寄ります。

アイラトビカズラは、つる性の常緑植物で、こんな派手な花をつけます。

が、残念ながら、開花は4月下旬~5月上旬なので、今はこんな殺風景。

でも、ここの「アイラトビカズラ」は樹齢1000年と推定され、1940年に国の天然記念物、1952年に特別天然記念物に格上げされた、すごいやつ。
こんな特別な木には伝説が付き物で、「昔、源平合戦の頃、壇ノ浦の合戦で敗れた平家の残党が相良寺に立てこもった際、豊後竹田の源氏方の緒方三郎が寺を焼討ちした。この時、寺の観音様が飛翔して、このカズラに飛び移り危うく難を逃れた。」とのこと。
さて、その「相良寺」に到着。

ここも桜が見頃のようです。

境内です。
本堂では、ここでもお宮参りの読経(?)がされています。

おじゃましないように終わってから覗かせていただきましたが、千手観音様がいらっしゃいます。

「さて、千手観音様の手は何本あるでしょう?」と観光客を案内しているガイドさんが質問。
答えは「42本」。
こういう❝内訳❞だそうです。「合掌している2本を除くと40本。観音様は1本の手で『25』のことができるので、25×40=1000。」、、、なるほど。
そんな千手観音様もお寺の販売品として一役かっておられます。
 (飴とか煎餅のパッケージになっておられました。)
(飴とか煎餅のパッケージになっておられました。)
黄色、ではなくて黄金(だそうです)のだるまも結構推していましたね。
 (これのミニチュア版が売られています。)
(これのミニチュア版が売られています。)
私は、お参りして、お願いした御朱印を待っている間にそんなに広くない境内をぶらぶら。
 (「開運の鐘」と桜。背景の瓦の景色がまた良し。)
(「開運の鐘」と桜。背景の瓦の景色がまた良し。)
御朱印は「千手観音様」と「薬師如来様」。
 (合掌。)
(合掌。)
お土産にお線香を買いました。

駐車場までは少し歩きますが、その途中、桜の花としては目を引く大輪を見つけました。
 (比較物がないので、大きさが分かりませんね。(笑))
(比較物がないので、大きさが分かりませんね。(笑))
「相良寺」、厳かというよりも(不遜かもしれませんが)何だか楽しい気持ちになるお寺でした。
次は菊池エリアに向かうのですが、「歴史公園鞠智城」(きくちじょう)に立ち寄ります。

事前にネットで見てはいましたが、実際は想像以上に広大です。
 (ここも空いています。)
(ここも空いています。)
シンボルは、この「八角形鼓楼」。

663年の「白村江の戦い」で唐・新羅の連合軍に大敗した大和朝廷が日本への侵攻に備えて、この時期、九州北部から瀬戸内・近畿にかけて築いた山城で「古代山城」(こだいさんじょう)と言うそうです。
鞠智城は、九州の統治の中心であった大宰府と、大宰府を守るための大野城・基肄(きい)城に、武器・食糧を補給する支援基地の古代山城だった、とのことです。
「防人」の碑もあります。

山城の遺構はパッと見るだけでは分かりませんが、鞠智城跡をぐるっと散策できるように整備されています。

こちらは、鞠智城のガイダンス施設「温故創生館」。

入館無料ですが、充実していて、入るとすぐに係の方が「『鞠智城』の7分程度の紹介ビデオがありますが、ご覧になりますか?」と声をかけてくださいます。
お願いすると、立派なシアタールームでたった一人、ど真ん中に座って勉強させていただきました。(笑)
鞠智城跡には「お宝の池」(だったかな)と呼ばれる、当時の人工池があるのですが、ここから様々な物が出土するそうで、この「銅造菩薩立像」も。
 (12.7cmのかわいい像です。)
(12.7cmのかわいい像です。)
鞠智城、古代史ファンなら垂涎のスポットではないでしょうか。
立ち寄って良かった、いい施設でした。
もちろん、桜も美しかったです。

見晴らしのいい芝生に座ってのんびりとランチしているご夫婦がいらっしゃいましたが、広大で景色もよくのんびりしていて、いいお花見スポットですね。
「お昼は菊池のお店で。」と思っていますが、もう14時を回っていて、お腹が空きました。
道中、気になる2つの「道の駅」に寄りながら菊池エリアへ。
まずは、「道の駅 水辺プラザかもと」。
どうやら、いろいろな施設が複合しているようです。

この建物が、物産館と、UCHさんおススメのパン屋さんがある建物。

こちらは、駐車場をはさんで反対側にある「みずべの野菜園」。
 (新鮮野菜が買えるのかな? 時間の関係で入りませんでした。)
(新鮮野菜が買えるのかな? 時間の関係で入りませんでした。)
「水辺プラザ」というだけあって、川のほとりの桜がきれいです。

物産館・パン屋さんに入って、UCHさんおススメの「米粉パン」を発見。

「八十八パン」は「米」の字を分解して「八十八」、なるほど。
売り切れてなくて良かったぁ、、、この米粉パンと、ご当地ドレッシングを自分のお土産に。

米粉パン、日曜日の朝食でさっそくいただきましたが、美味しい!
「米粉」っていうのが分かる、もっちりした味わいのある、癖になる美味しさですね。
続いて、「道の駅 七城メロンドーム」。
 (なぜか笑えるメロンドーム。)
(なぜか笑えるメロンドーム。)
店内をいろいろと見て回りましたが、こちらを本日の夕食用に購入。
 (「旭志牛カレー」。)
(「旭志牛カレー」。)
せっかくメロンドームに立ち寄りましたので、メロンソフトを。
 (おっさんのおひとりソフト。)
(おっさんのおひとりソフト。)
なかなかのボリュームで350円、各地のソフトを夫婦で食べていますが、コスパフォ良し、だと思います。
そして、15時15分頃、お目当ての昼食処、菊池の「寿温泉食堂」に到着。

人気のいなりや巻き寿司は売切れだろうから、何か定食でも、、、と思ったら、ラストオーダー時刻はまですが、「ごめんなさい、今日はもう終わりました。」とのこと。
お花見シーズンでお客さんが多かったようです、、、残念、、、と思ったら、レジ横に巻き寿司が2パックだけ残っていました。
奇跡的にテイクアウト巻き寿司をゲットできました。
この「寿温泉食堂」、この通りを少し行くと、もう「菊池公園」。

「菊池公園」は県北の有名なお花見スポットですので、お客さんが食事をするためにどんどん寄るのでしょうね。
本日の桜を見る最終目的地は、「菊池公園」・「菊池神社」。
本日一番の人出ですが、菊池神社の駐車場にすんなり入れることができました。
まずは菊池神社にお参りを。

菊池神社は、明治3年創建。
主神は、南北朝の争乱時代、九州における南朝方の雄として活躍した菊池武時・武重・武光の3代、とのことです。
山門は、左に桜、右に紅葉という春と秋に❝対応❞しているようです。

境内には、文字を彫り抜いた竹が多数置かれています。

夜のイベントがあるのだろうと思って、帰ってからネットで調べてみると、竹細工が盛んなお土地柄で「ほの宵まつり」というイベントが開催されるそうです。
 (「ほの宵まつり」。ネットより拝借。)
(「ほの宵まつり」。ネットより拝借。)
境内は桜が見頃です。

本殿のお隣のこちらも桜がお見事。

お参りさせていただきましたので、御朱印を。

境内を出て、「菊池公園」の散策へ。
境内から出るとすぐに「菊池武時」公の像があります。
 (かなり小ぶりです。)
(かなり小ぶりです。)
公園内も桜がこれでもかと咲き誇っています。

本日一番の人出といっても、写真の通り(の空きっぷり)ですから、遅めの昼食のためのベンチもすぐに見つかりました。
「寿温泉食堂」の巻き寿司を開きます。

普通の巻き寿司に見えますが、ひとつひとつの具の味がいいのか、酢飯の具合がいいのか、全体のバランスがいいのか、とにかく美味しいです。

いなりや定食メニューもいつかは食べてみたいものです。
ベンチに座って、こんな景色を眺めながらの❝巻き寿司ランチ❞でした。
 (ちょっとした広場にベンチがひとつ、私一人、、、贅沢なお花見。)
(ちょっとした広場にベンチがひとつ、私一人、、、贅沢なお花見。)
「観月楼展望所」という所までぶらぶら登ってみました。

ここからみる公園の景色はこの絶景。

大満足の景色です。
公園内はとにかく桜、桜、桜、、、見事な見頃の桜を見ながら駐車場に戻りました。
菊池神社、菊池公園、素晴らしい桜でした。
今年も桜を堪能しました。
土曜日はピンポイントで暖かい日でしたので、歩いた疲れも取るために、帰路、「平山温泉」に立ち寄ります。

平山温泉「元湯」に到着。

小ぢんまりとした作りですが、立ち寄り客というよりは地元のみなさんの公衆浴場になっている感じでした。
 (立ち寄り湯300円。回数券がお得です。)
(立ち寄り湯300円。回数券がお得です。)
内湯。
 (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。)
泉質は、「美肌の湯」と言われる「アルカリ性単純硫黄泉」で、❝とろりすべすべ❞という感じで、私の好きな泉質。
露天も併設されています。
 (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。)
熱い湯が苦手な私で内湯がちょうど良かったので、露天の方はちょっとぬるいかな。
野趣を楽しむなら露天、温泉を楽しむなら内湯って感じでしょうか。
小さな売店は地元野菜などが豊富。

大好物のトマトが安かったので迷わず購入。
玉子も買おうかなと思ったのですが、単身住まいには多過ぎるので思い止まりました。
 (玉子はそこそこの値段かな? でも美味しいのでしょうねぇ。)
(玉子はそこそこの値段かな? でも美味しいのでしょうねぇ。)
いい温泉に浸かって、すっかり疲れも取れました。
リフレッシュして帰路のドライブも楽しみます。
ナビが示している南関ICへの道中、きれいな景色に思わず停車。
 (時刻は17時半頃。)
(時刻は17時半頃。)
お宿のようですが、ズームしてみると、「奥山鹿温泉」とありました。
 (きっと素晴らしい温泉なのでしょうね。)
(きっと素晴らしい温泉なのでしょうね。)
菜の花と桜のコラボ景色は見ていても飽きませんが、そろそろ夕刻ですので、出発。
和水町、「いだでん」の「金栗四三」さんの故郷でした。

大河ドラマは苦戦しているようですが、、、。
南関ICが近づいてきました。

帰りの九州道も順調に流れて、19時にはレンタカーを返却。
大満足の2019年の「桜ドライブ」でした。
UCHさん、いろいろと地元の情報をありがとうございました。
そして、夕食は、「七城メロンドーム」で買った「旭志牛カレー」。
 (添える野菜は、平山温泉で買ったトマト。器は「全国陶磁器フェア」で買った嘉麻市の「うつわ工房」の万能皿。)
(添える野菜は、平山温泉で買ったトマト。器は「全国陶磁器フェア」で買った嘉麻市の「うつわ工房」の万能皿。)
「旭志牛カレー」、なかなかの辛口で、具もしっかりしていて、レトルトカレーとしてはかなりレベルが高いと思います。
お値段も650円とややお高めですが。(笑)
早春の梅、春の桜、、、やっぱり季節の花を見ると心が豊かになりますね。
季節は初夏へ、GWの連続イベントが楽しみです!
 (単身住まいの屋上より。)
(単身住まいの屋上より。)

 (素晴らしい!)
(素晴らしい!) (「BIGのり弁」(白身魚フライver)。)
(「BIGのり弁」(白身魚フライver)。)










 (曇っていても、桜の樹の下を歩くと、気持ちも弾んで明るくなります。)
(曇っていても、桜の樹の下を歩くと、気持ちも弾んで明るくなります。) (改装前の水槽が写っている
(改装前の水槽が写っている (この奥に以前と同じ引き戸タイプの入口があります。)
(この奥に以前と同じ引き戸タイプの入口があります。)
 (手前の大きな島は、先日釣行に訪れた
(手前の大きな島は、先日釣行に訪れた
 (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。) (「ココット料理」は写メ忘れ。)
(「ココット料理」は写メ忘れ。)
 (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。) (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。) (天守閣が見えると元気が出ます。)
(天守閣が見えると元気が出ます。)


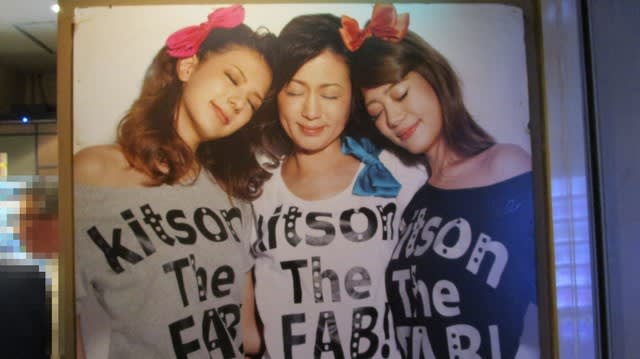 (大繁盛でした。ママさん、妹(マーガリン)さんに会いました。)
(大繁盛でした。ママさん、妹(マーガリン)さんに会いました。)


 (眼下はあの有名なゴルフコース。)
(眼下はあの有名なゴルフコース。)

 (「月読」と「新月」という温泉があります。)
(「月読」と「新月」という温泉があります。)


 (夏場はプールになる施設を美しい花で飾り立てています。)
(夏場はプールになる施設を美しい花で飾り立てています。)
 (「新月」の方。)
(「新月」の方。)

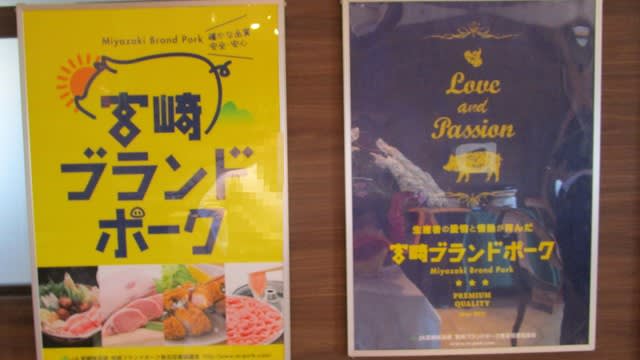













 (チョコの❝角❞は、3月21日にリニューアルオープンした
(チョコの❝角❞は、3月21日にリニューアルオープンした (熊本県の県北エリアをめぐります。)
(熊本県の県北エリアをめぐります。) (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。)
 (金色の紙は、御朱印の該当ページを示す❝しおり❞として使います。)
(金色の紙は、御朱印の該当ページを示す❝しおり❞として使います。)
 (写真左を上っていくと、「チブサン古墳」という古墳時代後期の前方後円墳があります。)
(写真左を上っていくと、「チブサン古墳」という古墳時代後期の前方後円墳があります。) (柵のあたりの岩肌には絵(装飾)が彫られています。)
(柵のあたりの岩肌には絵(装飾)が彫られています。) (こちらは絵は彫られていません。)
(こちらは絵は彫られていません。) (このあたりを「水遊び公園」と言うようです。)
(このあたりを「水遊び公園」と言うようです。)



 (昨年観覧しようと思いネットで予約を試みましたが、時すでに遅し、完売でした。)
(昨年観覧しようと思いネットで予約を試みましたが、時すでに遅し、完売でした。) (この手の大作は制作に数ヶ月を要するそうです。灯籠師は多忙なり。御朱印帳が限定品になる所以かもしれません。)
(この手の大作は制作に数ヶ月を要するそうです。灯籠師は多忙なり。御朱印帳が限定品になる所以かもしれません。)
 (この灯籠はもちろん金属製。)
(この灯籠はもちろん金属製。) (独特の石門が密教っぽい。)
(独特の石門が密教っぽい。)


 (何とも広々とした贅沢な足湯広場です。)
(何とも広々とした贅沢な足湯広場です。)



 (「燈籠殿」。)
(「燈籠殿」。)
 (田原坂にも近いですからね。)
(田原坂にも近いですからね。) (境内から見ていますので❝裏側❞です。)
(境内から見ていますので❝裏側❞です。) (右の高台にあるのは、おそらくお食事処。)
(右の高台にあるのは、おそらくお食事処。)





 (これぐらいのゆったり感。)
(これぐらいのゆったり感。)




 (買う人がいるのでしょうか。)
(買う人がいるのでしょうか。) (「栗(山鹿産)」に惹かれました。)
(「栗(山鹿産)」に惹かれました。) (デジカメのズームで。)
(デジカメのズームで。)






 (飴とか煎餅のパッケージになっておられました。)
(飴とか煎餅のパッケージになっておられました。) (これのミニチュア版が売られています。)
(これのミニチュア版が売られています。) (「開運の鐘」と桜。背景の瓦の景色がまた良し。)
(「開運の鐘」と桜。背景の瓦の景色がまた良し。) (合掌。)
(合掌。)
 (比較物がないので、大きさが分かりませんね。(笑))
(比較物がないので、大きさが分かりませんね。(笑))
 (ここも空いています。)
(ここも空いています。)



 (12.7cmのかわいい像です。)
(12.7cmのかわいい像です。)


 (新鮮野菜が買えるのかな? 時間の関係で入りませんでした。)
(新鮮野菜が買えるのかな? 時間の関係で入りませんでした。)


 (なぜか笑えるメロンドーム。)
(なぜか笑えるメロンドーム。) (「旭志牛カレー」。)
(「旭志牛カレー」。) (おっさんのおひとりソフト。)
(おっさんのおひとりソフト。)




 (「ほの宵まつり」。ネットより拝借。)
(「ほの宵まつり」。ネットより拝借。)


 (かなり小ぶりです。)
(かなり小ぶりです。)


 (ちょっとした広場にベンチがひとつ、私一人、、、贅沢なお花見。)
(ちょっとした広場にベンチがひとつ、私一人、、、贅沢なお花見。)



 (立ち寄り湯300円。回数券がお得です。)
(立ち寄り湯300円。回数券がお得です。) (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。) (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。)
 (玉子はそこそこの値段かな? でも美味しいのでしょうねぇ。)
(玉子はそこそこの値段かな? でも美味しいのでしょうねぇ。) (時刻は17時半頃。)
(時刻は17時半頃。) (きっと素晴らしい温泉なのでしょうね。)
(きっと素晴らしい温泉なのでしょうね。)

 (添える野菜は、平山温泉で買ったトマト。器は「
(添える野菜は、平山温泉で買ったトマト。器は「
 (もうすぐ「小富士」バス停という所に、大根が天日干しされていました。)
(もうすぐ「小富士」バス停という所に、大根が天日干しされていました。) (バスは1時間に1本もない、超ローカル線。)
(バスは1時間に1本もない、超ローカル線。) (背景の山が
(背景の山が

 (今日の散策の無事を祈ってお参り。)
(今日の散策の無事を祈ってお参り。) (バスを降りてすぐに見に行ってみました。)
(バスを降りてすぐに見に行ってみました。)



 (船越湾の「紺」。)
(船越湾の「紺」。) (イノシシでも撃つハンターがいるのでしょうか。)
(イノシシでも撃つハンターがいるのでしょうか。)



 (ここからもアプローチできるようですが、まずこの案内板を見つけることはできないでしょう。(笑))
(ここからもアプローチできるようですが、まずこの案内板を見つけることはできないでしょう。(笑)) (ヒバ系かと思いましたが、多分「カイズカイブキ」という和風の種類ですね。)
(ヒバ系かと思いましたが、多分「カイズカイブキ」という和風の種類ですね。) (スイセンも見頃ですね。)
(スイセンも見頃ですね。)

 (葦か何かの育成実験場のような雰囲気ですが、何の看板もありませんでした。)
(葦か何かの育成実験場のような雰囲気ですが、何の看板もありませんでした。) (「雷山川」。川なんですね。)
(「雷山川」。川なんですね。) (恥ずかしながらまだ「牡蠣小屋」に行ったことがありません。)
(恥ずかしながらまだ「牡蠣小屋」に行ったことがありません。) (妙に新しい。)
(妙に新しい。)
 (線路をまたぐ歩道橋に駅がある。)
(線路をまたぐ歩道橋に駅がある。) (筑前前原駅までは2つ。)
(筑前前原駅までは2つ。)