大阪・関西万博。パンフレットによると正式名称は「2025年 日本国際博覧会」。開催まであと数日というタイミングで内覧会に参加する機会をいただきましたので行って来ました。
 (ネットより拝借。)
(ネットより拝借。)
当日大阪入りしましたが、電車でのアプローチは1本のみ、地下鉄中央線の夢洲駅(ゆめしま)で、これまでの終点のコスモスクエア駅から1駅延伸。前回の大阪万博(1970年)では会場へのアクセスとして地下鉄の御堂筋線が千里中央駅まで延伸されましたが、いつの間にかその先の箕面萱野駅まで2駅伸びているのを今日知って、何となく無関係でないような気持ちになりました。
 (夢洲駅の改札を出ると、開放感のある広々としたアプローチに出ました。)
(夢洲駅の改札を出ると、開放感のある広々としたアプローチに出ました。)
メインゲートだと思いますが「東ゲート」から入場します。空港の保安検査場のようなセキュリティを通過して入場すると、想像以上に広大な景色が広がります。
 (遠くに見えるのが今回の万博のシンボル「大屋根リング」。)
(遠くに見えるのが今回の万博のシンボル「大屋根リング」。)
内覧会ですので、事前予約のパビリオンのみの見学となりますが、集合時刻までまだ時間がありますので、まずは大屋根リングに行ってみます。ご存知の通り、大屋根リングは清水の舞台のような木造の巨大建築物。
 (すごい。閉会後これを壊してしまうのはもったいない、、、ですが、保存した場合何に使うのかというアイデアは思い付きませんし、木造なのでそもそも耐久性がどれくらいかも分かりません。)
(すごい。閉会後これを壊してしまうのはもったいない、、、ですが、保存した場合何に使うのかというアイデアは思い付きませんし、木造なのでそもそも耐久性がどれくらいかも分かりません。)
ガイドさんの説明によると、大屋根リングの内側に世界各国のパビリオン、外側に日本の企業・自治体のパビリオンという配置になっているそうです。大屋根リングを通り抜けて内側に入ると、こんな感じで各国のパビリオンがそこそこ密集して建っています。
 (隈研吾さんの作品かと思うような木を使ったこちらのパビリオンはマレーシア館。もちろん、入場不可。)
(隈研吾さんの作品かと思うような木を使ったこちらのパビリオンはマレーシア館。もちろん、入場不可。)
ラッキーにも大屋根リングに上ることができるようですので、行ってみます。階段(現在通行不可)、エスカレーター、エレベーターがあります。
 (大屋根リングの上はこんな感じでぐるりと一周歩くことができます。どなたかが言っていましたが、一周約30分だそうです。今は歩いていて気持ちのいい季節ですが、開催期間のほとんどが夏ですから、逃げ場がない周回散策路を歩くのはきついでしょうね。)
(大屋根リングの上はこんな感じでぐるりと一周歩くことができます。どなたかが言っていましたが、一周約30分だそうです。今は歩いていて気持ちのいい季節ですが、開催期間のほとんどが夏ですから、逃げ場がない周回散策路を歩くのはきついでしょうね。)
大屋根リングからの眺望はなかなかのもの。会場全体を俯瞰できます。
 (さっき見たマレーシア館ってこんな複雑な作りなのですね。さすが万博、各パビリオンとも凝った作りです。よく間に合ったものだと感心していると、ガイドさんによると、開催まであと10日もないですが、まだ内装を工事している館もあるそうです。)
(さっき見たマレーシア館ってこんな複雑な作りなのですね。さすが万博、各パビリオンとも凝った作りです。よく間に合ったものだと感心していると、ガイドさんによると、開催まであと10日もないですが、まだ内装を工事している館もあるそうです。)
それにしても大屋根リングの構造は美しい。
 (この中を歩くことができれば日陰なので暑さをしのげるし、美しい構造を鑑賞することもできると思いますが、今日見たところでは残念ながら屋根の下は周回できないみたい。)
(この中を歩くことができれば日陰なので暑さをしのげるし、美しい構造を鑑賞することもできると思いますが、今日見たところでは残念ながら屋根の下は周回できないみたい。)
それでは集合時刻となりましたので、予約しているNTTパビリオンへ。
 (柱を使った建築ではなく、テントのような構造になっているそうです。3つのゾーン(建物)から成っていて、外には半透明の小さな布が16万枚(だったかなぁ)、ひらひらと付けられています。)
(柱を使った建築ではなく、テントのような構造になっているそうです。3つのゾーン(建物)から成っていて、外には半透明の小さな布が16万枚(だったかなぁ)、ひらひらと付けられています。)
ここは入口ではなく、ゾーン(建物)の間のスペース。
 (左が16万枚あるという小さな布。右のカラフルな布は被災した中能登で生産されている布(化繊)で、復興への貢献という意味合いもあるそうです。)
(左が16万枚あるという小さな布。右のカラフルな布は被災した中能登で生産されている布(化繊)で、復興への貢献という意味合いもあるそうです。)
NTTパビリオンの構造を支えるカーボンファイバーワイヤー(千数百本って言ってたかなぁ)は触ると音階の異なる電子音が鳴ります。
 (この白いものがカーボンファイバーワイヤー。触ると涼やかな電子音が鳴ります。待っている間、面白くて触りまくっていました。(笑))
(この白いものがカーボンファイバーワイヤー。触ると涼やかな電子音が鳴ります。待っている間、面白くて触りまくっていました。(笑))
で、入場。1つ目のゾーンにて。
 (1回70人が入場するそうです。)
(1回70人が入場するそうです。)
あとはネタバレになるので省略しますが、IOWN(アイオン)を使ったPerfumeのパフォーマンスを3Dで観ることができます。すごいですよ。
NTTパビリオンを出て、会場を歩いていると、「予約なしで入場できま~す」と呼び込みをしている日本企業のパビリオンもありましたが、そのまま帰路につきました。万博と言えば、毎回話題になる一番人気の展示品があります。1970年の大阪万博は「月の石」、2005年の愛知万博は「冷凍マンモス」。2025年の大阪・関西万博ではいったい何でしょう。個人的にはこちら「大阪ヘルスケアパビリオン」の「人間洗濯機」に注目しています。(笑)
 (あまりの天気の良さにパース図のように見えますが、今日撮った写真です。)
(あまりの天気の良さにパース図のように見えますが、今日撮った写真です。)
内覧会、もっと人もまばらなのかと思ったら、もう開催したのかと錯覚するくらい人がいました。内覧会を利用してオペレーションの最終確認やスタッフの実地訓練を兼ねているみたいですので、関係者でにぎわっているということなのかもしれません。大阪・関西万博、いよいよ開催です。現地で体験するとワクワク感が増しますが、やはり暑さ対策が気になるところですので、まずはニュースやネットの情報で各パビリオンのコンテンツを見て、行ってみたくなったら訪れてみようと思います。










 (東京の自宅にも既に到着済み。)
(東京の自宅にも既に到着済み。) (マスクが売っているのは当たり前、今や値崩れの状況を見ています。)
(マスクが売っているのは当たり前、今や値崩れの状況を見ています。)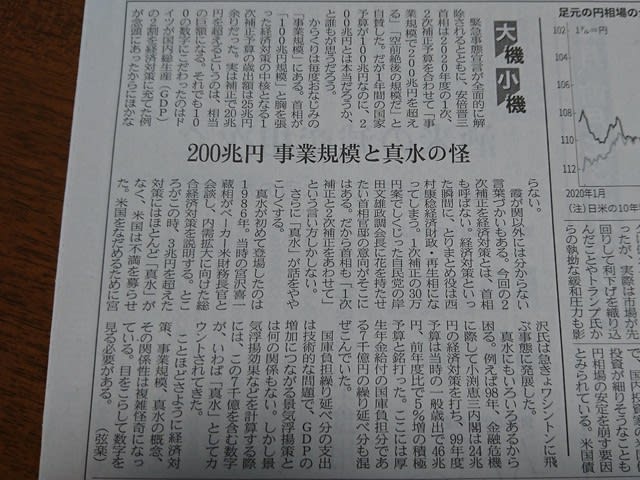
 (金曜日の午後13時半頃の博多駅。)
(金曜日の午後13時半頃の博多駅。) (すぐに届きました。漁協だからできる養殖業者から直接仕入れる大判うなぎ、とのこと。)
(すぐに届きました。漁協だからできる養殖業者から直接仕入れる大判うなぎ、とのこと。) (「芋屋金次郎」天神店はこんな感じだそうです。)
(「芋屋金次郎」天神店はこんな感じだそうです。) (今週はこの2袋。両方とも高知のもの。)
(今週はこの2袋。両方とも高知のもの。)




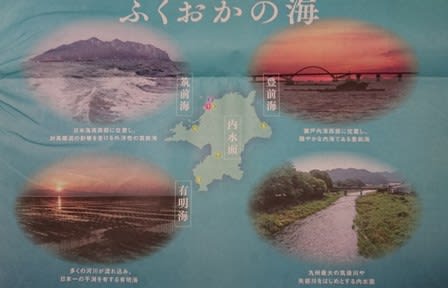

 (上野原の
(上野原の (カメラのミスショットが面白かったので。)
(カメラのミスショットが面白かったので。) (
(


 (快晴!)
(快晴!) (お土産の絵ハガキです。実際もこの通り。)
(お土産の絵ハガキです。実際もこの通り。) (お土産の絵はがきより。)
(お土産の絵はがきより。)
 (私。ヘルメットとJFEの上着着用。手には軍手。)
(私。ヘルメットとJFEの上着着用。手には軍手。)