水曜日、
京都新聞日曜版のシリーズ企画「ソフィアがやってきた!」で
学校訪問授業を行いました。
光華小学校の5年生の皆さんに
1時間あまり
音や音楽についてお話しました。
詳しい内容を書きたいのはヤマヤマですが・・・。
京都新聞11月2日の日曜版を楽しみにしています。
カラーで、たぶん2ページくらい
けっこう大きく載るようです。
京都新聞日曜版のシリーズ企画「ソフィアがやってきた!」で
学校訪問授業を行いました。
光華小学校の5年生の皆さんに
1時間あまり
音や音楽についてお話しました。
詳しい内容を書きたいのはヤマヤマですが・・・。
京都新聞11月2日の日曜版を楽しみにしています。
カラーで、たぶん2ページくらい
けっこう大きく載るようです。













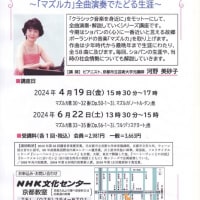
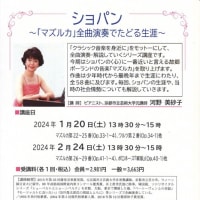
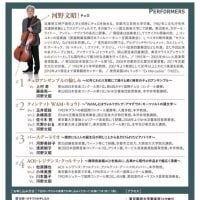
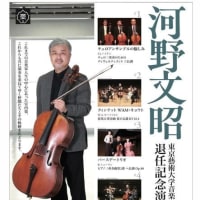
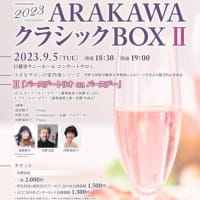








まず、主人が今朝先に新聞を広げていたようで、
私が起きてくると「新聞見てみ!!」と言いながら
自分で開いて見せてくれました~~
・・・絶対音感・・はなくてもこの頃の子供は、
絶対音が身に付く体質(?)なんでしょうか。
たとえばポニョ。
耳について離れないほどCMで流れたためか、
たいがいの小学生が鼻歌で
「ポーニョポーニョ♪~」と歌うキーは自然と原音キーになってます。
恐るべし近頃の子供たち!!
絶対音感って、やっぱりその「絶対音感」というコトバ自体のインパクトがあるのですね。
何年か前、ノンフィクションの「絶対音感」という本がベストセラーになりました。
その本の内容としては、絶対音感を神聖視していないのですが、本を読んでいない多くの人達が「絶対音感」を、何か凄いことのように思ったのでしょう。
ちなみに、21世紀の「ド」の音の高さは、バッハの時代ではほぼ「レ♭」であったし、また、場所(街)によっても高さは違っていた(パイプオルガン)ので、「絶対」というのはないのです。
本当に大切なのは「ハーモニー感」(和音の機能の違い)で、それはヨーロッパ人には伝統があるので簡単なのですが、明治時代になるまで和音を知らなかった日本人にとってはたいへん苦手なことでした。
そのようなコンプレックスが尾を引いていると思われます。
絶対音感のない、素晴らしい音楽家はたくさん存在しますよ~。