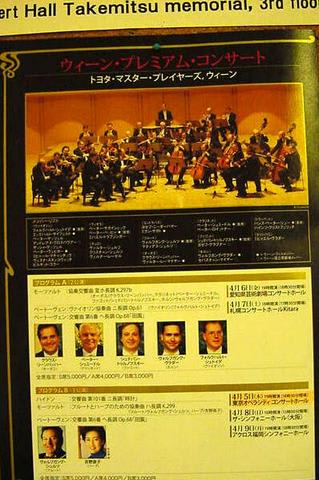1幕オペラで前半何か波動が合わなかった・・歌手男声、声量豊富PA使用かな?、オケ音量豊富4階の3列目でも大音響?・・でも、極端なリズム感が肌に,耳に合わない・・陽の中の,陰,影の旋律美が無い感じ、アンサンブルが大味で・・
演出&舞台美術:ペーター・ムスバッハ,演出は面白いですね 第4場の「サロメの踊り(7つのヴェールの踊り)」でサロメは踊らない・・ヨカナーン:アラン・タイトスの首を・・この場面から,演劇ですね・・ヨカナーンを縛り上げ,ヘロディアスとサロメがヨカナーンを愛撫??・・する様なシーンで、最近WOWOWで再放映された,氷の微笑のシーンが突然浮かび・・寒気が、M・S??・・この辺から果然面白く成って来ました
サロメの演技,歌唱が良かったですね
指揮] ファビオ・ルイジ・・メリハリはあり,面白い音楽波動と感じましたが,流れがせっかち?な・・ドチラカと言うとオケ中心で,歌手との呼吸感が・・
終演後、1階袖で観ましたが,傾斜が急な舞台で,歌手の方々は大変の様でした。
最近のドイツ系では 1、ベルリン歌劇場 2、バイエルン放送 3ミュンヘン・ドレスデンかな
ドレスデン国立歌劇場[指揮] ファビオ・ルイジ
《サロメ》 ◇11月26日(月) 東京文化会館4FL3-19・23000円妥当な額
原作:オスカー・ワイルドの戯曲「サロメ」
台本:ヘドヴィッヒ・ラッハマンによる原作の独語訳
演出&舞台美術:ペーター・ムスバッハ
衣裳:アンドラ・シュミット=フッテレル
照明:アレクサンダー・コッペルマン
サロメ:カミッラ・ニールンド
ヘロデ:ヴォルフガング・シュミット
ヘロディアス:ガブリエレ・シュナウト
ヨカナーン:アラン・タイトス
《火の危機》を発表後、この作品と対になる一幕もののオペラを構想したことに始まるといわれる。物語はもともと『新約聖書』の一挿話だが、オスカー・ワイルドの戯曲になる頃には、預言者の生首に少女が接吻するという世紀末的退廃芸術にまで変容している。音楽としては、自身の交響詩により進化した極彩色による濃厚な官能表現が見事に生きている。
前奏なしの4場構成。第4場の「サロメの踊り(7つのヴェールの踊り)」が著名で単独の演奏や録音も存在する。ただし、劇の流れからするとこの部分はやや浮いており、前後の緊張感あふれる音楽・歌唱を弛緩させているという評価も少なからず存在する。この「欠陥」は次作の《エレクトラ》でほぼ克服されている。
[編集] 初演
1905年12月9日 ドレスデン宮廷歌劇場
指揮 エルンスト・フォン・シューフ
演出 ヴィルムヘルム・ヴィンク
日本初演は1962年4月24日、フェスティバルホール(大阪)において、マンフレート・グルリット指揮、東京フィルハーモニー交響楽団他によって行われた。
編成
105名~108名必要
ピッコロ 1、フルート 3、オーボエ 2、イングリッシュホルン 1、ヘッケルフォン 1、E♭クラリネット 1、B♭管クラリネット 2、A管クラリネット 2、バスクラリネット 1、ファゴット 3、コントラファゴット 1、ホルン 6、トランペット 4、トロンボーン 4、バスチューバ 1、ティンパニ 2、タムタム 1、シンバル 1、大太鼓 1、小太鼓 1、タンブリン 1、トライアングル 1、木琴 1、カスタネット 1、グロッケンシュピール 1、(打楽器で6人~7人必要)、チェレスタ 1、ハープ2、第1ヴァイオリン 16、第2ヴァイオリン 16、ヴィオラ10~12、チェロ 10、コントラバス 8、ハルモニウム、オルガン
R.シュトラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホテル・・オペラで遅くなり帰宅出来ない時に,利用・・何ヶ月に一度の利用ですが,わがまま聞いてくれて,最近はマイルーム・同じ部屋を利用させてもらってます。
朝の朝食も落着いた場で・・1泊8700円程
ホテル・ヴィラフォンテーヌ日本橋
ホテル
</iframe>拡大地図を表示