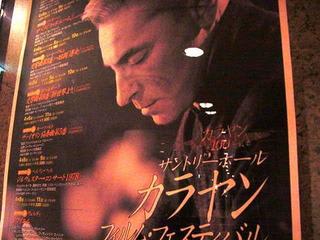24日 ザルツブルク音楽祭? 文化会館・上野4FR2-35・28,000円・高い
序曲から古楽器弦群はノーヴィブラートの響きが、ハーディングより大人しいアタック感ですが・・序曲、1幕と耳慣れせずで、充足感が無い、
二幕から歌手もオケも音楽の流れが爽やかですね・・音楽、アリアの聴かせ所、聞きたい所で・・終始余分な天使ケルビム、意味不明・バレエダンサー?動きが・・目障り、目障り・・でしたが
音楽の流れは、幕を追う後とにオケ、歌手との共振性が高まり、楽しめました、
指揮:ロビン・ティチアーティ、若い26歳とか、音楽に耳障りも無く、音楽の流れが自然、歌手との呼吸感も優れてます・・ハーディングに続く指揮者に成るかな?・・コンサート指揮で聴いてみたいと思います。
フィガロの結婚 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
台本:ロレンツォ・ダ・ポンテ
演出:クラウス・グート
指揮:ロビン・ティチアーティ
アルマヴィーヴァ伯爵 … スティーブン・ガッド
アルマヴィーヴァ伯爵夫人 … エイリン・ペレス
スザンナ … ジェニファー・オローリン
フィガロ … アレックス・エスポジト
ケルビーノ … ジュルジータ・アダモナイト
バルトロ … ブリンドリ・シェラット
マルチェリーナ … キャサリン・ゲルドナー
バジリオ … パトリック・ヘンケンス
ドン・クルツィオ … ミハエル・ハイム
アントニオ … アダム・プラチェトカ
バルバリーナ … エレナ・モンティ
ラムセス・シグル … 天使ケルビム(黙役)
合唱団 フィルハーモニア・クワイア・ウィーン
エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドイツ人演出家のクラウス・グートは、ザルツブルク音楽祭などの大きなプロジェクトに早くから参加しており、古典作品から現代作品までレパートリーとしている。03年、「さまよえるオランダ人」の演出でバイロイト音楽祭にデビュー。05年にはウィーン祝祭週間で初めてアーノンクールと共演し、06年のザルツブルク音楽祭「フィガロの結婚」でも両者の共演が行われた。
指揮のロビン・ティチアーティはロンドン生まれ。バイオリン、ピアノなどを学んだ後、15歳から指揮に転向、コリン・デイビスとサイモン・ラトルに師事した。05年には最年少の指揮者としてスカラ・フィルにデビュー。06年夏のザルツブルクのモーツァルト劇音楽「シピオーネの夢」で、この音楽祭最年少の指揮者デビューとなる。07年1月のツアーからグラインドボーンの音楽監督に就任し、同年5月に同制作「コジ・ファン・トゥッテ」で指揮デビューした。エイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団(OAE)は、そのユニークな能力と音楽創(づく)りの先駆的な精神によって、オリジナル楽器の演奏を通じて作曲時の意図を聴取できる歴史的臨場体験を・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
指揮は1983年、イギリス生まれのロビン・ティチアーティ。オーケストラはエイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団。歌手は、06年の公演でスザンナ役を歌ったジェニファー・オローリンをはじめ、若手の伸び盛りの歌手がそろった。
バイロイト、ルツェルンなど著名な音楽祭の日本公演が実現するなか、
ザルツブルク音楽祭の日本公演は多くの音楽ファンが待ち望み、過去にも構想が持ち上がったが、メーンのウィーン・フィルの参加が得られず、見送られてきた。それだけに今回の公演は注目を集めた。
しかし、宣伝媒体には音楽祭の公式のロゴが入っているものの、「音楽祭日本公演」「音楽祭制作オペラの日本公演」と2つの表記が存在。「配役には総監督のフリムが関わり、その背後で私もザルツブルク音楽祭の質にふさわしいかどうか吟味した」とシュタットラー総裁は音楽祭の日本公演であると明言。
フィガロ 写真が多く掲載してます