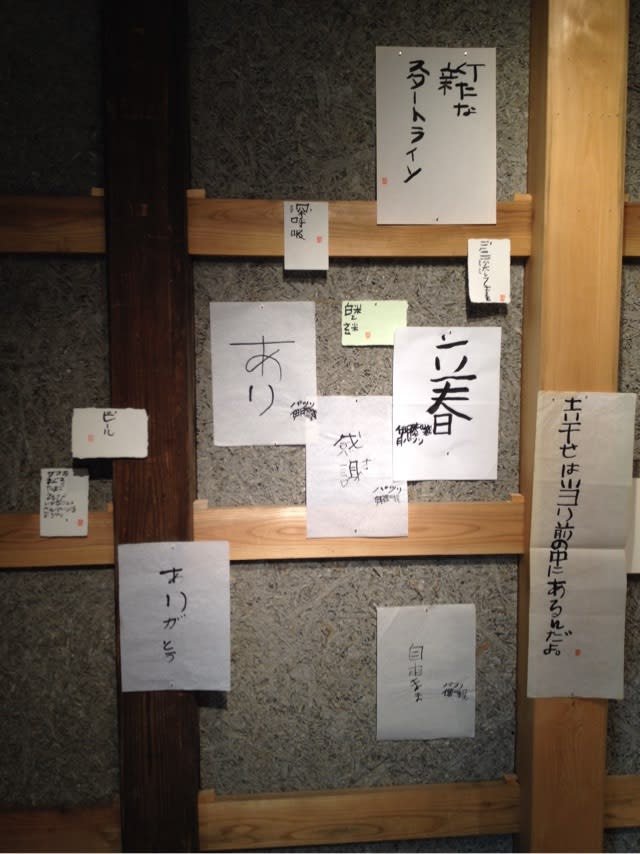ちょうど 「SMAP独立・解散か?」 という報道が流れた翌日に
「草なぎ鍋作ってみました」 という記事を書いたところ、
これがものすごいアクセス数を稼いでくれていますので、そのおこぼれに与るべく、
この騒ぎが沈静化してしまう前に 「草なぎ剛問題」 について連投しておきたいと思います。
ただちょっと今日の問題、ひじょうにこのブログでは書きにくい話題であります。
奥歯に物のはさまったような表現になることも多々あるかと思いますが、
その点お含みおきいただきながら読んでいただければと思います。

先の記事で私は、彼のことを一貫して 「草なぎ剛」 と表記してきました。
で、こんな注記も付けておきました。
「(※草なぎのなぎは弓ヘンに前の旧字の下に刀)」
この注記はどこかのウェブニュースにあったものをそのままパクってきたものです。
私は当初あの記事を書くとき、「なぎ」 の字は正しい漢字に変換して書いていました。
「くさなぎ」 から一発変換はされませんでしたが、何番目かにはあの字が出てきて、
編集画面上ではそれがきちんと表示されていました。
ところが記事を公開する前にプレビュー画面で確認してみたところ、
彼の名前がことごとく文字化けしてしまっていたのです。
これからやってみますね。
《草剛》
今 《 》 の中には彼の名前を正しい漢字表記で打ち込み、
編集画面上ではそれが正しく映し出されています。
しかし、これをプレビュー画面で見てみると、《 》 の中の 「草」 と 「剛」 の間に、
ちょっと縦長の長方形と、儒教の 「儒」 の字が並んで表示されてしまうのです。
スマホ (特にiPhone) で見ている人にはまた違う見え方をしていて、
アルファベットや数字が並んだコード番号 (JIS+792C) が表示されているかと思います。
とまあこんな具合に正しい漢字を入力しているにもかかわらず文字化けしてしまうのです。
そんなわけですので、あの記事を公開する前に表記はすべて 「草なぎ剛」 に改めたのでした。
あのときはプレビュー画面での文字化けに怖じ気づいて実際にウェブ公開はしませんでしたが、
今回試行してみたところ、プレビュー画面で文字化けしていても気にせずにウェブ公開してしまえば、
Windowsパソコンで見る限りはきちんと 「なぎ」 の漢字は表示されていました。
( 《 》 内の漢字が正しく読めた人はここから先読んでも面白くないかもしれません。)
しかし、やはりスマホ (iPhone?) だと文字化けしてしまうようです。
プレビュー画面というのはブログを執筆している私にしか見えませんので、
読者の皆さんには関係ありませんね。
しかし、スマホ (特にiPhone) でご覧になっている方は大勢いらっしゃると思うので、
この文字化け現象は由々しき問題です。
(スマホでも文字化けしていないとか、パソコンだけど文字化けしているという方は、
どんな環境でお使いかコメント欄でお知らせいただけると幸いです。)
それにしても、スマホ (iPhone?) になるとなぜ文字化けしてしまうのでしょうか?
彼の名前がなぜウェブ上で 「草なぎ剛」 と表記されるのかという点に関しては、
以前から多くの人が疑問に思っていたようで、YAHOO!知恵袋等にその答えが散見されます。
「草なぎ剛の 「なぎ」 はなんでいつもひらがななのですか?」
「草なぎ剛の 『なぎ』 って、何故漢字で変換出来ないの?」
これらの問いに対する回答はそれはそれで納得できましたが、
私の知りたいこととはちょっとずれているようにも思えます。
私の場合、漢字変換はできているし、ブログ編集画面上ではきちんと表示もされています。
それがプレビュー画面やiPhoneで見ると文字化けしてしまうのです。
どうもよくわかりません。
試しに他のSNSだとどうなるのか、彼の名前を正しく入力・変換しアップしてみました。
すると Facebook でも Twitter でも正しい文字が表示されていました。
なんだ、そっちは大丈夫なのか。
それじゃあこの場合はどうでしょうか?
私のブログは Facebook と Twitter に連携していて、
ブログをアップすると両SNSに投稿通知が自動的にアップされるようになっています。
その際に、gooブログの編集画面上で一言書くと、それがSNSへのコメントとして付加されます。
そのコメントの中に彼の名前を書いてみるとどうなるのでしょうか?
これも試しにやってみました。
すると Facebook のコメント欄では 「草剛」 と 「なぎ」 の漢字はなかったものとされていました。
Twitter では 「草?剛」 と半角のクエスチョンマークに文字化けしていました。
(試行後すぐにブログの投稿もSNSの投稿も削除したので今はもう見られません。)
やはりいろんな環境によって文字化けしたりしなかったりしてしまうみたいですね。
誰がどんな環境で見てくださるかわからない以上 「草なぎ剛」 で行くしかなさそうです。
…と思ってあきらめかけていたんですが、先ほどググっていたときにこんなサイトを発見しました。
「HTMLで難しい漢字を表示させる」
このサイトは素晴らしくって、まさに 「草なぎ剛」 という文字列を例に出しながら、
この 「なぎ」 という漢字をどんな環境でも正しく表示させる方法を解説してくれていました。
言ってる内容は専門的すぎてほとんど理解できませんでしたが、
唯一、Unicode という世界共通の文字コードを使えばいいらしい、ということだけは理解できました。
そうするための具体的方法として、草なぎの 「なぎ」 という漢字であれば、
「24389」 というのが Unicode 上の対応する数字で、その前に半角の「&」 と 「#」、
その後ろに半角のセミコロン 「;」 を付けてあげると、あの漢字が表示されるというのです。
ではやってみますよ。
それっ!
《草彅剛》
いかがですか?
ちゃんと表示されていますか?
パソコンの人もスマホの人もアップルの人もちゃんと 《草彅剛》 になっていますか?
編集画面上ではあくまでも 「草」 と 「剛」 の間にあるのは記号と数字だけなんです。
ああ、今度は逆にこの編集画面上でどう打ち込んであるのかをお伝えできないな。
こうしてみましょう。
《草彅剛》
半角の記号と数字だったものを全角に置き換えてみました。
これならこのまま表示されていることでしょう。
編集画面上では、これらの記号と数字が打ち込んであるだけなんです (半角で)。
でも、皆さんの画面上ではあの 「なぎ」 という漢字が正しく表示されているんじゃないですか?
もう一度やってみますよ。
《草彅剛》
おおっ、素晴らしいっ
これでもうパソコンで見ようがiPhoneで見ようが、
誰が見ても正しい漢字で彼の名前を表記することができるのですね。
おめでとう草彅さん、おめでとうSMAP
というところでこの話題、終了かと思っていたんですが、まだ少し問題が残っていました。
この記事、一気に書き上げることができずに何度か下書として保存しながら書いているのですが、
一度下書として保存したものを再び立ち上げると、
以前の編集画面では 《草彅剛》 と入力していたはずが (記号・数字は半角)、
新たに開いた編集画面では正しく 《草彅剛》 と変換されてしまっているのです。
なんだ、いいじゃないかと思われるかもしれませんが、
これを再び公開するとまた文字化けしてしまって 《草剛》 となってしまうのです。
(おわかりかと思いますが、このへん私はこの間に学んだシステムを逆手にとって入力しています。)
つまりこの記事は再編集するたびに、
正しく表示されていたはずの6ヶ所の 「彅」 の字 (ここも含む) が文字化けに戻ってしまうのです。
どういう仕組みかわかりませんが、とにかくそういうシステムのようです。
したがってこの記事は一度公開したら、もう手を入れ直したりせずそのまま放っておくか、
どうしても手直ししたい場合には、そのつどあの6ヶ所を Unicode に修正しなくてはいけないようです。
うーん、大変だ 。
。
私はけっこうあとから読み返して何度も文章に手を入れるタイプなので、
この記事もつい 「てにをは」 とかを直してしまうかもしれません。
そのたびに Unicode 修正のことを思い出せるのかどうか、はなはだ心配です。
この記事を読んでみて文字化けだらけで意味が通じないということがありましたら、
文章に手を入れたときに Unicode 修正のことを忘れたのだと思うので、ぜひ私までご一報ください。
以上、ウェブ上では書きにくい 「草彅剛問題」 でした。
(おっと、これで修正箇所は7ヶ所になった。)
「草なぎ鍋作ってみました」 という記事を書いたところ、
これがものすごいアクセス数を稼いでくれていますので、そのおこぼれに与るべく、
この騒ぎが沈静化してしまう前に 「草なぎ剛問題」 について連投しておきたいと思います。
ただちょっと今日の問題、ひじょうにこのブログでは書きにくい話題であります。
奥歯に物のはさまったような表現になることも多々あるかと思いますが、
その点お含みおきいただきながら読んでいただければと思います。

先の記事で私は、彼のことを一貫して 「草なぎ剛」 と表記してきました。
で、こんな注記も付けておきました。
「(※草なぎのなぎは弓ヘンに前の旧字の下に刀)」
この注記はどこかのウェブニュースにあったものをそのままパクってきたものです。
私は当初あの記事を書くとき、「なぎ」 の字は正しい漢字に変換して書いていました。
「くさなぎ」 から一発変換はされませんでしたが、何番目かにはあの字が出てきて、
編集画面上ではそれがきちんと表示されていました。
ところが記事を公開する前にプレビュー画面で確認してみたところ、
彼の名前がことごとく文字化けしてしまっていたのです。
これからやってみますね。
《草剛》
今 《 》 の中には彼の名前を正しい漢字表記で打ち込み、
編集画面上ではそれが正しく映し出されています。
しかし、これをプレビュー画面で見てみると、《 》 の中の 「草」 と 「剛」 の間に、
ちょっと縦長の長方形と、儒教の 「儒」 の字が並んで表示されてしまうのです。
スマホ (特にiPhone) で見ている人にはまた違う見え方をしていて、
アルファベットや数字が並んだコード番号 (JIS+792C) が表示されているかと思います。
とまあこんな具合に正しい漢字を入力しているにもかかわらず文字化けしてしまうのです。
そんなわけですので、あの記事を公開する前に表記はすべて 「草なぎ剛」 に改めたのでした。
あのときはプレビュー画面での文字化けに怖じ気づいて実際にウェブ公開はしませんでしたが、
今回試行してみたところ、プレビュー画面で文字化けしていても気にせずにウェブ公開してしまえば、
Windowsパソコンで見る限りはきちんと 「なぎ」 の漢字は表示されていました。
( 《 》 内の漢字が正しく読めた人はここから先読んでも面白くないかもしれません。)
しかし、やはりスマホ (iPhone?) だと文字化けしてしまうようです。
プレビュー画面というのはブログを執筆している私にしか見えませんので、
読者の皆さんには関係ありませんね。
しかし、スマホ (特にiPhone) でご覧になっている方は大勢いらっしゃると思うので、
この文字化け現象は由々しき問題です。
(スマホでも文字化けしていないとか、パソコンだけど文字化けしているという方は、
どんな環境でお使いかコメント欄でお知らせいただけると幸いです。)
それにしても、スマホ (iPhone?) になるとなぜ文字化けしてしまうのでしょうか?
彼の名前がなぜウェブ上で 「草なぎ剛」 と表記されるのかという点に関しては、
以前から多くの人が疑問に思っていたようで、YAHOO!知恵袋等にその答えが散見されます。
「草なぎ剛の 「なぎ」 はなんでいつもひらがななのですか?」
「草なぎ剛の 『なぎ』 って、何故漢字で変換出来ないの?」
これらの問いに対する回答はそれはそれで納得できましたが、
私の知りたいこととはちょっとずれているようにも思えます。
私の場合、漢字変換はできているし、ブログ編集画面上ではきちんと表示もされています。
それがプレビュー画面やiPhoneで見ると文字化けしてしまうのです。
どうもよくわかりません。
試しに他のSNSだとどうなるのか、彼の名前を正しく入力・変換しアップしてみました。
すると Facebook でも Twitter でも正しい文字が表示されていました。
なんだ、そっちは大丈夫なのか。
それじゃあこの場合はどうでしょうか?
私のブログは Facebook と Twitter に連携していて、
ブログをアップすると両SNSに投稿通知が自動的にアップされるようになっています。
その際に、gooブログの編集画面上で一言書くと、それがSNSへのコメントとして付加されます。
そのコメントの中に彼の名前を書いてみるとどうなるのでしょうか?
これも試しにやってみました。
すると Facebook のコメント欄では 「草剛」 と 「なぎ」 の漢字はなかったものとされていました。
Twitter では 「草?剛」 と半角のクエスチョンマークに文字化けしていました。
(試行後すぐにブログの投稿もSNSの投稿も削除したので今はもう見られません。)
やはりいろんな環境によって文字化けしたりしなかったりしてしまうみたいですね。
誰がどんな環境で見てくださるかわからない以上 「草なぎ剛」 で行くしかなさそうです。
…と思ってあきらめかけていたんですが、先ほどググっていたときにこんなサイトを発見しました。
「HTMLで難しい漢字を表示させる」
このサイトは素晴らしくって、まさに 「草なぎ剛」 という文字列を例に出しながら、
この 「なぎ」 という漢字をどんな環境でも正しく表示させる方法を解説してくれていました。
言ってる内容は専門的すぎてほとんど理解できませんでしたが、
唯一、Unicode という世界共通の文字コードを使えばいいらしい、ということだけは理解できました。
そうするための具体的方法として、草なぎの 「なぎ」 という漢字であれば、
「24389」 というのが Unicode 上の対応する数字で、その前に半角の「&」 と 「#」、
その後ろに半角のセミコロン 「;」 を付けてあげると、あの漢字が表示されるというのです。
ではやってみますよ。
それっ!
《草彅剛》
いかがですか?
ちゃんと表示されていますか?
パソコンの人もスマホの人もアップルの人もちゃんと 《草彅剛》 になっていますか?
編集画面上ではあくまでも 「草」 と 「剛」 の間にあるのは記号と数字だけなんです。
ああ、今度は逆にこの編集画面上でどう打ち込んであるのかをお伝えできないな。
こうしてみましょう。
《草彅剛》
半角の記号と数字だったものを全角に置き換えてみました。
これならこのまま表示されていることでしょう。
編集画面上では、これらの記号と数字が打ち込んであるだけなんです (半角で)。
でも、皆さんの画面上ではあの 「なぎ」 という漢字が正しく表示されているんじゃないですか?
もう一度やってみますよ。
《草彅剛》
おおっ、素晴らしいっ

これでもうパソコンで見ようがiPhoneで見ようが、
誰が見ても正しい漢字で彼の名前を表記することができるのですね。
おめでとう草彅さん、おめでとうSMAP

というところでこの話題、終了かと思っていたんですが、まだ少し問題が残っていました。
この記事、一気に書き上げることができずに何度か下書として保存しながら書いているのですが、
一度下書として保存したものを再び立ち上げると、
以前の編集画面では 《草彅剛》 と入力していたはずが (記号・数字は半角)、
新たに開いた編集画面では正しく 《草彅剛》 と変換されてしまっているのです。
なんだ、いいじゃないかと思われるかもしれませんが、
これを再び公開するとまた文字化けしてしまって 《草剛》 となってしまうのです。
(おわかりかと思いますが、このへん私はこの間に学んだシステムを逆手にとって入力しています。)
つまりこの記事は再編集するたびに、
正しく表示されていたはずの6ヶ所の 「彅」 の字 (ここも含む) が文字化けに戻ってしまうのです。
どういう仕組みかわかりませんが、とにかくそういうシステムのようです。
したがってこの記事は一度公開したら、もう手を入れ直したりせずそのまま放っておくか、
どうしても手直ししたい場合には、そのつどあの6ヶ所を Unicode に修正しなくてはいけないようです。
うーん、大変だ
 。
。私はけっこうあとから読み返して何度も文章に手を入れるタイプなので、
この記事もつい 「てにをは」 とかを直してしまうかもしれません。
そのたびに Unicode 修正のことを思い出せるのかどうか、はなはだ心配です。
この記事を読んでみて文字化けだらけで意味が通じないということがありましたら、
文章に手を入れたときに Unicode 修正のことを忘れたのだと思うので、ぜひ私までご一報ください。
以上、ウェブ上では書きにくい 「草彅剛問題」 でした。
(おっと、これで修正箇所は7ヶ所になった。)













































 )
)