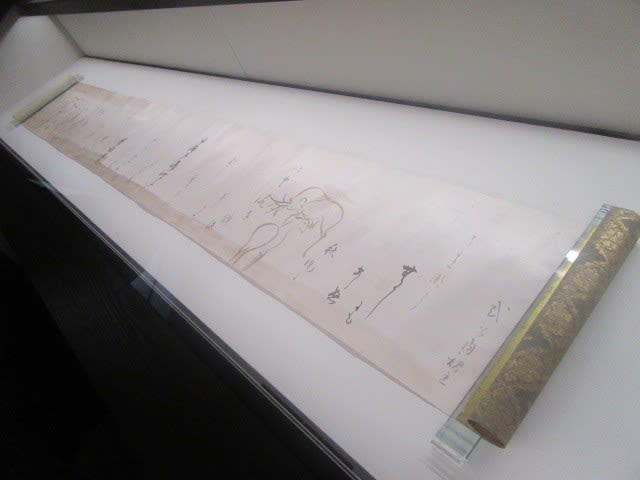おはようございます。
これも、あやうく見逃すところだった。最終日の日曜日、根津美術館の”染付誕生400年”展をみてきた。メイン展示はもちろん良かったが、得した気分になれたのが、庭園の茶室(弘仁亭・無事庵)で十四代今泉今右衛門の作品の展示があったことと、展示室5で百椿図(伝狩野山楽筆)に久し振りに再会できたこと。さらには、興福寺の梵天・帝釈天の112年振りの”再会”まで見させてもらい、とても実り多い展覧会だった。これらを一度に紹介できるかどうか分からないが、とにかく、はじめてみよう。できなければ、”つづく”にすれば良いのだから、ブログは気楽でいいね(汗)。
”染付誕生”というと、ぼくは昨秋の長崎・佐賀旅行を思い出す。その紀行文を書いたのだが、実は今回の展覧会にも深くかかわる有田訪問記だけ、書き残していて、ずっと気になっていた。ちょうどいい機会なので、ここで、拾い上げよう(汗)。
日本磁器発祥の地、有田の歴史は、17世紀初頭の朝鮮人陶工李参平が、泉山で陶石(磁器の原料)を発見したことから始まる。それまで陶器が主流であった我が国の陶磁器生産に大変革がもたらされた。この泉山陶石は代官所により厳しく管理され、利用される範囲も限られ、最も上質なものは御道具山(鍋島藩窯)が使用し、それ以外は内山、外山などの窯焼きが購入する場合は等級の区別があった。”400年かけてひとつの山を焼き物に変えた”と言われる泉山磁石場は、昭和5年に国の史跡に指定された。
泉山磁石場

陶石

陶山神社 有田焼陶祖・李参平碑や鳥居、狛犬を始めとする名工たちによる陶芸品の数々が鎮座する。



有田は、日本の磁器発祥の地。古い登り窯のレンガを利用したトンバイ塀がつづく。

肥前磁器は”伊万里焼”として、染付や白磁、青磁や色絵へと、中国の技術も取り入れながら、飛躍的に発展してゆく。この展覧会では、山本正之コレクション(根津美術館蔵)を中心に、17世紀から19世紀まで、順を追って、肥前磁器の歴史を観てゆこうというもの。楽しく、見させてもらった。ちらしにあがっている名作だけを以下に掲げておきます。
染付流水菊花文稜花鉢 肥前・江戸時代 17世紀 流水に浮かぶ菊花を中央に描いた大鉢。奇抜なのは内面周縁の文様で、斜めに傾いた束垣や竹、梅が細い線でダイナミックに描かれている(説明は原文のまま)。

染付鷺矢羽根文皿 肥前・江戸時代 17世紀 中央に片足で佇む一羽の白鷺、その周囲には矢羽根文が巡らされている。白鷺は肥前磁器の定番文様であり、本作はその最も早い例のひとつ。

染付雪柴垣文軍配形皿 肥前・江戸時代 17世紀 軍配の形をした器には、雪が降り積もった柴垣が描かれ、その背景は呉須が塗り詰められている。鮮やかな呉須の青と、雪にみる素地の純白が、皿全体に清浄な趣を与える。技術が高まり、文様や形が和様化する寛文(かんぶん)期の作。

色絵寿字文独楽形鉢 肥前・江戸時代 17-18世紀 赤絵や金彩などでふんだんに上絵を施した金襴手の優品。中央には「寿」の一字を、周囲の4つの窓には宝尽文が描かれた吉祥の器である。


さらに、現代の名工の作品が庭園の茶室内で展示されているのだが、それについては次回ということで。
それでは、みなさん、今日も一日、大事なお皿をうっかり落とさぬように(笑)、お元気で!