こんばんわ。
蔦屋重三郎展/コンテンツビジネスの風雲児が東博で始まり、その初日に見てきました。東博の常設展は写真撮影が許可されているが、特別展となると不許可になる。ただ今回は最終章(附章)だけがOKとなっていた。

第一会場(第1,2章)の入り口は巨大な吉原の大門。そして、大門につづく仲通りには毎春恒例だったという桜まつり、満開桜の大木が幾本も並ぶ。ここだけは写真を撮らせてもらいたかった。NHKの大河ドラマ”べらぼう”のセットをお借りしたものだという。
章立ては次の通り。
第1章 吉原細見・洒落本・黄表紙の革新
第2章 狂歌隆盛―蔦唐丸、文化人たちとの交流
第3章 浮世絵師発掘―歌麿、写楽、栄松斎長喜
附章 天明寛政、江戸の街
順に紹介するより、写真撮影が可能だった最終章から始めた方が書きやすいかな。ここは蔦重が吉原から日本橋に移した地本問屋「耕書堂」の界隈。ここで、洒落本や浮世絵などを扱い、北斎や歌麿、写楽などの絵師の作品や、山東京伝や大田南畝などの戯作者の作品を出版し多くの実績を残した。
附章 天明寛政、江戸の街
蔦重が見い出し、売り出した写楽と歌麿の名作の大写しが迎えてくれる。


蔦重の耕書堂

店内の様子

さまざまな本が。禁現大福帳、風俗八色談など洒落本など。

啌多雁取帳(うそしっかりがんとりちょう)シリーズ

蔦重の席。

隣りのお店。

何のお店? ”べらぼう”店のようだ。番組に使用された小道具が売りに出ている(笑)。これらの本物は本展で展示されているが、ほぼ同じ形態のもの。

吉原細見や一目千本も。

蔦重の最初のヒット作、吉原細見・籬(まがき)の花。恋川春町の”金々先生栄花夢”も。

伊藤佐智子による衣裳デザイン 下の段、左から。平賀源内、花の井、蔦重。

雛型若菜初模様。礒田湖龍斎の代表的なシリーズで、100枚以上が知られている。吉原の高名な花魁を描いたもので、流行の着物や髪形などを描いた 。

平賀源内のエレキテル。第1章では本物(重要文化財)が展示されている。

日本橋の花火も見られますよ。

エレキテルだけではなく、これまで紹介したものはすべて各章に本物が飾られている。ここで再度紹介することはないので(逃げて)、公式サイトの解説を写し、多少の感想を付け加え、蔦重展の記録としたい。
第1章 吉原細見・洒落本・黄表紙の革新
蔦屋重三郎は寛延3年(1750)、幕府公認の遊廓である吉原の地に生まれた。彼の出版人としての活動は、その吉原の情報誌『吉原細見』の出版に携わるところから始まる。蔦重はすぐさま優れた手腕を発揮し、富本正本や往来物といった定番商品、さらには人気の作者や絵師を抱えて戯作の出版に乗り出した。風刺や滑稽を織り交ぜた黄表紙や洒落本は大衆の心をとらえ、朋誠堂喜三二や恋川春町、山東京伝ら才子の傑作を世に送り出す。(公式サイトより)
ここには、山東京伝の作品も多数、集結。その一つ。
山東京伝 箱入り娘面屋人魚 版元、蔦唐丸(蔦重の狂歌名)、絵の人物も蔦重がモデルとされる。

第2章 狂歌隆盛―蔦唐丸、文化人たちとの交流
天明期(1781~89)を中心に、江戸では狂歌が爆発的な人気を博する。武士や町人、役者や絵師らさまざまな階層の人が集まり、江戸を謳歌する狂歌を詠み、遊び戯れた。蔦重はそこに、狂歌師「蔦唐丸」として参入する。しかし彼の関心はクリエイターとしての文芸活動にとどまらない。四方赤良(大田南畝)や唐衣橘洲、朱楽菅江ら当代一流の文化人たちとの交流のなかで、狂歌集、狂歌絵本を一手に刊行するプロデューサーとして商才を発揮し、江戸文化の発信源となる。
歌麿のデビュー作、”画本虫撰”がこの章で登場。狂歌に虫の絵を添える。
宿屋飯盛撰/喜多川歌麿画
歌麿 歌まくら

第3章 浮世絵師発掘―歌麿、写楽、栄松斎長喜
寛政期(1789~1801)、蔦重は浮世絵界に進出する。喜多川歌麿、東洲斎写楽、栄松斎長喜といった名だたる絵師たちを発掘し、彼らの魅力を最大限に生かした浮世絵を企画・出版する。蔦重版の作品を特徴づけるのは、人物の顔を大胆にクローズアップした「大首絵」の構図である。この手法により、歌麿はあらゆる年齢や階層の女性の心情を描き分け、写楽は歌舞伎役者の個性をとらえた。今を生きる人々の内面を映し出した錦絵は、版元・蔦重の、そして浮世絵の人物表現の一つの到達点を示している。
歌麿、写楽の名作がこの章に集結。
歌麿 江戸三美人

歌麿 婦女人相十品 ポッピンを吹く娘

写楽 市川鰕蔵の竹村定之進 三代目大谷鬼次の江戸兵衛

とても面白い展覧会でした。
では、おやすみなさい。
いい夢を。




















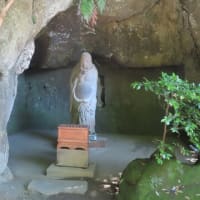




今はTVで放映されてますので、一層、人も多かったことと思います。
今回は特に、TVも関連付けられていて、展示の仕方が分かりやすく、誰でも楽しめるように工夫されているのですね。
流石!東博ですね^^
蔦重が版元の早稲田コピーなども、これまでにいくつか読んでいました。
山東京伝作の箱入り娘面屋人魚も、その一つでした。
marbo様は版画がお好きだとのことで、これまでにも版元の名を意識されていたことでしょう。
尊敬いたします^^
今回は版画もずいぶん多かったのではないでしょうか。
marbo様の喜びの顔が目に浮かぶようです^^
ご紹介いただき、感謝いたします。
ありがとうございます。
Rancyouさんがいつも読まれている江戸の古書の原本がずらりと並び、もし、来られていたら、感激すると思います。ぼくは浮世絵がうれしかったですね。ありがとうございました。