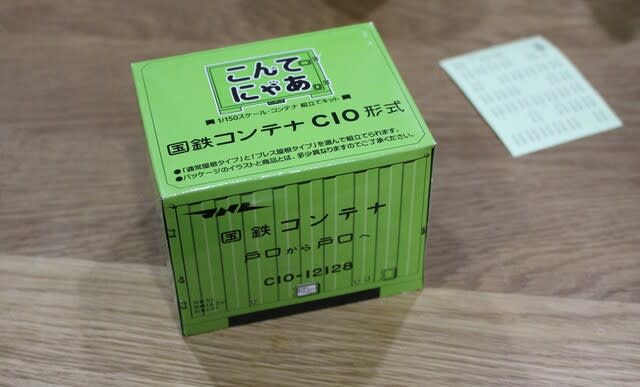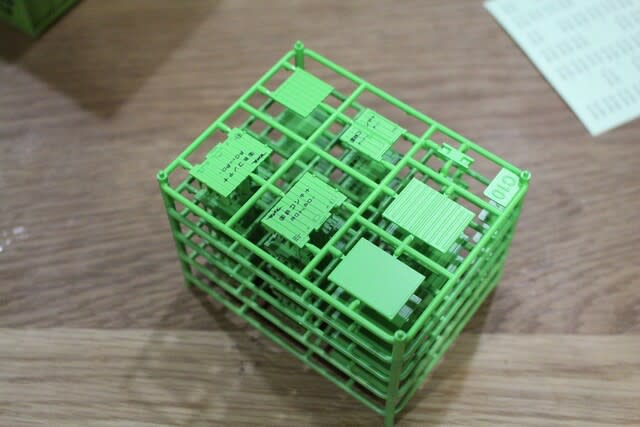前々回のブログでイギリス型Nゲージの「パディントン号」が入線した話を書きました。そのパディントンですが、もともとは児童文学ですので、子供のおもちゃなどになっています。
私が2099年にパディントン駅で買ったのがこちら。

駅の構内に「パディントン・スタンド」というグッズ売店があり、玩具や書籍が売られています。原作のイメージに近い青いダッフルコートにしました。


胸元には「このクマをよろしくお願いします」というパディントンを象徴する札がついています。
そしてこちらはだいぶ古びてしまったのですが、1980年に父が欧州を訪れた際に買ってきてくれたものでした。

パペットスタイルになっていて自立しませんので、使わなくなったお茶の缶を芯にして立たせています。
ガブリエル・デザインズという版権許諾を得たオリジナルのぬいぐるみを作っていた会社の製品というのが、例の荷札にも記されています。ウィキペディアによると、ガブリエル・デザインズの経営者の子供がBBCの人気番組、トップ・ギアで司会を務めていたジェレミー・クラークソンとあります。もともと紅茶ポットに被せる布製のカバー「ティー・コージー」を販売していたと英語版のウィキペディアには書いてありますが、それ以上の情報は分かりません。パディントンのぬいぐるみは版権を得ていないものもあったようですから、父はきちんとしたお店で買ったようです。「うちの子供が大好きでね」と英語で店員さんに話したところ、店員さんもとても喜んでいた、と聞かされました。今以上にポンドが強かった時代ですので、ちょっとした買い物だったことでしょう。しばらくは実家でテレビの横に鎮座し、今の寓居では自分が買った方のぬいぐるみと共にアクリルケースに収められていますが、細かいほこりなども入ってしまい、気の毒なことをさせてしまっています。
パディントンのぬいぐるみはこんなかわいらしいものもあります。

彼のトレードマークのトランクの中に

小さなパディントンのぬいぐるみが入っています。大きいぬいぐるみが14.99ポンド、こちらは4.99ポンドでした。
Nゲージの「パディントン」と比べてみましょう。

2009年のロンドン滞在では、他にも本を買って帰りました。帰国後、通勤時間がそれなりに長かったので読んでみましたが、自分が子供の頃喜んで読んだのはこんな世界観の作品だったのかという気分になりました。児童文学ですので中学卒業程度の(私のような乏しい)英語力でもなんとかなりますが、ときどき難しい言い回しが出てきたりしたことを覚えています。

お店の買い物袋も捨てずにとってあります。丈夫な紙袋です。
パディントン駅には銅像もあります。待ち合わせスポットのようになっていて写真が撮れず、こちらはウィキペディアから持ってきました。

パディントンの関連商品ですが、我が家には他にもケーキ皿だったり、日本で購入した英語の絵本などがあります。メトロカードのデザインにも使われていましたし、三井銀行のキャラクターだったこともあり、キャッシュカードのデザインにも使われていました。カテゴリーを鉄道としながら「玩具道楽」の方に脱線してしまいましたが、メトロカードの名前が出てきたところで、ようやく鉄道の方に戻ってきました。

ロンドンで買った原書(などと言うとおおげさですが、日本語版では「パディントンのどろぼう退治」というタイトルだそうです)とSFメトロカード。メトロカードの方は東京メトロの販売機で普通に売られていたと思います。なお、パディントン駅は地下鉄も多く乗り入れており、世界初の地下鉄路線の駅の一つにも数えられています。東洋初の地下鉄である東京の地下鉄のカードのデザインに使われたのも何かの縁でしょう。

本の栞のかわりに使っていたパディントン→ヒースローまでの列車のチケット。
私が2099年にパディントン駅で買ったのがこちら。

駅の構内に「パディントン・スタンド」というグッズ売店があり、玩具や書籍が売られています。原作のイメージに近い青いダッフルコートにしました。


胸元には「このクマをよろしくお願いします」というパディントンを象徴する札がついています。
そしてこちらはだいぶ古びてしまったのですが、1980年に父が欧州を訪れた際に買ってきてくれたものでした。

パペットスタイルになっていて自立しませんので、使わなくなったお茶の缶を芯にして立たせています。
ガブリエル・デザインズという版権許諾を得たオリジナルのぬいぐるみを作っていた会社の製品というのが、例の荷札にも記されています。ウィキペディアによると、ガブリエル・デザインズの経営者の子供がBBCの人気番組、トップ・ギアで司会を務めていたジェレミー・クラークソンとあります。もともと紅茶ポットに被せる布製のカバー「ティー・コージー」を販売していたと英語版のウィキペディアには書いてありますが、それ以上の情報は分かりません。パディントンのぬいぐるみは版権を得ていないものもあったようですから、父はきちんとしたお店で買ったようです。「うちの子供が大好きでね」と英語で店員さんに話したところ、店員さんもとても喜んでいた、と聞かされました。今以上にポンドが強かった時代ですので、ちょっとした買い物だったことでしょう。しばらくは実家でテレビの横に鎮座し、今の寓居では自分が買った方のぬいぐるみと共にアクリルケースに収められていますが、細かいほこりなども入ってしまい、気の毒なことをさせてしまっています。
パディントンのぬいぐるみはこんなかわいらしいものもあります。

彼のトレードマークのトランクの中に

小さなパディントンのぬいぐるみが入っています。大きいぬいぐるみが14.99ポンド、こちらは4.99ポンドでした。
Nゲージの「パディントン」と比べてみましょう。

2009年のロンドン滞在では、他にも本を買って帰りました。帰国後、通勤時間がそれなりに長かったので読んでみましたが、自分が子供の頃喜んで読んだのはこんな世界観の作品だったのかという気分になりました。児童文学ですので中学卒業程度の(私のような乏しい)英語力でもなんとかなりますが、ときどき難しい言い回しが出てきたりしたことを覚えています。

お店の買い物袋も捨てずにとってあります。丈夫な紙袋です。
パディントン駅には銅像もあります。待ち合わせスポットのようになっていて写真が撮れず、こちらはウィキペディアから持ってきました。

パディントンの関連商品ですが、我が家には他にもケーキ皿だったり、日本で購入した英語の絵本などがあります。メトロカードのデザインにも使われていましたし、三井銀行のキャラクターだったこともあり、キャッシュカードのデザインにも使われていました。カテゴリーを鉄道としながら「玩具道楽」の方に脱線してしまいましたが、メトロカードの名前が出てきたところで、ようやく鉄道の方に戻ってきました。

ロンドンで買った原書(などと言うとおおげさですが、日本語版では「パディントンのどろぼう退治」というタイトルだそうです)とSFメトロカード。メトロカードの方は東京メトロの販売機で普通に売られていたと思います。なお、パディントン駅は地下鉄も多く乗り入れており、世界初の地下鉄路線の駅の一つにも数えられています。東洋初の地下鉄である東京の地下鉄のカードのデザインに使われたのも何かの縁でしょう。

本の栞のかわりに使っていたパディントン→ヒースローまでの列車のチケット。