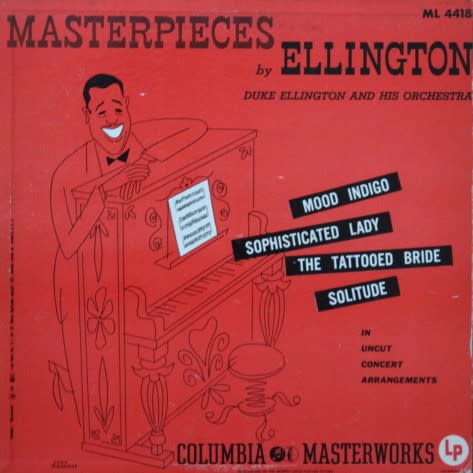Duke Ellington and His Orchestra featuring Maharia Jackson / Black, Brown And Beige ( 米 Columbia CL 1162 )
奴隷制度と人種差別をテーマにした組曲ということで煙たがられる作品だろう。娯楽の中にそんなものを持ち込むなよ、というのが大方の本音だろう。
まあ、そういう気持ちはわからないではないが、これはそういうのを抜きにしてもただただ素晴らしい音楽だ。先入観抜きに愉しめばいいと思う。
例えば、ドイツという国はナチスの歴史を国を挙げて悔やみ、恥じ、2度と繰り返すまいとしている。学校で先生の質問に子供たちが手を挙げる際は
真っ直ぐに挙手せず、人差し指を立てて合図するという。一方、アメリカはどうだろう。奴隷制度という黒歴史にどう向き合っているのだろう。
人間の暗部や恥部に向き合うのは辛いことだけど、エリントンは正面切ってそういうものに取り組んでいる。
でも、そういう重苦しい雰囲気はここにはない。エリントン楽団だけが出せる芳香漂うアンサンブルで空間が埋め尽くされる快楽度の高さ。
オーケストラがまるで生きているかのように音楽をドライヴする。
マヘリア・ジャクソンの歌が始まると、鳥肌が立ちっぱなしになる。心は震え続ける。彼女の抑制された感情の移ろいがそのままこちらに乗り移る。
背後で鳴るエリントンのピアノのなんと美しいことか。このアルバムのエリントンのピアノの音色は本当に美しい。
Come Sunday という主題が様々な形で変奏され、寄せては遠ざかる波のように音楽を揺らす。B面は完全にオペラで、エリントン楽団の繊細で精緻で
洗練を極める演奏が圧巻。まるで欧州の名門オーケストラを聴いているかのようだ。
全体的に穏やかで優しい旋律で奏でられて、それは心を慰撫し癒す。この中に込められたそういう想いは深く、音楽の隅々にまで行き渡っている。
何かを糾弾し煽動しようとする要素は微塵もない。許しと祈りの音楽で、それを物憂げでそれでいて明るい色調に纏めた素晴らしい音楽だと思う。
コロンビアの録音も相変わらずの見事さで、こういう音楽の受け皿はやはりこのレーベル以外には考えられない。1943年の初演の際の評価は
芳しくなかったそうだが、素直に音楽を享受するには難しい時代だったのだろう。以来15年間、エリントンはこの企画を温め続けて、マヘリアという
歌手が現れるの待ち、録音技術が整ったこのタイミングで再演した。音楽を聴く意味を噛みしめることができる、素晴らしいアルバムである。