今日は休みだったので、ちょうど今日から展示が始まる、金印を見に、「日本国宝展」(上野の東京国立博物館)に行って来ました。期間限定の展示がいろいろあり、いつ行こうか?と考え、まだ見たことがなく、高校日本史でもポピュラーな、「金印」が展示されている時に行こうと決めていました。
展示初日ということもあり多かったのかな?お昼前に行って「30分待ち」という表示。私はもちろん大学生料金(笑)。一般は1600円ですが大学生は1200円、高校生は900円、中学生以下は無料。実際には20分ほどで入れました。
全体の中で印象に残ったものをいくつか紹介します。
入るとすぐに、法隆寺の「玉虫厨子」(飛鳥時代 7世紀)がありました。高校の修学旅行などで見ていますが・・・玉虫の羽はどこに貼られているのか・・・みんな目をこらして探していました。ある女性の方が、「あっ、あそこ!」といって、場所を周りの人に教えてくれました。私もそういった声を聞かなければわかりませんでした。いやー本当に、かすかな緑色の光が一点、きらっと光って見えました。あれ1枚しか残っていないのかな?どこにあるのか聞いても見つけられない人もいました。あれは、ある角度からしか見えないんじゃないでしょうか。ちなみにショップで本物の玉虫の入ったキーホルダーが売っていました。ちょっと不気味でした。
平等院鳳凰堂の上の壁の所に飛んでいる「雲中供養菩薩像」(平安時代 1053年)も二人来ていました。これも修学旅行で見たことがあるものですが、楽器を奏でている姿がかわいらしく、動きがあって、私はこれが結構好きです。会えてうれしかった。心の中であいさつしました。
藤ノ木古墳出土の「金銅製鞍金具」(古墳時代 6世紀)も、よく写真では見ていましたが実物を見ることができました。きれいな金色をしていました。
「僧形八幡神坐像」「神功皇后坐像」(平安時代 9世紀)も来ていましたが、何しろ国宝ばかりですから、とりたてて人だかりがあったわけでもありませんでした。教科書でもおなじみで、以前にも生で展示を見た記憶がありますが、改めて、小ぶりの像だなと思いました。
そして、「金印」(弥生時代 1世紀)ですが、部屋の真ん中あたりにその展示スペースはありました。とにかく、ガラスケースを囲んでおしくらまんじゅう状態。ちょっとあれは参りました。
その実物は、まさにゴールド・黄金の輝き。周りの人達も、「小さい」と口々に言っていましたが、小さいです。小さいですが、金色の存在感はさすがです。大きさは、一辺の長さが2.3cm、高さ2.2cm、重さは108.7gとのことです。ですから結構重いんですよ。そんな金の塊、持ったことないですから、実感はないですが、普通の卵の重さは60gくらい、と家庭科で教わったような気がします。その倍くらいの重さがあるんですよね。小さいのにずっしり重いんでしょうね。
彫られている文字は「漢委奴国王」。それが下にある鏡に映るようにして展示されています。それを見ようとして、みんな、正面の方に殺到して、ぎゅうぎゅうおしくらまんじゅうになるんです。そして時々、係員の女性が間に入って、「押し合わないで譲り合ってご覧ください」と言いながら、ガラスを拭いていました。お客さんがガラスに手(や顔?)を押し付けるので、ガラスを拭かねばならないのですね。
結構あれは危険です。そのうちガラスが割れるんじゃなかろうか?何か、展示・見学方法を変えた方がいいのでは?列を作って順番に流して行った方がいいかも?
私は、ぎゅうぎゅう押されながら最前列に行く気にはなれず、一応、すき間から鏡に映った印面を見ましたが、あんまり字ははっきり見えない。それでまあ、正面以外は結構ガラ空きだったりするので、反対側から、しゃがんで下の方から覗きこんで、印面を確認しました。反対側からでも印面は直接よく見えました。
先日の大学通信教育の科目修得試験で、「金印をめぐる諸問題について記せ。」という設題もあり、その解答も用意したのですが(以前説明したように、10問の設題の中から当日示される番号の問題を解答する)、そこで勉強したことからいくつかここにも書きますと、発見したのは、江戸時代、福岡藩の志賀島の百姓、甚兵衛さん。甚兵衛さんが田の溝を修理していた時に発見されたのでした。
こういうものを、自分のものにしてしまわないで、正直に届け出て、今の世に至るまで大切に保管されていたということは、すばらしいことですね。日本人の美徳だと思います。
これが、偽物ではなく本物だということは、印のサイズや金の成分などから確実なようですが、この印の読み方は、いくつか説があります。教科書的には、「かんのわのなのこくおう」と読む、ということになっていて、私も生徒にそう教えてきました。紀元57年に漢の光武帝から奴国が印綬をもらったという『後漢書』東夷伝の記事があり、それに該当するということで、読み方も「奴の国王」でいいということになりますが、これがほぼ定説でよいとは思いますが、これを、「漢のいとこく(委奴国)の王」と読む、という説もあるようです。「いとこく」は、『魏志』倭人伝にも出て来る「伊都国」になります。
まあ、確かに、にんべんがないのに「委」を「倭(わ)」と読むのか?という素朴な疑問はあるでしょう。
ここでは軽く、そういう説もあるということに触れるだけにしておきましょう。
さて、他の部屋で印象に残ったものですが、
「支倉常長像」は、よく見ると、左手の薬指に指輪がしてあって、結構おしゃれだね、と気が付きました。
「元興寺極楽坊五重小塔」も、こんなサイズのものが、国宝であったんだ、と再確認させられました。とても精巧です。
法隆寺の「広目天立像」(飛鳥時代 7世紀)は、今まで注目したことがありませんでしたが、顔が、あの同じ法隆寺にある百済観音と似ている、と思いました。作者か、作った人の出身国が同じなのかなと思いました。
そして、かなり大きな仏像もはるばる京都から来てくれていました。それは、今回のチケットやポスターにも代表的作品として写真が載せられている、京都三千院の「観音菩薩坐像・勢至菩薩坐像」(平安時代 1148年)の2体です。
私は、興福寺仏頭をはじめ、飛鳥・奈良時代の仏像が好みなのですが、近頃、平安時代の仏像も、いくらか好みになってきました。嗜好(というのかな?)って、変わるんでしょうか。もちろん、飛鳥・奈良時代の仏像も好きなのは変わりませんが。
この三千院の二つの菩薩像は、とても穏やかで、微妙な、慈悲の表情を浮かべています。
「死者を極楽浄土に導くために来迎する阿弥陀如来に随う2体の菩薩です。膝を開いて正座し、上体を前かがみにする姿勢には、来迎像にふさわしい前方に向かう動きが感じられます。」(東博HPより)
とあるように、横から見ると、前かがみになっているのがわかります。そうやって、死者を迎えているのだそうで、そういう説明が、現地の説明板にも書いてあって、それを読むと、みんな、なるほどなと感じて、しげしげと仏像を見つめていました。手に持っているお椀(蓮華?)に死者を入れて極楽に運んで行く?というようなことが書いてありました。
この菩薩さんの表情がとてもよくて、死への恐怖のような気持ちも受け止めてくれそうな感じがしました。安心して極楽往生できそうな雰囲気です。父親はクリスチャンですし、私もキリストの言葉をよく読む方ですので、仏教の教えにはうといのですが、今日見たこの仏像は安らぎを感じ、ちょうど今日、亡くなったというニュースが駆けめぐった高倉健さんも、この菩薩さんに付き添われて、極楽に安らかに行ってくれていたらいいな、という思いがふとわいてきました。
いつも散財してしまう、ショップでの買い物ですが、金印は、レプリカ(木箱入り)が3,000円以上で、ちょっとどうかなと手を出しませんでした。代わりに原寸大で印面がゴム印になっているもの(710円)を購入しました。
私は以前から、ただのゴム印(原寸大)は持っていて、前の学校でちょうど金印について学習する時には、そのゴム印を回して、プリントに押したい生徒には押させていました。
今日買ったものは、蛇のデザインのつまみなどもそれなりにリアルなので、こっちを回覧した方が生徒もイメージを実感しやすいかなと思います。

その他、買おうか迷ってやめたのは、「縄文のヴィーナス」のぬいぐるみです。手触りがよくて、持っていると元気が出そうでしたが・・・小さいストラップのものは買いました。
それにしても、今回もいくつか見ましたが、土偶のデザインは、力強くて、芸術的で、見事ですね。縄文の底力を感じます。埴輪か土偶か、といったら、土偶の方が芸術性を感じます。東日本の宝ですね。
今回の国宝展は、日本中の国宝の10分の1が集結しているとのこと。11月21日からは、国宝土偶の「神ファイブ」も展示されるとのこと。
そして、金印は、今日11月18日から30日までの「12日間限定!」(HPより)です。
お客さんが殺到して見るのが大変な金印ですが、福岡市の博物館では常設展示されているらしいので、福岡に行って見れば、もっとじっくり見られるのでしょうね。


東博のマスコットは、ハニワのトーハクくんとユリノキちゃん。本館前の立派な木は、だからユリノキなんでしょうね。上野の紅葉は、まだもう少し先が見頃のようでした。
時間を忘れて博物館に滞在した、世の中は平日の、休日でした。
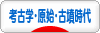 にほんブログ村
にほんブログ村
展示初日ということもあり多かったのかな?お昼前に行って「30分待ち」という表示。私はもちろん大学生料金(笑)。一般は1600円ですが大学生は1200円、高校生は900円、中学生以下は無料。実際には20分ほどで入れました。
全体の中で印象に残ったものをいくつか紹介します。
入るとすぐに、法隆寺の「玉虫厨子」(飛鳥時代 7世紀)がありました。高校の修学旅行などで見ていますが・・・玉虫の羽はどこに貼られているのか・・・みんな目をこらして探していました。ある女性の方が、「あっ、あそこ!」といって、場所を周りの人に教えてくれました。私もそういった声を聞かなければわかりませんでした。いやー本当に、かすかな緑色の光が一点、きらっと光って見えました。あれ1枚しか残っていないのかな?どこにあるのか聞いても見つけられない人もいました。あれは、ある角度からしか見えないんじゃないでしょうか。ちなみにショップで本物の玉虫の入ったキーホルダーが売っていました。ちょっと不気味でした。
平等院鳳凰堂の上の壁の所に飛んでいる「雲中供養菩薩像」(平安時代 1053年)も二人来ていました。これも修学旅行で見たことがあるものですが、楽器を奏でている姿がかわいらしく、動きがあって、私はこれが結構好きです。会えてうれしかった。心の中であいさつしました。
藤ノ木古墳出土の「金銅製鞍金具」(古墳時代 6世紀)も、よく写真では見ていましたが実物を見ることができました。きれいな金色をしていました。
「僧形八幡神坐像」「神功皇后坐像」(平安時代 9世紀)も来ていましたが、何しろ国宝ばかりですから、とりたてて人だかりがあったわけでもありませんでした。教科書でもおなじみで、以前にも生で展示を見た記憶がありますが、改めて、小ぶりの像だなと思いました。
そして、「金印」(弥生時代 1世紀)ですが、部屋の真ん中あたりにその展示スペースはありました。とにかく、ガラスケースを囲んでおしくらまんじゅう状態。ちょっとあれは参りました。
その実物は、まさにゴールド・黄金の輝き。周りの人達も、「小さい」と口々に言っていましたが、小さいです。小さいですが、金色の存在感はさすがです。大きさは、一辺の長さが2.3cm、高さ2.2cm、重さは108.7gとのことです。ですから結構重いんですよ。そんな金の塊、持ったことないですから、実感はないですが、普通の卵の重さは60gくらい、と家庭科で教わったような気がします。その倍くらいの重さがあるんですよね。小さいのにずっしり重いんでしょうね。
彫られている文字は「漢委奴国王」。それが下にある鏡に映るようにして展示されています。それを見ようとして、みんな、正面の方に殺到して、ぎゅうぎゅうおしくらまんじゅうになるんです。そして時々、係員の女性が間に入って、「押し合わないで譲り合ってご覧ください」と言いながら、ガラスを拭いていました。お客さんがガラスに手(や顔?)を押し付けるので、ガラスを拭かねばならないのですね。
結構あれは危険です。そのうちガラスが割れるんじゃなかろうか?何か、展示・見学方法を変えた方がいいのでは?列を作って順番に流して行った方がいいかも?
私は、ぎゅうぎゅう押されながら最前列に行く気にはなれず、一応、すき間から鏡に映った印面を見ましたが、あんまり字ははっきり見えない。それでまあ、正面以外は結構ガラ空きだったりするので、反対側から、しゃがんで下の方から覗きこんで、印面を確認しました。反対側からでも印面は直接よく見えました。
先日の大学通信教育の科目修得試験で、「金印をめぐる諸問題について記せ。」という設題もあり、その解答も用意したのですが(以前説明したように、10問の設題の中から当日示される番号の問題を解答する)、そこで勉強したことからいくつかここにも書きますと、発見したのは、江戸時代、福岡藩の志賀島の百姓、甚兵衛さん。甚兵衛さんが田の溝を修理していた時に発見されたのでした。
こういうものを、自分のものにしてしまわないで、正直に届け出て、今の世に至るまで大切に保管されていたということは、すばらしいことですね。日本人の美徳だと思います。
これが、偽物ではなく本物だということは、印のサイズや金の成分などから確実なようですが、この印の読み方は、いくつか説があります。教科書的には、「かんのわのなのこくおう」と読む、ということになっていて、私も生徒にそう教えてきました。紀元57年に漢の光武帝から奴国が印綬をもらったという『後漢書』東夷伝の記事があり、それに該当するということで、読み方も「奴の国王」でいいということになりますが、これがほぼ定説でよいとは思いますが、これを、「漢のいとこく(委奴国)の王」と読む、という説もあるようです。「いとこく」は、『魏志』倭人伝にも出て来る「伊都国」になります。
まあ、確かに、にんべんがないのに「委」を「倭(わ)」と読むのか?という素朴な疑問はあるでしょう。
ここでは軽く、そういう説もあるということに触れるだけにしておきましょう。
さて、他の部屋で印象に残ったものですが、
「支倉常長像」は、よく見ると、左手の薬指に指輪がしてあって、結構おしゃれだね、と気が付きました。
「元興寺極楽坊五重小塔」も、こんなサイズのものが、国宝であったんだ、と再確認させられました。とても精巧です。
法隆寺の「広目天立像」(飛鳥時代 7世紀)は、今まで注目したことがありませんでしたが、顔が、あの同じ法隆寺にある百済観音と似ている、と思いました。作者か、作った人の出身国が同じなのかなと思いました。
そして、かなり大きな仏像もはるばる京都から来てくれていました。それは、今回のチケットやポスターにも代表的作品として写真が載せられている、京都三千院の「観音菩薩坐像・勢至菩薩坐像」(平安時代 1148年)の2体です。
私は、興福寺仏頭をはじめ、飛鳥・奈良時代の仏像が好みなのですが、近頃、平安時代の仏像も、いくらか好みになってきました。嗜好(というのかな?)って、変わるんでしょうか。もちろん、飛鳥・奈良時代の仏像も好きなのは変わりませんが。
この三千院の二つの菩薩像は、とても穏やかで、微妙な、慈悲の表情を浮かべています。
「死者を極楽浄土に導くために来迎する阿弥陀如来に随う2体の菩薩です。膝を開いて正座し、上体を前かがみにする姿勢には、来迎像にふさわしい前方に向かう動きが感じられます。」(東博HPより)
とあるように、横から見ると、前かがみになっているのがわかります。そうやって、死者を迎えているのだそうで、そういう説明が、現地の説明板にも書いてあって、それを読むと、みんな、なるほどなと感じて、しげしげと仏像を見つめていました。手に持っているお椀(蓮華?)に死者を入れて極楽に運んで行く?というようなことが書いてありました。
この菩薩さんの表情がとてもよくて、死への恐怖のような気持ちも受け止めてくれそうな感じがしました。安心して極楽往生できそうな雰囲気です。父親はクリスチャンですし、私もキリストの言葉をよく読む方ですので、仏教の教えにはうといのですが、今日見たこの仏像は安らぎを感じ、ちょうど今日、亡くなったというニュースが駆けめぐった高倉健さんも、この菩薩さんに付き添われて、極楽に安らかに行ってくれていたらいいな、という思いがふとわいてきました。
いつも散財してしまう、ショップでの買い物ですが、金印は、レプリカ(木箱入り)が3,000円以上で、ちょっとどうかなと手を出しませんでした。代わりに原寸大で印面がゴム印になっているもの(710円)を購入しました。
私は以前から、ただのゴム印(原寸大)は持っていて、前の学校でちょうど金印について学習する時には、そのゴム印を回して、プリントに押したい生徒には押させていました。
今日買ったものは、蛇のデザインのつまみなどもそれなりにリアルなので、こっちを回覧した方が生徒もイメージを実感しやすいかなと思います。

その他、買おうか迷ってやめたのは、「縄文のヴィーナス」のぬいぐるみです。手触りがよくて、持っていると元気が出そうでしたが・・・小さいストラップのものは買いました。
それにしても、今回もいくつか見ましたが、土偶のデザインは、力強くて、芸術的で、見事ですね。縄文の底力を感じます。埴輪か土偶か、といったら、土偶の方が芸術性を感じます。東日本の宝ですね。
今回の国宝展は、日本中の国宝の10分の1が集結しているとのこと。11月21日からは、国宝土偶の「神ファイブ」も展示されるとのこと。
そして、金印は、今日11月18日から30日までの「12日間限定!」(HPより)です。
お客さんが殺到して見るのが大変な金印ですが、福岡市の博物館では常設展示されているらしいので、福岡に行って見れば、もっとじっくり見られるのでしょうね。


東博のマスコットは、ハニワのトーハクくんとユリノキちゃん。本館前の立派な木は、だからユリノキなんでしょうね。上野の紅葉は、まだもう少し先が見頃のようでした。
時間を忘れて博物館に滞在した、世の中は平日の、休日でした。









