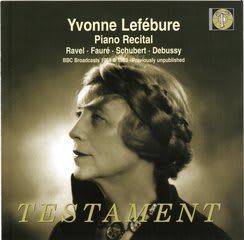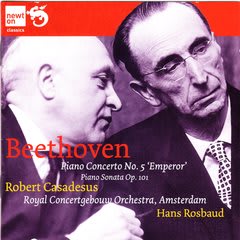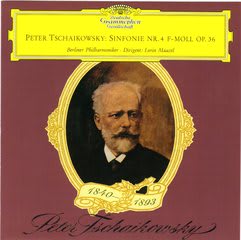半年ごとに、新譜CDの中から書いておきたいと思ったものを自由に採り上げて、詩誌『孔雀船』に掲載して、もう20年以上も経ちました。2011年までの執筆分は、私の第二評論集『クラシック幻盤 偏執譜』(ヤマハミュージックメディア刊)に収めましたが、本日は、最新の執筆分で、昨日書き終えたばかりの今年上半期分です。いつものように、詩誌主宰者のいつもながらのご好意で、このブログに先行掲載します。なお、当ブログのこのカテゴリー名称「新譜CD雑感」の部分をクリックすると、これまでのこの欄の全ての執筆分が順に読めます。
ソニー系に米コロンビアと米RCAの原盤権が集約されたおかげで、このところテーマ別に集大成された様々なボックス物が登場している。この『ERIK SATIE & Friends』と題されたものは、サティの作品を中心に、その仲間たちの音楽も集めた一三枚組。それぞれオリジナルLPのオモテ・ウラを当時のままに再現した紙ジャケットに封入され、CDの盤面も当時のレーベル面を再現するという念の入ったもの。すなわち、「音符」も「犬」も居て、二つ目、六つ目、白犬、影付き犬も登場する。(この話、レコードマニアでなければ伝わらない?)音は、どれもかなりいい。カサドシュ夫妻の弾く『四手のピアノ曲集』は、これまで様々の復刻盤でずっと裏切られていたが、今回の盤でやっと納得。プーランクのピアノ伴奏によるベルナックの『フランス歌曲集』やクレスパンの歌う『サティ+ラヴェル歌曲集』も、思わず、歌声に惚れ込んだ。クレスパンの伴奏、サティ作品のピアノ独奏、ロイヤル・フィルを指揮してのサティと、三者三様のフィリップ・アントルモンのセンスにもすっかり感心した。『パラード』でアントルモン指揮のほかに一九四九年録音のエフレム・クルツ盤も収録するなど、同曲異演で四〇年代後半から七〇年代後半までのサティ解釈の変遷も追える。サティを六〇年代半ばに追いかけ始めた私にとっては、米コロンビア系のモノラル録音は見落としていたものも多かったし、七〇年から八〇年にかけてのアメリカレーベルのサティ録音(ヴァルサーノやマッセロスによるピアノ曲)にも目配りしていなかったことを思い知らされた。
レジナルド・ケルのクラリネットで一九五〇年録音のモーツァルト「協奏曲」と五一年録音の「五重奏曲」を聴くCDが、タワーレコードの限定発売で復刻された。私にとって見慣れないドイツ・グラモフォン表紙での発売だが、これはジンブラー・シンフォニエッタとの協奏、ファイン・アーツ・カルテットとの五重奏とれっきとしたアメリカ録音だから、一九五〇年代初頭まで米デッカとドイツ・グラモフォンが提携していた時代のもの。米デッカのオリジナルは確か幾何学模様とアルファベットをあしらったものだったはずだが、我が家のどこに紛れてしまったものか、見当たらないので確証はない。レジナルド・ケルは、戦前からイギリスで活躍し、いくつもの名門オーケストラの主席奏者を歴任しているから、いわゆるイギリス管楽器演奏の伝統の中の一人――というより草創期の人と言っていいだろう。見事なアゴーギクの妙技で、よく揺れ動き、伸び縮みする音楽を奏でる名人だということはわかっていたが、今回のCDではさらに、よく走り、跳ねる自在な音楽の持ち主であることに気づかされた。アメリカ録音だからだろうなどと色めがねで判断してはいけない。あわてて一九四〇年のサージェント指揮ロンドン・フィルとの協奏、四五年のフィルハーモニアSQとの五重奏というEMI録音を聴き直してみたが、そうした思いで聴くと、ここでもその傾向がはっきり聞き取れる。一九五〇年前後の演奏に、既に現在に連なるものの芽が生まれていることに気づく感覚が、自分の中で最近研ぎ澄まされて来ていることに、改めて愕然とした。
■何と、一七歳の潮田益子の協奏曲録音が、一挙に発売!
二〇一三年五月に七一歳で亡くなったヴァイオリニスト潮田益子の未発表音源が、フォンテックから二枚のCDとなって登場した。彼女の夫君であるローレンス・レッサー氏の協力によるもので、ライナーノートに寄せられた文章によれば、「彼女の若い時からの膨大な録音テープを聴き、改めて宝物に出会ったような気分になった」のだそうだが、それは、私にとっても同じだった。彼女の独自の感性の魅力に私が取り憑かれたのは一九七一年録音の小澤征爾指揮日本フィルとのシベリウスとブルッフの協奏曲から。その後、六八年に森正の指揮でチャイコフスキーとバルトークの協奏曲を録音しているのを知り、一九六六年のチャイコフスキー・コンクール入賞直後にヨーロッパやアメリカでの演奏を始めた彼女の青春時代の録音は、この二枚と新星堂から復刻されたことのある東芝録音のバッハくらいだと思っていたからである。今回、彼女が一七歳だった一九五九年録音の協奏曲2曲(プロコフィエフ第二番/グラズノフ)をそれぞれメインとし、各々に最晩年二〇一二年の室内楽録音を組み合わせるという構成で二枚発売され、プロコフィエフではストラヴィンスキー『ミューズを率いるアポロ』『デュオ・コンツェルタンテ』、グラズノフでは同じくストラヴィンスキー『ディヴェルティメント』とバルトーク『無伴奏ソナタ』と、彼女が晩年に残した重要な仕事も聴けるのだが、私が何より驚いたのは少女時代の潮田から、既に自身のイメージが確立している人の堂々とした音楽が鳴り響いてくることだ。改めて彼女の功績に感謝しつつ、その冥福を祈った。
前項の一九五九年、まだ一七歳の潮田益子協奏曲で伴奏しているのは、プロコフィエフが恩師齋藤秀雄指揮する桐朋学園オーケストラ。そして、グラズノフが森正指揮のABC交響楽団である。ABC交響楽団とは懐しい名前だ。日本の交響楽団運動の父と讃えられる近衛秀麿が朝日放送の支援を受けていた時期の自身のオーケストラの名称だったと思う。思えば、日本の西洋音楽受容の歴史は、第二次大戦が終わって十余年というこの時期でも、その歩みはまだまだ端緒から這い出した程度だったと言っていい。これまでに幾度か書いてきたことだが、私は、日本の交響楽運動が、本当の意味で自分たちのものとして自立したのは、岩城宏之、小澤征爾、若杉弘というほぼ同世代の三人が、それぞれの音楽観を全世界に発信し始めた一九六〇年代後半以降だと思っている。だが、それでもベートーヴェンは手強かった。小澤、若杉が結局「ベートーヴェン全集」に手を出さなかったのは、偶然ではない。それほどに西欧の音楽伝統の岩盤は堅固なのだ。だが、岩城だけは違った。おそらく、この三人のなかで岩城が一番、西欧文化に対するコンプレックスが少なかったのだと思う。無理せず、ムキにもならず自然に接することができたのは、なぜだったのだろう。まだその答えが見つかっていないが、明らかに岩城だけが、最後の最後まで、自分の(すなわち日本人の)感じるドイツ音楽を、何の衒いもなく高らかに響かせることができた。この七七年と七九年の札幌交響楽団との演奏会記録で聴く「第4」「第7」からは、そうした岩城の雄叫びが聞こえる。
【付記】
上記「ベートーヴェン全集~」について、念のため補足します。小澤ファンはご存知のことと思いますが、小澤~サイトウキネンによって、ずいぶん長い年月をかけ、ばらばらに録音したベートーヴェンの交響曲が全曲録音を終えています。ただ、このことと私が言いたかったこととは違います。また、私の第一評論集(洋泉社・刊「コレクターの快楽」)にも収録しましたが、若杉~読響の最初の重要な録音が「田園」であることも、指摘しています。決して「幻想」ではないのです。一方、岩城は極く初期に「運命/未完成」の録音とは別に、「運命」を再録音してまで、一気に「全集」としての交響曲録音を完成させ、アンサンブル金沢との全曲演奏を機に二度目の全集、そして、ご承知の「振るマラソン」の記録映像まで残しました。