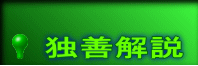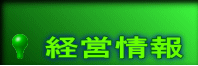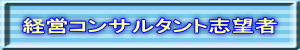■■【一口情報】 敬語の誤用を放置して良いのか

先日、NHKのテレビ番組で敬語講師をされている山岸弘子氏が、「逆転敬語」ということをおっしゃっていました。その番組を中心にお話します。

◆ 敬語の現状
昔、私が学生時代に英語を学んでいるときに、英語の教師が「正しい英語を学びたかったら、BBCの放送を聴きなさい」とアドバイスをしてくれました。それからは、英語だけではなく、私は、正しい日本語を学ぶためには、NHKのアナウンサーの日本語を参考にするようにしました。
ところが、最近は、NHKのアナウンサーも、私のような日本語の専門家でもない、素人でも首を傾げたくなるような日本語を多々使っているのを耳にします。ましてや、アナウンサーでない、特に芸能人に多いように思えるのですが、日本語がでたらめなことを憂いています。
山岸氏は、「間違い敬語」を指摘していました。彼女の体験を紹介していました。
スカートを買いに行ったところ、店が「スカートを拝見しますか?こちらのスカートには裏地がついていらっしゃいますよ」という声をかけてきたそうです。
この言葉は謙譲語を使った表現で、客を低める間違い敬語が含まれています。
この種の誤りは「いただきます」という謙譲語にしばしば耳にしたり、目にしたりします。もっとも、それを文化庁もNHKも「丁寧語」として容認してしまっていますので、誤りと言えなくなってしまっています。
近年、言葉の専門家が「日本語は揺らぎの時代に入っている」と誤用を追認する時代になってしまっていて、「本当にそれで良いのだろうか」と首を傾げたくなります。
◆ 正しい敬語の使い分けポイント
山岸氏は、敬語を使い分けるときに、着目したい関係を3つのポイントで説明しています。
1.上下関係
2.親疎関係
3.ウチ・ソト関係
上下関係は、自分より上か下かを基準とし敬語を使い分けます。親疎関係は、親しい関係か親しくない関係かということを基準とし敬語を使い分けます。
3番目のウチ、ソトの関係について説明をしています。
敬語の学習においては、グループ内の人をウチの人と呼び、グループ外の人をソトの人と呼ぶことが行われています。家族にたとえますと、家族はウチ、家族外はソトとなります。会社で考えますと、社内の人はウチ、社外の人はソトとして考えます。
今日におけます敬語の使い方のルールでは、ソトの人に話すときには、ウチの人を立てて話さないのが基本です。
家族にたとえますと、ソトの人に話すときに、「私の父がおっしゃっていました」「私の母がいらっしゃるそうです」と表現しますと違和感を与えます。なぜなら、打ちに対して敬語や丁寧語を使っていることが多いのです。
同じように、社外の人に話すときに、「弊社の部長がおっしゃっていました」「弊社の課長がいらっしゃるそうです」と話すのは敬語の使い分けのルールに反します。
本来低めるべきウチの人を立ててしまうことから、「ウチ、ソトが逆転した敬語」と呼ばれることもあります。
山岸氏は、増えている誤用例を3つに分類しています。
1.社外の人に話すときに、社内の上司の行為を尊敬語で表してしまう
2.社外の人の行為を謙譲語で表してしまう
3.社外の人の前で、自分の行為を誤った謙譲語で表し、行為の及ぶ先の社内の上司を立ててしまう
◆ 尊敬語誤用の代表事例
山岸氏は、誤用の多い例として、まず尊敬語の誤用について話していました。
「1.社外の人に話すときに、社内の上司の行為を尊敬語で表してしまう」場合の例です。
社外の人に話すときには、社内の人の行為は謙譲語で表します。誤用例と正しい言い方の例を挙げます。
× 弊社の部長がおっしゃっていました
○ 弊社の部長が申しておりました
× 弊社の部長がご覧になりました
○ 弊社の部長が拝見いたしました
× 弊社の部長がいらっしゃいます
○ 弊社の部長がまいります
自分の会社の人、すなわち「ウチの人」に尊敬語を使って、「ソトの人」に話しているのです。部長は社内の人間ですから、社外の人に対して、一段提げて表現しなければならないのです。
たとえ、部長であろうとも「ウチの人」ですから、この場合には尊敬語を使わないのです。もちろん、自分と対部長の場合には、尊敬語や丁寧語で話さなければならないことはいうまでもありません。
◆ 謙譲語誤用の代表例
「2.社外の人の行為を謙譲語で表してしまう」場合の例です。
社外の人の行為は尊敬語で表します。
× 担当者にうかがってください
○ 担当者にお聞きください
× 受付でいただいてください
○ 受付でお受け取りください
× 資料を拝見してください
○ 資料をご覧ください
「うかがう」というのは謙譲語です。社外の人に対して「うかがう」という言葉を使うことは、「うかがう」が謙譲語ですので、社外の人を一段提げてしまうことになります。結果的には、社内の人、この場合には、自社の担当者なのでしょうか、その人が社外の人より上にみる表現となってしまうのです。
そのほか、あちらこちらで耳にする誤用は、謙譲語の「お…する」を社外の人の行為に使う誤用です。「お…してください」「ご…してください」「お…していただけますか」「ご…していただけますか?」という形で使われることが多い間違いです。
「して」を取ると正しい言い方になります。正しい用例は、「こちらでお待ちください」、「こちらの用紙にご記入ください」、「ご了承ください」となります。
◆ 自分の行為に対する謙譲語誤用の代表例
上記最後の「3.社外の人の前で、自分の行為を誤った謙譲語で表し、行為の及ぶ先の社内の上司を立ててしまう」という例です。
謙譲語にはⅠとⅡの2種類あることを知っていると誤用を防ぐことができるようになると山岸氏はおっしゃっていました。
【謙譲語 Ⅰ】
自分側から相手側又は第三者に向かう行為・ものごとなどについて、その向かう先の人物を立てて述べるもの
【謙譲語 Ⅱ】
自分側の行為・ものごとなどを、話や文章の相手に対して丁重に述べるもの
謙譲語Ⅰは、「行為の及ぶ先を立てる働き」がありますので、その場合には、謙譲語Ⅱに言い換えます。
謙譲語Ⅰ、謙譲語Ⅱについて、文化庁敬語の指針は、2007年に発表しています。
謙譲語Ⅰは、「自分側から相手側又は第三者に向かう行為・ものごとなどについて、その向かう先の人物を立てて述べるもの」です。また、謙譲語Ⅱは「自分側の行為・ものごとなどを、話や文章の相手に対して丁重に述べるもの」と説明されています。
山岸氏は、いろいろな講座を実施していますが、謙譲語の2分類を導入した結果、学習の成果を挙げていらっしゃいます。
最初は難しく感じる受講者ですが、使い分けがわかると誤用がどんどん減っていくとのことです。
代表的な例として、下記を山岸氏は挙げていらっしゃいます。
× 弊社の部長には私から申し上げます
○ 弊社の部長には私から申します
× 弊社の担当者にお伝えします
○ 弊社の担当者に申し伝えます
× 弊社の担当者からうかがっています
○ 弊社の担当者から聞いております
◆ 敬語誤用を避ける方法
山岸氏は、増えている代表的な誤用例を例示しなが、説明しています。誤用を以下に減らすかについて、氏は、次のように話していました。
誤用は誰にもありますが、それが繰り返されますと、品格を下げることにも繋がりかねません。本来高めるべき「ソトの人」を低めてしまって、「ウチの人」を立ててしまうような敬語誤用が度重なりますと、「当社を一段低く見ている」「見下している」と受け止められる恐れも出てきます。
山岸氏は、まずは、正しい言い方をインプットし、口に出して練習することが間違いを減らす近道だとおっしゃっています。
そのほか、ウチの言葉をソトに持ち出していることでしばしば質問を受けることについて例を挙げています。
取引先の新人が「了解です」と言うのですが、「”了解”は敬語ですか?」という質問や、社外の人に返事をするとき、「了解しました」と、「承知しました」どちらが適切ですかという質問が例示されています。
「了解」は無線や指示命令系統がはっきりしている組織で使われることが知られています。氏が調べた範囲では、危険を伴う作業をする職場やスピードが求められる職場でも使われているそうです。
便利な言葉ですが、敬意を示すべきソトの人には言い換えたい言葉と氏はおっしゃっています。「承知いたしました」「かしこまりました」「確かに承りました」などと言い換えができます。
「了解」という言葉を例に挙げていましたが、ウチの言葉をそのままソトに持ち出すのは注意が必要だと警告しています。
相手が求めている言葉とかけ離れている言葉を使いますと、相手に違和感を与えます。
自分が使いたい言葉を選ぶのではなく、相手が受け取りやすい言葉、相手の気持ちに配慮した言葉、相手に安心感を与える言葉を選ぶことが、人と人の関係を作り、職場と職場の関係を築き上げていく、と氏は経験的に警告していました。
6回にわたりまして、敬語誤用の避け方について既述してきましたが、私自身もしばしば間違いをしています。それを後で気がつくこともありますが、他の人から指摘されることもあります。
誤用したときには、口に出していうことで、記憶を定かにできるような気がします。












 公的機関から入手した、海外向けのセミナーや各種情報を、各機関の指定条件を下にお届けします。
公的機関から入手した、海外向けのセミナーや各種情報を、各機関の指定条件を下にお届けします。