2013/01/27 ローマ書八9-11「イエスをよみがえらせた方の御霊が」
ゼカリヤ書二6-13 イザヤ書五七15-19
短い、このたった三節の中に、「もし」という言葉が三度繰り返されます。原文を読みますと、9節の後半も「もし」という言い方をしているのです 。もし、キリストの御霊を持たない人であれば、キリストのものではありません、と直訳できます。あまり、もし、もし、と畳みかけられると、自分はどうなんだろうか、神の御霊が自分の中に住んでいるのだろうか、キリストが私のうちにおられるのだろうか、と何となく不安に思わないではなくなる。自分は大丈夫だろうか、と落ち着かなくなる気もします。
けれども、これも原文を読むとハッキリするのですが、9節は実は、「あなたがたは、しかし、」という言い方で始まるのですね。非常に強い言い方で、
「あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。」
そして、そのことに加えて、
「神の御霊があなたがたのうちに住んでおられるのであれば」
なのです。つまり、「神の御霊があなたがたのうちに住んでおられますか、どうですか、ダメだったら話は別ですけれど、御霊が住んでおられるのであれば、あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいるですけれどね」、そんな曖昧な話をしているのではないのですね。あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいる。なぜなら、神の御霊があなたがたのうちに住んでおられるわけですから。そのように言っているのです。
繰り返してお話ししてきましたように、パウロはこのローマ書の前半では、キリストの福音を語っています。キリストの一方的な恵みによる救いです。だから、ここではパウロは読者に向かって、こうしなさい、ああしなさい、肉によらず御霊に従いなさい、というような命令・勧告はほとんどしていません。ここでもそうです。前回の8節まででも、肉にある者は神を喜ばせることが出来ません、と言っていたのですが、それは、あなたがたが肉の中にあるなら神様を喜ばせることは出来ませんよ、気をつけなさい、と言いたかったのではない。この9節でハッキリと、
「けれども、あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいるのです」
と言い切っているのです。ただ、それが無条件に、ではなくて、神の御霊が私たちのうちに住んでおられるということが前提・証拠としてある。ただの言葉ではなく、本当に私たちのうちにおられる。それを裏付ける事実として、御霊が私たちのうちに住んでおられる事実を持ち出しているのです。同じ事が、あとの「もし」にも言えます。
「キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。」
けれども、パウロは読者の教会に、キリストの御霊を持たない人がいるかもしれない、と考えているのではありません 。あなたがたはキリストのもの。私たちはもう罪の奴隷ではなく、神の奴隷、義のしもべである、と言ってきたのです 。ある方は、キリストのもの、というのを言い換えて、キリスト者、クリスチャンと説明します。あなたがたがキリスト者であるという以上は、神の御霊が住んでおられるのだ。神の御霊が住んでくださったからこそ、私たちがキリストを信じ、悔い改め、神に従おうと歩み始めることが出来た。それは、人間の力、肉によっては決して始めることも、願うことも出来ないものでした。しかし、キリストが私たちを捉えてくださいました。
「キリスト・イエスにある者」
としてくださいました。それは、ただ私たちの与(あずか)り知らないところで所属が変わったとか役所かどこかで手続きがなされた、というだけの話とは違うのです 。御霊が私たちを捉え、御霊が私たちの中に住んでくださっている。それによって、私たちが新しく、キリストのものとなって、信仰や悔い改めをいただいているのです。私たちはキリストのもの、キリスト者、である。そのように言えるのは、ただキリストが私たちに、御自身の御霊を通して住んでくださっているからなのです。
「10もしキリストがあなたがたのうちにおられるなら、からだは罪のゆえに死んでいても、霊が、義のゆえに生きています。」
この10節の「霊」は私たちの霊ではなく、定冠詞付きの霊、すなわち、神の御霊です。私たちの体は死んでも、私たちの霊や魂は死なない、という霊肉二元論ではありません。からだは罪のゆえに死んでいる(やがて死ぬ、ではなく、今、生きながら罪に死んでいる状態である)としても、その私たちのうちにキリストがおられ、いのちの御霊が生きていてくださる。そう言っているのです。エデンの園で主に背いたアダム以来、罪と共に死が人類に入って来ました。しかし、キリストが私たちのうちにおられるなら、義の故に-あの、十字架において果たされた義、不義なる者を義としてくださる神の義のゆえに-御霊が私たちの中に住まわれ、私たちのいのちとなっていてくださるのです。これが次の11節にも繋がっていくのです 。
「11もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が、あなたがたのうちに住んでおられるなら、キリスト・イエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなたがたのうちに住んでおられる御霊によって、あなたがたの死ぬべきからだをも生かしてくださるのです。」
内容的には10節を繰り返して強調しているのですが、さらに一歩踏み込んでいる、とも言えます。特に、「イエスを死者の中からよみがえらせた方」と二度も同じ事を言う辺りに、パウロの熱い思いが伝わってこないでしょうか。十字架に死なれたイエス様を、父なる神は御霊によってよみがえらせなさいました。もちろん、イエス様御自身、永遠で全能の神ですから、イエス様がよみがえった、と言っても可笑(おか)しくはないのですが 、聖書は御父が御霊によってイエス様をよみがえらせなさった、イエス様はよみがえらされた、といつも受け身で語っています。そして、そのイエス様をよみがえらせた方の御霊が、私たちのうちにも住んでおられて、この私たちのからだ(私のからだ、皆さんのそのからだ)に住んでいてくださる。イザヤ書五七15にも、主が民の中に住まわれる、という言い方がありました。他にもあちこちに、聖書の契約が、主が民の中に住まわれることを柱とするものとして語られています 。主が私たちのうちに住まわれる、というのは、聖書の救い理解、神の民のあり方を語っています。けれども、それが私たちのからだに住まわれる、と言われているのですね。私たちのこのからだ、生身のこのからだに、神が御霊を住まわせておられる。それは、この私たちのからだは、生きているようであっても罪に死んでいる、実際の死に向かってゆっくりと朽ちていくようなからだであるけれども、そこにイエス様のよみがえりのいのちを持つ御霊がいのちとなっておられて、このからだを生かしてくださるためだ。そう言われているのです。
当然ですが、イエス様の御霊が復活のいのちをもって私たちのうちにおられるからといって、私たちが死ななくなるわけではありません。病気が健やかに癒えるとか、鋼(はがね)のように頑強なパワーを持つと約束されているのでもありません。むしろ、どんなに健康で肉体美を誇るような体であったとしても(実際、ギリシャの彫刻のような体が当時も憧れられていたわけですが)、それをも「死すべきからだ」「罪のゆえに死んでいる」とパウロが言い切るように、やがては死ぬからだの健康をどんなに飾ったところで御霊のいのちとは別のものでしかないのでしょう。私たちのからだは、本当に不思議な力や構成を持っている神秘的なものでもありますが、同時にやはり、朽ちるもの、病気をしたり老化したりするものです。また、現代の医学では、DNAだとか脳の働きやホルモンバランスなどが解明されてきて、それぞれの体の要素から、私たちの性格や行動、感情、男女差、好みなどがどれだけ影響を受けて、縛られているか、ということも言われています。そういう、このからだの中に、御霊が住んでおられる。私たちの弱さ、脆さ、痛み、不自由…。そういうものを全部ご存じの上で、御霊が私たちのうちに住まわれている。そして、私たちを、不老不死や無病息災とは根本的に異なる、イエス様の復活のいのち、自分を与えるいのち、厳しくも思いやりに満ちたいのち、神によって与えられた十字架の道を委ねきって生き、死ぬ、そういういのちに満たしてくださるのです。
主イエス様をよみがえらせた方の御霊が、私たちのからだにも住んでおられる。これは物凄い事を言っているわけです。あまりに凄すぎて、ピンと来ないこともあるでしょう。そして、それに比べれば遥かに些細(ささい)であるはずの日常的なこと、周囲の人間、また自分自身の問題などに思いを向けて、不満や虚しさを訴えてしまったりするのです。だからこそ、私たちがキリスト者であるからには、このからだがよみがえりのいのちの御霊によって生かされているのだ、と心に教え、目を天に向けて、本当に主にあって自由にされ、何者にも振り回されず、主に結ばれて歩む者とされたいと願うのです。
「いのちの御霊が私共を住まいとしておられます。私共の貧しさ、弱さや欠けを先刻承知の上でこの私共のからだ、歩みを通して、イエス様の愛、死、いのちを現したもう。そのお約束に私共をお委ねします。主が私共の主であられることがどれほど尊く、確かであるかを共に知り、信じて歩ませてください。総会をも祝し、ひとりひとりが主の宮として成長する中で、この教会の歩みが主のいのちを輝かせるものとなりますように」
文末脚注
1 ただし、9節の最初は、あとの3回と違う、エイペルという言葉です。後の3回はエイです。
2 「さらに、読者がたは、ここで御霊が、今度は「父なる神の御霊」、今度は「キリストの御霊」として、無頓着に呼び変えられていることに注意しなければならない。これは、単に、御霊の満ち満ちた方が、われわれの仲保者であり・首(かしら)でありたもうキリストの上にひろがり、これにより、そこから、われわれのひとりびとりにもその分け前が注がれるからだけではない。それのみでなく、この同一の御霊がまた、その本質を一つにし、永遠なる同一の神性を持ちたもうところの、御父と御子とに共通な御霊であるからでもある。しかし、そうであるけれども、われわれは、キリストによることなくしては、神との連絡を何一つも持つことがないので、使徒は慎重にも、われわれから遠くへだたっておられるように見える父なる神〔の御霊〕というところからはじめて、次にキリスト〔の御霊〕へとくだって来るのである。」カルヴァン、206頁
3 ローマ書六6、18など。
4 ローマ書八1。
5 永遠の聖定ということでは、世の始まる前、すでに神の側で私たちの救いは定まっていました。十字架において、私たちの救いのみわざは成し遂げられました。その意味では、私たちは、自分の外において救いが果たされたことを信じます。しかし、その「外」の救いが私たちの「中」に働いて、信仰があり、救いを確証することが出来る、という事実もあるのです。Extra nos(私たちの外)での救いが、In nobis(私たちのうちに)来るという両面が、改革主義的な救い理解の特徴です。
6 「神の子たちが霊的であると価値付けられるのは、彼らが完全・無欠な完成されたものになっているがゆえにではなく、ただ、かれらのうちで始まっている新しい生命のみのゆえにである」カルヴァン、206頁
7 他にも、「私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。」(ガラテヤ書二20)、「私にとって生きることはキリスト死ぬこともまた益です。」(ピリピ書一21)などが、この箇所とこの解釈に重なります。
8 事実、イエス様は御自身を「墓の中にいる者がみな、子の声を聞いて出て来るときが来ます」(ヨハネ伝五28)、「わたしを遣わした方のみこころは、わたしに与えてくださったすべての者を、わたしがひとりも失うことなく、ひとりひとりを終わりの日によみがえらせることです」(ヨハネ伝六39)、「わたしはよみがえりです。いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生きるのです。」(ヨハネ伝十一25)とおっしゃいます。イエス様のことばによって、死者はよみがえる、と明言されています。ただ、それは、御霊抜きに、ではなく、御霊が「イエスの御霊」としてお働きになる、御子のみわざでもあるのです。御父、御子、御霊は、バラバラに働かれるのではなく、三位一体としてそれぞれにお働きをなさるのです。
9 出エジプト二九46「彼らは、わたしが彼らの神、主であり、彼の間に住むために、彼らをエジプトの地から連れ出した者であることを知るようになる。わたしは彼らの神、主である。」など。
ゼカリヤ書二6-13 イザヤ書五七15-19
短い、このたった三節の中に、「もし」という言葉が三度繰り返されます。原文を読みますと、9節の後半も「もし」という言い方をしているのです 。もし、キリストの御霊を持たない人であれば、キリストのものではありません、と直訳できます。あまり、もし、もし、と畳みかけられると、自分はどうなんだろうか、神の御霊が自分の中に住んでいるのだろうか、キリストが私のうちにおられるのだろうか、と何となく不安に思わないではなくなる。自分は大丈夫だろうか、と落ち着かなくなる気もします。
けれども、これも原文を読むとハッキリするのですが、9節は実は、「あなたがたは、しかし、」という言い方で始まるのですね。非常に強い言い方で、
「あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。」
そして、そのことに加えて、
「神の御霊があなたがたのうちに住んでおられるのであれば」
なのです。つまり、「神の御霊があなたがたのうちに住んでおられますか、どうですか、ダメだったら話は別ですけれど、御霊が住んでおられるのであれば、あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいるですけれどね」、そんな曖昧な話をしているのではないのですね。あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいる。なぜなら、神の御霊があなたがたのうちに住んでおられるわけですから。そのように言っているのです。
繰り返してお話ししてきましたように、パウロはこのローマ書の前半では、キリストの福音を語っています。キリストの一方的な恵みによる救いです。だから、ここではパウロは読者に向かって、こうしなさい、ああしなさい、肉によらず御霊に従いなさい、というような命令・勧告はほとんどしていません。ここでもそうです。前回の8節まででも、肉にある者は神を喜ばせることが出来ません、と言っていたのですが、それは、あなたがたが肉の中にあるなら神様を喜ばせることは出来ませんよ、気をつけなさい、と言いたかったのではない。この9節でハッキリと、
「けれども、あなたがたは肉の中にではなく、御霊の中にいるのです」
と言い切っているのです。ただ、それが無条件に、ではなくて、神の御霊が私たちのうちに住んでおられるということが前提・証拠としてある。ただの言葉ではなく、本当に私たちのうちにおられる。それを裏付ける事実として、御霊が私たちのうちに住んでおられる事実を持ち出しているのです。同じ事が、あとの「もし」にも言えます。
「キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。」
けれども、パウロは読者の教会に、キリストの御霊を持たない人がいるかもしれない、と考えているのではありません 。あなたがたはキリストのもの。私たちはもう罪の奴隷ではなく、神の奴隷、義のしもべである、と言ってきたのです 。ある方は、キリストのもの、というのを言い換えて、キリスト者、クリスチャンと説明します。あなたがたがキリスト者であるという以上は、神の御霊が住んでおられるのだ。神の御霊が住んでくださったからこそ、私たちがキリストを信じ、悔い改め、神に従おうと歩み始めることが出来た。それは、人間の力、肉によっては決して始めることも、願うことも出来ないものでした。しかし、キリストが私たちを捉えてくださいました。
「キリスト・イエスにある者」
としてくださいました。それは、ただ私たちの与(あずか)り知らないところで所属が変わったとか役所かどこかで手続きがなされた、というだけの話とは違うのです 。御霊が私たちを捉え、御霊が私たちの中に住んでくださっている。それによって、私たちが新しく、キリストのものとなって、信仰や悔い改めをいただいているのです。私たちはキリストのもの、キリスト者、である。そのように言えるのは、ただキリストが私たちに、御自身の御霊を通して住んでくださっているからなのです。
「10もしキリストがあなたがたのうちにおられるなら、からだは罪のゆえに死んでいても、霊が、義のゆえに生きています。」
この10節の「霊」は私たちの霊ではなく、定冠詞付きの霊、すなわち、神の御霊です。私たちの体は死んでも、私たちの霊や魂は死なない、という霊肉二元論ではありません。からだは罪のゆえに死んでいる(やがて死ぬ、ではなく、今、生きながら罪に死んでいる状態である)としても、その私たちのうちにキリストがおられ、いのちの御霊が生きていてくださる。そう言っているのです。エデンの園で主に背いたアダム以来、罪と共に死が人類に入って来ました。しかし、キリストが私たちのうちにおられるなら、義の故に-あの、十字架において果たされた義、不義なる者を義としてくださる神の義のゆえに-御霊が私たちの中に住まわれ、私たちのいのちとなっていてくださるのです。これが次の11節にも繋がっていくのです 。
「11もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が、あなたがたのうちに住んでおられるなら、キリスト・イエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなたがたのうちに住んでおられる御霊によって、あなたがたの死ぬべきからだをも生かしてくださるのです。」
内容的には10節を繰り返して強調しているのですが、さらに一歩踏み込んでいる、とも言えます。特に、「イエスを死者の中からよみがえらせた方」と二度も同じ事を言う辺りに、パウロの熱い思いが伝わってこないでしょうか。十字架に死なれたイエス様を、父なる神は御霊によってよみがえらせなさいました。もちろん、イエス様御自身、永遠で全能の神ですから、イエス様がよみがえった、と言っても可笑(おか)しくはないのですが 、聖書は御父が御霊によってイエス様をよみがえらせなさった、イエス様はよみがえらされた、といつも受け身で語っています。そして、そのイエス様をよみがえらせた方の御霊が、私たちのうちにも住んでおられて、この私たちのからだ(私のからだ、皆さんのそのからだ)に住んでいてくださる。イザヤ書五七15にも、主が民の中に住まわれる、という言い方がありました。他にもあちこちに、聖書の契約が、主が民の中に住まわれることを柱とするものとして語られています 。主が私たちのうちに住まわれる、というのは、聖書の救い理解、神の民のあり方を語っています。けれども、それが私たちのからだに住まわれる、と言われているのですね。私たちのこのからだ、生身のこのからだに、神が御霊を住まわせておられる。それは、この私たちのからだは、生きているようであっても罪に死んでいる、実際の死に向かってゆっくりと朽ちていくようなからだであるけれども、そこにイエス様のよみがえりのいのちを持つ御霊がいのちとなっておられて、このからだを生かしてくださるためだ。そう言われているのです。
当然ですが、イエス様の御霊が復活のいのちをもって私たちのうちにおられるからといって、私たちが死ななくなるわけではありません。病気が健やかに癒えるとか、鋼(はがね)のように頑強なパワーを持つと約束されているのでもありません。むしろ、どんなに健康で肉体美を誇るような体であったとしても(実際、ギリシャの彫刻のような体が当時も憧れられていたわけですが)、それをも「死すべきからだ」「罪のゆえに死んでいる」とパウロが言い切るように、やがては死ぬからだの健康をどんなに飾ったところで御霊のいのちとは別のものでしかないのでしょう。私たちのからだは、本当に不思議な力や構成を持っている神秘的なものでもありますが、同時にやはり、朽ちるもの、病気をしたり老化したりするものです。また、現代の医学では、DNAだとか脳の働きやホルモンバランスなどが解明されてきて、それぞれの体の要素から、私たちの性格や行動、感情、男女差、好みなどがどれだけ影響を受けて、縛られているか、ということも言われています。そういう、このからだの中に、御霊が住んでおられる。私たちの弱さ、脆さ、痛み、不自由…。そういうものを全部ご存じの上で、御霊が私たちのうちに住まわれている。そして、私たちを、不老不死や無病息災とは根本的に異なる、イエス様の復活のいのち、自分を与えるいのち、厳しくも思いやりに満ちたいのち、神によって与えられた十字架の道を委ねきって生き、死ぬ、そういういのちに満たしてくださるのです。
主イエス様をよみがえらせた方の御霊が、私たちのからだにも住んでおられる。これは物凄い事を言っているわけです。あまりに凄すぎて、ピンと来ないこともあるでしょう。そして、それに比べれば遥かに些細(ささい)であるはずの日常的なこと、周囲の人間、また自分自身の問題などに思いを向けて、不満や虚しさを訴えてしまったりするのです。だからこそ、私たちがキリスト者であるからには、このからだがよみがえりのいのちの御霊によって生かされているのだ、と心に教え、目を天に向けて、本当に主にあって自由にされ、何者にも振り回されず、主に結ばれて歩む者とされたいと願うのです。
「いのちの御霊が私共を住まいとしておられます。私共の貧しさ、弱さや欠けを先刻承知の上でこの私共のからだ、歩みを通して、イエス様の愛、死、いのちを現したもう。そのお約束に私共をお委ねします。主が私共の主であられることがどれほど尊く、確かであるかを共に知り、信じて歩ませてください。総会をも祝し、ひとりひとりが主の宮として成長する中で、この教会の歩みが主のいのちを輝かせるものとなりますように」
文末脚注
1 ただし、9節の最初は、あとの3回と違う、エイペルという言葉です。後の3回はエイです。
2 「さらに、読者がたは、ここで御霊が、今度は「父なる神の御霊」、今度は「キリストの御霊」として、無頓着に呼び変えられていることに注意しなければならない。これは、単に、御霊の満ち満ちた方が、われわれの仲保者であり・首(かしら)でありたもうキリストの上にひろがり、これにより、そこから、われわれのひとりびとりにもその分け前が注がれるからだけではない。それのみでなく、この同一の御霊がまた、その本質を一つにし、永遠なる同一の神性を持ちたもうところの、御父と御子とに共通な御霊であるからでもある。しかし、そうであるけれども、われわれは、キリストによることなくしては、神との連絡を何一つも持つことがないので、使徒は慎重にも、われわれから遠くへだたっておられるように見える父なる神〔の御霊〕というところからはじめて、次にキリスト〔の御霊〕へとくだって来るのである。」カルヴァン、206頁
3 ローマ書六6、18など。
4 ローマ書八1。
5 永遠の聖定ということでは、世の始まる前、すでに神の側で私たちの救いは定まっていました。十字架において、私たちの救いのみわざは成し遂げられました。その意味では、私たちは、自分の外において救いが果たされたことを信じます。しかし、その「外」の救いが私たちの「中」に働いて、信仰があり、救いを確証することが出来る、という事実もあるのです。Extra nos(私たちの外)での救いが、In nobis(私たちのうちに)来るという両面が、改革主義的な救い理解の特徴です。
6 「神の子たちが霊的であると価値付けられるのは、彼らが完全・無欠な完成されたものになっているがゆえにではなく、ただ、かれらのうちで始まっている新しい生命のみのゆえにである」カルヴァン、206頁
7 他にも、「私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。」(ガラテヤ書二20)、「私にとって生きることはキリスト死ぬこともまた益です。」(ピリピ書一21)などが、この箇所とこの解釈に重なります。
8 事実、イエス様は御自身を「墓の中にいる者がみな、子の声を聞いて出て来るときが来ます」(ヨハネ伝五28)、「わたしを遣わした方のみこころは、わたしに与えてくださったすべての者を、わたしがひとりも失うことなく、ひとりひとりを終わりの日によみがえらせることです」(ヨハネ伝六39)、「わたしはよみがえりです。いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生きるのです。」(ヨハネ伝十一25)とおっしゃいます。イエス様のことばによって、死者はよみがえる、と明言されています。ただ、それは、御霊抜きに、ではなく、御霊が「イエスの御霊」としてお働きになる、御子のみわざでもあるのです。御父、御子、御霊は、バラバラに働かれるのではなく、三位一体としてそれぞれにお働きをなさるのです。
9 出エジプト二九46「彼らは、わたしが彼らの神、主であり、彼の間に住むために、彼らをエジプトの地から連れ出した者であることを知るようになる。わたしは彼らの神、主である。」など。










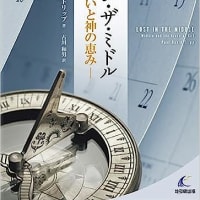
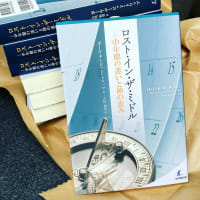

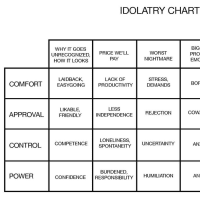
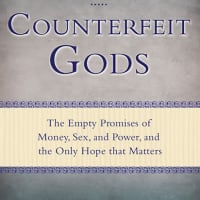
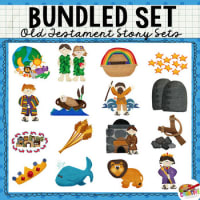
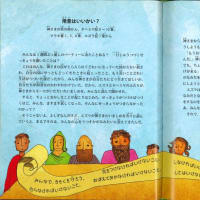
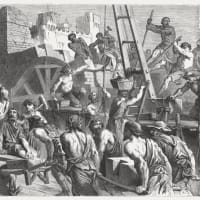


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます