
「窓の話をしよう。」「机の話をしよう。」と二編の詩は語り始め、三編目で「なくてはならないものの話をしよう。」となって、四編目に詩集タイトルの詩「世界はうつくしいと」につながる。その詩は「うつくしいものの話をしよう。」という詩句から始まる。
うつくしいものの話をしよう。
いつからだろう。ふと気がつくと、
うつくしいということばを、ためらわず
口にすることを、誰もしなくなった。
そうしてわたしたちの会話は貧しくなった。
うつくしいものをうつくしいと言おう。
この詩行のつながり、人によっては押しつけがましさや慨嘆が前面に出たり、ぼやきや愚痴っぽく聞こえたりするのだろうが、そんな陳腐への傾斜を上手くかわす。もちろん精神性の強さと緊張感がそうさせるのだが、詩のなかの「ふと気がつくと、」や「ためらわず」がためらうように記述されることで、静かで深い思いが伝わるのだ。
そして、詩は詩を書く詩人の自信のようなものを漂わせながら、うつくしいと言えるものを綴っていく。
風の匂いはうつくしいと。渓谷の
石を伝わってゆく流れはうつくしいと。
午後の草に落ちている雲の影はうつくしいと。
最初に「風の匂い」で入ることで、そのあとの「うつくしい」ものが、すべて風の動きに乗ったまなざしの移動を感じさせる。そしてそれが、
過ぎてゆく季節はうつくしいと。
さらりと老いてゆく人の姿はうつくしいと。
時のうつろいに転換されて、人の時間に戻ってくる。あっ!と思う。見事だ。だが、ここでとどまらない。このあとに、やさしい口調の厳しい反語が唯一呈示される。疑問反語をしめす「か」が使われるのだ。
一体、ニュースとよばれる日々の破片が、
わたしたちの歴史と言うようなものだろうか。
そして、詩人のゆるぎない価値観が直球で切り込まれる。
あざやかな毎日こそ、わたしたちの価値だ。
ここにある「あざやかな毎日」という言葉に、一日に対して人間が持つべき責任のようなものがこもる。そう、ただ単に、ささやかな毎日が価値だというような言い方をするわけではないのだ。ささやかな毎日を「あざやかな毎日」と置いている。そのささやかさの中にも「あざやかな」ものを見いだすまなざしと、「うつくしいものをうつくしい」と言う言葉を、会話を持つことが、静かに要求されているのだ。だから、次の句が続いて繰り返される。
うつくしいものをうつくしいと言おう。
日常をうつくしいと感じる感性。日常の中にある時間に宿るうつくしさ。
幼い猫とあそぶ一刻はうつくしいと。
シュロの枝を燃やして、灰にして、撒く。
灰のイメージを呈示する。最終二行のための死への準備がなされる。そして、詩は次の二行で閉じられる。
何ひとつ永遠なんてなく、いつか
すべて塵にかえるのだから、世界はうつくしいと。
一気に有限性に対峙する。言葉は、この有限な生が持つ無限へのあこがれなのかもしれない。世界のうつくしさは、それが永遠ではないから、消えてしまうから、その一瞬、うつくしいのだ。言葉はそれを記述する。うつくしさを、永遠への夢とつなげる。だが、その言葉自体も、決して永遠なんかではない。そもそも、永遠にうつくしさを見いだすものではないのだ。だが、そこに記述され残された言葉は、そんな有限さをも伝えながら、諦観を宿しながら、生の側に開かれていることで、「うつくしい」のだ。
この詩集の「モーツァルトを聴きながら」、好きだな。
ここのところ毎年のように詩集が出ている。前詩集『幸いなるかな本を読む人』よかった。
うつくしいものの話をしよう。
いつからだろう。ふと気がつくと、
うつくしいということばを、ためらわず
口にすることを、誰もしなくなった。
そうしてわたしたちの会話は貧しくなった。
うつくしいものをうつくしいと言おう。
この詩行のつながり、人によっては押しつけがましさや慨嘆が前面に出たり、ぼやきや愚痴っぽく聞こえたりするのだろうが、そんな陳腐への傾斜を上手くかわす。もちろん精神性の強さと緊張感がそうさせるのだが、詩のなかの「ふと気がつくと、」や「ためらわず」がためらうように記述されることで、静かで深い思いが伝わるのだ。
そして、詩は詩を書く詩人の自信のようなものを漂わせながら、うつくしいと言えるものを綴っていく。
風の匂いはうつくしいと。渓谷の
石を伝わってゆく流れはうつくしいと。
午後の草に落ちている雲の影はうつくしいと。
最初に「風の匂い」で入ることで、そのあとの「うつくしい」ものが、すべて風の動きに乗ったまなざしの移動を感じさせる。そしてそれが、
過ぎてゆく季節はうつくしいと。
さらりと老いてゆく人の姿はうつくしいと。
時のうつろいに転換されて、人の時間に戻ってくる。あっ!と思う。見事だ。だが、ここでとどまらない。このあとに、やさしい口調の厳しい反語が唯一呈示される。疑問反語をしめす「か」が使われるのだ。
一体、ニュースとよばれる日々の破片が、
わたしたちの歴史と言うようなものだろうか。
そして、詩人のゆるぎない価値観が直球で切り込まれる。
あざやかな毎日こそ、わたしたちの価値だ。
ここにある「あざやかな毎日」という言葉に、一日に対して人間が持つべき責任のようなものがこもる。そう、ただ単に、ささやかな毎日が価値だというような言い方をするわけではないのだ。ささやかな毎日を「あざやかな毎日」と置いている。そのささやかさの中にも「あざやかな」ものを見いだすまなざしと、「うつくしいものをうつくしい」と言う言葉を、会話を持つことが、静かに要求されているのだ。だから、次の句が続いて繰り返される。
うつくしいものをうつくしいと言おう。
日常をうつくしいと感じる感性。日常の中にある時間に宿るうつくしさ。
幼い猫とあそぶ一刻はうつくしいと。
シュロの枝を燃やして、灰にして、撒く。
灰のイメージを呈示する。最終二行のための死への準備がなされる。そして、詩は次の二行で閉じられる。
何ひとつ永遠なんてなく、いつか
すべて塵にかえるのだから、世界はうつくしいと。
一気に有限性に対峙する。言葉は、この有限な生が持つ無限へのあこがれなのかもしれない。世界のうつくしさは、それが永遠ではないから、消えてしまうから、その一瞬、うつくしいのだ。言葉はそれを記述する。うつくしさを、永遠への夢とつなげる。だが、その言葉自体も、決して永遠なんかではない。そもそも、永遠にうつくしさを見いだすものではないのだ。だが、そこに記述され残された言葉は、そんな有限さをも伝えながら、諦観を宿しながら、生の側に開かれていることで、「うつくしい」のだ。
この詩集の「モーツァルトを聴きながら」、好きだな。
ここのところ毎年のように詩集が出ている。前詩集『幸いなるかな本を読む人』よかった。










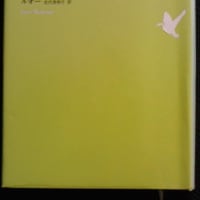
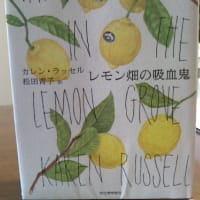
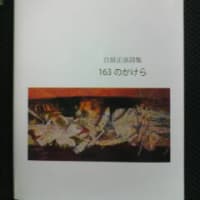
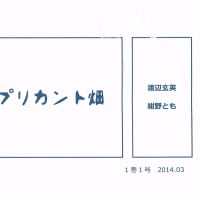
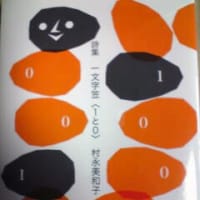
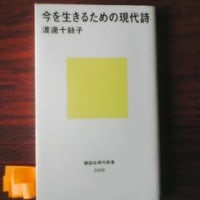










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます