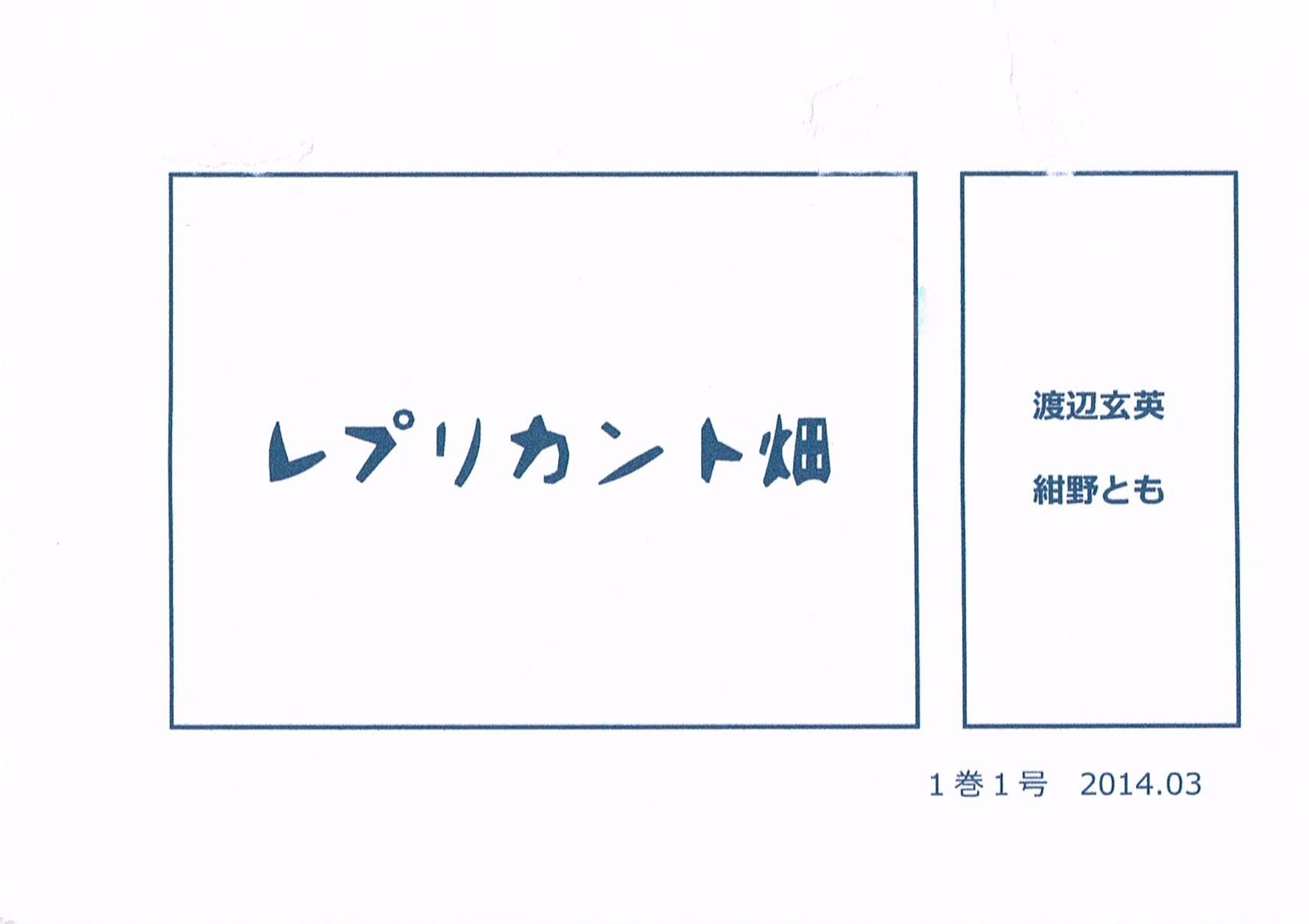
創刊されたおしゃれな詩誌。スマホサイズを意識しているような大きさ、薄さ。持ち歩けるサイズとして文庫本があるのだが、そして、詩誌にもポケットサイズを意識した詩誌が存在するけれど、あっ、この大きさが出たか、という感じ。
詩はスタイルだと思う。文体という意味も含めて。で、詩誌も、スタイルなのであって、そこにあるありさまがすでに選択されたものなのだ。で、例えばその形からいって、中井ひさ子さんや坂多瑩子さんら4人で作っている「4B」、秋亜綺羅さんの「ココア共和国」、逆行するように大判写真入りの田島安江さんたちの「SOMETHING」などは、詩誌のありようが洒落ていると思う。もちろん、詩の充実度もで、その充実度でいえば、その他にも毎号興味深く読んでいる詩誌はある。
と、まず開く前の話はここまでで、詩はスタイルだと思うから続く。
スタイルでありエクリチュールである。だから、様相が話し言葉であっても書かれものとして痕跡を記す。考えれば、ケータイやスマホは実は文字盤に文字表記をした段階でエクリチュールになっている。つまりエクリチュールの過剰をボクたちは生きている。同時にそれはシニフィアンの過剰でもある。ボクらが欠落感を感じたとすれば、それは案外、シニフィエの欠落といってもいいのかもしれない。語彙の貧困などというおきまりの言葉で考えていたら、実は事態は逆なのだ。むしろ溢れる語彙の海に溺れているのかもしれない。それを語彙として認識するかの問題はあるが。語彙というより文字記号、文字的記号の氾濫なのかもしれない。もちろん、文字は記号でしょ、といわれたら、このボクの言い回しは反復になる。
で、詩にいく。渡辺玄英さんの詩「未読の街」は、こう始まる。
これはずいぶん前に書かれたものだ
読みづらい文章の中に
欠落した言葉があって
欠けた言葉の向こうに
ぼんやりと夕日が差している
ひとが影になって歩いている
えっ、と思う。「ひと」がいる風景を書いているときに「ひと」でないひとが、むしろ「影」のように存在している。レプリカントな感覚を引き出しているのだ。それは、すでに、冒頭から始まっていて、「ずいぶん前に書かれた」「読みづらい文章の中に」入っていくから起こっているわけで。そこに入っていくときに、書かれたものを読んでいる「ひと」は、「ひと」の「影」になり、書かれたものの中の「影」に出会う。エクリチュールの中に入ることで、存在しているかもしれない街に出会うということが、とりもなおさず、エクリチュールの外にいる「わたし」を薄くする。しかも、エクリチュールの中の「ひと」や「街」は、「欠落した」言葉が、欠落しているのに「ある」。さらに、「欠けた言葉」の「向こう」にあるのだ。
言葉が世界を作りながら、言葉の欠落に世界があるという、「認識」には、記号の森の気配だけが漂っている。漂っているというのは感覚として正しくないかもしれない。なんだか跋扈しているようでもあるし、覆っているようでもあるし、走り去っているようでもあるのだ。そこをどう感じるかは読者の感覚の経験が試されている。
しかし、とにかく、気配であったとしても、実体として「ある」のだ。この実体とは何か。言葉が作りだす実体なのだ。矛盾しているかな。なぜなら、言葉は本来、実体を指示しないはずだから。言葉は概念を指示する。もちろん、実物を持ってきたときに言葉と呼応することはあるが。であれば、言葉が作りだす実体といういい方は、その矛盾を生きているという実感が背景にあって成立するはずなのだ。言葉の世界は、実体のない世界にもなりうるのであり、実体のない世界を実感するというエクリチュールの矛盾が引き受けられている。ああ、言い回しが難しすぎる。ボク自身が落ちこんでいる、エクリチュールの沼に。
ただ、ここで問題なのは、記号のリアルを生き得るかという問題なのだ。すでに、もう「リアル」という言葉に頼ってしまっている。うーむ、記号と概念であれば、記号は概念を指示し、概念は指示される。しかし、記号と記号であった場合、指示すると指示されるの関係は固定されない。これは、オリジナルとコピーの関係にもなるし、本物(?)とレプリカの問題にもなるし、「ひと」と「レプリカント」の問題にもなる。
そして、その気配を感じとるのは「影」を見ることができるか、「音」を聴くことができるかで、詩の続きは、こうなる。
ありふれた住宅街にすり鉢状に
窪んだ公園があって
だれかが砂利をふむ音が
耳元にきこえてくる(ほかに音はない
(まだわたしはあそこに立っている
と、なる。ゆっくりと地軸が傾くように影が移動しながら、置き去りにされていく自我が見える。すでに自我なんて言葉はない。わたしがわたしを認識するには首を傾げるしかないのだ。「窪んだ」欠落。
それは五年前かもしれないし五年後かもしれない
これからわたしがどこに向かうのかわからない(が
わたしがそこで生きるかわりに
かれはこれを書いたのだかもしれない
パーツに分断すれば、古風な表現が組み合わされて、奇妙な感じと無機的な抒情を醸し出す。「五年前かもしれないし五年後かもしれない」。時間はエクリチュールの中では可逆する。あるいは、曖昧性を獲得できる。この一行があるから次の行の詩句がかつての近代詩的な抒情から切り離される。
そして、書かれたものとして生きると「わたしがそこで生きる」の因果関係が静かに交換される。指示するーされるの変換やエクリチュールと実世界の変換が行われる。さらに、書かれたものは一本の線で消されるのだ。消されたものは疑いか、可能性か。この消すという線もエクリチュールが可能にする記述だ。消されたものの下も残る。ないをあるに、あるをないにする言葉の、書かれた言葉の、姿。
こんな詩句も現れる。
影ができたから日はかたむく
地面が濡れたから雨は降る というように
この文章が不完全に記されたから
わたしはここで傾いている
(わたしはかれだ(かもしれない
「結果が原因を生む」という詩句のあとに続く部分だ。因果が逆転する。指示するものとされるものを逆転させる。ボクらはボクらの存在する文脈を静かに崩壊させる。
雨が降るから地面が濡れるのではない。地面が濡れたから雨が降るのだ。ボクらは先に直感する。その直感の現場では因果は逆転している。現象を生きるとはそういうことなのだ。
と、同時に、言葉の世界は通常の論理の因果を危機にさらすことも可能である。書かれたものは、書き言葉を支える論理の組み替えを、それ自体で揺さぶる。だから、同じように続く詩句の、「不完全に記された」から「わたし」は「傾いて」いるは、本来、わたしが傾いているから不完全に記されたのだが、先行的に「記される」世界を生きた場合、ここでも因果は逆になる。指示すると指示されるという関係は、意味すると意味されるという関係は、読むと読まれるという関係は、書くと書かれるという関係は、交換可能になる。だからエクリチュールの外の「わたし」はエクリチュールの中の「かれ」になり、そうなる「かもしれない」のだ。
そういえば、寺山修司の短歌に、読んでいる本の物語の中に入る短歌があった。寺山も「わたし」の行き迷いの中で、レプリカントな「ひと」=「私」を歌の中に導入するのが魅力だった。ただ、寺山の場合、歌の中を生きる虚構の「私」は、「私」の影ではなくやはり、強い「私」であったような気がする。
詩の第一連は終わり、第二連は、こう始まる。二連の始まりまで引いておく。
ずいぶん前に書いたものだこれは
書かれているわたしが書いていたかれを思い浮かべて
(それで影のように(幾重にも(わ
(わたしが重なって立ち竦む
例えばあの公園の銀杏の木、という
文章の下に埋葬されているわたしたちを
わたしは覚えていて
「書かれているわたし」と「書いていたかれ」というように「わたし」と「かれ」の入れ替わりが起こっている。「わたし」が「かれ」を書記していたのに、「かれ」が「わたし」を書いている。読む「わたし」もいつか、まなざされる「わたし」になっている。
そのあとにクローズアップされた目元のシーンが記述される。
みひらいた目元が仄かにあかく染まっている
映画的な、あるいはアニメ的な手法も書かれているなと思う。
書かれるものの可能性へと詩は開かれていく。そこに詩は宿る。同時に、それは、書かれるものの不可能性を詩が引き受ける、その詩の痛みを滲みだしていく。それは、同時に記号の森を生きるボクたちの現代の抒情ともいえるものに重なる。記号の森での存在の可能性は、記号化される存在の限りない逸脱の痛みをよぎらせる。
「言葉の欠落」の中で生きるボクたちには、「いくつもの言葉の欠落」はあるのだろうが、ボクを示すものは、「欠落」の中にしかない。
と、書いていくと詩を理屈っぽくしてしまったかもしれないけれど、むしろ、この詩の魅力は、そんな理屈や論理から離れられる書法の面白さである。そして、限りない迷子感覚と、時間よりも空間的な広がりのただ中に置き去りにされたような「わたし」という文字の魅力なのだ。
紺野ともさん「親和水域2014」も面白い。この展開のスリリングさと言葉の持久できる体力は魅力的で、冒頭から
細切れのお百度に決まった道は必要ないが、どうしても
同じ道を選びがちなのは性分なのか
大通りはいつもの凪
人魚は普段通りのほほえみ
(心のうちはいつもみせない)
乳酸菌の坂をのぼらない
それでも背中には乳酸がいる
(粒がぶつかりあって溶ける)
海は荒れていないだろうか
海の家のボートが乾ききっている
(表皮がささくれだっている)
海岸近くのコルシカ島はまだ夜明け前、仕込みの暗い白
色電球の刃がこちらをにらむ。槍の先を見据えた角地で
とつながっていく。読み進めるときにわくわくした感じが持てる。そして、行替えのない詩句が10行ほどが過ぎたあと、行替え詩に移り変わりながら、
断崖から落ちるアイたちは
ユウに援けを求めない
という二行が現れる。さらにそのあと詩句相互が挑み合うようにして詩を成立させていく。愉しい詩に出会えた。得した気分だ。
収録詩2篇。得した気分を味わえた詩誌だった。
詩はスタイルだと思う。文体という意味も含めて。で、詩誌も、スタイルなのであって、そこにあるありさまがすでに選択されたものなのだ。で、例えばその形からいって、中井ひさ子さんや坂多瑩子さんら4人で作っている「4B」、秋亜綺羅さんの「ココア共和国」、逆行するように大判写真入りの田島安江さんたちの「SOMETHING」などは、詩誌のありようが洒落ていると思う。もちろん、詩の充実度もで、その充実度でいえば、その他にも毎号興味深く読んでいる詩誌はある。
と、まず開く前の話はここまでで、詩はスタイルだと思うから続く。
スタイルでありエクリチュールである。だから、様相が話し言葉であっても書かれものとして痕跡を記す。考えれば、ケータイやスマホは実は文字盤に文字表記をした段階でエクリチュールになっている。つまりエクリチュールの過剰をボクたちは生きている。同時にそれはシニフィアンの過剰でもある。ボクらが欠落感を感じたとすれば、それは案外、シニフィエの欠落といってもいいのかもしれない。語彙の貧困などというおきまりの言葉で考えていたら、実は事態は逆なのだ。むしろ溢れる語彙の海に溺れているのかもしれない。それを語彙として認識するかの問題はあるが。語彙というより文字記号、文字的記号の氾濫なのかもしれない。もちろん、文字は記号でしょ、といわれたら、このボクの言い回しは反復になる。
で、詩にいく。渡辺玄英さんの詩「未読の街」は、こう始まる。
これはずいぶん前に書かれたものだ
読みづらい文章の中に
欠落した言葉があって
欠けた言葉の向こうに
ぼんやりと夕日が差している
ひとが影になって歩いている
えっ、と思う。「ひと」がいる風景を書いているときに「ひと」でないひとが、むしろ「影」のように存在している。レプリカントな感覚を引き出しているのだ。それは、すでに、冒頭から始まっていて、「ずいぶん前に書かれた」「読みづらい文章の中に」入っていくから起こっているわけで。そこに入っていくときに、書かれたものを読んでいる「ひと」は、「ひと」の「影」になり、書かれたものの中の「影」に出会う。エクリチュールの中に入ることで、存在しているかもしれない街に出会うということが、とりもなおさず、エクリチュールの外にいる「わたし」を薄くする。しかも、エクリチュールの中の「ひと」や「街」は、「欠落した」言葉が、欠落しているのに「ある」。さらに、「欠けた言葉」の「向こう」にあるのだ。
言葉が世界を作りながら、言葉の欠落に世界があるという、「認識」には、記号の森の気配だけが漂っている。漂っているというのは感覚として正しくないかもしれない。なんだか跋扈しているようでもあるし、覆っているようでもあるし、走り去っているようでもあるのだ。そこをどう感じるかは読者の感覚の経験が試されている。
しかし、とにかく、気配であったとしても、実体として「ある」のだ。この実体とは何か。言葉が作りだす実体なのだ。矛盾しているかな。なぜなら、言葉は本来、実体を指示しないはずだから。言葉は概念を指示する。もちろん、実物を持ってきたときに言葉と呼応することはあるが。であれば、言葉が作りだす実体といういい方は、その矛盾を生きているという実感が背景にあって成立するはずなのだ。言葉の世界は、実体のない世界にもなりうるのであり、実体のない世界を実感するというエクリチュールの矛盾が引き受けられている。ああ、言い回しが難しすぎる。ボク自身が落ちこんでいる、エクリチュールの沼に。
ただ、ここで問題なのは、記号のリアルを生き得るかという問題なのだ。すでに、もう「リアル」という言葉に頼ってしまっている。うーむ、記号と概念であれば、記号は概念を指示し、概念は指示される。しかし、記号と記号であった場合、指示すると指示されるの関係は固定されない。これは、オリジナルとコピーの関係にもなるし、本物(?)とレプリカの問題にもなるし、「ひと」と「レプリカント」の問題にもなる。
そして、その気配を感じとるのは「影」を見ることができるか、「音」を聴くことができるかで、詩の続きは、こうなる。
ありふれた住宅街にすり鉢状に
窪んだ公園があって
だれかが砂利をふむ音が
耳元にきこえてくる(ほかに音はない
(まだわたしはあそこに立っている
と、なる。ゆっくりと地軸が傾くように影が移動しながら、置き去りにされていく自我が見える。すでに自我なんて言葉はない。わたしがわたしを認識するには首を傾げるしかないのだ。「窪んだ」欠落。
それは五年前かもしれないし五年後かもしれない
これからわたしがどこに向かうのかわからない(が
わたしがそこで生きるかわりに
かれはこれを書いたのだ
パーツに分断すれば、古風な表現が組み合わされて、奇妙な感じと無機的な抒情を醸し出す。「五年前かもしれないし五年後かもしれない」。時間はエクリチュールの中では可逆する。あるいは、曖昧性を獲得できる。この一行があるから次の行の詩句がかつての近代詩的な抒情から切り離される。
そして、書かれたものとして生きると「わたしがそこで生きる」の因果関係が静かに交換される。指示するーされるの変換やエクリチュールと実世界の変換が行われる。さらに、書かれたものは一本の線で消されるのだ。消されたものは疑いか、可能性か。この消すという線もエクリチュールが可能にする記述だ。消されたものの下も残る。ないをあるに、あるをないにする言葉の、書かれた言葉の、姿。
こんな詩句も現れる。
影ができたから日はかたむく
地面が濡れたから雨は降る というように
この文章が不完全に記されたから
わたしはここで傾いている
(わたしはかれだ(かもしれない
「結果が原因を生む」という詩句のあとに続く部分だ。因果が逆転する。指示するものとされるものを逆転させる。ボクらはボクらの存在する文脈を静かに崩壊させる。
雨が降るから地面が濡れるのではない。地面が濡れたから雨が降るのだ。ボクらは先に直感する。その直感の現場では因果は逆転している。現象を生きるとはそういうことなのだ。
と、同時に、言葉の世界は通常の論理の因果を危機にさらすことも可能である。書かれたものは、書き言葉を支える論理の組み替えを、それ自体で揺さぶる。だから、同じように続く詩句の、「不完全に記された」から「わたし」は「傾いて」いるは、本来、わたしが傾いているから不完全に記されたのだが、先行的に「記される」世界を生きた場合、ここでも因果は逆になる。指示すると指示されるという関係は、意味すると意味されるという関係は、読むと読まれるという関係は、書くと書かれるという関係は、交換可能になる。だからエクリチュールの外の「わたし」はエクリチュールの中の「かれ」になり、そうなる「かもしれない」のだ。
そういえば、寺山修司の短歌に、読んでいる本の物語の中に入る短歌があった。寺山も「わたし」の行き迷いの中で、レプリカントな「ひと」=「私」を歌の中に導入するのが魅力だった。ただ、寺山の場合、歌の中を生きる虚構の「私」は、「私」の影ではなくやはり、強い「私」であったような気がする。
詩の第一連は終わり、第二連は、こう始まる。二連の始まりまで引いておく。
ずいぶん前に書いたものだこれは
書かれているわたしが書いていたかれを思い浮かべて
(それで影のように(幾重にも(わ
(わたしが重なって立ち竦む
例えばあの公園の銀杏の木、という
文章の下に埋葬されているわたしたちを
わたしは覚えていて
「書かれているわたし」と「書いていたかれ」というように「わたし」と「かれ」の入れ替わりが起こっている。「わたし」が「かれ」を書記していたのに、「かれ」が「わたし」を書いている。読む「わたし」もいつか、まなざされる「わたし」になっている。
そのあとにクローズアップされた目元のシーンが記述される。
みひらいた目元が仄かにあかく染まっている
映画的な、あるいはアニメ的な手法も書かれているなと思う。
書かれるものの可能性へと詩は開かれていく。そこに詩は宿る。同時に、それは、書かれるものの不可能性を詩が引き受ける、その詩の痛みを滲みだしていく。それは、同時に記号の森を生きるボクたちの現代の抒情ともいえるものに重なる。記号の森での存在の可能性は、記号化される存在の限りない逸脱の痛みをよぎらせる。
「言葉の欠落」の中で生きるボクたちには、「いくつもの言葉の欠落」はあるのだろうが、ボクを示すものは、「欠落」の中にしかない。
と、書いていくと詩を理屈っぽくしてしまったかもしれないけれど、むしろ、この詩の魅力は、そんな理屈や論理から離れられる書法の面白さである。そして、限りない迷子感覚と、時間よりも空間的な広がりのただ中に置き去りにされたような「わたし」という文字の魅力なのだ。
紺野ともさん「親和水域2014」も面白い。この展開のスリリングさと言葉の持久できる体力は魅力的で、冒頭から
細切れのお百度に決まった道は必要ないが、どうしても
同じ道を選びがちなのは性分なのか
大通りはいつもの凪
人魚は普段通りのほほえみ
(心のうちはいつもみせない)
乳酸菌の坂をのぼらない
それでも背中には乳酸がいる
(粒がぶつかりあって溶ける)
海は荒れていないだろうか
海の家のボートが乾ききっている
(表皮がささくれだっている)
海岸近くのコルシカ島はまだ夜明け前、仕込みの暗い白
色電球の刃がこちらをにらむ。槍の先を見据えた角地で
とつながっていく。読み進めるときにわくわくした感じが持てる。そして、行替えのない詩句が10行ほどが過ぎたあと、行替え詩に移り変わりながら、
断崖から落ちるアイたちは
ユウに援けを求めない
という二行が現れる。さらにそのあと詩句相互が挑み合うようにして詩を成立させていく。愉しい詩に出会えた。得した気分だ。
収録詩2篇。得した気分を味わえた詩誌だった。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます