○
田村隆一は、エッセイ「肉体は悲しい」で、「幻を見る人」について書いている。よく使われる一節だが、彼が企図したことの一端がわかる。
「幻を見る人」にあっては、自由詩のスタイルをとりながら、あくま
でも静的に収斂されていく。音響も色彩もない、黒と白の無声映画のよ
うな世界だ。形容詞も副詞もない。いわば、「小鳥」「空」「野」「窓」「叫
び」「部屋」「屍骸」だけで成立している世界で、あらゆる修飾語から切
りはなされている単語、裸体のままの単語を有機的にむすびつける動詞
も、「墜ちてくる」「聴えてくる」だけにすぎない。そして、「小鳥」と「叫
び」に共通の運命をあたえているものは、「射殺された」という、きわめ
てアクセントの強い形容句である。この詩に、もしひびきがあるとすれ
ば、この箇所だけであって、小鳥のはばたきはおろか、人間の「叫び」
そのものさえ、読むものの耳にはきこえない、まったく無声の世界であ
る。
田村隆一「肉体は悲しい」
では、彼のこの企図の動機の一端は何なのだろうか。それは、「恐怖・不安・ユーモア」というタイトルになったインタヴューからすくい取ることができる。この発言は一九六九年に初出されているものだから、『四千の日と夜』に限定して書かれたものではないのかもしれないのだが、田村隆一の新しい詩を創作することへの意志と自らを更新し続けようとする持続への決意が表明されている。
彼は、情緒について書く。
だからぼくは、例の昭和初期からの日本のモダニズムの詩がみんな感
覚的になってきたということは、まあ一理ある。ー古い情緒的なものに
抵抗してモダニストたちは感覚というものを尊重してきたわけでしょう。
情緒を避けるために感覚に移行していく。ところが、古い情緒は避けら
れたけれども、新しい情緒をつかまえることはできないわけです。いわ
ゆるモダニズムの詩ではね。しかし、情緒というものは、人間をいちば
ん生かしている原動力だと思うんです。ぼくは古い情緒は嫌いだけれど
も、やはり何らかの新しい情緒がないと、人間のいわゆる生に対する感
覚というか、また生の諸価値というものは出てこないような気がするん
です。ところが、不平不満だとどうしても感覚的にならざるを得ない。
田村隆一「恐怖・不安・ユーモア」
この意識が、彼に純度の高い言葉の詩を書かせた。そぎ落とされた言葉は、それ自体ぎりぎりのところで言葉の無機質化への傾斜に踏みとどまり、その言葉が持つ情緒から余分な情感を剥ぐ。感覚的な処理ではなく、論理の擬装をまとうことで、明晰な論理自体が持つ抒情を支持する。だが、詩句は衝突し合うことで、論理の整合性に絡め取られることを拒絶する。了解可能な情緒におけるわかりやすさの罠のなかから戦後は、切り離されなければならなかったのだ。その切断面においてこそ、戦前的なるものは意味を持ち、戦後の生は生自体を獲得できるのである。その情緒の継続的変質は、おそらく今現在も続いているのだろう。もちろん、継続伝承され続ける情緒との共生、混合、そして対峙、拮抗をくり返しながら。
水溶性の情緒は忌避されるが、田村隆一は情緒を軽蔑しはしない。「ただ情緒そのものは軽蔑しちゃいけないと思うんです。まあ、古い情緒はいやらしいし、ぼくのいちばん嫌いなものですけど、しかし、やはり新しい情緒がないと人間のほんとの悲しみとか喜びとかは歌えないですよ」と言う。「ほんとの悲しみとか喜び」を歌うために、それを思索し、「新しい情緒」を模索している。「情緒」をあるものではなく探査、思索するものとして考えているのである。僕らはこのラディカルさにも、ある戦後精神をみることができるのかもしれない。
僕は、ここを読んだとき、かつて読んだミラン・クンデラの『小説の精神』のあとがきを思い出した。訳者である金井裕はクンデラを紹介しながら、五○年代に若い叙情詩人として出発したクンデラの「歌のわかれ」としての叙情詩人から散文作家への移行について触れている。そして、「抒情詩の精神と小説の精神」を「世界を見、理解する異った対立する二つの仕方」であり、「スターリン主義の絶頂期にあって抒情的態度がことのほか高揚される時代に青春を過した私は、そこに抒情とテロルが不分明なかたちで馴れあっているのを見た」というクンデラのインタヴューを引きながら、
彼(クンデラ)は、この〈馴れあい〉の例として、ポール・エリュア
ールがチェコのシュールレアリスト、サヴィス・カランドラの処刑の際
に書いた詩をあげ、詩人の「抒情的高揚がほとんど奇跡的といってよい
くらいみごとに」、「自我と世界との批判的距離を無くさせ」、詩人自身が
いかに「死刑執行者に自己同化」しているかを指摘するのである。これ
を要するに、叙情的精神とは、対象に無批判的に自己同化を行い、「人間
生活の他の表示」、いいかえれば「イロニー、分析、理解、冒険、思考…
…等を掻き消してしまう」精神にほかならない。
ミラン・クンデラ『小説の精神』「訳者あとがき」から
と、クンデラの叙情的精神との「わかれ」をまとめている。そして、金井裕は、クンデラが、この叙情的精神に対置させる〈小説の精神〉について、「小説とは、『さまざまに異った世界観の出合いの場であり』、『それぞれ異なった世界観の存在』によって構成される『相対的世界』にほかならない」ものだと、書く。そして、「この相対性の精神に、いいかえれば、他者の尊重、他者の思想の、他者の宗教の尊重という原則に、つまり寛容の精神に到達したのだとすれば、この精神は、『相対的世界』によって構成される小説の構造のなかに、だれひとり絶対的な〈真実〉の所有者ではなく、しかしだれもが〈真実〉への権利を主張しうる小説の〈想像的空間〉のなかに、もっともよく具現化されているはずである」と、クンデラの考えを整理してみせる。チェコの歴史を生きたクンデラはより強く「相対的世界」を感じるのかもしれない。だが、おそらく戦中を生きた精神のなかにも、このことと同様の抒情に対する嫌悪と懐疑は強く傷をとどめたのではないかと思う。ある「抒情的高揚」が判断の介在を容赦しない場をつくる抒情の限界。そして、絶対性として現れるものが、実は、決して唯一の絶対ではないという懐疑。
ところが、「恐怖・不安・ユーモア」では、「相対」という言葉を使いながらこういった展開になっている。
欲望を軸にした、不平、不満、不安、それから怒りでも、いろんな怒
りがあるわけでしょう。それが欲望を軸にする場合にはどうしても相対
的な怒りになりますね。現代の社会体制とか、資本によるいろいろな支
配がある、それによって人間が疎外されたりするんですけど、怒りがそ
ういう外にばかり向かっていく。むろん、その怒り自身はたいへん大切
なものです。その怒りがなかったら、われわれの世の中は救いようがあ
りませんからね。ただ、そういう怒りはどうしても相対的なものになり
やすい。たとえば、ある社会的な状況が解消すればなくなるわけです。
むしろ社会的状況や政治的状況を解消させるために怒りが必要なのかも
しれないからね。しかし、またもう一つには状況が変っても変らないと
いう怒りがあるわけでしょう。だからその相対的な怒りと絶対的な怒り
とがうまくその軸で交叉しないと、詩としての根源的な力が出てこない
んじゃないかと思うんです。
田村隆一「恐怖・不安・ユーモア」
まず、「相対的」という言葉の使い方が違う。クンデラは相対的な世界観にウェイトを置き、ポリフォニーが想定されているが、田村隆一は、相手に、対象に、相対するというところにウェイトを置いて「相対的」という言葉を使っている。そして、その対象に支配されない根源性が想定されている。様々な支配への相対的な怒りと、対象自体にとらわれない絶対的な怒りという分け方の中に、相対性に絡め取られない自己の絶対性への何か孤独な信頼があるのではないだろうか。この信頼は無批判で妄念的な信頼ではない。個が個として存在するときに、その存在自体が様々なものを剥奪されながらも、なお残るであろう存在の持つ情感や思念といったものではないのだろうか。だが、はたして、そんなものがあるのだろうか。あるのだ、ということが言葉に賭けられる。人間を言語として考えれば、言語によって書かれる詩は、その詩の存在によって人間とつり合おうとするのではないだろうか。田村隆一の垂直な下降は同等に垂直な言葉の上昇をつり合わせる。この詩人にとって、相対性とは、それを選びとらせるほどの魅力を与えるものではないのだ。おそらく、散文作家は、この田村隆一をこそ相対化して、散文中の人物にしていくのかもしれない。だが、田村隆一は生身のそのまま登場人物として生きているのだ。
ただ、ここで、彼は「相対的な怒りと絶対的な怒り」とが「交叉」する「軸」という言い方をする。状況の解消と共に解消する情感と対象を喪失しても人が持ってしまう存在それ自体が持つ情感という二つが、交叉する軸という考え方には、第一詩集『四千の日と夜』から第二詩集『言葉のない世界』以降への時の経過による変化が表れているのかもしれない。
『四千の日と夜』には、剥ぎ取られた存在が、それでもなお、詩を通して獲得した存在それ自体の在りようや、死を通過してこそ現れてくる言葉の世界での存在や、その極限で滴り出てくる情感がある。それが、その状態を抱え込みながら、第二詩集以降、田村隆一自身が語るように「現実的な手がかり」を必要としていく彼の歩みが、この言い回しには宿っているのかもしれない。そう、「絶対的な怒り」だけではなく、そこに「相対的な怒り」との交叉を見つめていこうとする移行があるのかもしれない。
○
もう少し「絶対的」と「相対的」にこだわってみたい。相対的とは他と比較しうる世界である。それぞれが他との比較において存在する。絶対的とは比較を無くした世界である。この「絶対的」と「相対的」ということを世界の内在化と世界の外在性との関係として考えてみると、それは内在化された世界と言葉との関係とも重なってくる。交感不可能な言葉を表現において求めるという行為は、そこでは言葉によって外在化される、自身の内在化した世界との一体化を求める行為であり、自身の内在化したものの絶対性を外部に働きかけようとする行為なのだ。ただし、当然、言葉化されて表出したものは、外在した世界の視線にさらされることになる。
だが、その段階に行く以前の段階において、いったいに、世界を自己のなかに内在化することは、自分自身を世界に対して超越的な位置に置くことになるのではないだろうか。それが、権力を手に入れれば、超越的な力は内在化した世界をそのイメージのままに外在化させようとするのだろう。だが、個人が個人として世界を内在化させる場合、世界との間に親和性があれば一体感のある状態を生み出すのだろうが、おそらく内在化の強さは、世界との違和や齟齬によるのではないだろうか。そして、自身の超越性や違和や齟齬を回避するためには、世界を内在化すると同時に、自らを世界に内在化させなければならない。というより、そうさせないと、実際に生活をしていくことはできないのであるが、もし、そうしなければ、世界を内在化した自らは、内部世界と外部世界の親和が果たせず、孤絶の中に直立することになるだろう。その直立を生きながら、内在化した世界を、言葉の世界で外在化する。実は、そこに絶対性と相対性の「交叉」する「軸」があるのだ。当然ここに、「詩としての根源的な力」が宿る軸が生まれる。これは、そのまま、実体としての「小鳥」と言葉としての「小鳥」と「野」の関係に等しい。ただ、この場合の実体にあたるものが、すでに強烈にイメージとして実体を離れ、内在化しているのだ。
江藤淳は『成熟と喪失』の中で「人はイメジで生きている」と書いているが、人はおそらく想像力で生きている。詩とは本来、世界の内在化を始点としているのではないだろうか。だが、それは、常に言葉によって外在化される。外在化されるとは、つまり、違和や齟齬、親和を引き受けてしまうということなのだ。田村隆一は、その第一詩集『四千の日と夜』において、世界を内在化することの必然を表現するという外在化をやってのけるのである。そのことの意味と宿命を問うている。それは例えば、世界との違和や齟齬を詩のテーマとして表現するということとは違うのである。詩自体において、そのことを表しているのである。つまり、詩の創造自体が世界と詩人との関係を構造として持っていることを告げずに表現したのである。内在化した世界を、言葉によって、詩の世界に構築するという詩人の意味と宿命を明らかにしたのである。
田村隆一は、エッセイ「肉体は悲しい」で、「幻を見る人」について書いている。よく使われる一節だが、彼が企図したことの一端がわかる。
「幻を見る人」にあっては、自由詩のスタイルをとりながら、あくま
でも静的に収斂されていく。音響も色彩もない、黒と白の無声映画のよ
うな世界だ。形容詞も副詞もない。いわば、「小鳥」「空」「野」「窓」「叫
び」「部屋」「屍骸」だけで成立している世界で、あらゆる修飾語から切
りはなされている単語、裸体のままの単語を有機的にむすびつける動詞
も、「墜ちてくる」「聴えてくる」だけにすぎない。そして、「小鳥」と「叫
び」に共通の運命をあたえているものは、「射殺された」という、きわめ
てアクセントの強い形容句である。この詩に、もしひびきがあるとすれ
ば、この箇所だけであって、小鳥のはばたきはおろか、人間の「叫び」
そのものさえ、読むものの耳にはきこえない、まったく無声の世界であ
る。
田村隆一「肉体は悲しい」
では、彼のこの企図の動機の一端は何なのだろうか。それは、「恐怖・不安・ユーモア」というタイトルになったインタヴューからすくい取ることができる。この発言は一九六九年に初出されているものだから、『四千の日と夜』に限定して書かれたものではないのかもしれないのだが、田村隆一の新しい詩を創作することへの意志と自らを更新し続けようとする持続への決意が表明されている。
彼は、情緒について書く。
だからぼくは、例の昭和初期からの日本のモダニズムの詩がみんな感
覚的になってきたということは、まあ一理ある。ー古い情緒的なものに
抵抗してモダニストたちは感覚というものを尊重してきたわけでしょう。
情緒を避けるために感覚に移行していく。ところが、古い情緒は避けら
れたけれども、新しい情緒をつかまえることはできないわけです。いわ
ゆるモダニズムの詩ではね。しかし、情緒というものは、人間をいちば
ん生かしている原動力だと思うんです。ぼくは古い情緒は嫌いだけれど
も、やはり何らかの新しい情緒がないと、人間のいわゆる生に対する感
覚というか、また生の諸価値というものは出てこないような気がするん
です。ところが、不平不満だとどうしても感覚的にならざるを得ない。
田村隆一「恐怖・不安・ユーモア」
この意識が、彼に純度の高い言葉の詩を書かせた。そぎ落とされた言葉は、それ自体ぎりぎりのところで言葉の無機質化への傾斜に踏みとどまり、その言葉が持つ情緒から余分な情感を剥ぐ。感覚的な処理ではなく、論理の擬装をまとうことで、明晰な論理自体が持つ抒情を支持する。だが、詩句は衝突し合うことで、論理の整合性に絡め取られることを拒絶する。了解可能な情緒におけるわかりやすさの罠のなかから戦後は、切り離されなければならなかったのだ。その切断面においてこそ、戦前的なるものは意味を持ち、戦後の生は生自体を獲得できるのである。その情緒の継続的変質は、おそらく今現在も続いているのだろう。もちろん、継続伝承され続ける情緒との共生、混合、そして対峙、拮抗をくり返しながら。
水溶性の情緒は忌避されるが、田村隆一は情緒を軽蔑しはしない。「ただ情緒そのものは軽蔑しちゃいけないと思うんです。まあ、古い情緒はいやらしいし、ぼくのいちばん嫌いなものですけど、しかし、やはり新しい情緒がないと人間のほんとの悲しみとか喜びとかは歌えないですよ」と言う。「ほんとの悲しみとか喜び」を歌うために、それを思索し、「新しい情緒」を模索している。「情緒」をあるものではなく探査、思索するものとして考えているのである。僕らはこのラディカルさにも、ある戦後精神をみることができるのかもしれない。
僕は、ここを読んだとき、かつて読んだミラン・クンデラの『小説の精神』のあとがきを思い出した。訳者である金井裕はクンデラを紹介しながら、五○年代に若い叙情詩人として出発したクンデラの「歌のわかれ」としての叙情詩人から散文作家への移行について触れている。そして、「抒情詩の精神と小説の精神」を「世界を見、理解する異った対立する二つの仕方」であり、「スターリン主義の絶頂期にあって抒情的態度がことのほか高揚される時代に青春を過した私は、そこに抒情とテロルが不分明なかたちで馴れあっているのを見た」というクンデラのインタヴューを引きながら、
彼(クンデラ)は、この〈馴れあい〉の例として、ポール・エリュア
ールがチェコのシュールレアリスト、サヴィス・カランドラの処刑の際
に書いた詩をあげ、詩人の「抒情的高揚がほとんど奇跡的といってよい
くらいみごとに」、「自我と世界との批判的距離を無くさせ」、詩人自身が
いかに「死刑執行者に自己同化」しているかを指摘するのである。これ
を要するに、叙情的精神とは、対象に無批判的に自己同化を行い、「人間
生活の他の表示」、いいかえれば「イロニー、分析、理解、冒険、思考…
…等を掻き消してしまう」精神にほかならない。
ミラン・クンデラ『小説の精神』「訳者あとがき」から
と、クンデラの叙情的精神との「わかれ」をまとめている。そして、金井裕は、クンデラが、この叙情的精神に対置させる〈小説の精神〉について、「小説とは、『さまざまに異った世界観の出合いの場であり』、『それぞれ異なった世界観の存在』によって構成される『相対的世界』にほかならない」ものだと、書く。そして、「この相対性の精神に、いいかえれば、他者の尊重、他者の思想の、他者の宗教の尊重という原則に、つまり寛容の精神に到達したのだとすれば、この精神は、『相対的世界』によって構成される小説の構造のなかに、だれひとり絶対的な〈真実〉の所有者ではなく、しかしだれもが〈真実〉への権利を主張しうる小説の〈想像的空間〉のなかに、もっともよく具現化されているはずである」と、クンデラの考えを整理してみせる。チェコの歴史を生きたクンデラはより強く「相対的世界」を感じるのかもしれない。だが、おそらく戦中を生きた精神のなかにも、このことと同様の抒情に対する嫌悪と懐疑は強く傷をとどめたのではないかと思う。ある「抒情的高揚」が判断の介在を容赦しない場をつくる抒情の限界。そして、絶対性として現れるものが、実は、決して唯一の絶対ではないという懐疑。
ところが、「恐怖・不安・ユーモア」では、「相対」という言葉を使いながらこういった展開になっている。
欲望を軸にした、不平、不満、不安、それから怒りでも、いろんな怒
りがあるわけでしょう。それが欲望を軸にする場合にはどうしても相対
的な怒りになりますね。現代の社会体制とか、資本によるいろいろな支
配がある、それによって人間が疎外されたりするんですけど、怒りがそ
ういう外にばかり向かっていく。むろん、その怒り自身はたいへん大切
なものです。その怒りがなかったら、われわれの世の中は救いようがあ
りませんからね。ただ、そういう怒りはどうしても相対的なものになり
やすい。たとえば、ある社会的な状況が解消すればなくなるわけです。
むしろ社会的状況や政治的状況を解消させるために怒りが必要なのかも
しれないからね。しかし、またもう一つには状況が変っても変らないと
いう怒りがあるわけでしょう。だからその相対的な怒りと絶対的な怒り
とがうまくその軸で交叉しないと、詩としての根源的な力が出てこない
んじゃないかと思うんです。
田村隆一「恐怖・不安・ユーモア」
まず、「相対的」という言葉の使い方が違う。クンデラは相対的な世界観にウェイトを置き、ポリフォニーが想定されているが、田村隆一は、相手に、対象に、相対するというところにウェイトを置いて「相対的」という言葉を使っている。そして、その対象に支配されない根源性が想定されている。様々な支配への相対的な怒りと、対象自体にとらわれない絶対的な怒りという分け方の中に、相対性に絡め取られない自己の絶対性への何か孤独な信頼があるのではないだろうか。この信頼は無批判で妄念的な信頼ではない。個が個として存在するときに、その存在自体が様々なものを剥奪されながらも、なお残るであろう存在の持つ情感や思念といったものではないのだろうか。だが、はたして、そんなものがあるのだろうか。あるのだ、ということが言葉に賭けられる。人間を言語として考えれば、言語によって書かれる詩は、その詩の存在によって人間とつり合おうとするのではないだろうか。田村隆一の垂直な下降は同等に垂直な言葉の上昇をつり合わせる。この詩人にとって、相対性とは、それを選びとらせるほどの魅力を与えるものではないのだ。おそらく、散文作家は、この田村隆一をこそ相対化して、散文中の人物にしていくのかもしれない。だが、田村隆一は生身のそのまま登場人物として生きているのだ。
ただ、ここで、彼は「相対的な怒りと絶対的な怒り」とが「交叉」する「軸」という言い方をする。状況の解消と共に解消する情感と対象を喪失しても人が持ってしまう存在それ自体が持つ情感という二つが、交叉する軸という考え方には、第一詩集『四千の日と夜』から第二詩集『言葉のない世界』以降への時の経過による変化が表れているのかもしれない。
『四千の日と夜』には、剥ぎ取られた存在が、それでもなお、詩を通して獲得した存在それ自体の在りようや、死を通過してこそ現れてくる言葉の世界での存在や、その極限で滴り出てくる情感がある。それが、その状態を抱え込みながら、第二詩集以降、田村隆一自身が語るように「現実的な手がかり」を必要としていく彼の歩みが、この言い回しには宿っているのかもしれない。そう、「絶対的な怒り」だけではなく、そこに「相対的な怒り」との交叉を見つめていこうとする移行があるのかもしれない。
○
もう少し「絶対的」と「相対的」にこだわってみたい。相対的とは他と比較しうる世界である。それぞれが他との比較において存在する。絶対的とは比較を無くした世界である。この「絶対的」と「相対的」ということを世界の内在化と世界の外在性との関係として考えてみると、それは内在化された世界と言葉との関係とも重なってくる。交感不可能な言葉を表現において求めるという行為は、そこでは言葉によって外在化される、自身の内在化した世界との一体化を求める行為であり、自身の内在化したものの絶対性を外部に働きかけようとする行為なのだ。ただし、当然、言葉化されて表出したものは、外在した世界の視線にさらされることになる。
だが、その段階に行く以前の段階において、いったいに、世界を自己のなかに内在化することは、自分自身を世界に対して超越的な位置に置くことになるのではないだろうか。それが、権力を手に入れれば、超越的な力は内在化した世界をそのイメージのままに外在化させようとするのだろう。だが、個人が個人として世界を内在化させる場合、世界との間に親和性があれば一体感のある状態を生み出すのだろうが、おそらく内在化の強さは、世界との違和や齟齬によるのではないだろうか。そして、自身の超越性や違和や齟齬を回避するためには、世界を内在化すると同時に、自らを世界に内在化させなければならない。というより、そうさせないと、実際に生活をしていくことはできないのであるが、もし、そうしなければ、世界を内在化した自らは、内部世界と外部世界の親和が果たせず、孤絶の中に直立することになるだろう。その直立を生きながら、内在化した世界を、言葉の世界で外在化する。実は、そこに絶対性と相対性の「交叉」する「軸」があるのだ。当然ここに、「詩としての根源的な力」が宿る軸が生まれる。これは、そのまま、実体としての「小鳥」と言葉としての「小鳥」と「野」の関係に等しい。ただ、この場合の実体にあたるものが、すでに強烈にイメージとして実体を離れ、内在化しているのだ。
江藤淳は『成熟と喪失』の中で「人はイメジで生きている」と書いているが、人はおそらく想像力で生きている。詩とは本来、世界の内在化を始点としているのではないだろうか。だが、それは、常に言葉によって外在化される。外在化されるとは、つまり、違和や齟齬、親和を引き受けてしまうということなのだ。田村隆一は、その第一詩集『四千の日と夜』において、世界を内在化することの必然を表現するという外在化をやってのけるのである。そのことの意味と宿命を問うている。それは例えば、世界との違和や齟齬を詩のテーマとして表現するということとは違うのである。詩自体において、そのことを表しているのである。つまり、詩の創造自体が世界と詩人との関係を構造として持っていることを告げずに表現したのである。内在化した世界を、言葉によって、詩の世界に構築するという詩人の意味と宿命を明らかにしたのである。










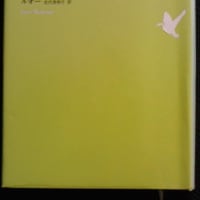
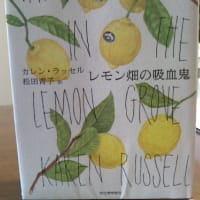
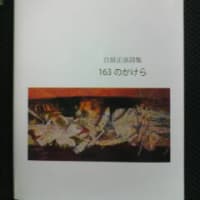
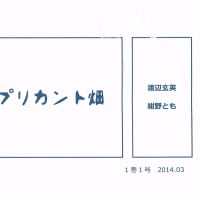
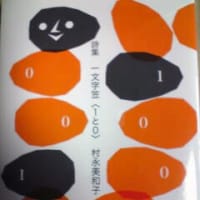
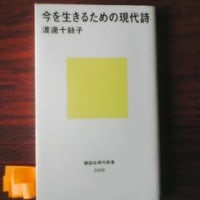




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます