 | ランド・オブ・ザ・デッド ディレクターズ・カット [DVD]ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパンこのアイテムの詳細を見る |
2005アメリカ/カナダ/フランス
監督・脚本:ジョージ・A・ロメロ
出演:サイモン・ベイカー、デニス・ホッパー、アーシア・アルジェント、ロバート・ジョイ、ジョン・レグイザモ、ユージン・クラーク
ゾンビについて考えるキャンペーン(自分だけ~)なので鑑賞
この作品では、なんつーかな、
ゾンビが前提となった社会において、その前提が変化しつつあるときの
人間の行動を描いたドラマ
という感じでしたね。
変化するゾンビ側にはそれなりに物語があって
(ゾンビの歩みにふさわしく緩慢な物語であるけれど)
その変化に影響を受ける人間側にも物語がある
(ちょっと勧善懲悪的な)
どちらを描きたかったのだろうというともちろん両方なんでしょうけど、
想像するに、ゾンビが変化する~というアイディア一発でそれにうっとりして作り上げちゃったのかな~と
つまり人間側のドラマは全然面白くないと(笑)
花火ど~んと打ち上げてそれに見とれて動きが止まるゾンビという設定に
きっとうきうきしてとりくんだでしょうし、その設定を最後に生かすというアイディアも思いついたときには、やた!と手を打ち鳴らしたでしょう(笑/想像)
ゾンビ愛の映画
****
冒頭から笑わせてくれるのは、「少し前」とかクレジットされて、ゾンビが発生した旨を知らせるメディアの音声とかをちょろっと流して、すぐに「現在」とかいって本筋に入っちゃうとこ。
「ゾンビってモノがいます。皆さん知ってますよね?はい、では本編です。」
てな、すごい図々しい横着なつくり(笑)
こういう図々しさがなんだか気に入った。
どうやらゾンビのいる世界では、人間は大都市に囲いを作って住み、雇われ者が地方都市(ゾンビが闊歩している)に残された食料とかを集めて来てそれで生計が立っている社会を形成しているらしい。
雇われものたちは当然地方都市へ赴く際はゾンビとの戦いになるのだけれど、常套手段は、派手な装甲車で集落に乗り付け、まず花火をど~ん!と打ち上げる。
花火があがっている間は街行くゾンビたちは見とれて動きが止まるので、物資を集める間は花火をばんばん上げ続けるわけ。
だから基本戦闘は無しなんだけど、なかには野蛮な?好戦的なヤツがいて、やたらとゾンビを撃ちまくる。野蛮のリーダー格は「チョロ」とかいう名前で、変な名前だ。チョロは組織的な物資の調達の他に、数人で徒党を組んでえらい人に横流しするための酒とかタバコとかを個人的にくすねる。変なところに忍び込んだりするんでいきなりゾンビに襲われて仲間を危険にさらしたりするんで、組織のリーダー格で正義漢のライリーはチョロを快く思わない。
この調子で書いてくと切りがない~~
上流階級の連中は川の中州みたいなとこに要塞都市を作って、異様に豪勢な暮らしをしている。チョロはそこの一員になんとかして潜り込みたいという野心を持ってるわけだ。で、都市の大ボス・カウフマン(デニス・ホッパー!)にいろいろ貢ぎ物をして取り入ろうというわけだが、もちろんカウフマンはそんな小物は相手にしない。
で怒ったチョロがちょろちょろと悪巧みをする、それを退治するためにライリーとその友人スラック(アーシア・アルジェント!)達がカウフマンに雇われる。
でもそういう人間たちのイザコザとは関係なく、度重なる虐殺行為にゾンビたちは怒りを覚えて、「生前の習慣を繰り返すだけの能無し」から一歩踏み出し、銃の使い方を覚えちゃったりして、人間への復讐を始める。
膨大な数のゾンビが要塞都市に向って集結する!
そのさなかにイザコザを処理しなければ行けないライリーやチョロは、人間同士の戦いの上に、途中途中でゾンビの群れとも戦わニャいかんので、もうわやわや。
すべてに嫌気がさしてきたライリーは、カウフマンに加担するつもりは毛頭なく、チョロの装甲車を奪って北へ行こうと思ってるので、別にチョロなんか実はどおでもいい。
結局チョロは墓穴を掘ってああいうことになっちゃって、カウフマンに仕返しに向う。
都市に押し寄せてきたゾンビは、まず越えられないだろうと思われていた川を、勇気を出して?渡ってみたら、なんだ、渡れるじゃん、というわけで、都市の柵もめりめりおしやぶって侵入する。
いや~、人間を襲うは引き裂くわ食いつくわの大騒ぎ
なんとかこの事態を収めようと都市に引き返したライリーにももはや打つ手無し。
逃げようとしたカウフマンも派手に死ぬ。
ああ、結局ゾンビの世界になるのね・・ここも・・・
****
というお話でした。
なんかこう、ゾンビ自体の恐怖というのは一歩後退して、
ゾンビ変奏曲の一つとして、いちおう人間ドラマを乗せてみましたが、
実はまあゾンビの変化を撮りたかったんだろうなあという感じです。
ゾンビが意思を持つについて、目覚めたゾンビを描くことによって、これまではどれもワンオブゼムだったゾンビに、特権的なやつが出て来たことが面白い。
ビッグ・ダディと呼ばれる体格のいい黒人ゾンビとか、頬が避けている女性ゾンビとか、特定のヤツが主導者格っぽくなんども画面に映り、叫んだり威嚇したりする。
これによって、ゾンビに人格感が付与されている。人物の意思の表現とと映像的特権化にはこういう関係があったんだなあと、あらためて感じる。
と、同時に、これまでの非特権的クラウドとしてのゾンビが持っていた「他者感」がちょっと薄れている感じもする。
こういう「他者感」は映像表象的には根深い問題を持っていると思う。例えば欧米映画において、イスラム世界、アジア、先住民、オリエントが、時として人格レベルではない像=他者として描かれることがあるように(いや、別に欧米映画だけの問題ではないけれど)。
でもゾンビ(というか、見た範囲でのロメロのゾンビ)は、その表象の非特権化による他者性の湧出を、うまく恐怖や「居心地悪さ」と結びつけることで成立していたように思う。映像的非特権~絶対他者~恐怖というつながり。
そういう点ではこの映画は、その他者性に基づくゾンビ的気味悪さが損なわれていると思う。
人格を得たゾンビは固有名詞を与えられ、それに親近感を持つファンもいることだろうが、ワタシはどちらかというと、根源的居心地悪さを備える第1作などのほうが好みである。
******
第1作『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』では、冒頭田舎道をクルマが走る姿を遠景でずっと追って行く、あのショットだけでこれからおこるであろうことの禍々しさを十分予告していたと思う。
本作ではそういう心に残る秀逸なショットがないのが残念だ。
また、ゾンビの匿名性に基づく根源的恐怖は、新作『ダイアリー・オブ・ザ・デッド』では回復されていると思う。新作ではまるではじめてゾンビという設定を思いついたかのような、フレッシュな視点があると思う。この点も新作を気に入った理由の一つです。
*****
あとは、そうすね~、ゾンビと人間の境界にいるような男チャーリーの設定が中では居心地の悪い要素でしょうか。あれはなにか新しいものを感じますね。チャーリーをたどってどこへ行けるのか、よく考えないとわかりません。
アーシア・アルジェントは、役所としてはあまり活躍せずちょっと残念。
添え物的になっちゃって。キャラ的にも一時期のウィノナ・ライダーとかシガニー・ウェーバーとかとかぶるかも?
ま、こんなところです。
 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ
↑なにとぞぼちっとオネガイします。
son*imaポップスユニット(ソニマ)やってます。
CD発売中↓
詳しくはson*imaHPまで。試聴もできます。

↑お買い物はこちらで

 人気blogランキングへ
人気blogランキングへ


































 amazon
amazon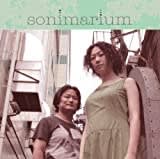 amazon
amazon