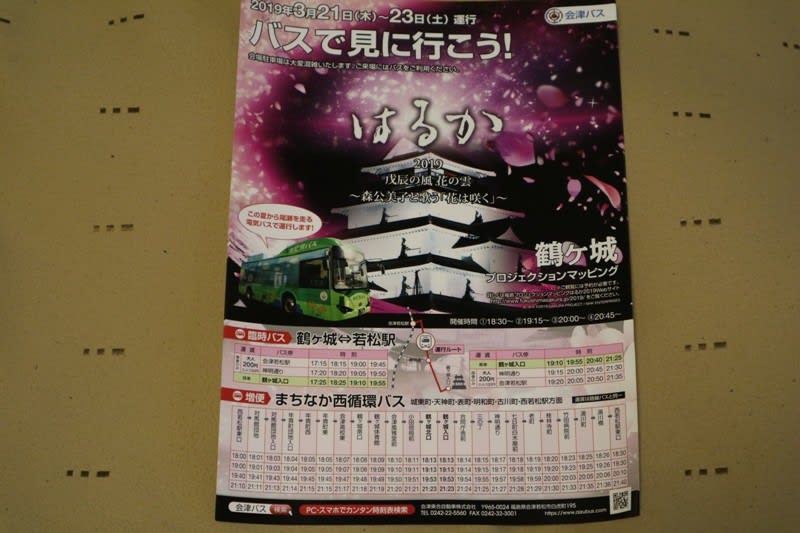出張2日目。会津若松からいったん郡山に戻って米沢に向かいます。朝の会津若松駅で少しだけ駅撮り。高校生が休みなので閑散としてます。磐越西線新津行227Dが入線してきました。キハ47 515(手前・首都圏色)とキハ47 1512(奥・新潟色)の2連。

前の投稿でイーなんちゃら系でごまかしたE721系、すんませんでしたm(_ _)m。3232M快速郡山行ワンマン2連。これに乗って郡山へ戻ります。こうして見ると床が低いのがよくわかりますね。

発車間際まで写真を撮ってたので席はなし。郡山までは1時間くらいなので今日はかぶりつきでいきます。会津若松を出て1つ目の広田駅。かつてはED77からタキ1900が解放されてスイッチャー君に引き渡されていたところ。住友大阪セメントの廃施設はそのまま残され、専用線のレールも一部は草むらの中にまだ残っているようです。

翁島あたりまではカーブと千分の20~25勾配が連続します。正面に磐梯山・・・なんですが、Ωカーブが連続するので磐梯山は右へ行ったり左へ行ったりします。手前の鎖のついた箱は磐梯町駅と猪苗代駅向けの現金ケースのようで、それぞれの駅でカギを持った職員が来て降ろしていきました。

スイッチバック時代の中山宿駅跡。

郡山からは新幹線で米沢へ。自由席でもいいダロとたかをくくっていたら何と満席でデッキ立ち。これは米沢で降りてからわかったのですが、どうやら春休みを利用して免許合宿に向かう若者が大挙して乗っていたようです。今まで気にしたことありませんでしたが、この時期はそういう需要もあるんだなーと気付いた次第。
米沢でひと仕事して(もちろん荒稼ぎじゃありませんw)、時間もいいので「牛肉どまん中」弁当を買い、念のため今度は新庄までの指定券を購入。

券売機の「座席表から選ぶ」画面でぽっかり空いたA席を何の躊躇もなくゲットしたのですが、乗ってみたらオーマイガー!。まわりじゅう合宿免許らしき女子で埋め尽くされていてテンションはすでに女子会モード。ゴメンナサイゴメンナサイと断ってやっと奥のA席に入れてもらっいました。予定では「米沢なう♪」みたいなノリで牛肉どまん中弁当の写真を撮ってからおいしくいただくつもりだったのですが、この状況では「ナニこのおっさん」的視線が刺さることは必至。チキンな筆者は写真はあきらめ、「食べるよ!」と無言のオーラを全身から発して一気に1,250円分を流し込んだのでした。これじゃ松屋と変わらん・・・( ̄▽ ̄;)
牛肉どまん中弁当に未練を残しつつ山形新幹線の終点駅新庄へ。端頭ホームに並ぶE3系1000番台(右)と2000番台(左)。そっくりですが"目つき"が違います。

反対側の在来線ホームの先にキニナル物体が見えたので行ってみると、堂々とした風格の3線機関庫が!元々はレンガ造りの機関庫の前後に木造の建屋を追加した格好になっています。

そして、さらにキニナルこの看板「抑止すったが?」。どうやら「抑止を確認したか?」という山形弁のようです。お国ことばというのは旅先で聞く機会はあっても、見る機会というのはそうそうないので珍しいですね。

ここから先は陸羽西線で余目へ向かいます。最上川に沿って走るので「奥の細道最上川ライン」の愛称が付けられています。入線してきたのはキハ110形200番台の2連。

水量豊富な最上川に寄り添いながら日本海を目指します。先ほどまで会話に余念がなかった外国人カップルも車窓にくぎ付けです。ではここで一句。「最上川 競いて早し キハ百十」

(余韻)
あまるめ~あまるめ~♪鳥海山きれいですね。。

午後2時をまわってやっと酒田に着きました。ここでもひと仕事するのですが、その前に、上りと下りのいなほ号=E653系1000番台が10分差で行き交うのでそれをカメラに収めます。作る♡とは断言しませんが若干取材モード入ってたりします。まあ3ヵ月前には長野駅で383系しなのを前に同じようなことをやっていたので、いつもの悪いクセが出ただけ・・・とご理解ください。。

しかしやる気スイッチはどこで入るかわからないもの。側線に予期せずこんな具合に編成を展示されるとスイッチ入っちゃいませんか?しかも順光で。。これは作れという指令に違いない。

酒田でひと稼ぎ仕事して出張仕事は終了。羽田行は満席で取れなかったので15:56発のいなほ12号で新潟へ向かい、新幹線乗り継ぎで帰京します。新潟駅は在来線の高架ホームができて新幹線とは同一ホームで乗り換えられるようになりました。左にこれから乗る「とき」が写っていますが、何と北陸新幹線と同じE7系です。先ごろ実施されたばかりのダイヤ改正で上越新幹線にも投入されたとのこと。2日間の出張の〆にふさわしい快適な乗り心地でした。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

前の投稿でイーなんちゃら系でごまかしたE721系、すんませんでしたm(_ _)m。3232M快速郡山行ワンマン2連。これに乗って郡山へ戻ります。こうして見ると床が低いのがよくわかりますね。

発車間際まで写真を撮ってたので席はなし。郡山までは1時間くらいなので今日はかぶりつきでいきます。会津若松を出て1つ目の広田駅。かつてはED77からタキ1900が解放されてスイッチャー君に引き渡されていたところ。住友大阪セメントの廃施設はそのまま残され、専用線のレールも一部は草むらの中にまだ残っているようです。

翁島あたりまではカーブと千分の20~25勾配が連続します。正面に磐梯山・・・なんですが、Ωカーブが連続するので磐梯山は右へ行ったり左へ行ったりします。手前の鎖のついた箱は磐梯町駅と猪苗代駅向けの現金ケースのようで、それぞれの駅でカギを持った職員が来て降ろしていきました。

スイッチバック時代の中山宿駅跡。

郡山からは新幹線で米沢へ。自由席でもいいダロとたかをくくっていたら何と満席でデッキ立ち。これは米沢で降りてからわかったのですが、どうやら春休みを利用して免許合宿に向かう若者が大挙して乗っていたようです。今まで気にしたことありませんでしたが、この時期はそういう需要もあるんだなーと気付いた次第。
米沢でひと仕事して(もちろん荒稼ぎじゃありませんw)、時間もいいので「牛肉どまん中」弁当を買い、念のため今度は新庄までの指定券を購入。

券売機の「座席表から選ぶ」画面でぽっかり空いたA席を何の躊躇もなくゲットしたのですが、乗ってみたらオーマイガー!。まわりじゅう合宿免許らしき女子で埋め尽くされていてテンションはすでに女子会モード。ゴメンナサイゴメンナサイと断ってやっと奥のA席に入れてもらっいました。予定では「米沢なう♪」みたいなノリで牛肉どまん中弁当の写真を撮ってからおいしくいただくつもりだったのですが、この状況では「ナニこのおっさん」的視線が刺さることは必至。チキンな筆者は写真はあきらめ、「食べるよ!」と無言のオーラを全身から発して一気に1,250円分を流し込んだのでした。これじゃ松屋と変わらん・・・( ̄▽ ̄;)
牛肉どまん中弁当に未練を残しつつ山形新幹線の終点駅新庄へ。端頭ホームに並ぶE3系1000番台(右)と2000番台(左)。そっくりですが"目つき"が違います。

反対側の在来線ホームの先にキニナル物体が見えたので行ってみると、堂々とした風格の3線機関庫が!元々はレンガ造りの機関庫の前後に木造の建屋を追加した格好になっています。

そして、さらにキニナルこの看板「抑止すったが?」。どうやら「抑止を確認したか?」という山形弁のようです。お国ことばというのは旅先で聞く機会はあっても、見る機会というのはそうそうないので珍しいですね。

ここから先は陸羽西線で余目へ向かいます。最上川に沿って走るので「奥の細道最上川ライン」の愛称が付けられています。入線してきたのはキハ110形200番台の2連。

水量豊富な最上川に寄り添いながら日本海を目指します。先ほどまで会話に余念がなかった外国人カップルも車窓にくぎ付けです。ではここで一句。「最上川 競いて早し キハ百十」

(余韻)
あまるめ~あまるめ~♪鳥海山きれいですね。。

午後2時をまわってやっと酒田に着きました。ここでもひと仕事するのですが、その前に、上りと下りのいなほ号=E653系1000番台が10分差で行き交うのでそれをカメラに収めます。作る♡とは断言しませんが若干取材モード入ってたりします。まあ3ヵ月前には長野駅で383系しなのを前に同じようなことをやっていたので、いつもの悪いクセが出ただけ・・・とご理解ください。。

しかしやる気スイッチはどこで入るかわからないもの。側線に予期せずこんな具合に編成を展示されるとスイッチ入っちゃいませんか?しかも順光で。。これは作れという指令に違いない。

酒田でひと

よろしければ1クリックお願いします。
にほんブログ村