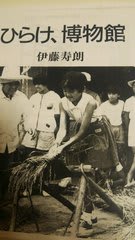わたしは今、みなさんのお宅にお届けしている活動報告「いまここ*島本」の原稿を書いています。お伝えしたいことはたくさんあるのに、紙面は限られています。より多くの方に読んでいただけるよう取捨選択して、工夫に工夫を重ねる作業です。
一方で、パソコンに集中して向きあえる時間も限られていて、もどかしい思いです。以下、会派「人びとの新しい歩み」(平野議員・戸田)を代表して行った大綱質疑のなかから、子育て支援にかかわる質疑答弁をお伝えすることにします。(未校正の会議録を削除・加筆)
■島本町の子ども・子育て支援事業」
「子ども・子育て支援事業計画」において、島本町の計画において、2015年度の認可定員数では不足分があるとされており、保育の需要量と供給量のバランスは引き続き厳しい状況です。子ども達は、4月から保護者が希望する保育所に入ることができるのでしょうか。
定数の見直しは過密を解消しません。現場の苦労を考慮しない考え方であり、認めることはできません。0歳児から2歳児について、町立保育所、山崎保育園、高浜学園、それぞれの入所申請数をお示し下さい。
新制度のもと、保護者にとって最も大きな変化と言えるのは、幼稚園の保育料の見直しです。お示しいただいている経過措置、低所得者への配慮などは評価するものですが、2015年度の申請を行う際、公立か私立か、3年保育か2年保育かを判断する際に、保育料は公表されていませんでした。よって、2016年度からの入園者が卒園するまでの経過措置が望ましいと考えますが、見解を問います。
■教育長答弁
就学前人口の増加と保育ニーズの高まりを背景に、ここ数年、保育所が過密化し、待機児童が発生する状況がございますが、町内認可保育所としては4番目となる高浜学園がオープンいたしました。このことによりまして、待機児童問題をはじめとする保育にかかる課題について、大きく改善が図られることを期待しております。
しかしながら、0歳児・1歳児を中心として特に保育需要が高まっていることや、全国の都市部に見られる現象と同様、新たに保育所を整備した場合、潜在的な利用希望が顕在化し、往々にしてますますニーズが増大する傾向を示しております。
従いまして、全ての入所希望をかなえることや、既存の保育所の過密状態を解消するには、依然として厳しい状況にあると認識しております。
そのため、待機児童の解消や多様な教育・保育ニーズへの対応するため、認可定員の見直しとともに、高浜学園を含めた既存の教育・保育施設を最大限活用してまいりたいと考えております。また地域型保育事業の整備や、認定こども園への移行などの検討も、引き続き行ってまいりたいと考えております。
なお、本年度の0歳児から2歳児につきましての入所申請数につきましては、予約申請期間内で転園希望を含み、町立保育所76人、山崎保育園71人、高浜学園95人でございました。
また、幼稚園保育料につきましては、その経過措置期間を平成27年度及び平成28年度の2ヵ年度とし、平成29年度の取り扱いは、平成27年度中のできる限り早い段階にお示ししたいと考えております。
以上です。民生教育消防委員会では(戸田は所属せず、会派の平野議員は委員長)では、委員会に所属する女性議員(公明党・共産党)が子育て支援ついて多くの質疑をしました。学童保育の待機児童については、当初の予定よりスケジュールを早めて対策が検討されます。なお、認可定員の見直しは保育環境の改悪になり認めることはできません。
画像
桜の木が上品な器に
なにげなく活けられています
水無瀬にあるオーガニックまんまの設えです
一方で、パソコンに集中して向きあえる時間も限られていて、もどかしい思いです。以下、会派「人びとの新しい歩み」(平野議員・戸田)を代表して行った大綱質疑のなかから、子育て支援にかかわる質疑答弁をお伝えすることにします。(未校正の会議録を削除・加筆)
■島本町の子ども・子育て支援事業」
「子ども・子育て支援事業計画」において、島本町の計画において、2015年度の認可定員数では不足分があるとされており、保育の需要量と供給量のバランスは引き続き厳しい状況です。子ども達は、4月から保護者が希望する保育所に入ることができるのでしょうか。
定数の見直しは過密を解消しません。現場の苦労を考慮しない考え方であり、認めることはできません。0歳児から2歳児について、町立保育所、山崎保育園、高浜学園、それぞれの入所申請数をお示し下さい。
新制度のもと、保護者にとって最も大きな変化と言えるのは、幼稚園の保育料の見直しです。お示しいただいている経過措置、低所得者への配慮などは評価するものですが、2015年度の申請を行う際、公立か私立か、3年保育か2年保育かを判断する際に、保育料は公表されていませんでした。よって、2016年度からの入園者が卒園するまでの経過措置が望ましいと考えますが、見解を問います。
■教育長答弁
就学前人口の増加と保育ニーズの高まりを背景に、ここ数年、保育所が過密化し、待機児童が発生する状況がございますが、町内認可保育所としては4番目となる高浜学園がオープンいたしました。このことによりまして、待機児童問題をはじめとする保育にかかる課題について、大きく改善が図られることを期待しております。
しかしながら、0歳児・1歳児を中心として特に保育需要が高まっていることや、全国の都市部に見られる現象と同様、新たに保育所を整備した場合、潜在的な利用希望が顕在化し、往々にしてますますニーズが増大する傾向を示しております。
従いまして、全ての入所希望をかなえることや、既存の保育所の過密状態を解消するには、依然として厳しい状況にあると認識しております。
そのため、待機児童の解消や多様な教育・保育ニーズへの対応するため、認可定員の見直しとともに、高浜学園を含めた既存の教育・保育施設を最大限活用してまいりたいと考えております。また地域型保育事業の整備や、認定こども園への移行などの検討も、引き続き行ってまいりたいと考えております。
なお、本年度の0歳児から2歳児につきましての入所申請数につきましては、予約申請期間内で転園希望を含み、町立保育所76人、山崎保育園71人、高浜学園95人でございました。
また、幼稚園保育料につきましては、その経過措置期間を平成27年度及び平成28年度の2ヵ年度とし、平成29年度の取り扱いは、平成27年度中のできる限り早い段階にお示ししたいと考えております。
以上です。民生教育消防委員会では(戸田は所属せず、会派の平野議員は委員長)では、委員会に所属する女性議員(公明党・共産党)が子育て支援ついて多くの質疑をしました。学童保育の待機児童については、当初の予定よりスケジュールを早めて対策が検討されます。なお、認可定員の見直しは保育環境の改悪になり認めることはできません。
画像
桜の木が上品な器に
なにげなく活けられています
水無瀬にあるオーガニックまんまの設えです